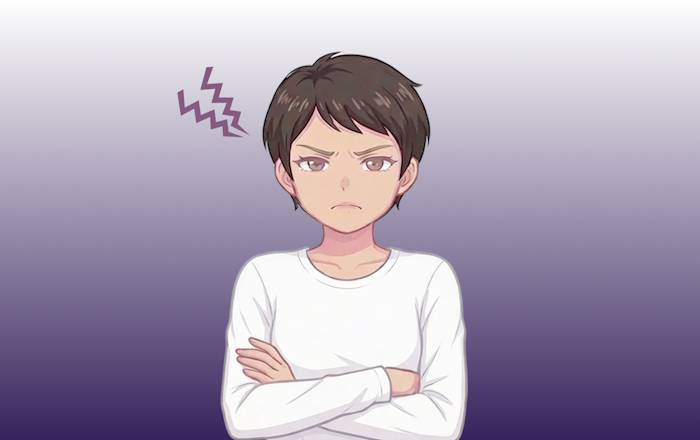取材・文/出井邦子 撮影/馬場隆
■チーズとコーヒーが決まり、手をかけないのが木村流です
『黄昏のロンドンから』をご存知だろうか。昭和52年、第8回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した、木村治美さんの処女作である。
初めて英国ロンドンに滞在したのは昭和49年8月から明くる年3月までの8か月足らず。夫(心理学者の故木村駿さん)のイギリス留学に伴う渡英だった。当時、木村さんは千葉工業大学助教授。1年間の大学休職を決断する。
「周囲への不義理は承知していたので、何か結果を残したいと思っていた。そんな時、東京教育大学英文科の恩師である外山滋比古先生が“ロンドン通信”を書くように勧めてくださったのです」
“啐啄同機(さいたくどうき)”という禅の言葉がある。卵の中の雛が殻を自分の嘴で破ろうとする音が“啐”、それに応じて親鳥が外から殻をつつき破るのが“啄”、転じて“得がたいよい機会〟という意味である。
「私の何か書きたいという気持ちと、先生の何か書けるんじゃないかという気持ちが同機でした」
その“ロンドン通信”が『英語文学世界』に連載され、処女作に結実。以来、大学で教鞭を執る傍ら、妻、母、女性の視点から旺盛な執筆活動を続けてきた。
■英国伝統の“マーマイト”
1年足らずの滞在を機に、その後も幾度となく英国を訪れた。それが食生活の面でも転機となった。例えば、“マーマイト”である。
「これは各種野菜をとことん煮詰め、イースト菌とかなりの塩を加えた英国のペーストです。初めてトーストに塗った時はオエーという感じでしたが、今では残り少なくなったマーマイトの瓶に湯を注いで飲むほど気に入っています」
マーマイトは輸入食品を扱う店や百貨店で入手できるという。

パンはトーストしてマーマイトを塗り、アボカドをのせることも。マーマイトの塩味をアボカドの甘みが和らげてくれる。マーマイトは英国に100年以上続くペースト、アボカドも同国で初めて出会った。
また、英国は紅茶の国といわれるが、さにあらず。コーヒーのほうが断然多く飲まれているそうだ。
「紅茶は葉をジャンピング(茶葉がポットの湯の中で上下に動くこと)させるなど、淹れ方がむずかしい。その点、コーヒーは作り置きができて、いつでもサービスできる。私も朝はコーヒーとチーズです」
そのチーズの魅力を教えてくれたのも英国。牛乳は多く飲めないが、チーズなら種類を問わず幾らでも食べられるというチーズ党。娘とふたりのつましい暮らしだが、チーズにだけは贅沢を許している。

【木村治美さんの定番・朝めし自慢】
前列中央から時計回りに、チーズ(ブリヤ サヴァラン フレ)、パン(フロッケントースト)、ほうれん草のオリーブ油炒め、コーヒー。フロッケントーストはライ押し麦を使用し、香ばしい風味が楽しめるパン。トーストにしたり、チーズを塗ってそのままいただいたりする。ほうれん草のオリーブ油炒めは顆粒コンソメで味付けし、フライパンのまま食卓へ。そのほうが器に盛るより冷めにくいという。
■エッセイ力は人生力、書くのに遅すぎることはない
健康法はウォーキングだ。自宅からの定番コースは5つほどあり、いずれも1時間ほどの距離。
「求道者的な表情で、脇目もふらず歩く人を見かけますが、私はそういうウォーキングは苦手。散歩も目的があったほうが楽しい」

健康法は歩くこと。「私は、ウォーキングにもお買い物とか映画を観るとか、目的があったほうが意欲がわきます」と木村さん。
生活感覚優先だが、それもこれも傘寿を過ぎてなお多忙だからだ。
平成元年、エッセイを書く輪を広げようと『KEG』(木村治美エッセイスト・グループ 問 503・3972・1645)を立ち上げ、東京各地でエッセイ教室を開く他、通信講座では添削指導も行なっている。
「エッセイと日記は違います。エッセイは書いている自分と、書かれている自分との間に距離を置くこと。自分を客観視することです。日記ではこの客観化がしにくい。日記は記録とはなり得ても、エッセイを書く目的である物事の見方や心の動きへの洞察力が身に付くという効能は期待できません」


通信講座の他、各所でエッセイ教室の講師を務めている。写真は東京「コミュニティクラブたまがわ」(玉川髙島屋S・C東館4階 電話:03・3708・6125)の『木村治美・エッセイの会』。受講生は15名ほどで、各々が提出したエッセイを合評する形式で講座が進む。
時は通り過ぎるのではない、積み重なっていく。エッセイを書くのに遅すぎることはない。エッセイ力は人生力、年齢を重ねるほどに味が出るという。

午前7時30分起床、朝食は8時頃。「外出先では、駅の立喰蕎麦屋や牛丼店にひとりで入ることもあります」と木村さん。15年前に亡くなった夫、木村駿さんが見守る居間で。
※この記事は『サライ』本誌2017年7月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです(取材・文/出井邦子 撮影/馬場隆)