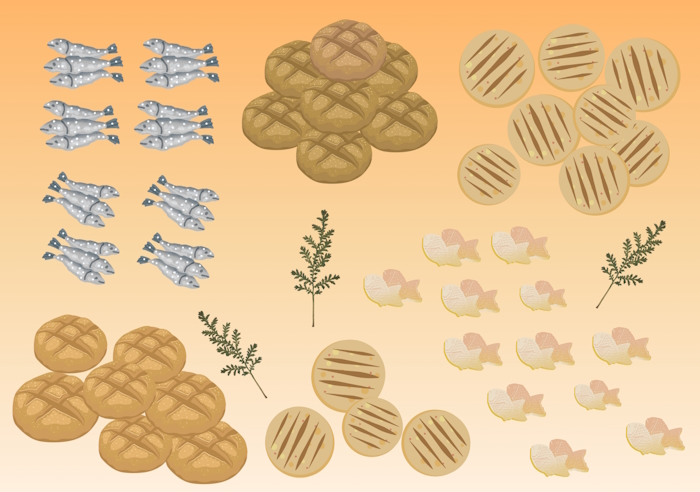文/鈴木隆祐
今年もいよいよ花見シーズンに突入しようとしている。満開の桜は否応なしに私たち日本人の心を浮き立たせるが、“観桜”ということになると、嵯峨天皇が812年3月に神泉苑(京都)にて「花宴の節(せち)」を催したのが始まり。それまで花見といえば“観梅”のことだった。
鎌倉〜室町を経て、武士階級にも観桜の風習は浸透したが、庶民に広まったのは江戸期に入ってから。その張本人は8代将軍・徳川吉宗と言われる。
5代将軍・綱吉による「生類憐れみの令」の発布以降、途絶えていた鷹狩りを復興させた吉宗だが、そのために田畑が荒らされると農民らの不評を買った。そこで鷹狩りの場に桜を植え、農民が花見の客の対応で潤うよう仕向けたのだ。
さらに、今では桜といえばソメイヨシノだが、これは江戸末期に今の駒込(染井村)で生まれた品種。それまでは桜といえばヤマザクラであり、もっと長い期間咲いて人々の目を楽しませた。
パッと咲いて散るソメイヨシノの普及に伴い、桜に対する庶民の美意識を育てたのが歌舞伎である。桜を扱うのはことに舞踊演目に多く、とりわけ歌舞伎舞踊の極美とされる。
そんな「桜」を扱う歌舞伎演目を3つ、ご紹介しよう。
■1:『京鹿子娘道成寺』
桜を扱う歌舞伎の演目といえば、まずは能に基づく『京鹿子娘道成寺(むすめかのこどうじょうじ)』が挙げられるだろう。紀州道成寺に伝わる安珍・清姫伝説の後日譚だ。
清姫の化身の大蛇ごと焼かれたため、鐘がなかった道成寺に再び鐘が奉納され、その供養が行われる。そこへ舞いを捧げたいとやってきた白拍子(踊り子)の花子の美しさにほだされた修行僧は、長らく女人禁制だった寺への入山を許してしまう。だが舞いながら鐘に近づく花子は、実は清姫の生まれ変わりだった。
この舞いは一時間に及ぶが、全編満開の桜を背景に展開される。しかし初演は1753年なので、ソメイヨシノの誕生にはまだ早い。
■2:『祇園祭礼信仰記』
さらに桜がもたらすケレン味が全開になるのが、1757年初演の『祇園祭礼信仰記』(ぎおんさいれいしんこうき)。その四段目「金閣寺」の桜吹雪の表現は圧巻だ。
謀反人の松永弾正は、金閣寺の楼上に暗殺した将軍・足利義輝の母を閉じ込め、一方、絵師・狩野雪村の娘・雪姫に横恋慕し、従わなければ夫の直信の命はないと脅す。雪姫はある日、自分の父を殺したのが弾正と知って斬りつけ、逆に桜の木に縛りつけられてしまう。雪姫は涙で鼠を描いたという祖父・雪舟の故事に倣い、爪先で桜の花びらを集めて鼠を描くと、それが命を得て縄を食いちぎって姫を助ける。
身悶えする雪姫の上に、桜の花びらがその姿をかき消すほど降り注ぐ。ここに歌舞伎の粋を知ると同時に、演出上の効果が、観る者の桜に対する意識を形成していった過程も見て取れる。
■3:『義経千本桜』
さて、歌舞伎で「桜」がタイトルに付く演目は多いが、その代表格といえば『義経千本桜』(よしつねせんぼんざくら)だろう。しかし原作の浄瑠璃自体に桜は登場しない。台詞にただ一言出てくるだけだ。それが現行の文楽・歌舞伎では、四段目の「道行初音旅」と「河連法眼館」の場面で桜が見られる。本作の文楽初演は1747年(歌舞伎は翌年)だが、“タイトルに偽りあり”ということで、後に加えられたのだ。
源義経の都落ちに絡め、その実、潜伏中の平家の三武将(知盛・維盛・教経)にスポットを当てて、“滅びのロマン”を描いた作品。全編に悲劇的ムードが漂い、「千本桜とは千本の卒塔婆のことで、吉野の桜を象徴的に結びつけた」との説も唱えられるほどだ。
ここにも観客の嗜好に合わせ変質する、歌舞伎の悠揚自在さが顕著に現れる。また、同時代的に盛んとなった花見の舞台への影響も察せられる。まさに私たちの桜好みが、歌舞伎とともに育まれた感覚だということが実感できる。
* * *
以上、今回は「桜」を扱う歌舞伎演目3つをご紹介した。
西行の名歌「ねがはくは 花の下にて 春死なむ そのきさらぎの 望月の頃」や、良寛の辞世の句とされる「散る桜 残る桜も 散る桜」を引くまでもなく、日本人は昔から桜が好きだが(そしてそれを「無常観」と結びつけたがる識者もいるが)、現在われわれが抱く桜のイメージが江戸歌舞伎の演出に大きく影響されているであろうことは、間違いなさそうだ。
まずもって春の訪れをそこかしこで告げるからこそ、桜は愛され、散るのを惜しまれてきたのだろう。年に一度の桜の季節を、存分に堪能いただきたい。
文/鈴木隆祐