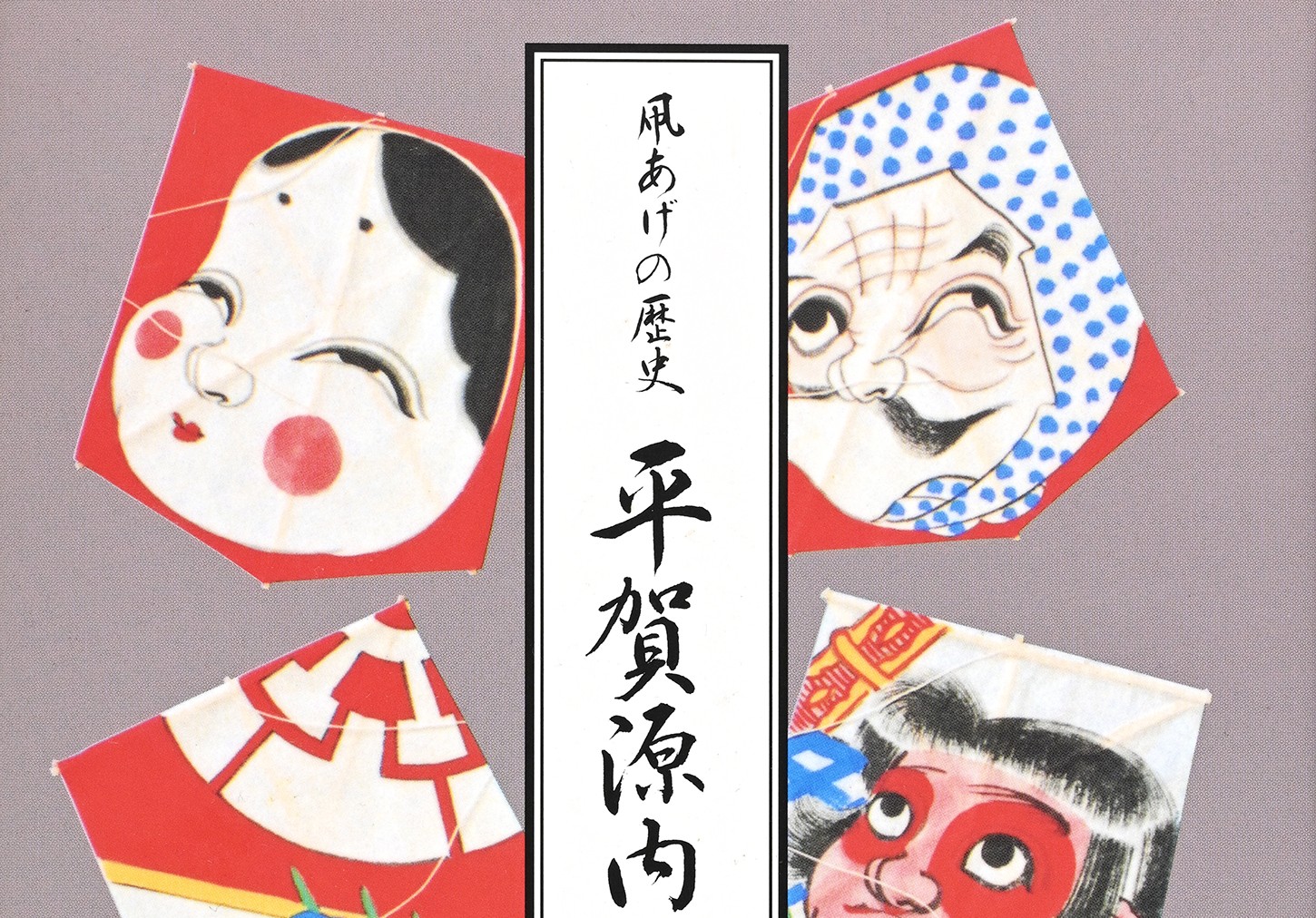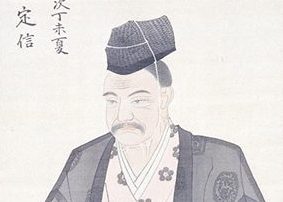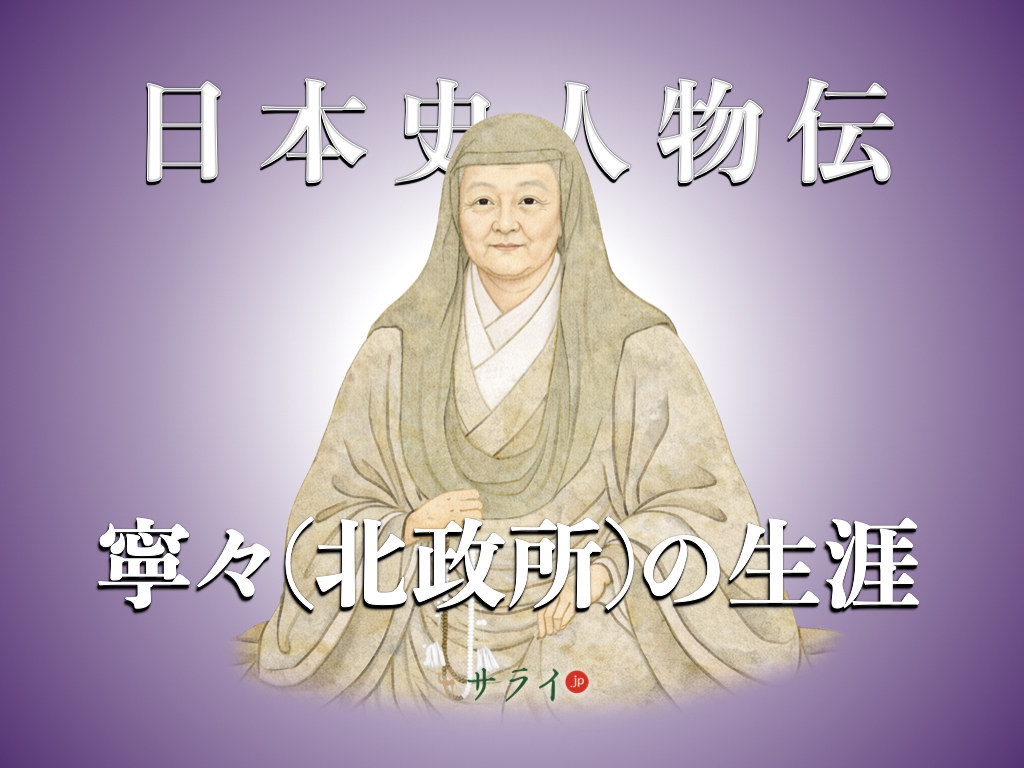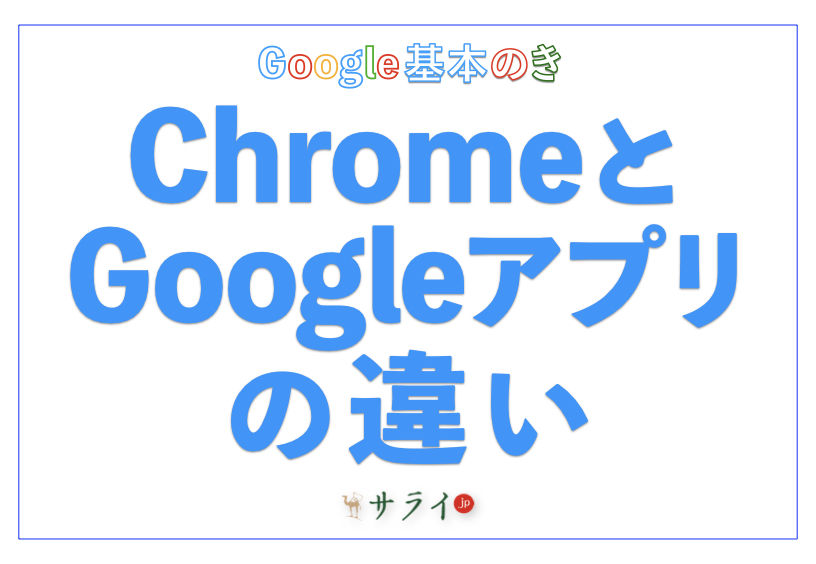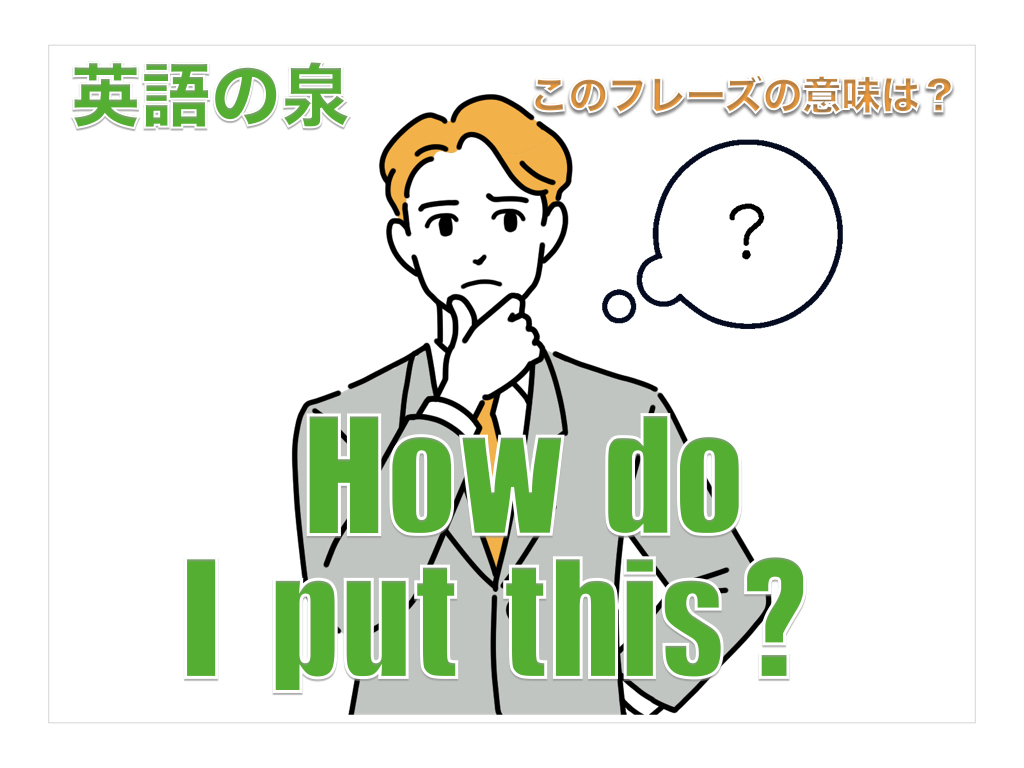ライターI(以下I):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(以下『べらぼう』)第44回では耕書堂で本を出したいという駿河出身の若者重田貞一(後の十返舎一九)が登場しました。演じているのが「ミュージカルのプリンス」の異名で知られる井上芳雄さんです。井上さんのファンの私の友人の中には、その「髷姿」に歓喜している人がいるほどです。
編集者A(以下A):前週もちらっと出演していましたが、本格的な参戦は今週の第44回からですね。物語が残り数回という段階で、しかも平賀源内(演・安田顕)と縁のある相良凧を持参しての登場というのは、なにやら深い意味がありそうですね。
I:その井上さんからコメントが寄せられています。
皆さん十返舎一九という名前は聞いたことがあると思うのですが、どんな人だったのかというと『東海道中膝栗毛』以外の情報はあまりないと思います。『べらぼう』では蔦屋(蔦重)に恋い焦がれて、ここに居させてほしいという、とても軽やかで、世渡り上手というか、明るく楽しく愉快にやっていける前向きなエネルギーのある人だと感じています。思ったより若い役だったんですよね。これから世に出ていこうという若いエネルギーを出せればいいなと、実年齢を隠して頑張りたいと思っております。
I:確かに、井上芳雄さんがいうように十返舎一九というと『東海道中膝栗毛』があまりにも有名です。劇中の時代から8年くらい経ってから刊行される本です。弥次さん喜多さんが東海道を旅する過程で発生する様々な珍事などを描いて大ベストセラーになる作品です。蔦重(演・横浜流星)の没年は寛政9年(1797)ですから、蔦重は彼の大ベストセラーを見届けることができなかったというわけですね。
A:それにしても、井上芳雄さんの若々しさには驚かされます。コメントの中に「実年齢を隠して頑張りたい」という箇所がありますが、このころの十返舎一九、当時はまだ重田貞一ですが、30歳前後という年齢。井上芳雄さんの実際の年齢が46歳なので、15歳ほど年上ということになりますが、違和感はまったくないですね。
A:Iさんは、『東海道中膝栗毛』に触発されて、東海道を徒歩で歩き通した経験がありますから、お詳しいと思いますので、少し解説してください。
I:『東海道中膝栗毛』は、お伊勢参りを思いついた弥次さん(栃面屋弥次郎兵衛)と喜多さん(弥次さん宅の居候の喜多八)が繰り広げる道中記です。初日は江戸から戸塚宿まで10里半(約42キロ)の行程です。当時は1日で行っていたようですが、現代人の足だと(信号などもありますし)、2日くらいかけて行く距離でしょうか。私は神社仏閣や老舗巡りをしながら歩いたため、もう少し時間がかかりました。東海道での江戸の出入り口となった高輪大木戸跡の石垣や、品川宿の少し先にある八百屋お七らが刑に処された鈴ヶ森刑場跡もあります。品川から先は川崎宿、神奈川宿、保土ヶ谷宿と続いて戸塚宿ですが、途中、宿場ごとの本陣跡や道標、一里塚跡などがあり、今も江戸時代の面影を探しながら旅をすることができます。
A:物語には、東海道のお菓子屋さん、甘味屋さんなどが登場するのですが、Iさんもそういうお店には立ち寄ったりしたんですか。
I:江戸時代から残っているお店はだいぶ少なくなりましたが、静岡県静岡市の丸子宿にあるとろろ汁の丁子屋は、弥次喜多がとろろ汁を食べた店といわれていて、今も茅葺屋根で当時の雰囲気を残しています。旧街道沿いに今も頑張ってやっているお店があると、やはり入ってみたくなりますね。そんなことより、井上さんのような「大物」が、物語が終盤に差し掛かった第44回に、田沼意次(演・渡辺謙)の領地ゆかりの「相良凧」を持って江戸にやってくるという意味を考えたいと思います。
A:相良凧は、田沼意次が領した相良藩ゆかりの「凧」。長崎に遊学した平賀源内が長崎からの帰路に立ち寄って、「改良」のきっかけになったとも伝承されている「凧」ですね。詳しくは別稿で、平賀源内生存説と絡めて展開していますが、「田沼意次・平賀源内」→「蔦屋重三郎」→「十返舎一九」という「時代を動かした人物交代の儀式」をみているようで感慨深いですね。
I:その儀式の象徴が「相良凧」という演出なわけですね。そういう思いでみていると、なんだか涙がこぼれてきますよね。

●編集者A:書籍編集者。『べらぼう』をより楽しく視聴するためにドラマの内容から時代背景などまで網羅した『初めての大河ドラマ~べらぼう~蔦重栄華乃夢噺 歴史おもしろBOOK』などを編集。同書には、『娼妃地理記』、「辞闘戦新根(ことばたたかいあたらいいのね)」も掲載。「とんだ茶釜」「大木の切り口太いの根」「鯛の味噌吸」のキャラクターも掲載。
●ライターI:文科系ライター。月刊『サライ』等で執筆。猫が好きで、猫の浮世絵や猫神様のお札などを集めている。江戸時代創業の老舗和菓子屋などを巡り歩く。
構成/『サライ』歴史班 一乗谷かおり