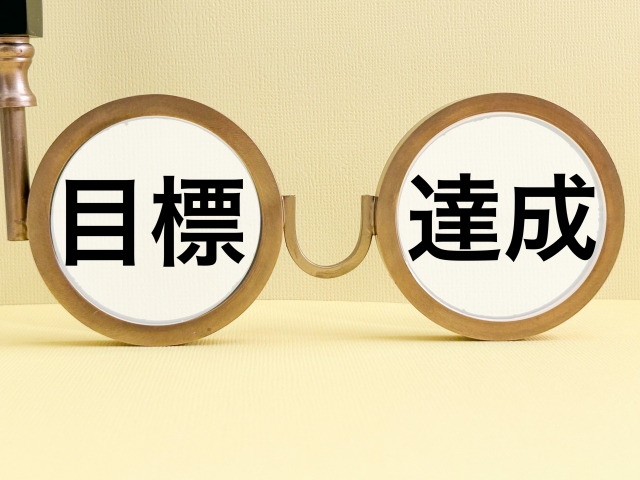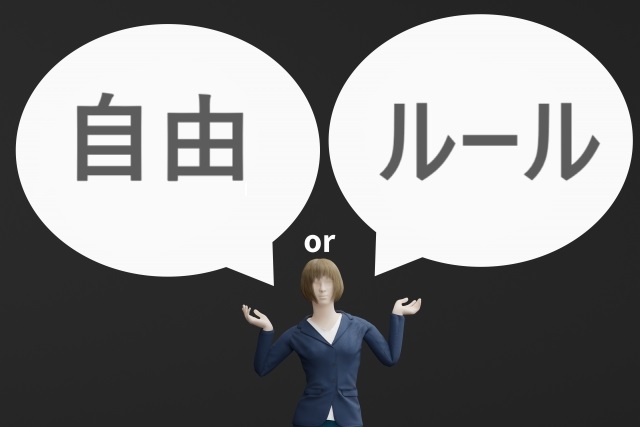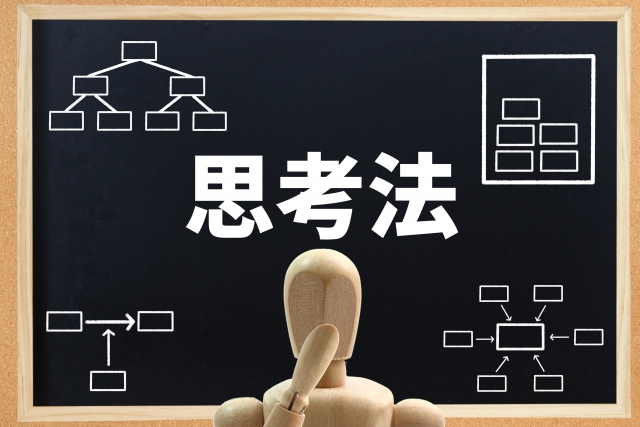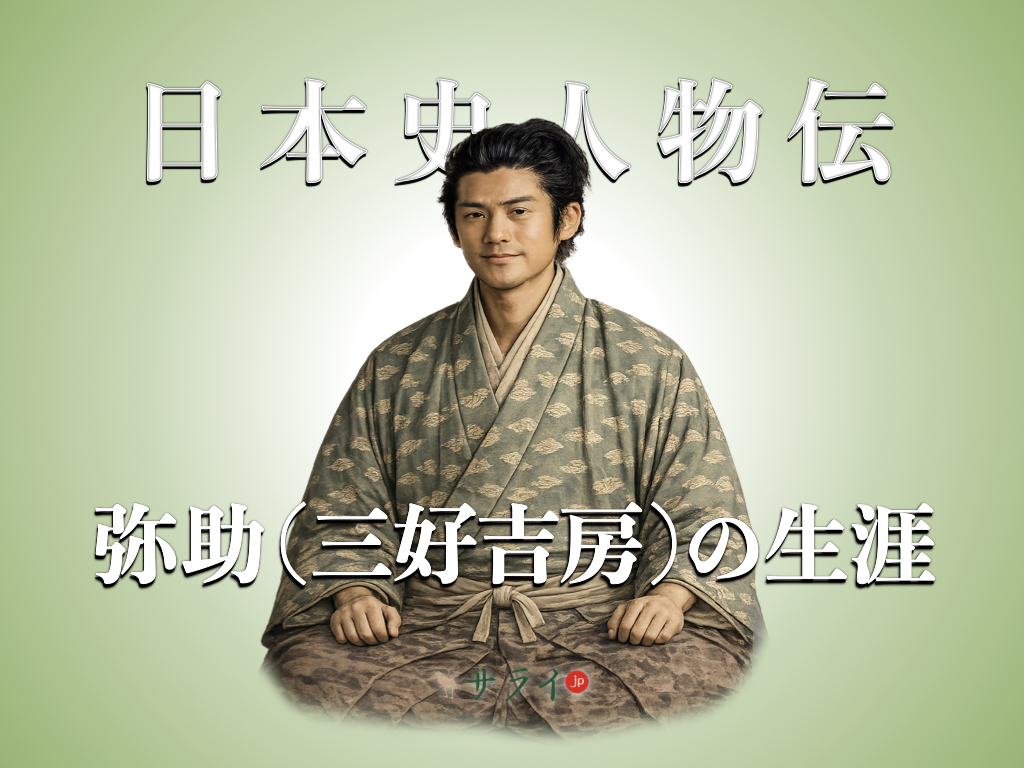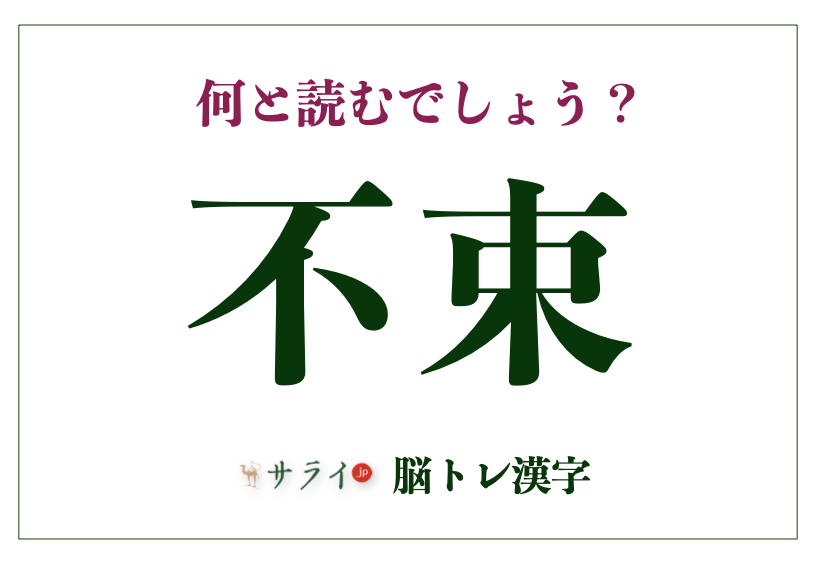マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)」が、ビジネスの最前線の用語や問題を解説するシリーズ。今回は、最近よく耳にするようになった「パープル企業」について解説します。
パープル企業= 居心地は良いが、成長が止まる「ゆるブラック企業」
近年、働き方改革の推進とともに、「パープル企業」という言葉が注目を集めています。残業やハラスメントがなく、人間関係も良好。一見すると理想的な「ホワイト企業」のようですが、その実、明確な目標や評価制度がなく、個人のスキルアップやキャリア成長が期待できない、そんな“ぬるま湯”のような環境は、意欲ある社員の離職を招き、組織全体の競争力を静かに蝕んでいきます。
では、どうすればこのパープル企業化を防ぎ、社員一人ひとりが成長を実感できる強い組織を築けるのでしょうか。本記事では「識学」の観点から、その具体的な方法と、管理職であるマネージャー層が今日から実践できることを解説します。
なぜ「パープル企業」が生まれるのか? 識学観点からの原因
識学では、組織のパフォーマンスが上がらない原因は、ルールや評価、役割における責任の所在などが曖昧なことによって生じる「認識のズレ」にあると考えます。パープル企業化は、まさにこの「認識のズレ」が蔓延した状態と言えます。
・「成長」に対する認識ズレ: 会社は社員に「成果を出すこと」で成長してほしいと考えているのに対し、社員は「仲良く働くこと」「居心地の良い環境にいること」を安定や成長と誤解してしまう。
・「役割・責任」に対する認識のズレ: マネージャーが部下のタスクに過剰に介入し、本来部下が負うべき「結果責任」が曖昧になる。部下は「言われたことだけやればいい」という姿勢になり、自律的な成長が止まる。
・「評価」に対する認識のズレ: 成果ではなく、「頑張り」や「人柄」といった情緒的な要素で評価が行われる。これにより、社員は困難な挑戦を避け、失敗しないように無難に過ごすことが最適解だと考えてしまう。
このようなズレが放置されることで、組織は「仲良しクラブ」と化し、市場の変化に対応できない競争力のない集団、すなわちパープル企業へと陥っていくのです。
パープル企業で働くことのリスク
短期的に見れば、パープル企業は心身ともに楽な働き方ができる魅力的な職場かもしれません。しかし、長期的な視点で見ると、以下のようなリスクが考えられます。
・市場価値の低下:スキルや経験が身につかないため、転職市場での自身の価値が相対的に低下してしまう恐れがある。
・環境変化への適応困難:会社の業績悪化や倒産など、不測の事態が起きた際に、他の環境で通用する能力が不足している可能性がある。
・モチベーションの低下:成長を実感できない環境に長くいると、仕事への意欲や向上心を失ってしまうことにつながりかねない。
パープル企業は、従業員を大切にしているように見えて、結果的にその成長を阻害してしまうという側面を持っています。自身のキャリアを主体的に考え、成長したいと願う人にとっては、慎重に判断すべき職場環境と言えるでしょう。
パープル企業化を防ぐ! 成長組織を作るための5つのポイント
識学の観点から、パープル企業化を防ぎ、成長し続ける組織を構築するためには、以下の5つのポイントが不可欠です。
1. 明確な「ルール」の設定
組織が目指すゴールはどこで、そこに至るまでの評価基準や行動規範は何なのか。これらを具体的かつ明確な「ルール」として言語化し、全社員で共有することが全ての土台となります。この共有されたルールが、社員の行動の拠り所となり、「何をすれば評価されるのか」という迷いをなくします。
2. 「位置」と「役割」の明確化
マネージャーは「管理」、部下は「実行」という、それぞれの「位置」に応じた「役割」と「責任」を明確に分離します。マネージャーはプレイヤーとして現場の仕事に手を出すのではなく、部下が成果を出すための環境設定(目標設定、権限移譲、評価)に徹することが重要です。これにより、部下は自身の役割責任を自覚し、成長機会を得ることができます。
3. 「結果」による公平な評価
社員の評価は、そのプロセスや努力量ではなく、与えられた役割において「どのような結果を出したか」という事実のみで行います。「良い人だから」「頑張っていたから」といった曖昧な評価を撤廃し、結果責任を明確にすることで、社員の意識は成果創出へと向かいます。
4. 「事実」に基づくコミュニケーション
フィードバックは、「良かった」「悪かった」といった主観や感情を排し、「目標に対して、何ができて、何ができなかったのか」という「事実」のみを伝えます。これにより、部下は課題を客観的に認識し、具体的な次のアクションを自ら考えることができるようになります。
5. 成長を促す「責任」と「権限」の明確化
部下を信頼し、「責任」とともに「権限」を明確にします。マネージャーは、部下が失敗を恐れずに挑戦できる環境を作り、もし失敗したとしても、その原因を追求するのではなく、次にどうすれば成功するのかを考えさせることが重要です。この「任せる」という行為が、部下の当事者意識と自己解決能力を飛躍的に高めます。
マネージャーが今日からできる3つのアクション
では、マネージャー層は具体的に何から始めれば良いのでしょうか。以下に、今日からすぐに実践できる3つのアクションをご紹介します。
1. 仕事の「完了定義」を明確に伝える
部下に業務を依頼する際、「何を」「いつまでに」「どのような状態になっていれば完了とするか」を具体的に定義して伝えます。「なるべく早く」「いい感じに」といった曖昧な指示は認識のズレを生む元凶です。完了定義が明確であれば、部下はゴールに向かって迷いなく進むことができます。
悪い例: 「この資料、いい感じにまとめておいて」
良い例: 「〇〇の目的で使うこの資料を、A・B・Cの項目を含めて、明日15時までにドラフト版として提出してください」
2. フィードバックは「事実」だけで行う
まず、設定した目標に対する「事実」を確認することから始めます。「目標達成のために設定した行動は、できた? できなかった?」と問いかけ、事実を部下自身の口から言わせることが重要です。できていない場合は、「なぜ?」と詰問するのではなく、「どうすれば次はできるか?」と未来の行動に焦点を当てた問いかけをしましょう。
3. 安易に「答え」を教えず、「待つ」
部下から「どうすればいいですか?」と質問された際、すぐに答えを教えてはいけません。それは部下から思考する機会を奪う行為です。「あなたはどうすれば良いと思う?」と一度問い返し、部下自身に考えさせる時間を与えましょう。この「待つ」という姿勢が、部下の自律性を育み、マネージャーがいない状況でも成果を出せる人材へと成長させます。
まとめ
識学が目指すのは、決して冷たい組織ではありません。馴れ合いや気遣いといった“ぬるま湯”の居心地の良さではなく、一人ひとりが自らの成長を実感し、その成長が正当に評価され、組織全体の成長に繋がるという、健全で生産的な環境です。
厳しい側面があるかもしれませんが、それこそが社員の「成長したい」という健全な欲求に応え、真のエンゲージメントを生み出します。パープル企業化の兆候を感じたら、まずはマネージャー層から意識と行動を変革し、成長実感にあふれる強い組織への一歩を踏み出してください。
識学総研:https://souken.shikigaku.jp
株式会社識学:https://corp.shikigaku.jp/