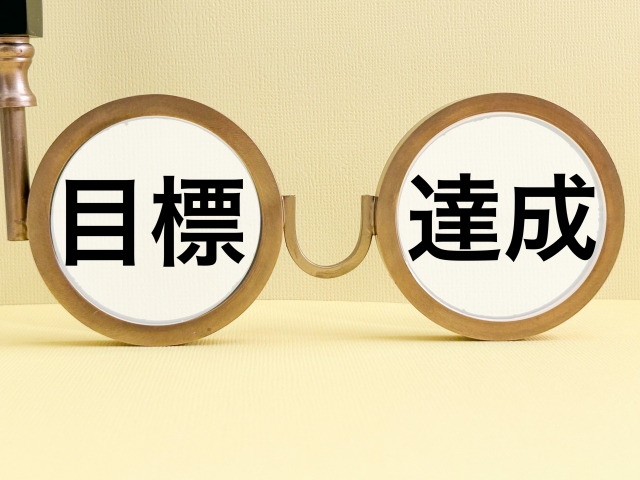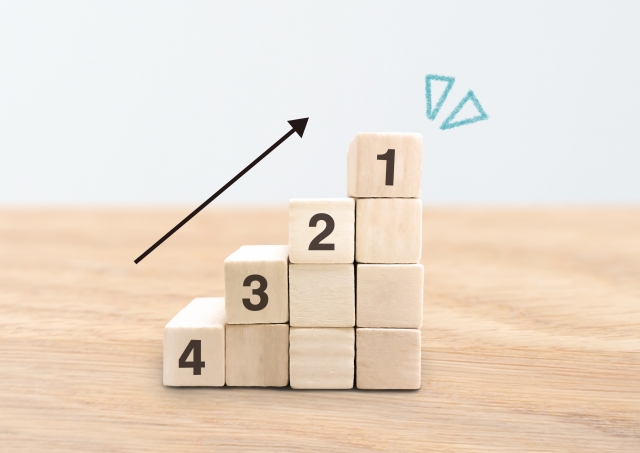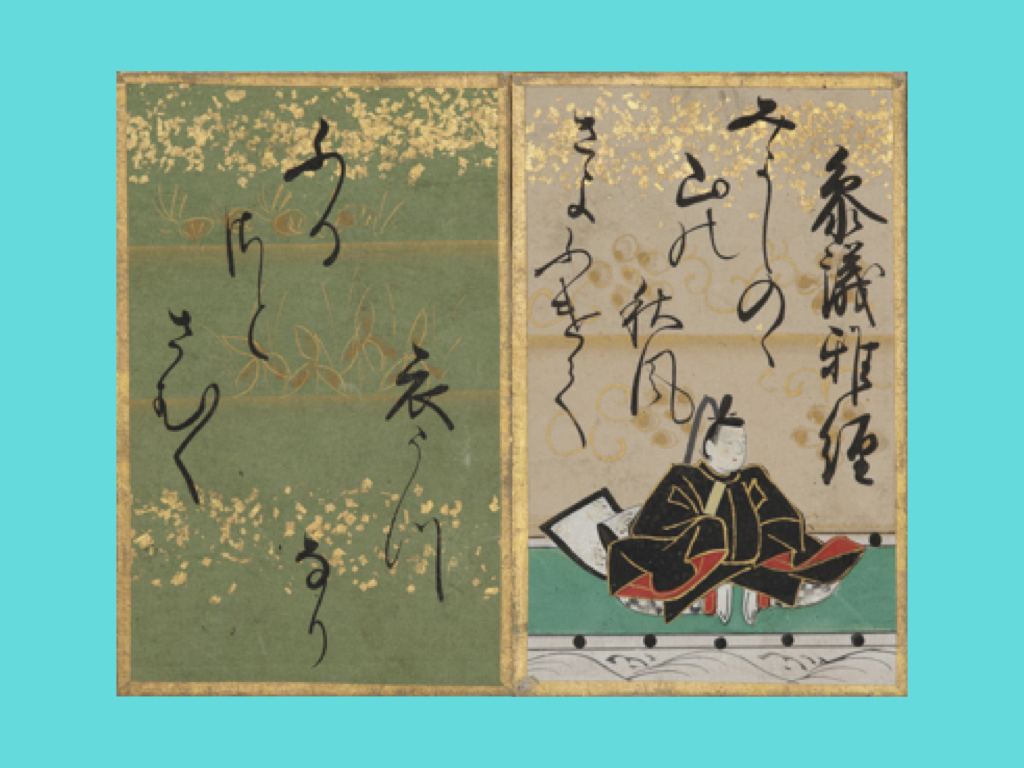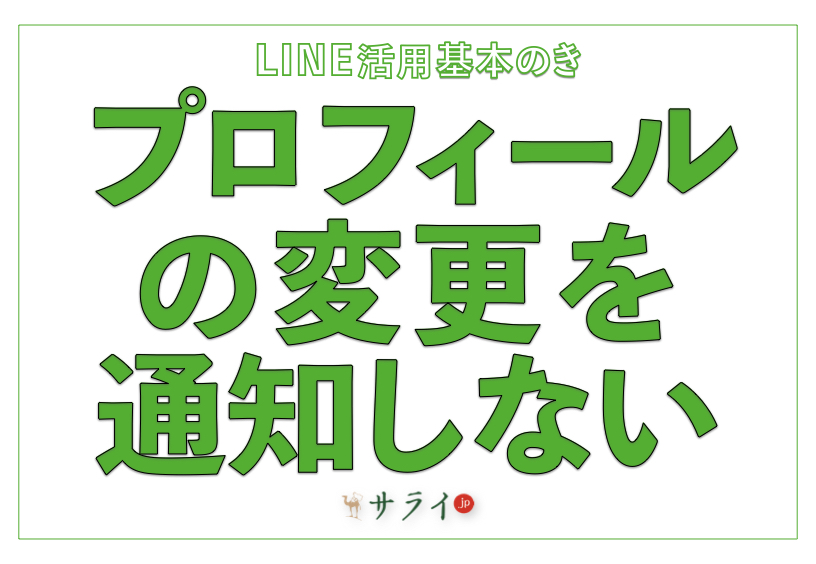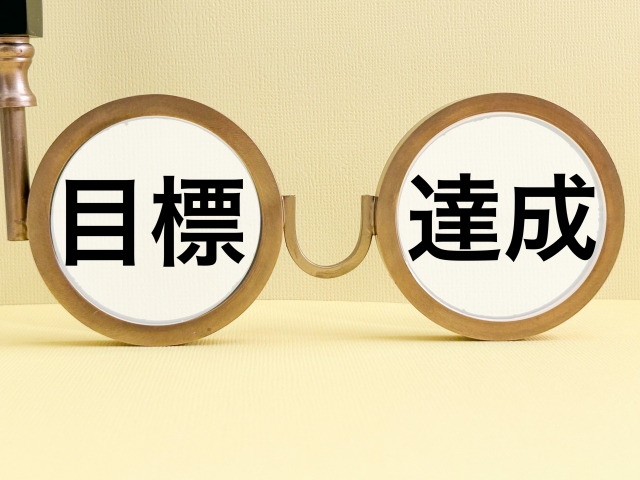
マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)」が、ビジネスの最前線の用語や問題を解説するシリーズ。今回は、部下のマネジメント方法について識学の視点から詳しく解説します。
なぜ部下は集中できないのか? 答えは「あなたのマネジメント」にあり!
ある部下が仕事に集中できず、期待した成果が出せない。同じチーム内には達成できているメンバーがいるので、目標自体は実現不可能ではない。多くのリーダーが直面するこの課題の原因は、部下のやる気や能力不足にあると思っていませんか? 実は、多くのケースでその答えは「上司のマネジメント方法」に隠されています。
そこで、部下の集中力を高め、目的達成に導くための具体的なマネジメント法を、3つのステップに分けて詳しく解説します。
ステップ1:ゴールが見えないマラソンを走らせていませんか?
未達が確定的な部下が集中できていない最も一般的な原因は、目標設定に達成イメージが持てず、何をすべきか分からないことにあります。上司から「もっと頑張ってほしい」「しっかりやってくれ」といった抽象的な指示だけでは、部下は具体的な行動に移せません。これは、ゴールが見えないマラソンを走るようなものです。「一体、あと何キロ走ればいいんだろう?」「何分でゴールすればいいんだろう?」と不安になり、途中で立ち止まってしまいます。
この問題を解決するには、大きな目標が抽象度が高いならば、部下が自力で到達するというイメージができるまで細かく分解することが不可欠です。
例えば、「新商品のオンライン販売を軌道に乗せる」という大きな目的は、登ったこともない山の頂上を目指すようなものです。この大きな山を、「まずは○○までに、5合目まで行く」「次に××を期限に7合目を目指す」といった小さな目標に分けます。具体的な期限と状態をタスクに落とし込むことで、部下は「何を」「いつまでに」やるべきかが明確になり集中しやすくなります。
新商品プロモーションのタスクであれば、以下のように分解できます。
NGな指示:「新商品のプロモーション、もっと頑張ってくれないか?」
効果的な指示:「来週金曜日までに、SNS投稿案を10個作成してほしい。条件は、興味を引く画像付きで。それが終わったら、次は記事の構成を○○までに。」
このように、期限と具体的なタスクをセットで提示することで、部下は得体のしれないプレッシャーではなく、具体的にイメージできる達成可能な目標に向かって動けるようになります。
未達がすでに確定していて集中力を欠いている部下に対しても同様です。そのまま「目標達成が見えないマラソンのゴール」に固執させても集中力は戻りません。上司がその目標をいったんリセットし、即座に行動できるような、非常に簡単な「約束」を再設定しましょう。
この「約束」は、集中力の低下によって減らしている行動量を再び増やすために具体的な行動に紐づけることが鍵です。例えば、「今週、顧客に5件電話をかける」「先月商談した顧客10件にメールを送る」といった、難易度の低いタスクを設定します。
ステップ2:「指示待ち部下」を「考える部下」に変える問いかけをしていますか?
未達が続く部下には、目標を細分化して提示するだけでは成長に繋がりません。逆に、部下の主体性を奪い、上司が常に細部にわたって指示を与えなければ動かない「言われたことだけやる」指示待ち人間に育ててしまいます。
部下からすると、「困って待っていたら上司が助けてくれる」という依存心が生まれたり、「いつも上司の細かな指示通りにやっているのだから成果が出ないのは自分のせいではない」と他責になったりします。このような状況では、部下はますます自分の結果に責任を持たなくなります。
部下の自律性を育てるには、上司は「どうすれば達成できるか」を部下自身に考えさせる必要があります。
NGな指示:「このプロジェクトはこう進めなさい。まずA社の担当者にはこう言って、B社の資料はこの通りに作成しなさい」
効果的なアプローチ:「来週の金曜までの〇〇というゴールに対して、どう進める?」と問いかけ、部下自身に具体的な行動計画を約束させる。
このプロセスを通じて、「どうすれば成果を出せるのか」を部下自身が考える習慣が身につきます。この際に上司は「一生懸命頑張ります」や「意識して進めます」といった曖昧な返答で承認するのではなく、「今週は5件電話します」「来週までに資料を3件作成します」のように、数字を用いて具体的に答えさせることで、部下を行動に集中させ責任感を醸成することができます。
ステップ3:成長機会を潰す「甘えの言い訳」を根絶できていますか?
目標が未達に終わった時、部下は「時間が足りなかった」「人が足りなかった」といった言い訳をしがちです。自分の行動以外に責任があるとした言い訳は、「必ず達成しなければいけない」という責任を正しく感じて動けていない証拠であり、このようなコミュニケーションを続けると「外部環境の理由にすれば、達成できなくても認められる」という甘えを生み出します。
優秀なマネージャーは、この言い訳を未達成の結果の後ではなく、目標設定してスタートする段階で事前に懸念点を洗い出すことを徹底します。
効果的なアプローチ:仕事を始める前に、「今週の目標を達成するにあたって、懸念事項やほしい権限はありますか?」と尋ねる。
これにより、部下は目標達成を阻む可能性のある要因を自ら特定し、上司は事前に解決策を提示したり、打開のための必要な権限を与えたりすることができます。この習慣を繰り返すことで、部下は「言い訳によって責任を免れることはできない」と認識するようになります。
まとめ:上司のマネジメントがチームの未来をつくる
部下が目標を達成できないのは、才能や人間力、経歴の問題ではありません。上司が「期待する結果の期限と状態を明確にする」「どうすれば達成できるか、具体的手段は部下に考えさせる」「目的達成を阻む原因の特定と進捗の確認、フィードバック」という3つのステップを実践することで、部下は集中して仕事に取り組めるようになり、自律的に成果を出せるようになります。
部下の意識を変えるのは部下自身ですが、上司にはそのための環境を整えることが求められます。上司はこの「部下の集中力を高める環境づくりの原則」を日々のマネジメントに取り入れることで、チーム全体のパフォーマンスを向上させることができます。
識学総研:https://souken.shikigaku.jp
株式会社識学:https://corp.shikigaku.jp/