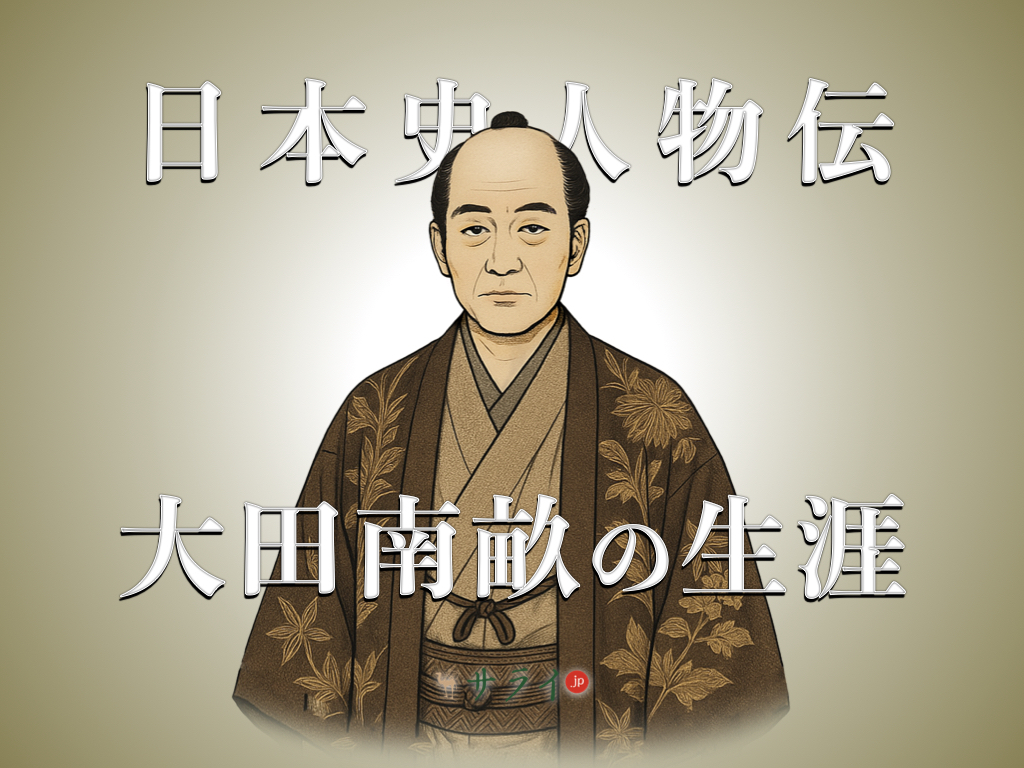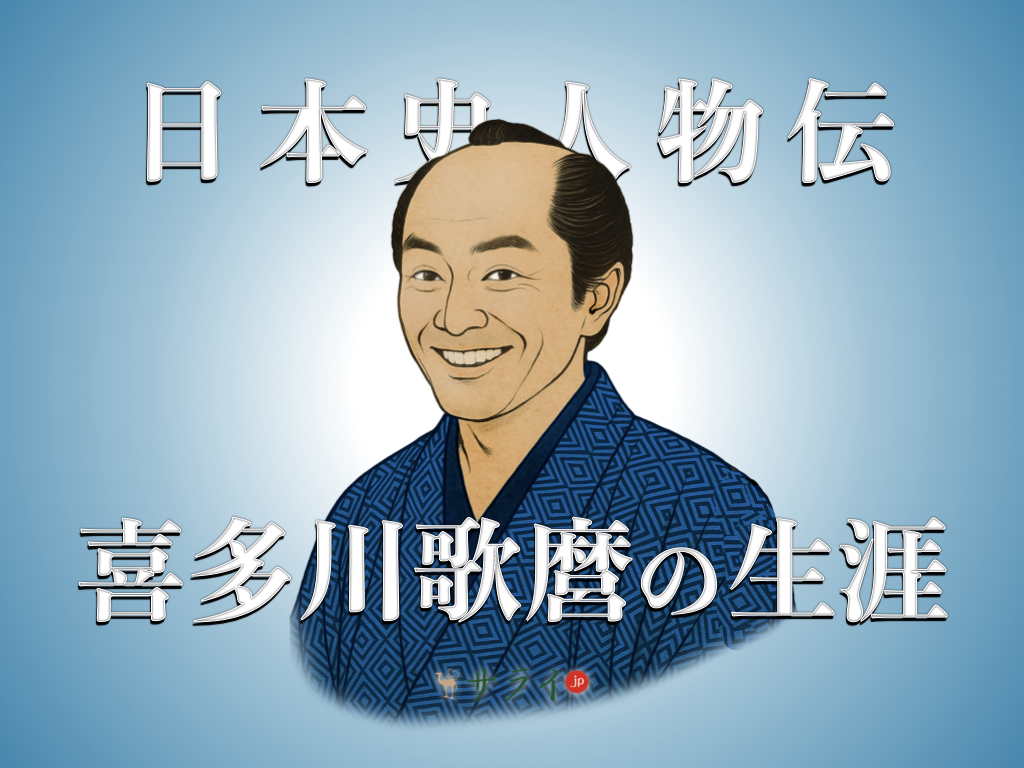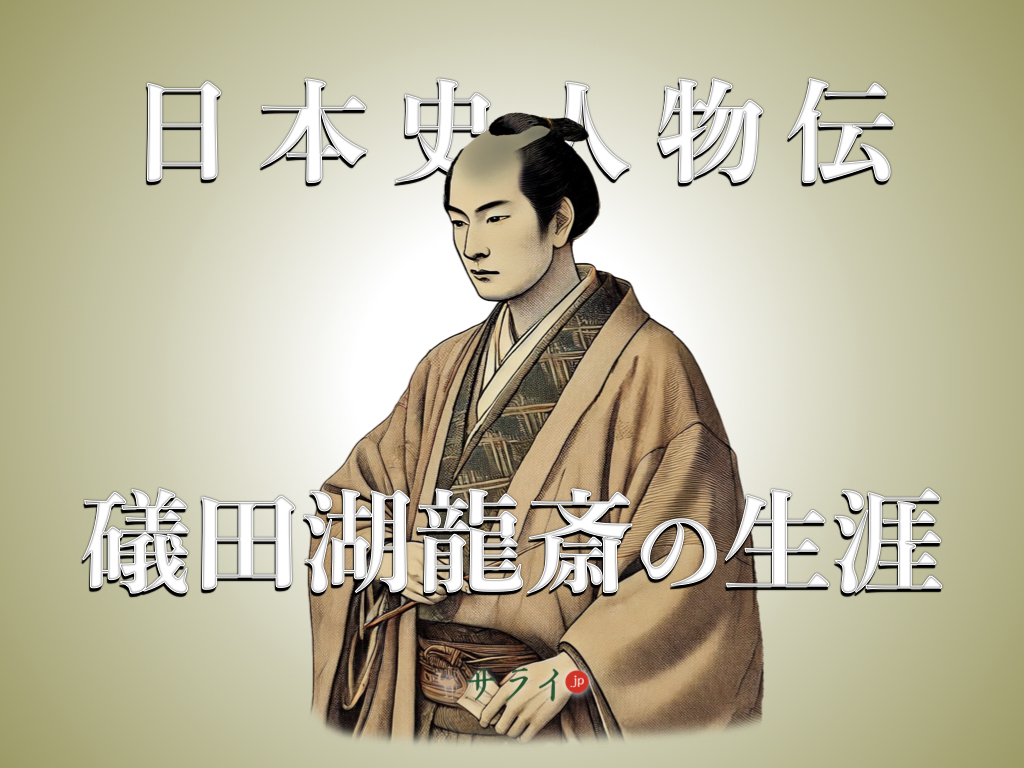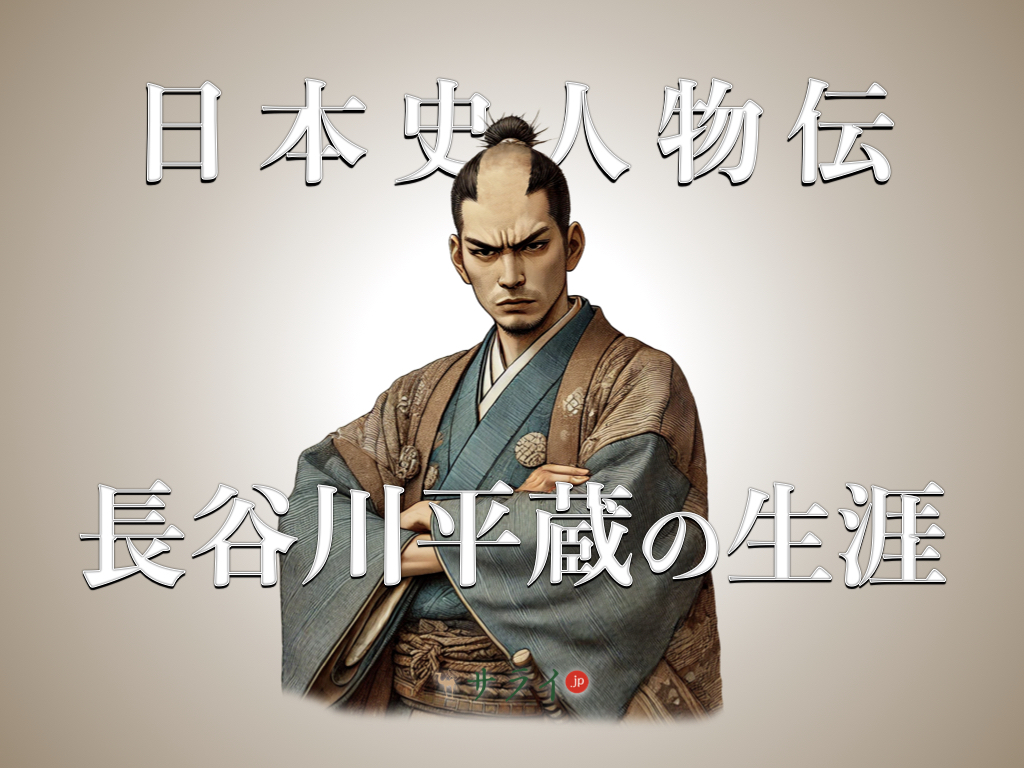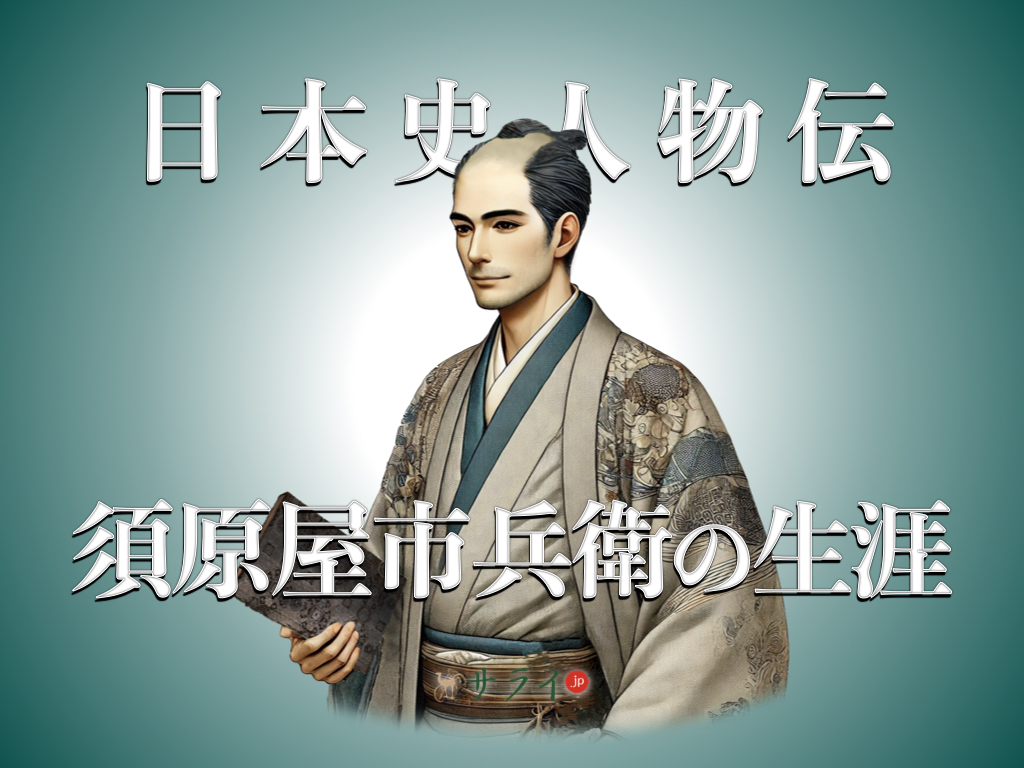はじめに-智恵内子とはどのような人物だったのか
智恵内子(ちえの・ないし)は、江戸時代中期から後期にかけて活躍した女性狂歌師です。夫である元木網(もとの・もくあみ)とともに、天明狂歌の興隆期にその名を知られ、同時代の朱楽菅江(あけら・かんこう)の妻・節松嫁々(ふしまつのかか)と並び称されました。女性として狂歌界の表舞台に立ったその存在は、江戸の文芸界においてひときわ輝きを放っています。
そんな智恵内子ですが、実際にはどのような人物だったのでしょう。史実をベースに紐解きます。
2025年NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、天明期の女性狂歌師(演:水樹奈々)として描かれます。

目次
はじめに-智恵内子とはどのような人物だったのか
智恵内子が生きた時代
智恵内子の生涯と主な出来事
まとめ
智恵内子が生きた時代
智恵内子が生きた18世紀後半は、狂歌文化が江戸で爆発的に広まり、いわゆる「天明狂歌」と呼ばれる黄金期を迎えた時代です。町人文化が成熟し、機知と教養を備えた文芸が好まれるなかで、狂歌もまた庶民の知的遊戯として親しまれていました。
唐衣橘洲(からごろも・きっしゅう)、四方赤良(よもの・あから、大田南畝のこと)、朱楽菅江、平秩東作(へづつ・とうさく)といった錚々たる人物が活躍したこの時代、女性である智恵内子が脚光を浴びたことは注目に値します。
智恵内子の生涯と主な出来事
智恵内子は延享2年(1745)に生まれ、文化4年(1807)に没しました。その生涯を、出来事とともに紐解いていきましょう。
夫とともに歩んだ江戸狂歌の黎明期
智恵内子は延享2年(1745)に生まれました。名は「すめ」といい、江戸後期を代表する狂歌師・元木網の妻でもあります。明和6年(1769)、夫の木網が初期の江戸狂歌壇に加わった頃から、内子もともに狂歌を詠むようになりました。
天明元年(1781)には、夫婦そろって隠居し、芝西久保土器町に「落栗庵」を構えます。ここを拠点に狂歌の指導にあたり、弟子たちは江戸中に広がっていきました。「江戸中はんぶんは西の久保の門人だ」(『狂歌師細見』)とまで評されるほどで、その存在感の大きさがうかがえます。
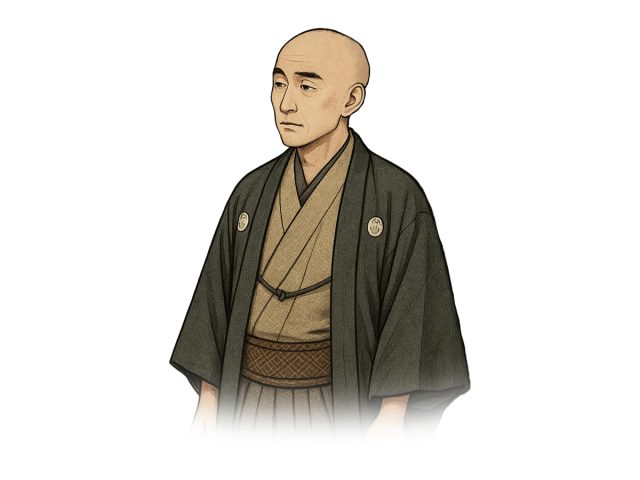
【知性と機知で名を成した女流狂歌師。次ページに続きます】