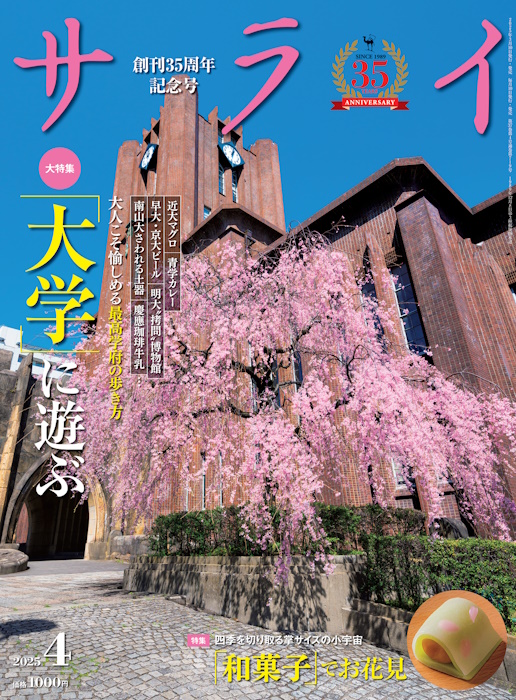早稲田大学|明治19年から始まった「校外教育制度」の伝統を継ぐ

規模も内容も、最も充実しているのが早稲田大学だ。資格に直結する専門職大学院や、実践的なビジネススキルを養成する履修証明プログラムに加え、公開講座は年間約1800講座を準備している。
「早稲田の社会人教育の歴史は建学のときまで遡ります」と解説するのは同大エクステンションセンター事務長の小泉邦人さん。
「明治15年(1882)に東京専門学校として創設され、その4年後から校外教育が始まりました。大学に通うのが困難な時代に“大学の知”を開放することを目的としたもので、『講義録』の発行や『巡回講話』も行なわれました」
講義録は、現在の通信教育に近く、その後『早稲田講義録』として全国、海外にも届けられた。受講者には、早稲田大学元総長の田中穂積や歴史学者の津田左右吉、元首相の田中角栄らがいたという。
教員が全国に赴いて講義をする巡回講話は、明治26年(1893)に始まり、それが公開講座である「オープンカレッジ」として受け継がれている。現在は、早稲田と中野のふたつのキャンパスで開講され、令和5年度には延べ2万9000人以上が受講した。
テーマは文学、歴史、芸術、現代社会など9つのジャンル。「仏教聖典の核心を読み解く」「巨大都市江戸の娯楽遊芸誌考」といった講座が目を惹く。また、会員(入会金8000円)になると各種特典も受けられる。

履修証明プログラムでも新たな試みを開始。令和4年度からの「Life Redesign College」だ。人生100年時代を視野に“自分らしいこれからの生き方を再設計する”という年間プログラムだ。対象は50歳以上で、同大日本橋キャンパスで実施される。
「本学の名誉教授が教官となり、ゼミナール形式で進める授業もあります。“第二の青春”を謳歌してもらうべく、サークル活動も盛ん。定員を大幅に超える応募をいただくため、拡充も検討中です」
早稲田の校外教育の伝統に、大きな流れが加わろうとしている。

名称:早稲田大学オープンカレッジ
講座数:約1800講座
料金:1講座6831円(会員5940円)~
場所:早稲田校(東京都新宿区西早稲田1-6-1)、中野校(東京都中野区中野4-22-3 早稲田大学
中野国際コミュニティプラザ)
特典:中央図書館利用、各種割引ほか(会員のみ)
申込期間:3月4日より先着順(会員先行期間あり)
問い合わせ:早稲田大学エクステンションセンター 電話:03・3208・2248
※料金は定期講座の対面方式。無料や割安なオンライン講座もある。
明治大学|無料で参加できる「特別企画」も豊富

大学の知的財産を社会に還元する目的で、平成11年に開設されたのが「明治大学リバティアカデミー」だ。生涯学習の拠点として、「教養・文化」「ビジネスプログラム」を中心に多彩な講座を提供している。たとえば令和6年度は、「神社と祭りの日本精神史」「古墳時代の最前線」「日本書紀の世界」といったテーマが開講された。
また、特別企画として、1回完結の無料講座を多彩なジャンルで実施。ホールで開講されるものが多く、入門的な講座として参加しやすい。令和6年度の「レクチャーコンサート ルイ14世時代の宮廷文化と音楽」と題した特別企画は、クラシックの演奏家や歌手を講師に招いて実演を披露し、大好評を博した。
名称:明治大学リバティアカデミー
講座数:約320講座
料金:1コマ3300円
場所:駿河台キャンパス(東京都千代田区神田駿河台1-1)
特典:特になし
申込期間:3月3日より先着順
問い合わせ:明治大学リバティアカデミー事務局 電話:03・3296・4423
東京藝術大学|美術や工芸、音楽の実技を習得できる

国内唯一の国立総合芸術大学である東京藝大の前身は、明治20年(1887)に発足した東京美術学校と東京音楽学校。公開講座は、同大の教育、研究を社会に開放し、社会人の芸術に関する教養を高め、芸術文化の向上に資することを目的とする。そのため、他大学では珍しい美術や工芸の講座が開講されている。
令和6年度は上野キャンパスで「楽茶碗を作ろう」「油画講座 素材の探求」「版画~木版画実技~」「漆芸装飾技法初級編」「彫刻(大型石膏像)をデッサンしよう」といった講座が実施された。同大美術学部は取手キャンパス(茨城県)にもあり、こちらでは、金継ぎや七宝、吹きガラスといった、工芸の講座が多く開かれている。
名称:東京藝術大学公開講座
講座数:約70講座
料金:1講座2500円~
場所:上野キャンパス(東京都台東区上野公園12-8)、千住キャンパス(東京都足立区千住1-25-1)、取手キャンパス(茨城県取手市小文間 5000)
特典:特になし
申込期間:講座により異なる
問い合わせ:東京藝術大学社会連携課 電話:050・5525・2031