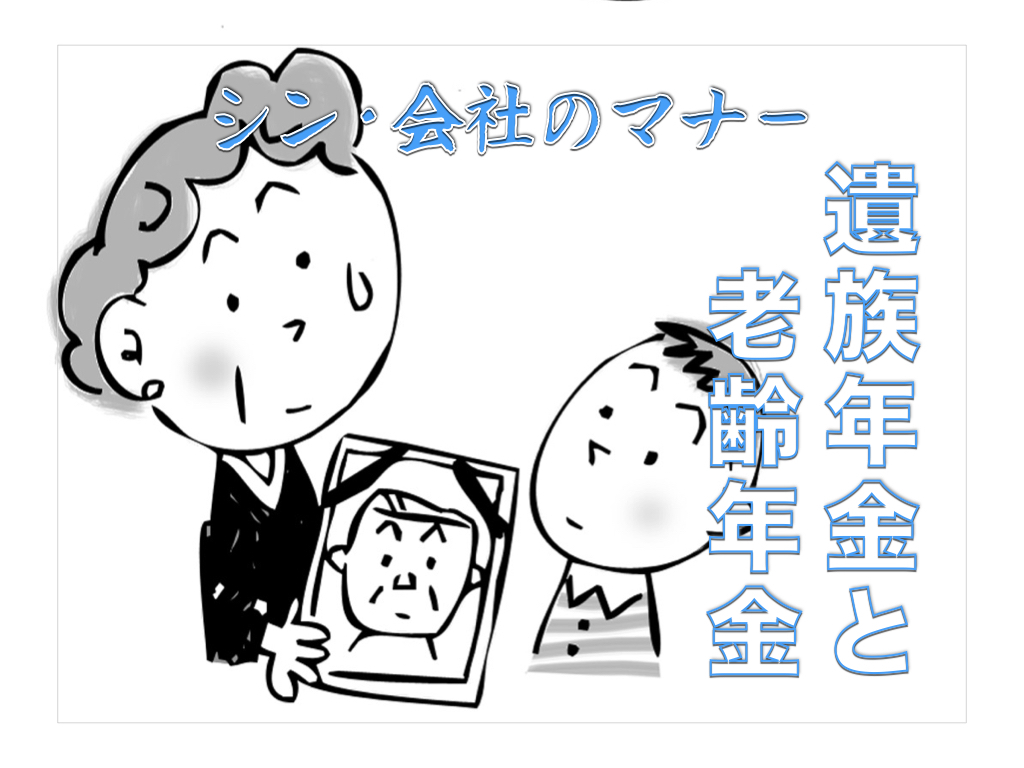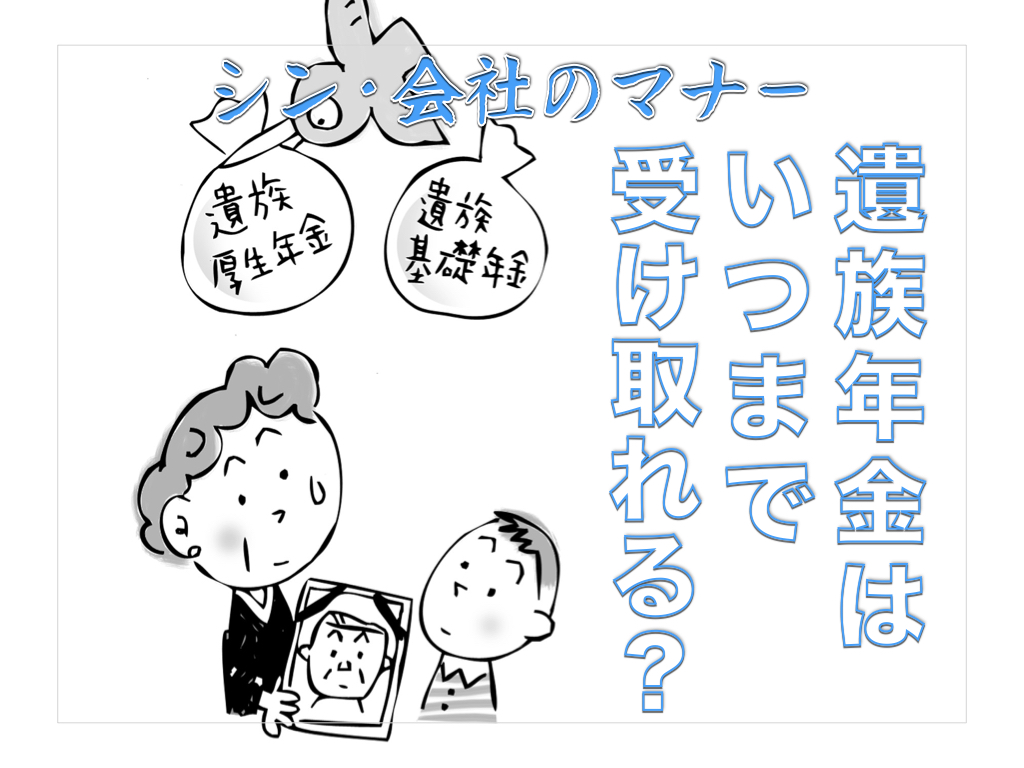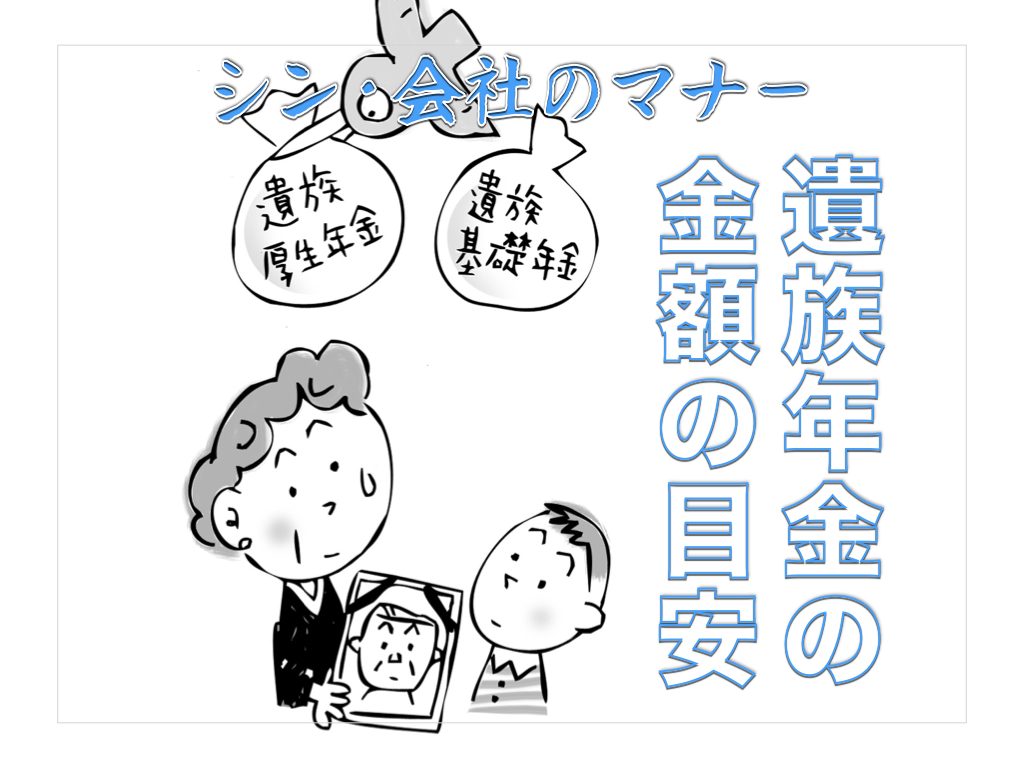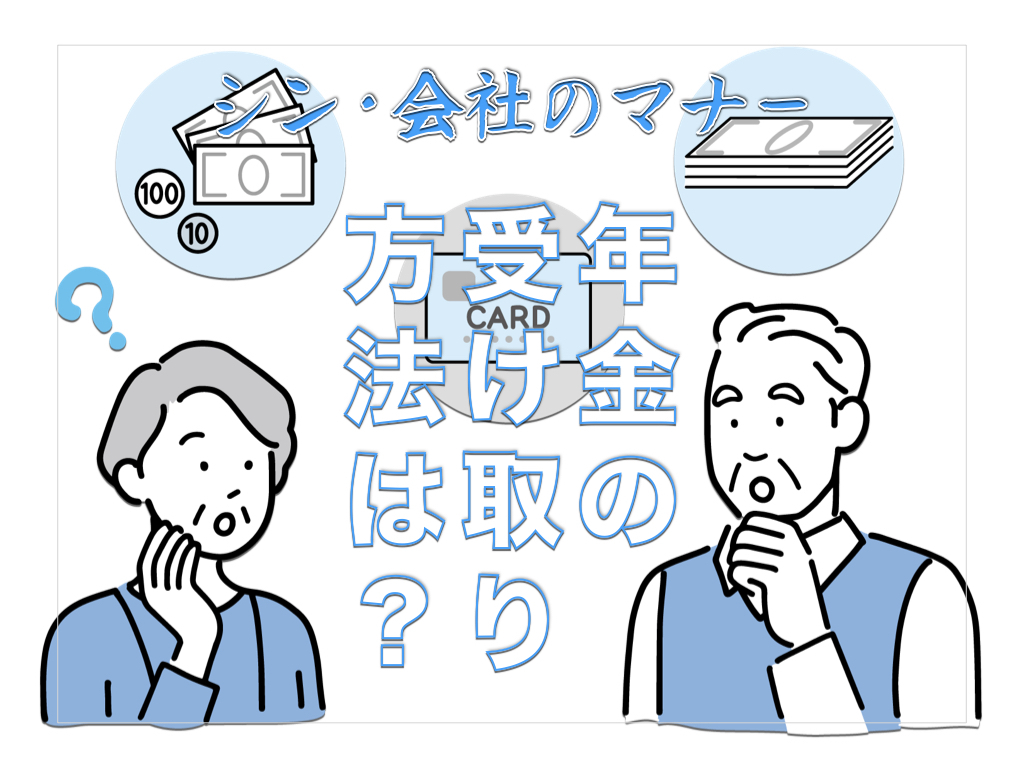離婚したくても、老後の生活が不安でできないという人は一定数いると思います。離婚した後、夫婦の年金は分割することが可能です。この年金分割の請求は一人でも手続きすることができるのでしょうか? 今回は、年金の分割の手続きを中心に、人事・労務コンサルタントとして、「働く人を支援する社労士」の小田啓子が解説していきます。
目次
年金分割とは?
年金分割の手続きは一人でできるのか?
年金分割手続きに必要な書類と提出方法
年金分割の注意点・デメリットとメリット
まとめ
年金分割とは?
年金の分割請求をするためには、年金分割とはどういうものか、制度の内容について見ていきましょう。
年金分割の基本的な概念を説明
離婚する時は、夫婦の共有財産は分けることが一般的です。年金はどうでしょうか? 年金も夫婦で分けあうことができることを知らない人は少なくありません。年金分割制度は、結婚生活で築いた財産は夫婦二人のものであるという考え方に基づいています。
たとえ働き手が夫だけであっても、婚姻期間中の収入で計算された年金は、離婚時に二人で分け合うことができるのです。この制度は、平成19年4月以降の離婚から適用されるようになりました。分割の対象となるのは、婚姻期間中の厚生年金記録です。国民年金は分割の対象になりません。
年金分割の対象となるケース
年金分割制度は二つあります。一つは合意分割制度です。婚姻期間中に厚生年金に加入していたことがある場合、加入期間中の二人の年金記録を当事者間で分割できる制度です。これは婚姻していた全期間が対象になります。
厚生年金の支給額は給与・賞与などの標準報酬で計算されますが、この制度を利用すると、給与収入の差が大きい夫婦だとしても、二人の標準報酬を合算して任意の割合で分け合うことが可能になります。なお、按分割合が話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所が決定します。
もう一つの制度は3号分割制度です。これは国民年金の第3号被保険者の人の請求により、配偶者の年金を当事者間で2分の1ずつに分割できる制度です。第3号被保険者というのは、厚生年金に加入している人に扶養されている配偶者を指します。対象となる期間は平成20年4月1日以降第3号被保険者であった期間です。なお、3号分割制度は相手の合意は必要ありません。
年金分割の手続きは一人でできるのか?
年金分割ができるのは離婚をした後ですが、この請求は一人でもできるのでしょうか? 年金分割の手続きについて見ていくことにします。
年金分割の手続きは一人で可能?
離婚を考えたとしても、相手の年金がいくらなのか、どう分割されるのかわからないと不安ですね。離婚する前であっても、分割の対象期間の年金の納付記録などの情報提供を求めることができます。年金事務所で情報請求の手続きをすると、日本年金機構から「情報通知書」が送られてきます。年金の分割は、「標準報酬改定請求書」を年金事務所に提出することによって行われます。
請求は一人でも可能ですが、話し合いで合意分割する場合、夫婦二人そろって年金事務所に按分割合の合意書を持参しなければなりません。基本的には、それぞれが2分の1ずつになることを限度として報酬の高い方から低いほうに報酬を分けるかたちで分割されます。話し合いで合意できなかった場合は、裁判所の決定した按分割合で分割することになります。
一方、3号分割の場合、合意は必要ありません。第3号被保険者であった人の請求により、相手の厚生年金の保険料納付記録は2分の1ずつに分割されます。分割できるのは平成20年4月以降の第3号被保険者期間に限られます。なお、合意分割の請求を行なった期間に3号分割の対象となる期間が含まれる場合は、同時に3号分割の請求があったものとみなされます。

年金分割手続きに必要な書類と提出方法
年金分割の手続きをする際には、年金事務所で「標準報酬改定請求書」を入手し、下記の書類を添付して提出します。
(1)請求日前1か月以内に交付された夫婦二人の生存を証明できる書類。戸籍謄本、抄本、住民票など。
請求書にマイナンバーを記入することで省略できます。
(2)婚姻期間を証明する書類
(3)話し合いで按分割合を決めたときは公正証書など。
裁判で決めた場合は審判書、調停調書の謄本、抄本。3号分割の場合は二人の合意は必要ないので、(3)の書類は不要となります。3号分割、裁判所が按分割合を決定した合意分割の場合は、郵送で提出することも可能です、手続きが完了すると「標準報酬改定通知書」が送られてきます。年金は改定後の報酬で計算された額になります。
年金分割の注意点・デメリットとメリット
続いて、年金分割の注意点を見ていきましょう。
自分で手続きを進める際の注意点
離婚するための準備としては、情報請求により年金納付の状況を確認することが重要です。相手方が国民年金の加入歴しかない場合は、分割を受けることはできません。標準報酬の分割を受けた期間は、厚生年金の被保険者であった期間とみなされます。すでに老齢厚生年金を受給している人はどうなるのでしょうか?
この場合は、標準報酬の改定が行なわれた翌月から年金額が改定されます。注意が必要なのは、振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している場合です。分割を受けた結果、自分の厚生年金加入期間が240か月以上になると振替加算はなくなります。
また、分割を受ける人が、年金の未納などで公的年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていない場合もあります。年金分割を受けた期間は、受給期間を満たすための月数にはカウントされません。なお、年金分割の請求は離婚後2年を過ぎるとできませんので、その点も知っておきましょう。
年金分割のメリット・デメリット
離婚時の年金分割は、報酬の多い方から少ない方に分割されることになるので、当然報酬の多い側はデメリットが大きいと感じるでしょう。分割を受ける側にもまったくデメリットがないとは言えません。分割する割合がなかなか合意できないと、裁判が長引くなど負担が大きくなることもあります。
とはいえ、年金分割は、収入の少ない側の離婚後の生活不安を軽減する意味でも、大きな助けになる制度です。分割を受ける側は、家事・育児の負担が年金の分割というかたちで金銭として評価されるメリットがあります。
まとめ
自分の年金は、自分だけのものと考える人は少なくありません。けれども、結婚生活は二人の協力のもとに成り立つものです。年金分割制度は、婚姻期間中の夫と妻の経済的貢献を公平に評価する制度です。この制度を知ることは、夫婦というものについて、改めて考えるよい機会になるかもしれません。
●執筆/小田 啓子(おだ けいこ)

社会保険労務士。
大学卒業後、外食チェーン本部総務部および建設コンサルタント企業の管理部を経て、2022年に「小田社会保険労務士事務所」を開業。現在人事・労務コンサルタントとして企業のサポートをする傍ら、「年金とライフプランの相談」や「ハラスメント研修」などを実施し、「働く人を支援する社労士」として活動中。趣味は、美術鑑賞。
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com