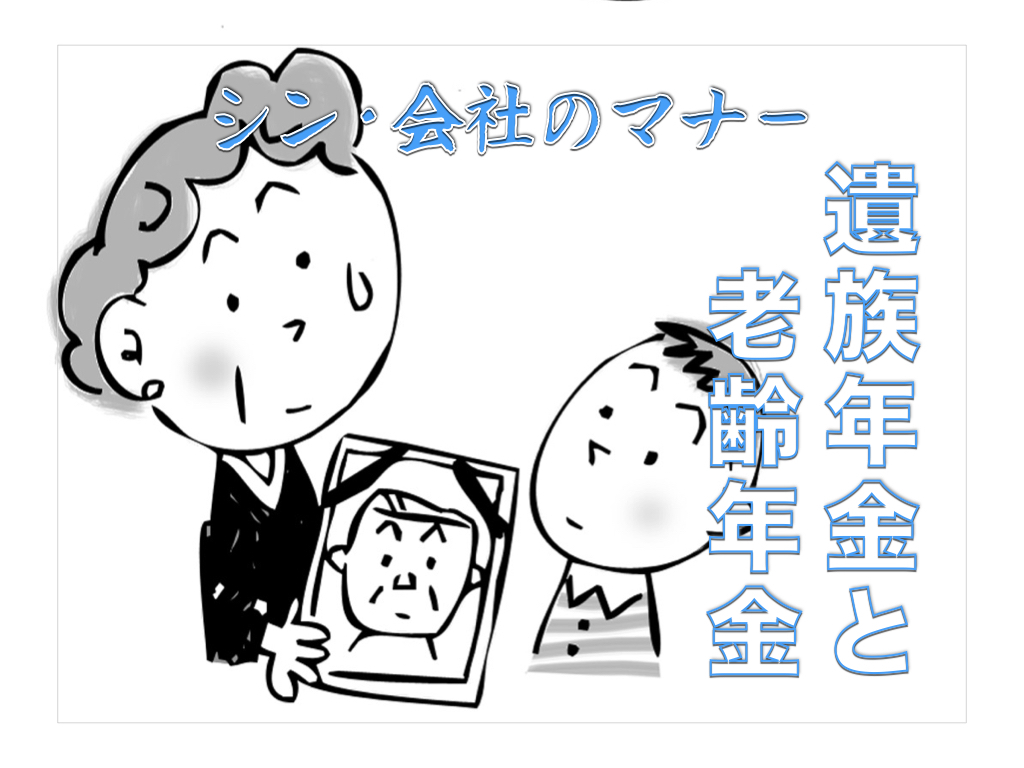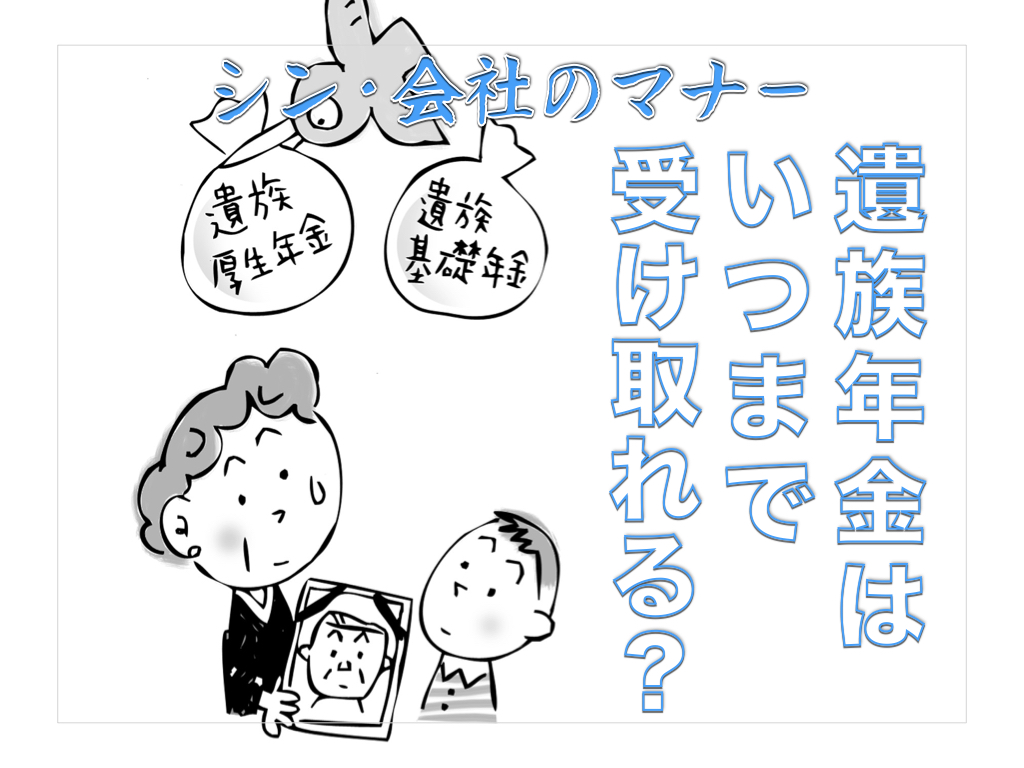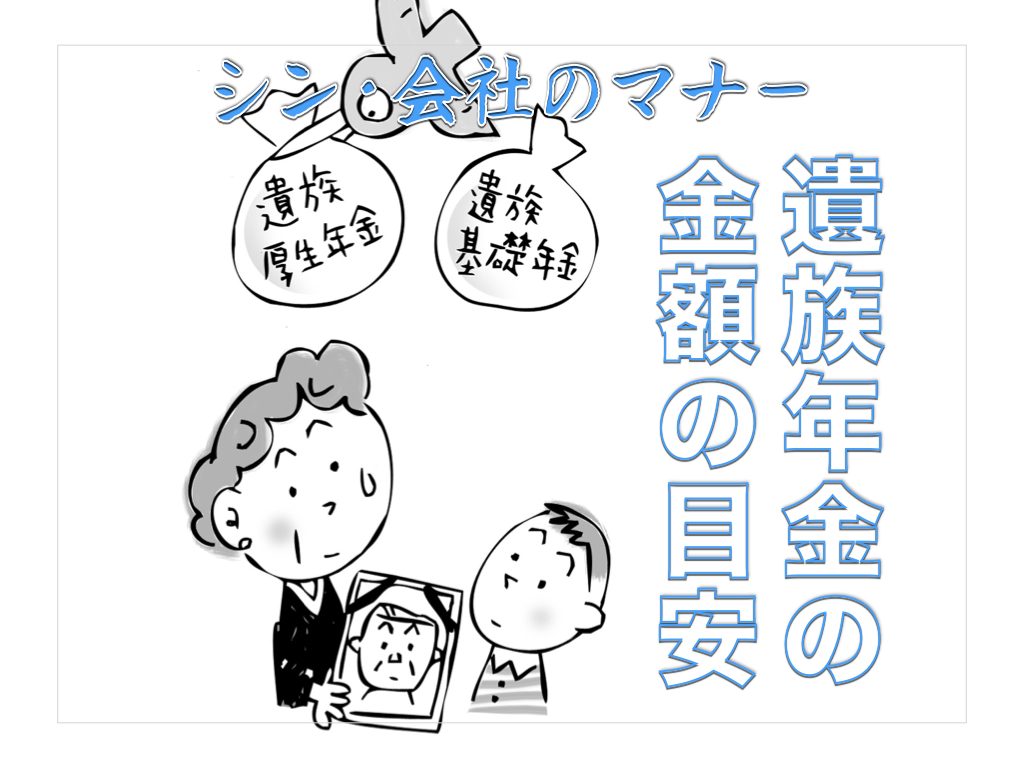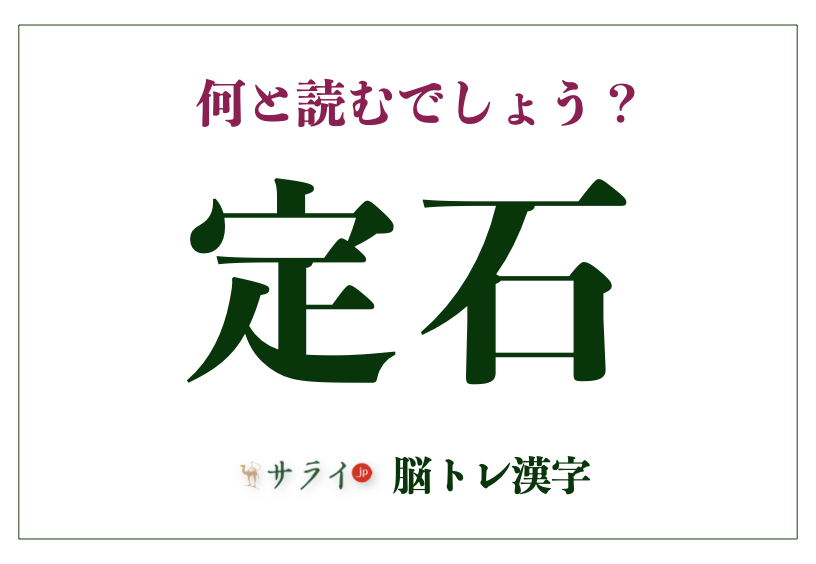仕事をリタイアした後、老後の生活の支えとなるのはやはり年金です。もしも家族が亡くなったとしたら、遺族年金と自身の老齢年金は同時に受給することはできるのでしょうか? 今回は、遺族年金と老齢年金の併給について、人事・労務コンサルタントとして「働く人を支援する社労士」の小田啓子が解説していきます。
目次
遺族年金と老齢年金の基本概要
遺族年金と厚生年金の違いと併給の可否
遺族年金と老齢年金を両方もらえる場合の条件
遺族年金の計算方法と金額の目安
まとめ
遺族年金と老齢年金の基本概要
基本的に、年金は2階建て構造になっています。1階部分は、全国民が対象の国民年金、2階部分は会社員などが加入している厚生年金です。この2つの制度にはそれぞれ、被保険者の老齢、障害、死亡に対応する年金があります。今回は、老齢年金と遺族年金に焦点をあてて見ていきます。
遺族年金とは?
遺族年金は、被保険者や年金受給者が亡くなったとき、残された家族の生活を支えることを目的としています。国民年金の遺族基礎年金は、受給できる遺族の範囲が狭く、年齢など一定の条件に該当する子のいる配偶者と子のみとなっています。
遺族厚生年金は、子のない配偶者でももらえますが、配偶者が夫の場合は55歳以上でないと受給資格はありません。妻の場合でも、30歳未満の子のない妻、または30歳未満で遺族基礎年金を受け取る権利がなくなった妻の遺族厚生年金は5年間のみの給付となっています。
老齢年金とは?
国民年金の老齢基礎年金は、加入月数に応じた定額、老齢厚生年金はその人の加入月数と報酬に比例して支給される年金です。自営業者など、国民年金のみ加入している人は国民年金の第1号被保険者と呼ばれており、老齢基礎年金の受給対象者となります。
会社員・公務員など、適用事業所に雇用されている人は第2号被保険者です。この人たちは、老齢基礎年金に上乗せされる形で老齢厚生年金を受け取ることができます。さらに、国民年金には、第3号被保険者という種別もあります。第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者であり、保険料の支払いは免除されています。老齢年金は、一部の人を除いて基本的に65歳からの支給になります。
遺族年金と厚生年金の違いと併給の可否
老齢年金受給者の家族が亡くなり、遺族年金の権利も得たとしたらどうなるのでしょうか? ここでは、年金の併給について解説します。
遺族年金と老齢年金の受給資格
老齢年金は、国民年金に加入していた人は1階部分の老齢基礎年金を、厚生年金にも加入していた人は、2階部分の老齢厚生年金も併せて受け取ることができます。老齢年金を受け取るための条件は、国民年金の保険料納付期間と免除期間を合算して10年以上あることが条件です。
老齢厚生年金は1か月でも厚生年金の加入期間があれば、その期間の報酬に応じて年金を受給することができます。一方、遺族基礎年金、遺族厚生年金を受給するためには、亡くなった人の保険料納付期間と免除期間の合算が25年以上あることが条件となっています。
そのほか、遺族年金は子の有無や年齢などのいくつかの条件が設けられており、受給者の年収が一定以下(850万円以下)であることなどの基準もあります。自身の老齢年金を受け取る場合は、年齢や年収などの制限はありません。
遺族年金と老齢年金の併給は可能か?
公的年金制度には「1人1年金の原則」が設けられています。同じ人に二重の所得保障を行なうと、不公平が生じるからです。したがって、複数の年金の受給資格を満たしていたとしても、2つ以上の年金をもらえるとは限りません。ただし、同一の支給事由に基づいている年金は併給されます。
「老齢厚生年金と老齢基礎年金」「遺族厚生年金と遺族基礎年金」などがこれに当たります。それでは、老齢と遺族という異なる事由による年金は、併給できないのでしょうか? これについては特例があり、65歳以上の受給権者に限っては、遺族厚生年金と老齢基礎年金、老齢厚生年金を併給することができます。国民年金の遺族基礎年金は、老齢基礎年金や老齢厚生年金と同時に受け取ることはできません。

遺族年金と老齢年金を両方もらえる場合の条件
複数の年金を同時にもらえるケースは、限られています。年金の併給についてもう少し詳しく見ていきましょう。
両方受給できるケース
老齢年金と遺族年金を併給するためには、受給者が65歳以上であることが条件です。65歳以上の人の多くは、自身の老齢基礎年金を受け取る権利がありますが、同時に遺族厚生年金を受け取ることも可能です。
老齢厚生年金はどうでしょうか? この場合は老齢厚生年金の受給が優先され、遺族厚生年金は自身の老齢厚生年金に相当する額が支給停止になります。つまり、老齢厚生年金より遺族厚生年金のほうが高い場合は、事実上、遺族厚生年金のみを受け取る場合と金額は同じになります。
選択を迫られるケース
遺族厚生年金は、原則として亡くなった人の老齢厚生年金の4分の3の金額です。悩ましいのは、自身の老齢厚生年金との差額分しか支給されないことですね。自身の老齢厚生年金のほうが高い場合は、遺族年厚生年金は支給されないことになります。
また、65歳以上の配偶者の場合は特例として、原則の計算式で求めた遺族厚生年金の3分の2と自分の老齢厚生年金の2分の1を足した金額を選択することも可能です。どちらが高いのかわからないという人もいるでしょう。実際の支給は、金額が最も高くなるよう計算された金額になります。
遺族年金の計算方法と金額の目安
遺族年金と老齢年金と併給したら、どのくらいの年金額になるのでしょうか? 具体的な金額を計算してみましょう。
遺族年金と老齢年金を併給する場合の計算
年金額の目安を計算するにあたり、遺族年金の受給対象者を65歳以上の妻と仮定します。ここでは、原則と特例の2種類の計算式を用いて、妻がもらえる月当たりの年金額を実際に計算してみましょう。
参考例)
夫の老齢厚生年金 12万円/月
妻の老齢基礎年金 6万円/月
妻の老齢厚生年金 8万円/月
(1)原則の式の遺族厚生年金+老齢基礎年金
12万円×4分の3=9万円
9万円+6万円 =15万円
(2)原則の式の遺族厚生年金×3分の2+老齢厚生年金×2分の1+老齢基礎年金
9万円×3分の2+8万円×2分の1=10万円
10万円+6万円=16万円
参考例の妻の年金は、(2)の特例の計算式のほうが受給額は多くなります。
申請の手続きと注意点
遺族年金も、老齢年金も請求をしないと受け取ることができません。老齢年金は受給資格年齢になると、年金の請求書類一式が届きます。遺族年金は、年金事務所や街角年金相談センターで年金請求書を入手しましょう。必要書類をそろえて年金の請求を行なうと、2か月程度で年金証書が送られてきます。
実際に年金が振り込まれるまでは、さらに1か月から2か月かかります。請求する期限は5年間です。遺族年金には支給停止、失権という制度があり、婚姻した場合などは権利が消滅します。また、老齢年金を繰り上げて受給している場合でも、65歳になるまで遺族厚生年と併給することはできないので注意が必要です。
そのほか、場合によっては年齢などによる制限もあるので、受給資格についてはしっかり確認しましょう。
まとめ
遺族年金は、支給停止や失権などのルールがある上に計算も複雑です。金額の目安がわからない場合は、年金事務所などに相談してみましょう。平素から年金に興味を持ち、老後の生活を予測してみることも大切です。
●執筆/小田 啓子(おだ けいこ)

社会保険労務士。
大学卒業後、外食チェーン本部総務部および建設コンサルタント企業の管理部を経て、2022年に「小田社会保険労務士事務所」を開業。現在人事・労務コンサルタントとして企業のサポートをする傍ら、「年金とライフプランの相談」や「ハラスメント研修」などを実施し、「働く人を支援する社労士」として活動中。趣味は、美術鑑賞。
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com