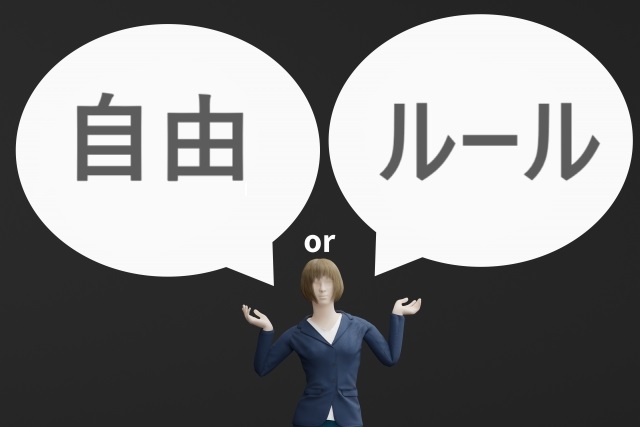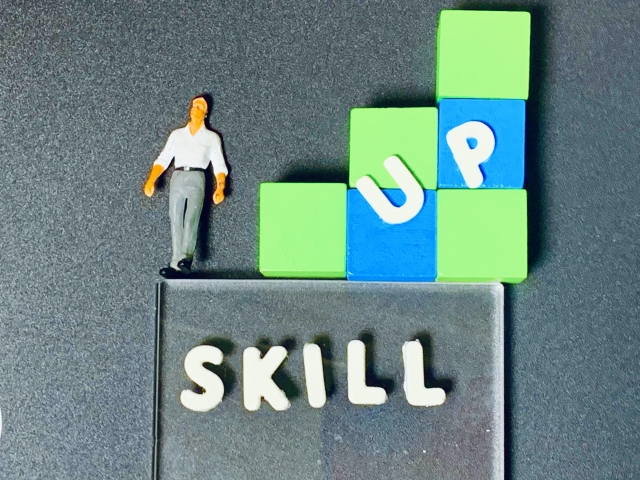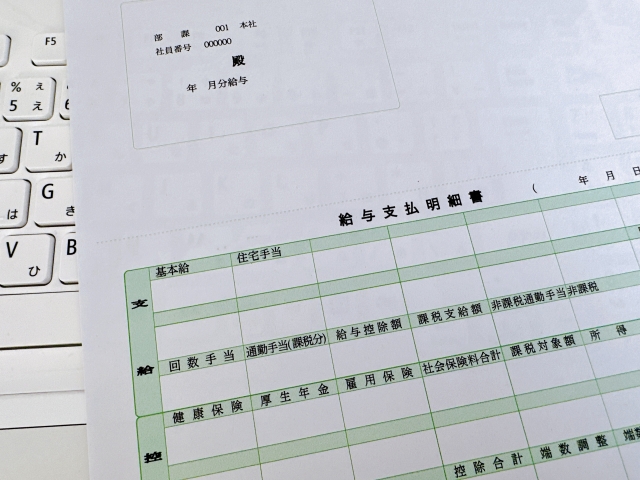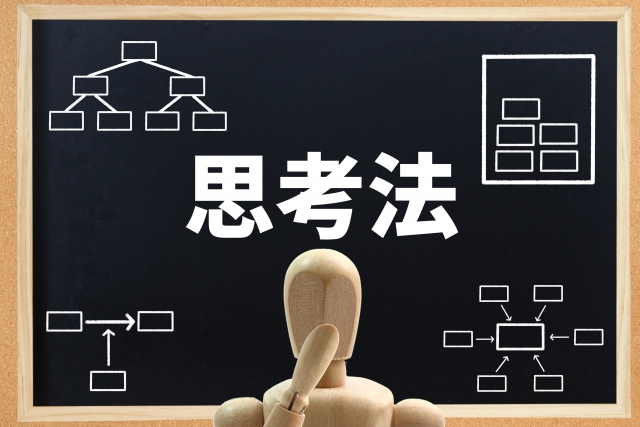マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)」が、ビジネスの最前線の用語や問題を解説するシリーズ。
あなたは度を越した「頑張り屋上司」ですか? 「部下のスキルが低くて仕事を任せられない」「自分でやった方が速い」「部下を育成する時間がない」このような思考から部下の育成を放棄していませんか?
「部下に適切な責任と権限を与えて仕事を任せていく」―上司として当たり前のふるまいですが、昨今「デリゲーション」という単語で改めて注目を集めています。
この記事では、「デリゲーション」という言葉の意味から、実践するときに気を付けるべきことまでを整理しました。「部下に仕事を任せられる上司」になる一助となれば幸いです。
デリゲーションって何?
デリゲーション(Delegation)とは、上司が部下に仕事を任せる「権限委譲」のことを指します。
組織の中では、多くの仕事をいかに上手く部下に任せて生産性を高めるかが重要になります。上司から仕事を任せられた部下は、さらに自身の部下に仕事を任せられるようになり、組織としての目標達成が加速していきます。デリゲーションはビジネス以外の分野にて、「代表任命」「代表派遣」「委任」などの意味で使われることもあります。
デリゲーションとエンパワーメントの違い
デリゲーションと似た言葉に「エンパワーメント」があります。「権限を与える」「力を与える」などの意味があります。ビジネスでは、社員一人ひとりに力をつけさせるため権限を与えるという意味で使われます。目的は社員の自主性や自律性の促進で、会社組織だけでなく教育や医療など様々な業界で注目されています。
デリゲーションとエンパワーメントの大きな違いは、部下の「成果」と「成長」のどちらを見るかという点です。
・デリゲーション:上司は部下に仕事を任せてその成果によって評価する
・エンパワーメント:社員の育成に重点を置いて、成果で評価するより「社員一人ひとりにスキルや自信をつけさせること」を目的とする
正しいデリゲーションが求められる理由
デリゲーションの目的を一言で表すなら「仕事を任せて社員を育て、それにより組織の生産性を向上させること」です。もう少し分解すると、
(1)意思決定のスピードアップ
組織におけるリーダーの最も重要な役割は意思決定することです。どれほど有能なリーダーでも、個人でこなせる仕事量には限界があります。全てリーダー(上司)にお伺いを立てる仕事の仕方をしていては意思決定が遅くなるばかりです。デリゲーションによって部下が自律的に意思を決定できれば、組織内での意思決定速度が向上し、生産性の向上が期待できます。
(2)マネジメント業務への専念
仕事をリーダーが全て背負っていては、組織は円滑に回りません。デリゲーションを活用すれば、リーダーの仕事が減ると同時に組織内で仕事が上手く回ります。本来、リーダーがやるべきではない業務から手が離れ、戦略立案、部下の育成といったリーダーの本業により多くのリソースを投入できるようになります。
ポイントは、「一度、部下に仕事を任せたら、上司は口出しをしない」点。上司が常に部下の仕事に介入していると、指示待ちになり、自律的に動く部下が育ちません。
(3)部下の育成
デリゲーションの狙いの一つに、部下にワンランク上の仕事を任せて部下の成長を促すことがあります。
責任が求められる難しい仕事をクリアする経験を積んでいく過程で、部下の能力や自信が向上し、長い時間軸で見ると組織の持続的成長につながります。上司から見ると最初は「大丈夫かな?」という不安があるかと思いますが、任せたからにはやらせてみることが重要です。
識学式「デリゲーション」のコツ
「部下に仕事を任せる」とは言っても丸投げではいけません。識学の観点からデリゲーションを成功させるコツは三つです。
(1)責任範囲の明確化
部下に移譲する責任の範囲を明確にする必要があります。業務を任せると言っても、何もかも部下に任せるのではなく、「この範囲は上司である自分が判断する必要がある」というものがあるはずです。この上司と部下の責任範囲を明確に線引きしておかないと、
・上司:この範囲は部下に任せたつもりだった
・部下:この範囲は自分の責任では決めてはいけないと思っていた
など、双方の責任の重複や空白地帯(どちらも自分の責任範囲だと思っていない領域)が発生し、結果として業務が遅れたり、お互いが責任の押し付け合いをしたりしてしまいます。部下に任せる前に責任範囲を明確にし、仕事を進める中で不明確な部分が出てきたら都度、質問・確認することを約束しておかなければなりません。
また、複数の部署が関与するプロジェクトなどは関係部署・関係者の責任範囲を明確にしておく必要があります。上下の責任範囲と同様、左右の責任範囲も区切っておかないと上記と同様に責任の重複や空白地帯を生むこととなり、プロジェクトが停滞してしまいます。
(2)責任と権限の一致
デリゲーションの本来の意味は「権限譲渡」です。しかしながら、部下に仕事を任せたと言っても権限譲渡がうまくできていないケースが多く発生しています。「部下に仕事を任せる=責任範囲を明確にする」が大切なのは先述しましたが、この際に“権限を過不足なく譲渡できているか”を今一度確認してください。“過不足なく”というのがポイントで渡した責任に見合った権限を付与する必要があります。
【責任>権限】
与えられた責任に対して権限が足りていない状態。権限の足りない部分が部下にとってはその責任を果たせない「言い訳」になってしまいます。例えば、プロジェクト遂行の責任を与えても、使える予算や人員(権限)が明らかに不足していると部下からすれば「予算も人も足りないのでプロジェクトが失敗してもしょうがない」という意識になるリスクが高まります。
【責任<権限】
責任よりも権限が大きい状態。責任のない範囲まで口出しすることが許されている状態で、いわゆる越権行為をしている状況です。この状態も避けなければなりません。特に、複数部署が関与するプロジェクトなどで、責任範囲を明確にする必要があることは先に述べましたが、その範囲を超えて他部署へ口を出したり、良かれと思って指導指示が出ていない後輩の育成に口を出したりしてしまうケースは発生しやすいので要注意です。
最後にして最大のポイントが、デリゲーションによって責任と権限を委譲した部下に責任を果たさせることです。つまり、上司として任せた仕事を達成させるためマネジメントをしなくてはなりません。「責任と権限を渡したから部下は仕事をしてくれるだろう」は上司側の錯覚です。先述したようにデリゲーションは部下に一段高いレベルの仕事を任せるわけですから、いきなりは出来ません。出来なかったことを出来るように上司側のマネジメントが必要なのです。ポイントは以下の通り。
(3)仕事を任せた部下のマネジメント
・部下の責任と権限を明確にして、どうなればその責任を果たしたことになるかゴールを設定する。
・ゴールしたタイミングで出来ていないことがあるのであれば、それを指摘する。
・部下は上司から指摘された自分の出来ていないことがどうすれば出来るようになるか考える。
・改善策を実行して責任を果たす約束を上司と部下で交わす。
これを繰り返すことで少しずつかもしれませんが、部下は与えられた責任を果たせるようになります。
まとめ
デリゲーションにより部下に仕事を任せていくことでリーダーの業務負担が軽減され、部下が成長し、ひいては組織全体の業務効率が向上します。しかしながら、ただ部下に仕事を丸投げにすればよいものではありません。任せた仕事の責任と権限の範囲を明確にしておかないと、余計に仕事が混乱するリスクがあります。また、任せっぱなしにせず、部下が与えられた責任を全うできるよう引き続き上司がサポートしていく必要があります。
全ての仕事を自分で抱えてしまっている「過度の頑張り屋上司」の方は是非とも、組織、部下、そしてご自身のためにデリゲーションをうまく使っていきましょう。
識学総研:https://souken.shikigaku.jp
株式会社識学:https://corp.shikigaku.jp/