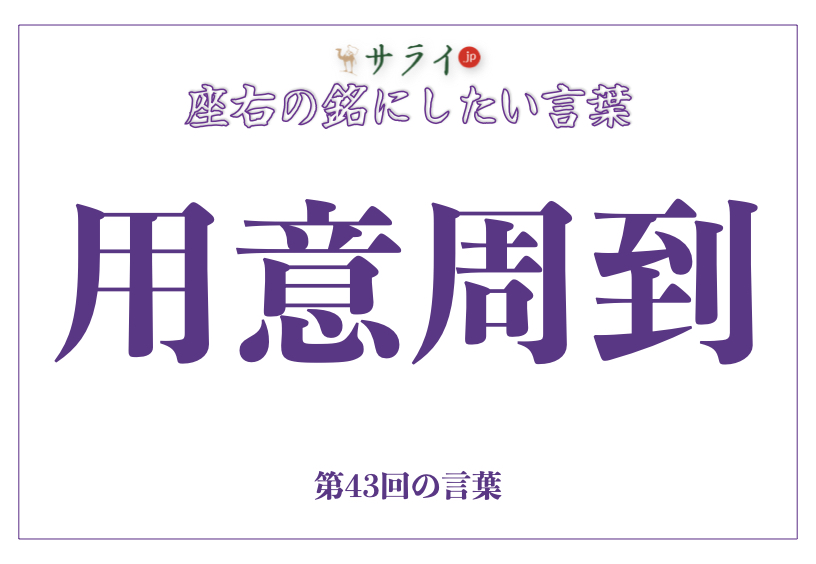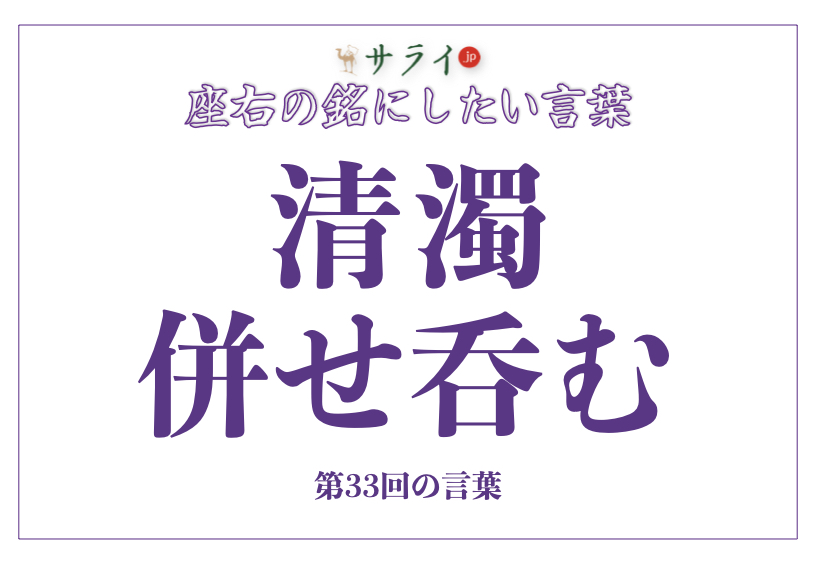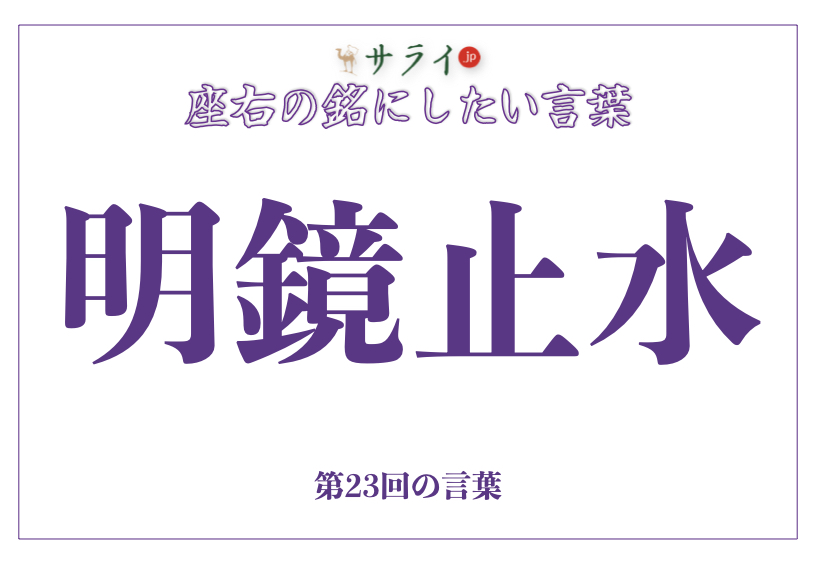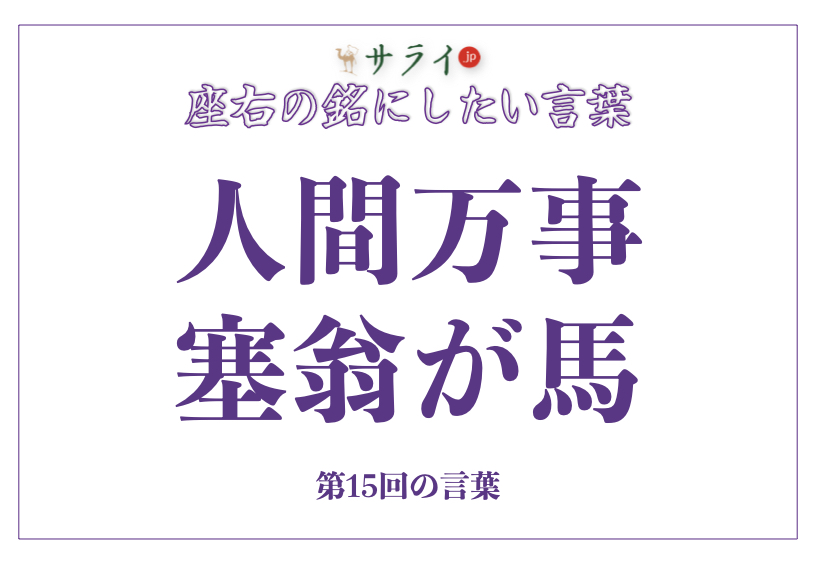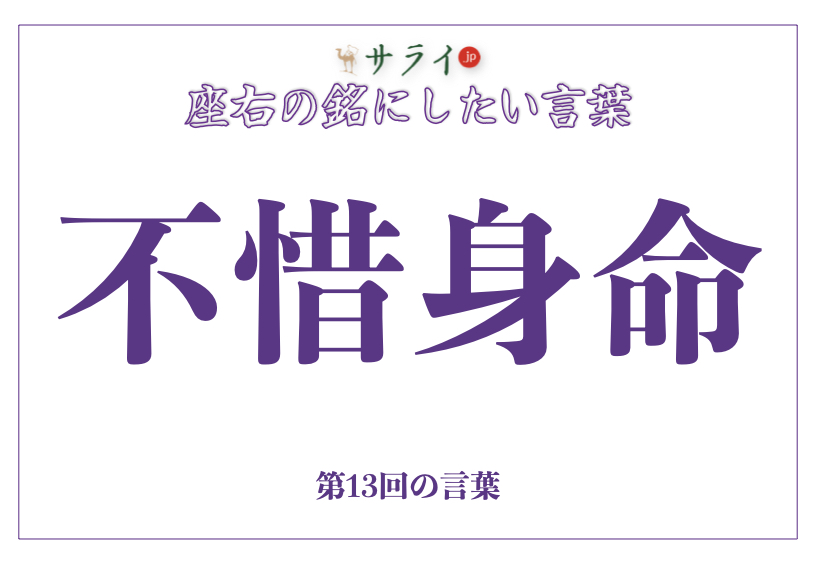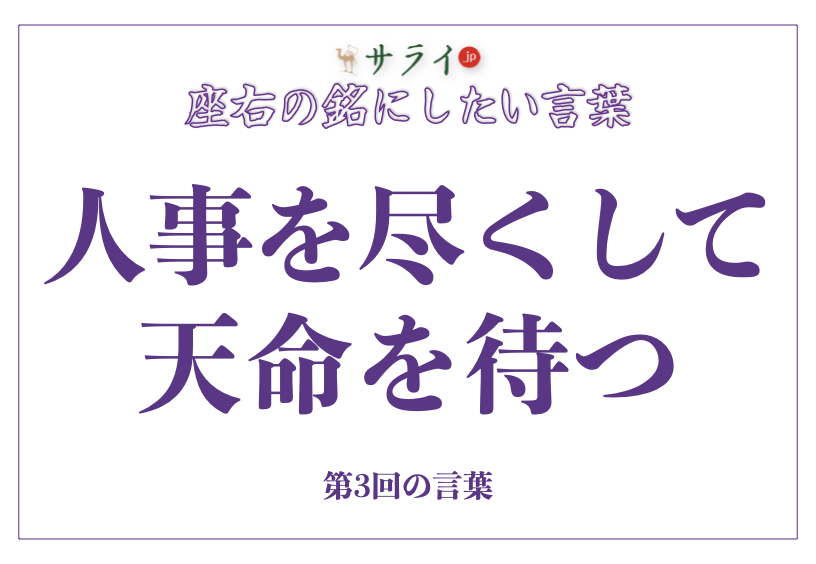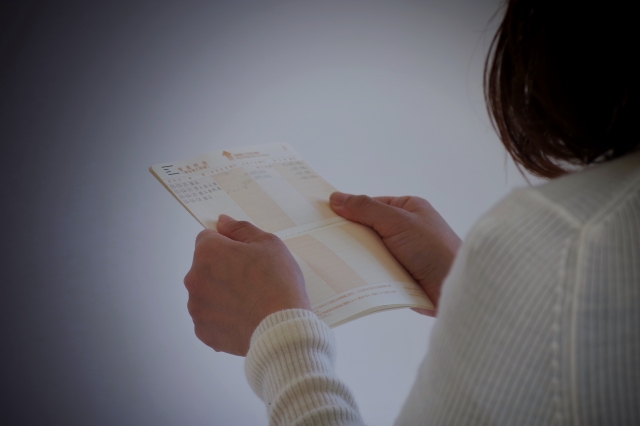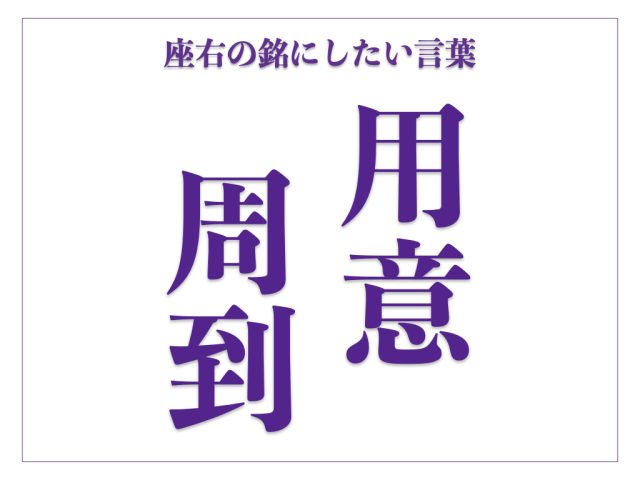
ある程度の歳になりますと、よほど親しい友人でもない限り、本音で意見してくれたり、苦言を呈してくれたりしないものです。まだまだ続く大切な人生において、考え方の柔軟さを保ち、激しく変化する社会へ順応するためには、何らかの指針を持っていた方がいいのかもしれません。
温故知新の諺の如く、先人が残してくれた言葉や金言にヒントを得てみては如何でしょう。第43回の座右の銘にしたい言葉は「用意周到(よういしゅうとう)」 です。
目次
「用意周到」の意味
「用意周到」の由来
「用意周到」を座右の銘としてスピーチするなら
最後に
「用意周到」の意味
「用意周到」について、『⼩学館デジタル⼤辞泉』では、「用意が行き届いて、手ぬかりがないこと。また、そのさま」とあります。物事を始める前に、必要な準備をしっかり整えておくこと。
単なる準備ではなく、将来を見据え、起こりうる事態を想定し、対策を練ることを意味します。人生100年時代において、想定外の出来事は避けられません。だからこそ、予め準備を整え、変化に柔軟に対応できる「用意周到」さが重要になるのです。
例えば、老後の生活資金。年金だけでは不安という方は多いでしょう。「用意周到」な人は、早いうちから貯蓄計画を立て、資産運用についても学び、将来に備えています。また、健康面でも、日々の食事や運動に気を配り、定期的な健康診断を受けるなど、健康寿命を延ばすための努力を怠りません。
さらに、趣味や地域活動など、老後の生活を充実させるための準備も進めています。これらの「用意周到」な行動は、将来への不安を軽減し、自信を持って人生を歩むための基盤となるのです。
「用意周到」の由来
「用意周到」には出典があるわけではなく、「用意」と「周到」という二つの言葉が組み合わさってできた言葉です。「用意」は準備を整えること、「周到」は細部まで行き届いていることを指します。
しかし、ただ準備するだけではなく、あらゆる可能性を想定し、それに対する対策を練ることまでを含んでいます。
「用意周到」という言葉は、古くから日本の文化に根付いており、特に戦国時代の武将たちは、戦の勝敗を左右するのは準備のよさであると認識していました。彼らは、敵の動きを予測し、万全の体制で臨むことが勝利につながると信じていました。この精神は、現代のビジネスや日常生活にも通じるものがあります。
「用意周到」を座右の銘としてスピーチするなら
用意周到を座右の銘としてスピーチする際の注意点は、準備万端であることを示すだけでなく、柔軟性や人間味も伝えることです。過剰な準備を強調すると、融通が利かない、石橋を叩きすぎて渡らないといった印象を与えかねません。
スピーチでは、用意周到であることのメリットを具体例で示し、同時に変化への対応力もアピールしましょう。以下に、「用意周到」を取り入れたスピーチの例をあげます。

用意周到の重要性と柔軟な対応についてのスピーチ例
今日は、「用意周到」という言葉についてお話しします。この言葉は、準備が整っていることを意味します。私自身、数年前に海外旅行を計画した際、事前にしっかりと準備をしたことで、素晴らしい体験を得ることができました。
その土地の情報を調べ、宿泊先を予約し、持ち物リストを作成しました。その際、急な天候の変化や交通機関の遅延なども考慮しました。その結果、旅行中はストレスなく、心から楽しむことができました。
この経験から学んだのは、何事も計画的に進めることの重要性です。しかし、用意周到さと完璧主義は違います。想定外のハプニングにも、柔軟に対応できるよう心掛けています。人生もまた、予期せぬ出来事の連続です。用意周到に準備をしつつ、変化を楽しめる心の余裕を持ちたいと考えています。
最後に
「用意周到」は、単なる事前準備以上の深い意味を持つ言葉です。サライ世代の方の人生において、この言葉を座右の銘とすることで、新たな挑戦や日々の生活がより充実したものとなるでしょう。
完璧を求めすぎず、かつ必要な準備は怠らない。このバランス感覚こそが、「用意周到」の真髄といえるのではないでしょうか。
●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com