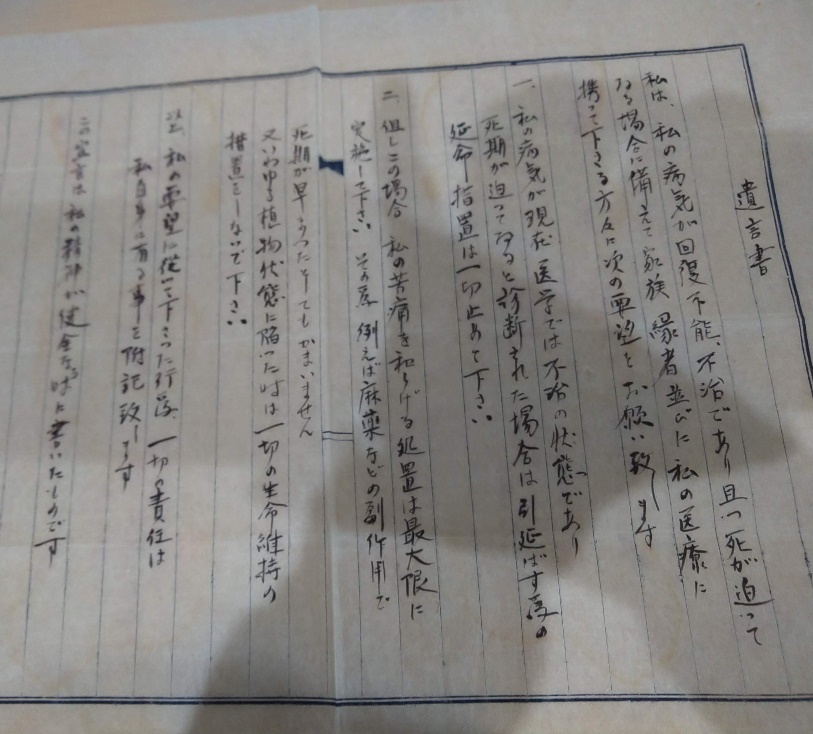取材・文/坂口鈴香

今回は幸福感について考えている。これまでにホームで暮らす高齢の方たちに話を聞くなかで、「味覚にはあまり自信がない」「食事にこだわりがない」という方のほうが、ホームでの食事に満足し、ひいては生活全般においても幸福度が高いように感じた。
【前編はこちら】
大量に残った安物の焼酎
90歳の父親を亡くしたばかりの宮坂志満さん(仮名)も、同じ気持ちを抱いているという。
「父は毎晩焼酎で晩酌するのを楽しみにしていました。『年取るとほかに楽しみはない。晩酌だけが楽しみだ』と言いながら、機嫌よく飲んでいました。それも一番安い4リットル入りの焼酎です。時々、孫たちから高価な酒をもらったりすることがあるとそれはそれでおいしそうに飲んではいるのですが、傍から見ると、表情は4リットル入りのものを飲んでいるときとそう変わらない。だったら安いので十分だろうと思って、安いものばかり買ってきていたんです。父は晩酌した夜に急死したのですが、買い置きしていた4リットルのペットボトルの焼酎が2本も残されていました」
残った安物の焼酎、家族は誰も飲んでくれなくて困っていると宮坂さんは笑う。そういえば、父親は食べ物の味についてもこだわりのない人だったと振り返る。
「私が食事の用意をしていたんですが、『今日の料理は失敗だったな』と思うときでも、何も言わずに完食してくれていました。嫌いなものもまったくなくて私はすごく楽だったんですが、あるとき、もしかしたら父の舌は鈍感なんじゃないかと思ったんです。焼酎の例もそのひとつ。そして、美味しいとか不味いとかあまり感じることなく、食へのこだわりがないくらいが、本人にとっても、家族にとっても一番幸せなんじゃないかと思うようになりました」
宮坂さんはそう言いつつも、父親から「これはうまい!」とほめられた記憶もあまりないと苦笑するのだが。
たまには普通のカレーが食べたい
一方で、こんな話も聞いた。
峰まゆみさん(仮名)は、91歳の母親が有料老人ホームに入居した後、すっかり意欲をなくし、食事以外は自室のベッドで横になってばかりだと心配している。
「入居する前、母と見学して食事も試食しました。母も、『この味は悪くないね』と言っていたのですが、入居後は『食事がおいしくない』と言い、あまり食が進まないようです。入院先からホームに移ってリハビリもないし、食事以外は寝てばかり。動かないので、食欲がなくなるのも当然と言えば当然なのですが」
一方ある介護型の有料老人ホームでは、高級料亭がレストランを運営しており、毎食「老舗旅館の豪華夕食」のような献立が続く。味はもちろん、器も一流だ。三食こんな料理が食べられるなんて、さぞ幸せだろうと思いきや、入居者からは「たまには普通のカレーやハンバーグが食べたい」という声が挙がるのだという。
高級料亭の味でも毎日は飽きる。毎日不味いよりは、ずっといいのだが。
あるホーム入居相談員はこう指摘する。
「不満を言う人はどこに行っても不満です。不満のタネはその気になればいくつでも見つかるからです。食事もそのひとつ。そして、高い前払い金を払って入居しても、まるで転職でもするかのように、新しいホームを見つけて住み替えるのです。お金があるからできることではありますが。そういう方たちの表情は、あまり幸せそうには見えないですね……」
何でもおいしいと言える幸せ
「足るを知る」――森鴎外の「高瀬舟」のテーマのひとつと言われている。弟殺しの罪人として遠島の刑となった喜助。その日をしのぐのが精いっぱいだった喜助は、島で食うに困らない暮らしができるだけで大いにありがたい、申し訳ないとまで言う。喜助の穏やかで満ち足りた表情は、「何でもおいしい」と言う大沼さん夫婦や船田さんの表情に通じると思うのは、深読みしすぎだろうか。
とはいえ、歳を取り、外出も思うようにできなくなってからの楽しみは、食事くらいだという人は多い。残された人生、数に限りある食事なのだから、おいしいものを食べたいと思うのも当然だ。だから、ホーム見学のときには「必ず試食をする」というのが鉄則なのだ。
それでも、「何でもおいしい」と心から言える幸せに勝るものはないのかもしれない。
「悔いが残らないよう、今のうちにおいしいものをたっぷり食べておく」というのも、老後の幸せのためのひとつの選択肢ではあるのだが。
取材・文/坂口鈴香
終の棲家や高齢の親と家族の関係などに関する記事を中心に執筆する“終活ライター”。訪問した施設は100か所以上。20年ほど前に親を呼び寄せ、母を見送った経験から、人生の終末期や家族の思いなどについて探求している。