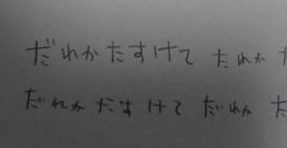取材・文/ふじのあやこ

一緒にいるときはその存在が当たり前で、家族がいることのありがたみを感じることは少ない。子の独立、死別、両親の離婚など、別々に暮らすようになってから、一緒に暮らせなくなってからわかる、家族のこと。過去と今の関係性の変化を当時者に語ってもらう。
*
認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパンが運営する「グッドごはん」では、ひとり親家庭を対象に、子どもにおける体験機会の状況についての調査(実施日:2024年6月1日~6月10日、有効回答数:3137人、インターネット調査)を実施。ひとり親家庭になって以降、子どもに体験活動をさせる頻度がどのように変化したかの問いに対して、「かなり減った」が55.9%、「やや減った」が20.8%となり、ひとり親になるということは子どもに多くの変化を与えることがわかる。
今回お話を伺った香苗さん(仮名・43歳)は小学生のときに両親が離婚。母親と2人で暮らす中で、自分が何かをするときには、自分のためではなく母親のためという気持ちが強かったと振り返る。
母親には働き続けられない理由があった
香苗さんは両親との3人家族だったが、父親の記憶はまったくないくらいに父親は家にいなかったという。
「両親が離婚するときもその報告は母親から受けただけでした。当時私は小学生の高学年だったのに父親の顔さえもうろ覚えです。それだけ父は私のことを見ることがなかったということ。父は離婚してから私に一度も会いに来ることがなかったので、本当に愛されてなかったんだろうなって思います」
母親は祖父母と不仲できょうだいもいなかった。頼れる存在はなく、家族と呼べるのは母親にとっては香苗さんだけ、香苗さんには母親だけだった。母親は起立性調節障害を患っており、普段から倦怠感や立ちくらみの症状があった。長時間働くことにも慣れておらず、正社員ではなく、短時間のパート勤務を掛け持ちしていた。
「父親の存在があったときは、母親は働いていませんでした。母は私が学校に行くときには一度起きてきてくれるもののしんどそうにすぐ横になることもありました。
離婚をして働き始めてからも、季節の変わり目などには体調を崩し、布団の中から出てこないこともありました。そんな母親の姿を見て、小さいながらも頼ってはいけない、私が頼られる存在にならなければと思いました」
小学生なのでもちろん働くことはできなかった。母親の負担にならないために、近所にいる大人に媚びることを覚えたという。
「お腹いっぱい食べられるのは給食だけ。でも給食の時間にご飯をたくさん食べることも恥ずかしかった。だから担任の先生に家のことをオーバー気味に話して、余ったパンなどをもらって帰っていました。他にも、近所に1人暮らししているおばあちゃんがいて、そのおばあちゃんの家でよく遊ばせてもらっていました。おばあちゃんはいつもお菓子をくれて、それでお腹を満たしていました」
【大人の味方をつける術を覚えた。次ページに続きます】