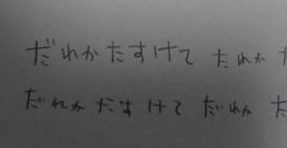人は誰かのために生きていると切実に感じる
仁志さんがお坊さんになってから、数年の歳月が経過。師僧の住職さんも、肉体的な負担が減ったから80代でも元気だという。
「お寺って、そこまで忙しくないんです。法事やお葬式があれば別ですが、それだって、毎週のようにあるわけではない。私はだいたい、金・土・日の3日間、朝、お寺に出勤して、お経をあげて、掃除をします。その後、仕事がないから、湯のみの茶渋を取ったり、墓参用のバケツを磨いたりして、昼には仕事が終わる。バケツなんてそこまでやらなくても…なんですが、お墓参りに来た人が気持ち良く、あの世にいる方と向き合って欲しいという気持ちがあるから、そうしています」
ひとり暮らしの高齢者、近所の子連れのお母さんの話し相手になることもあるという。
「人付き合いが希薄になって、誰とも話さない人が増えている。だから、墓参りに来る人も増えていると感じる。寺務所では墓参者のためにお線香を売っています。それに火をつけて渡すんですが、僕に対して、声をかけてくる人も増えている。“寒いですね”、“お子さん、大きくなりましたね”、“お元気ですね”などと話すうちに、お菓子をいただいたり、本堂にお参りいただいたりする機会が増えてくる。そのうちに、いろんなことを向こうが話す。僕は“ああそうですか”と聞いているだけなんですが、向こうの心が軽くなっているのが伝わる。そのときに、元奥さんだった人に、こういうことができていれば、別の未来があったんだろうなと。あのとき、僕は仕事が楽しくて仕方がなく、それ以外のものに興味さえ持てなかった。元奥さんが欲しかったのは、ともに生きているという実感だったんでしょうね」
それは、年齢を重ねて、物心ともに余裕があるから言えることだ。30代で仕事に夢中になり、エネルギーの全てを“会社が与えてくれるチャンス”に注ぎたい時代に、その他のことへの配慮は難しいだろう。
「そうなんですよ。大規模な公共事業も関わっていたから、世の中を便利にしている、よくしているという使命感、万能感があった。それは人を傲慢にさせる。それから、定年を経て、介護レンタル品を届ける仕事を通じて、いろんな人とすれ違って、それでも毎日は続いていく。人間、死ぬまで修行なのかもしれません」
住職さんはまだ元気だという。跡取りはおらず、仁志さんが跡を継ぐ可能性もあるのではないかと聞くと、「それはない。本山から別のお坊さんが派遣されるでしょう」と言っていた。
目まぐるしく動く時代、人々は不安を抱えて生きている。定年後の人生、人の心に寄り添う仕事に就くという選択肢もあるのだ。
取材・文/沢木文
1976年東京都足立区生まれ。大学在学中よりファッション雑誌の編集に携わる。恋愛、結婚、出産などをテーマとした記事を担当。著書に『貧困女子のリアル』 『不倫女子のリアル』(ともに小学館新書)、『沼にはまる人々』(ポプラ社)がある。連載に、 教育雑誌『みんなの教育技術』(小学館)、Webサイト『現代ビジネス』(講談社)、『Domani.jp』(小学館)などがある。『女性セブン』(小学館)などにも寄稿している。