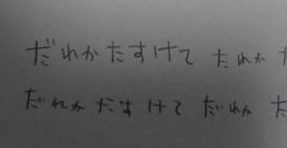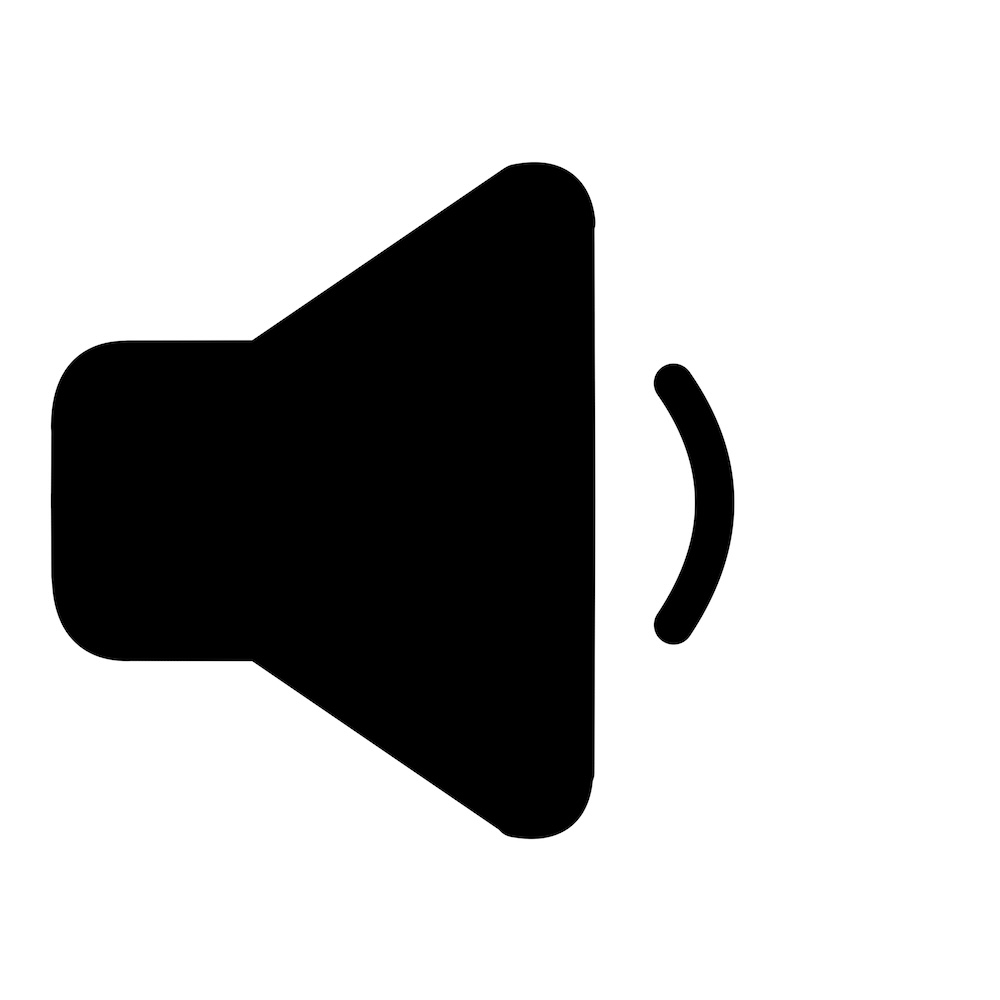親が死に、孤独が染み込んできて友達が欲しくなる
美保子さんは私立の女子中学校から女子大にエスカレーターで進学したが、友達はできなかったという。
「周囲と当たり障りなく社交をしていましたが、友達らしい人はできませんでした。やはり人間不信と恐怖があり、家に帰ると母とばかり話していました。母に愛されたから私は生きていられるんだと思います。母も一人っ子の私がかわいかったんだと思う。20歳になっても、膝枕してもらっていましたし、ハグもよくしてくれました。数年前に母が亡くなるまで、頭を撫でてもらっていたんです」
母娘が手を繋いで買い物に行き、美味しいものがあると「あ~ん」と食べさせる。70代の母親と50代の娘でそれをしているのは、かなり不思議な光景だ。美保子さんは仕事を継続的にした経験がないので、大学を卒業してから両親とべったり過ごしていたという。
「学校は“行きなさい”と言っていましたが、会社はそれほどでもなかったんです。大学卒業後、あるメーカーに勤務したんですが、仕事が覚えられなくて休みがちになり、3か月で辞めたときも親は何も言いませんでした」
美保子さん世代までは、「結婚して当たり前」という時代だった。母はいつか結婚して家庭に入る娘に、家事手伝いをさせて、どこかに嫁がせようとしていたのではないか。
「一時期、父から縁談や見合い話を持ち込まれたことがありましたが、母と私で難癖をつけて、断っていました。母が長男や地方出身者を避けていたのは、私をどこにもやりたくないという思いがあったんだと思います」
いま、美保子さんに大学卒業から40年間を振り返ってもらうと、母との海外旅行やゴルフ、テニス、お茶などの思い出ばかりが出てくる。
「時々働いてはいたんですが、続かない。父も“苦しい思いをするなら、ウチにいればいい”と言ってくれました。私一人くらい養うお金は十分ありますしね。母は友達が多く、その環の中に入っていました。でも、私が50代になったころから、その友達たちが櫛の歯が欠けるように亡くなっていき、最後は母が心臓疾患で亡くなってしまいました。4年前、母はまだ83歳だったんです」
母の後を追うように、父も87歳で亡くなる。美保子さんが一生食べられるくらいの財産はあるけれど、「たった一人になってしまった」という孤独がのしかかってきたという。
「誰も相談できる人がいないんです。コロナ禍のときは、“とにかく話す人が欲しい”と、占い師さんにのめり込んで、凄いお金を使ってしまったこともありました。でも、お金を介在している人間関係がおかしいと思って、ネットを調べたらマッチングアプリやサイトで“友活”(友達を作る活動)をするとあり、コロナ明けから始めたんです」
占い師に支払った金額は300万円だったという。孤独を埋めるのにその金額が妥当なのだろうか。
【踏み込まれるとうれしくなり、献身してしまう…その2に続きます】
取材・文/沢木文
1976年東京都足立区生まれ。大学在学中よりファッション雑誌の編集に携わる。恋愛、結婚、出産などをテーマとした記事を担当。著書に『貧困女子のリアル』 『不倫女子のリアル』(ともに小学館新書)、『沼にはまる人々』(ポプラ社)がある。連載に、 教育雑誌『みんなの教育技術』(小学館)、Webサイト『現代ビジネス』(講談社)、『Domani.jp』(小学館)などがある。『女性セブン』(小学館)などにも寄稿している。