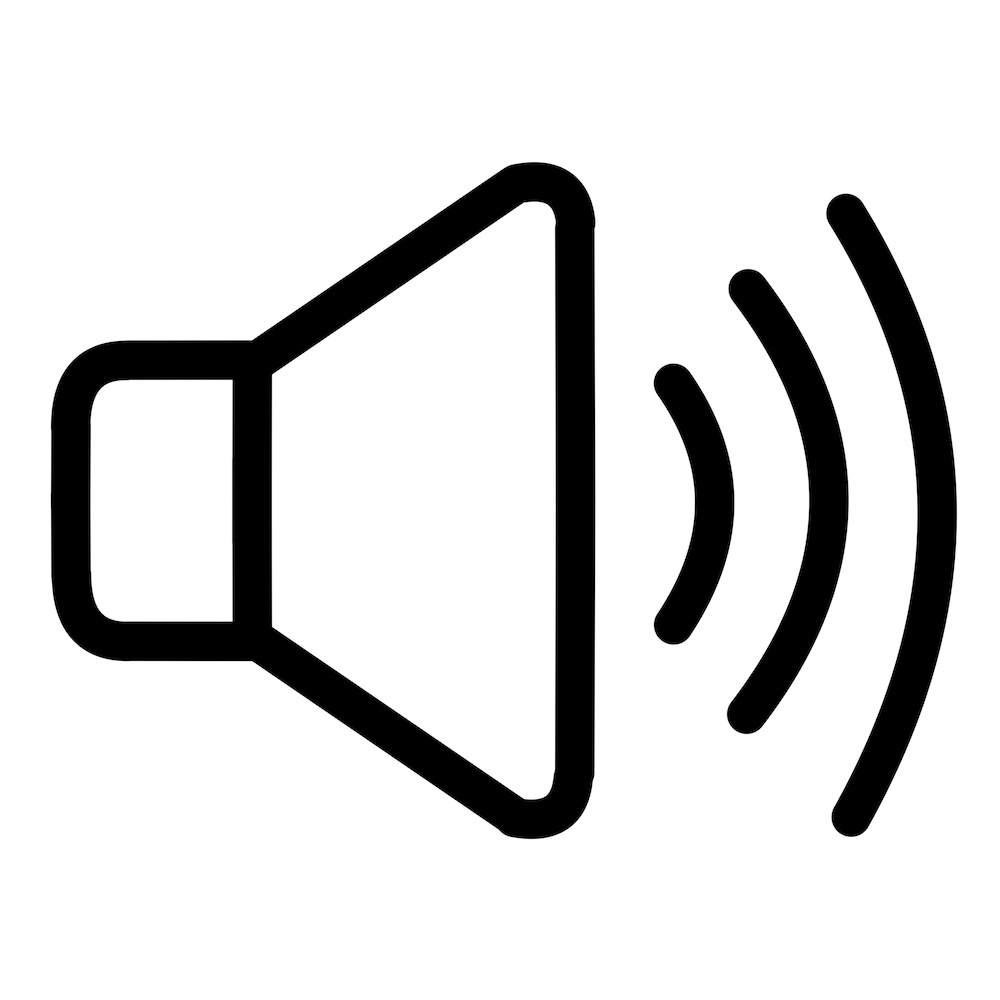取材・文/坂口鈴香

「朝ドラ『舞いあがれ!』五島の“ばんば”は大阪に行くしかなかったのか?」(https://serai.jp/living/1124789)で、離島で暮らす老いた親の介護や呼び寄せについて考えた。「舞いあがれ!」では、最終週になって、大阪で暮らしていた“ばんば”とその娘めぐみは、再び五島列島の中でも“二次離島”と呼ばれる小さな島に戻り、暮らすことになったわけだが、二人の離島での生活について思いをはせていると、『飛族』(村田喜代子著・文藝春秋)が想起された。そこで、改めて『飛族』を読み直してみた。
舞台は住民2人の“限界離島”
いわゆる二次離島の養生島で暮らす元海女のイオさんとソメ子さん――それも92歳と88歳という高齢のうえ、さらにその養生島にはもうこの二人しか住んでいない。“二次離島”とさえ言えないような、限界集落ならぬ、“限界離島”だ――の話だ。
といっても、老女を描かせたら右に出るものはいない村田喜代子さんのこと。単なる介護小説、老人小説になるはずがない。
養生島で最年長だったナオさんが97歳で亡くなり、島民がとうとう二人だけになったことから、92歳のイオさんの娘、ウミ子がイオさんをウミ子の住む本土に連れて帰ることを決心して、養生島に渡る。
ウミ子も「舞いあがれ!」のめぐみと同じように、若いころに島を出ている。まさにめぐみが“ばんば”を大阪に連れて帰ったときのような設定だ。だが二次離島といっても、若者も残っている“ばんば”の島とは違い、養生島からイオさんがいなくなると、88歳のソメ子さんが一人残されてしまう。そのことが、ウミ子がイオさんを本土に呼び寄せることにためらう理由のひとつとなっている。ソメ子さんは夫に先立たれ、子どももいないので、養生島よりほかに行く場所はない。ウミ子が、ソメ子さんを見捨てることはできないというのももっともだ。
役場にも事情がある。養生島は国境に近く、ここが無人島になれば国境に近い島がカラッポになってしまう。人の住む島は海の砦と同じ。人が去ると砦はカラになり、侵入者がそこを占拠する。役場職員の鴫さんは「無人島を一つ分捕ると、国境線の位置が現実にズレ込んでいきます」と言う。イオさんとソメ子さんは、図らずも領土を守るという大きな役割を果たしていたのだ。
一方で老人二人しか住んでいない島でも、島のインフラは必要になる。「船着き場に、定期船。道に、電信柱、水道なんかもいりますね」と鴫さんは言う。電気を切ることもなく、プロパンガスを船に積んで何時間もかけて運んで来なければならないという。一人当たりのコストを考えれば、気が遠くなるような話だ。
見知らぬ土地さ行って最期の息ば引き取りたくはない
老いた元海女二人は現役こそ退いているが、陽気がよくなると毎日海に通う。ソメ子さんはまだ海にも潜れるし、体も口も達者だ。
ウミ子は本土で夫の両親を見送り、その夫も亡くなった。経営する料理店は姪夫婦が一緒に働いてくれていて、イオさんを迎えるのに絶好の状況にある。
「島もいいけどね、山も温泉がいろいろあって、お母さんの体にもいいんじゃないかと思うけど」とイオさんを誘うが、イオさんは即座に「鰺坂家代々の墓ば捨てて島を出れてや? とんでもねえ。(中略)おまえは妙な気遣いばせんで、さっさと水曜の朝に船で去(い)んでしまえ」と拒否する。イオさんもソメ子さんを一人残して、娘のもとに行くことはできないという思いがないわけではないだろう。
そうこうしているうちに、ソメ子さんにも老いは容赦なく襲いかかる。ソメ子さんの眼はほとんど見えていないようだ。イオさんの家にお茶を飲みに来る回数が減り、足の運びものろくなっている。
“人間は齢とれば死なねばならない。ここで寿命がくれば孤独死しか途はない。(中略)ウミ子は今度ここへ帰って来て、母親のイオさんだけでなく、ソメ子さんの老い先も考えねばならなくなった。”
役場も手をこまぬいていたわけではなかった。“二人の耳にタコができるほど、本島の老人施設に入所して世話を受けるよう説得していた”のだという。ウミ子としても、“イオさんが最終的に身を落ち着ける場所は、老人施設でもウミ子の家でもどちらでもいいと思っている。”イオさんが身も心も安らかに暮らせる所ならいいのだ”
ウミ子の店の板前は「ゆっくり親の心を溶かせばいい」と言うが、「島の暮らしはそうもいかない」と返す。離島の環境は厳しいのだ。
“夏はいつ台風が来るか知れない。冬場は海が荒れて船の欠航はつきものだ。そんな間に年寄りはあっという間に逝ってしまいそうだ。年取った親を遠方に置いておくと、雨が降っても、風が吹いても、何につけても死にそうな気がする。”
それでもイオさんは、ウミ子のもとに行きたくないと改めて伝える。
「わしはこの齢になって見知らぬ土地さ行って最期の息ば引き取りたくはないぞ。長年の友達のソメさんともよう別れん。鰺坂家の墓を島に置いて出て行く気にもならん」「おまえはわしのことは諦めて、自分の家に帰るがいい」と。
イオさんの心の底からの叫びは胸を打つ。離島に限らず、離れて暮らす親に共通の思いだろう。
そしてウミ子は、決心する。何を決めたかは本書をお読みいただくとして、翻って「舞いあがれ!」だ。
「舞いあがれ!」のめぐみは、島に戻って介護の必要な“ばんば”と二人で暮らすと、互いに追い詰められてしまうのではないか、遠距離でも互いの生活を守りながら介護する道があったのではないか、と前回の記事でも書いたが、『飛族』を読んで考え直した。介護に正解はない。めぐみやウミ子、そして“ばんば”やイオさんが決めるのなら、それが正解なのではないか。たとえどんな結果になったとしても。
そういえば、“空飛ぶクルマ”で島に戻る“ばんば”も、いわば「飛族」だ。と、オチにもならないことを考えた。
取材・文/坂口鈴香
終の棲家や高齢の親と家族の関係などに関する記事を中心に執筆する“終活ライター”。訪問した施設は100か所以上。20年ほど前に親を呼び寄せ、母を見送った経験から、人生の終末期や家族の思いなどについて探求している。