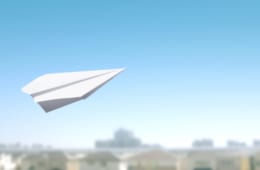文/印南敦史

どんな人でも、「自分は何歳まで生きられるのだろう?」と考えた経験は何度かあるはずだ。決してネガティブな意味とは限らないし、漠然と頭に思い描くだけかもしれない。だがいずれにしても、歳を重ねるとはそういうことだ。
さて、だいたい何歳くらいまで生きられそうだとイメージできるだろう?
『死ぬまで、働く。』(池田きぬ 著、すばる舎)の著者は現役の看護師だが、なんと本書を執筆された2021年の段階で97歳である。
看護学校に入ったのは17歳のとき。太平洋戦争が激しさを増すなかで赤十字の救護看護婦養成所を卒業し、神奈川県湯河原の療養所に看護婦(当時)として召集。以来ずっと看護師を続けてきたのだという。
現在は生まれ故郷である三重県津市の一志(いちし)町にあるサービス付き高齢者向け住宅「いちしの里」で働いているが、驚くべきは同所で働くようになったきっかけだ。88歳のとき、募集を見て自ら応募したというのである。
30代後半からは、管理者や婦長など人の上に立つ仕事をしてきたが、最後は一看護師として「そおっと勤めよう」と思ったのだとか。以来、9年が経過している。
夫は20年ほど前に亡くなり、それからずっとひとり暮らしです。家ではマイペースに、家事や家庭菜園の手入れをして過ごし、週1〜2回は職場に出勤して仕事をしています。職場にいると気持ちがシャキッとして、体もよく動きます。
こんなメリハリのある暮らしが、今の私にはちょうどいいようです。
勤務が終わると「体がえらい(=しんどい)な」と感じますが、家に帰ると「今日も働けた」という充実感があります。(本書「はじめに」より)
いちしの里はシフト制なので、自分が希望する日数、時間で働けるのだという。だから、「だいたい週1〜2日くらい、半日の勤務」が可能になっているわけだ。
88歳で働き始めたときは、月12日くらいの勤務でした。その後、徐々に増やしていって、2年目からは月21日勤務とほぼ常勤。その後、90歳を過ぎた頃から、勤務時間を少し減らして月100時間程度(月12〜18日勤務)、3年ほど前から、年齢を考えて月50時間程度(月8日勤務)になりました。(本書37ページより)
80代までは週5日、90代の前半は週3〜4日働けたものの、さすがに最近はそうもいかなくなったのだという。つまり試行錯誤を繰り返した末、“ちょうどいい”現在のシフトに行き着いたということなのだろう。
加えて最近は、独自の働き方も試しているようだ。
勤務日の夕方から職場に行き、その日は職場に泊まるのだ。家から職場までの行き来に利用しているバスは本数が少なく、時間を合わせるのが困難。とくに朝からのシフトのときはちょうどいい時間にバスが来ないこともあり、前日からの泊まり込みが助かるのだという。
だが前日から泊まる以上、手が足りないときには入居者の食事介助を手伝ったり、夜中に起きてくる入居者の世話をするなど、仕事は増えることになる。
そして翌日の勤務日には、朝は5時に起床し、5時半から2人の入居者にバイタル(脈拍、呼吸、体温、血圧)測定をし、胃ろうを行う。続いて7時頃からは2〜3人の朝食の介助をしたのち、9時から12時頃までは4人の入居者にバイタル測定、必要な人には胃ろう、痰吸引などの看護をする。
他にも仕事は多いようだが、こうやって確認してみるだけでも忙しさが手に取るようにわかる。そのため、思わず「大変だなあ」と感じそうにもなるが、御本人にとってはそれもまたやりがいにつながっているのだろう。
12時で勤務終了。半日ですけど早朝からなので、6時間半ほど働いているかしら。家から持ってきたお弁当を食べながら1時間ほど休憩して、バスに乗って家に帰ります。
時々、午後から出勤して夕方まで働いて、その日は職場に泊まり、翌日は朝から働くというような二日連続の勤務をすることもあります。(本書40〜41ページより)
自分でしようと思った行動が好きにできた若い頃と違って、いまは与えられたことをこなすのに精一杯だそう。そんなこともあり、なるべく訪問看護は1〜2件ではなく、6〜7件くらいと多めに担当する。
勤務時間内に効率よく終えられるように、訪問する順番などを自分なりに工夫するのだ。予定どおりに終わったときは「がんばったな」とうれしくなるそうだが、そんな充実感がまた、先の仕事へのモチベーションにつながっていくのかもしれない。
週1〜2回の勤務というのが、ちょうどよろしいですね。働く日があるから、その日を目標に1週間がんばろうと思えます。(本書42ページより)
職場の理解と本人のやる気や体力の問題が、見事にかみ合っているケースだといえそうだ。そしてそれは、高齢者の働き方を考えるうえで大きなヒントになるようにも思える。
* * *
93歳だった2018年には、75歳以上の医療関係者(当時)に顕彰される「山上の光賞」を受賞した。「目の前のことをコツコツと続けてきただけなので驚いた」とご本人はおっしゃるが、目の前のことをコツコツ続けることこそが重要であるはずだ。だからこそ、気をてらわずにやるべきことをやってきた著者の人生は、多くの人に学びを与えてくれることだろう。

池田きぬ 著
すばる舎
文/印南敦史 作家、書評家、編集者。株式会社アンビエンス代表取締役。1962年東京生まれ。音楽雑誌の編集長を経て独立。複数のウェブ媒体で書評欄を担当。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)、『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)、『人と会っても疲れない コミュ障のための聴き方・話し方』『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)、『書評の仕事』(ワニブックスPLUS新書)などがある。新刊は『「書くのが苦手」な人のための文章術』(PHP研究所)。2020年6月、「日本一ネット」から「書評執筆数日本一」と認定される。