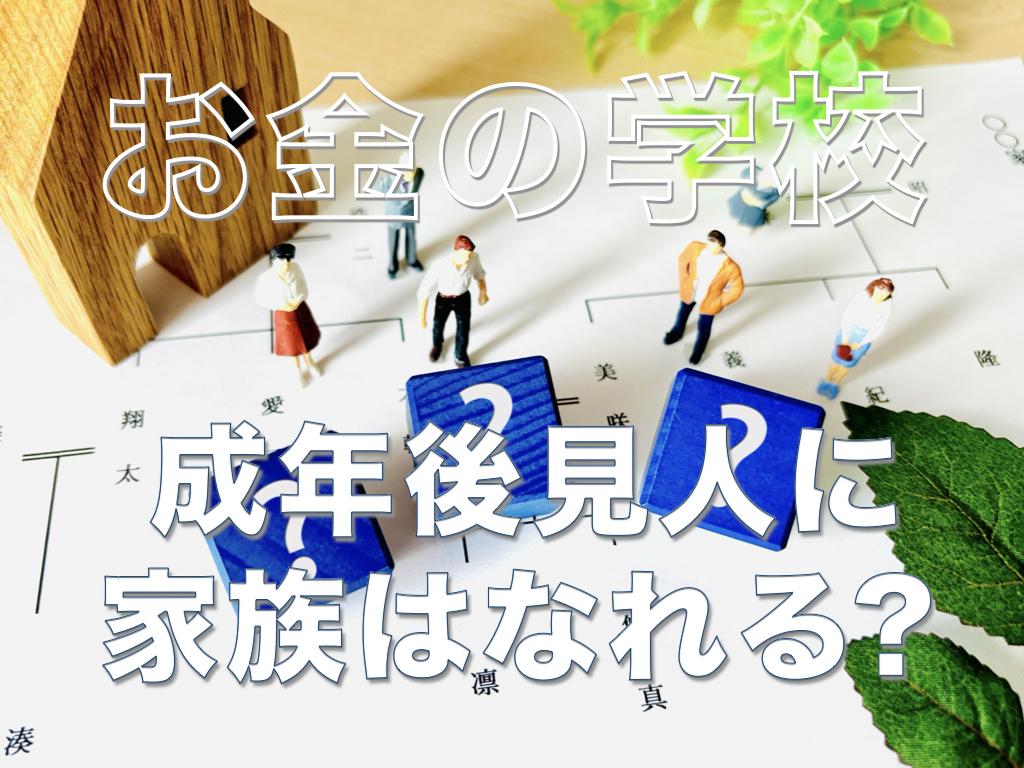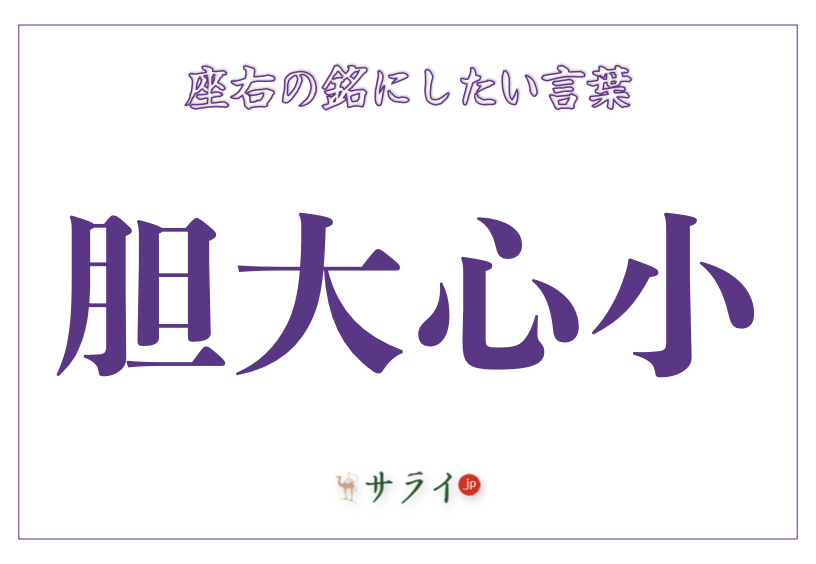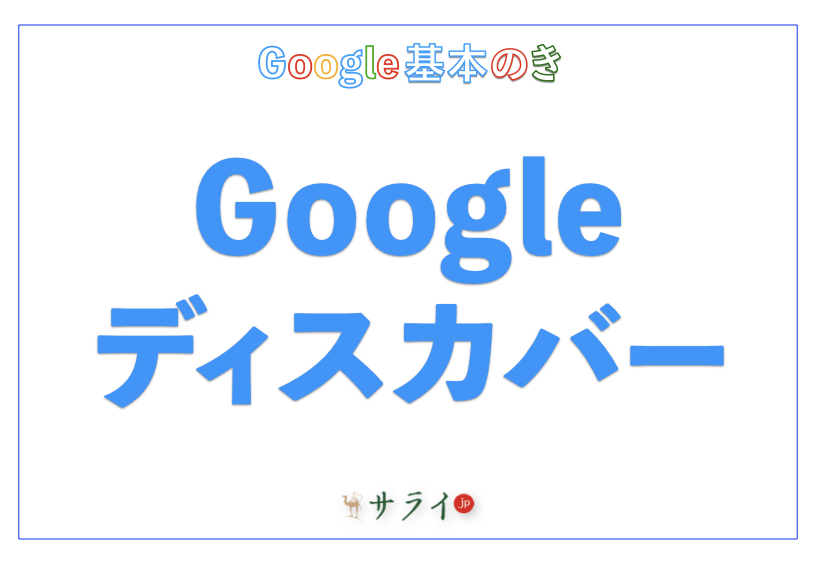「あのとき、ほんの少し勇気を出して声をかけていれば…」――そんなふうに、出会いの機会を逃してしまったことはありませんか? ためらっているうちに、その瞬間は過ぎ去り、二度と同じ機会は訪れない。そんな場面を、英語ではどのように表すのでしょう。
今回ご紹介するのは“miss the boat”です。

目次
“miss the boat” の意味は?
“chance” と “opportunity” の違い
“Carpe Diem” の解釈
最後に
“miss the boat” の意味は?
“miss the boat” を直訳すると、“miss” は(逃す)、“boat” は(ボート、船)ですが……、そこから転じて
正解は……
「チャンスを逃す」
という意味になります。
船が定刻になると出港してしまい、乗り遅れた人は次の船が来るまで長く待たなければならなかったため、「重要なチャンスや機会を逃す」ことのたとえとして使われるようになったそうです。

『プログレッシブ英和中辞典』(小学館)には、「1(特にビジネス・競争などで)好機を逃す.2 (問題などの)要点がわかっていない.」と書かれています。
例えば、
1. He missed the boat and didn’t get the job.
(彼はタイミングを逃して、その仕事に就けなかった。)
2. Gee! We missed the boat on that sale.
(うわ〜。あのセール逃しちゃった。)
などのように使われます。
“chance” と “opportunity” の違い
“miss the boat” では、「船」が「チャンス」を表しますが、別の英語表現で、「チャンス」や「機会」はどのように言うでしょうか? ここでは、微妙に違いがある、“chance” と“opportunity” の意味を整理してみましょう。
chance
“chance” は、基本的に「偶然」や「運よく舞い込んだ機会」を意味します。自分で意図的につくり出したわけではなく、たまたま訪れた機会です。必ずしもいい意味だけで使われるわけではなく、悪い意味合いでも使えます。
例文
1. I met her by chance.
(偶然、彼女に会った。)
2. There’s a good chance it will rain tomorrow.
(明日は雨が降る可能性が高いよ。)
opportunity
“opportunity” は、「願いを叶えるための好機」を意味します。“chance” と違って、偶然訪れるものというよりは、目的に向かって生かす、価値のある機会をさすことが多く、努力や準備を伴います。それをつかめば、成長や利益へとつながる可能性が高いような時に使います。
例文
1. This job is a great opportunity for your career.
(この仕事はあなたのキャリアにとって絶好の機会ですよ。)
2. Studying abroad is a wonderful opportunity to broaden your knowledge and experience.
(留学は知識や経験を広げるための素晴らしい機会ですよ。)
“Carpe diem” の解釈
文学や芸術作品の中で、しばしば登場するラテン語の表現に“Carpe diem”(カルペ・ディエム)があります。
これは「今日できることを精一杯楽しみ、生かそう」という人生観を表した、紀元前1世紀の古代ローマ詩人ホラティウスの言葉です。原文は“Carpe diem, quam minimum credula postero”(今日を摘め、明日に過信するな)と続きます。
“Carpere” はもともと「摘む」という意味を持ちます。花を摘むように、その日を味わう。そこから「今この瞬間を大切に生きよ」「未来を案じすぎず、与えられた今を慈しみ、楽しもう」という意味へと広がっていきました。

この表現は、一般的に英語で “Seize the day.” と訳されます。映画『Dead Poets Society』(邦題:いまを生きる)によって広く知られるようになりましたが、興味深いのは、この英訳にやや積極的な響きが加わっていることです。
“seize” には「つかむ」「奪い取る」といった力強いニュアンスがあり、「今日という日をしっかりとつかみ、最大限生かせ」という印象を与えます。スピーチや広告コピーでも好まれる理由は、この前向きな響きにあるのでしょう。
一方、ラテン語原文の「今を大切に生きる」には英語の「つかむ」という動作は含まれていません。翻訳は、原文の解釈に加えて訳者の意図が重なり、時に意味や温度感が変わります。そこにまた、言葉の面白さと難しさがあると思います。
また “Carpe diem” は、ファッションやタトゥーのデザインにも取り入れられます。とくにスカル(しゃれこうべ)と組み合わされたデザインは、「死を意識して、今を精一杯生きる」というメッセージを強く象徴する表現として用いられます。さまざまな解釈や表現方法があるのも、この言葉の魅力ですね。
最後に
“Carpe diem” は、日本語では映画『Dead Poets Society』の影響もあり、「今を生きる」と訳されたり、「今を楽しめ」と訳されることがあります。このふたつだけでも、言葉が醸す雰囲気はずいぶん異なります。
1915年(大正4年)、吉井勇が作詞した歌曲《ゴンドラの唄》の冒頭には、「いのち短し 恋せよ少女(おとめ)」という有名な一節があります。吉井が“Carpe diem” を知っていたかは定かではありませんが、大正ロマンの香りとともに、「人生は有限。先のことばかり案じず、今この時を大切に」という精神が共鳴しているように思えます。
“Let’s be sure we don’t miss the boat on any opportunities!”
(できるだけ、機会を逃さないようにしたいですね。)
次回もお楽しみに。
●執筆/池上カノ
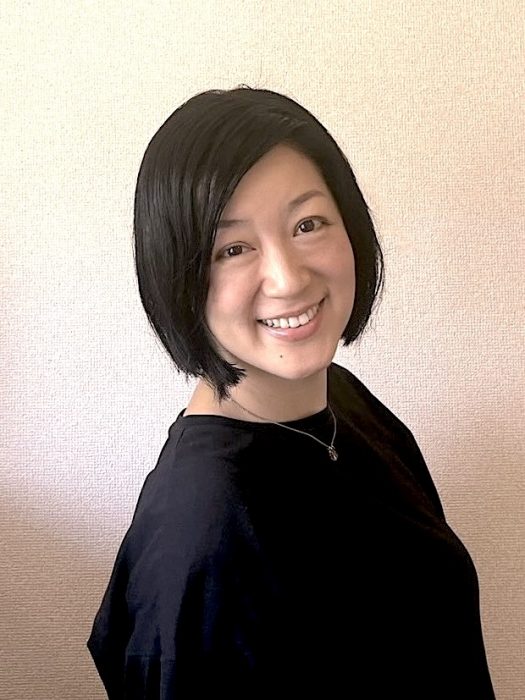
日々の暮らしやアートなどをトピックとして取り上げ、 対話やコンテンツに重点をおく英語学習を提案。『英語教室』主宰。 その他、他言語を通して、それぞれが自分と出会っていく楽しさや喜びを体感できるワークショップやイベントを多数企画。
インスタグラム
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com