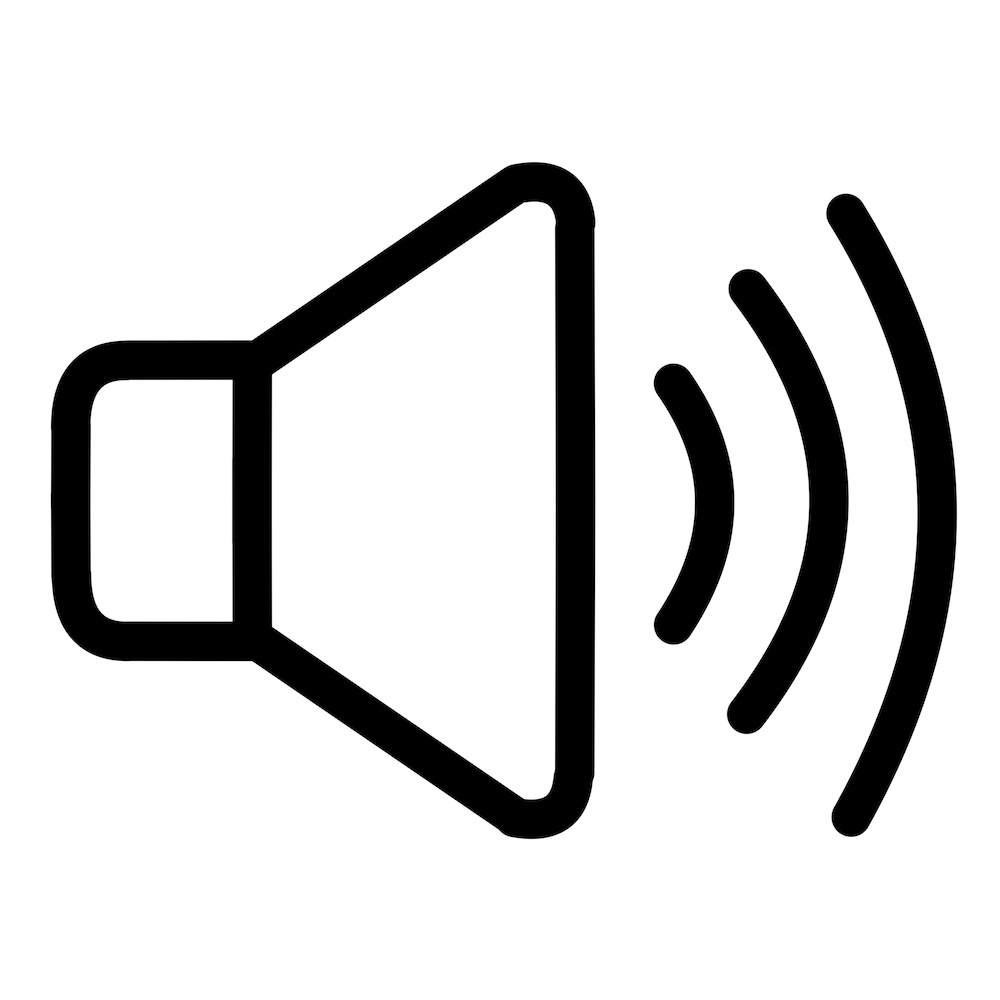多くの人がそうであるように、私もかねてから、戦国時代について漠然とした関心は抱いていた。ところが残念なことに、なかなか“そこから先”へ進めなかったのも事実だ。
理由は簡単で、自身の圧倒的な知識のなさを痛感していたからである。しかも、そうやって二の足を踏んでいる間にも多くの研究が進み、いままで通説だと考えられていたものが次々と覆されていった。
戦国のイメージが、どんどん様変わりしていったわけである。そうなると余計に近寄り難くなり、いつまで経っても本質の部分に近づけないという状態になっていたのだ。
だが『逆転の戦国史』(砂原浩太朗 著、小学館)を読んだ結果、そんなモヤモヤが少なからず解消されたようにも思えた。それは本書が、刻々と変わりつつある「新しい戦国」を伝えるべく編まれたものだからなのだろう。
小説家らしく、フィクションや逸話の面白さも尊重しつつ、近年明らかとなってきた戦国の実像を読者にお見せしたいと思う。いたずらに通説を否定するつもりはない。私が感じたような高揚感とともに、新説へのあざやかな転換を楽しんでいただければと願っている。(本書「はじめに」より引用)
ベースとなっているのは、歴史小説家である氏による「サライ.jp」の連載「にっぽん歴史夜話」。そのなかから、織田信長と明智光秀に関係する戦国時代のエピソードを中心に、新規書き下ろしのエピソードも追加して再構成している。
そのため私のような“戦国時代素人”でも、純粋に入り込んでいくことができたのだ。
そもそも、「『天才』ではなかった信長」と題された第一章からして冴えている。
多くの小説や映像作品の影響もあり、信長には「天才的な武将、過激な改革者」というようなイメージがついてまわっていたのではないだろうか。だが、その生涯は「天才」「英雄」「革命児」といったことばで片づけられるものではないというのである。
そこで、あえて天才史観を封印することにより、信長の希有な個性を浮かび上がらせようとしているのだ。
たとえば信長と聞いて思い出すのは、やはり「桶狭間の戦い」だろう。1560(永禄3)年、2万5千の大軍を率いる駿河・遠江(ともに静岡県)の今川義元を、ほぼ1/10の兵力で討ち取ったという戦。しかも、信長はこのとき27歳だった。そのため武名は諸国に伝えられ、現在にいたる英雄伝説が生まれたわけだ。
この戦いが奇襲戦の典型として旧大日本帝国参謀本部に注目されたことも、信長崇拝の要因となった(ただし現在では、奇襲ではなく正面突破という説が定着しつつあるそうだ)。
また、名だたる武田の騎馬隊を、織田・徳川連合軍の鉄砲隊が殲滅させた「長篠・設楽ヶ原の戦い」も有名だ。
ところが知名度の高さにかかわらず、この戦いには不明な点が多いと著者は指摘する。
信長方の鉄砲が「千挺なのか三千挺なのか」という問題からはじまり、有名な「三段撃ち」の是非、そもそも敵方に世間で言われるような騎馬隊があったのかという点まで、解明されていない疑問が山積しているというのである。
しかも彼の軍事史を振り返って見てわかるのは、しばしば手ひどい敗戦や苦戦を経験していること。むしろ華々しい勝利のほうが少ないようで、だとすればたしかに従来のイメージとは大きく異なる。
敗北の例にはことかかないが、ひとつ挙げるなら、一五七〇年、越前(福井県)朝倉氏討伐に出向いた折、義弟にあたる近江(滋賀県)の浅井長政が離反するという危機に見舞われた。かろうじて逃れ、居城の岐阜へもどる途次では、狙撃されて銃弾が体をかすめている。本能寺以前、信長の肉体がもっとも死に近づいた瞬間だった。ちなみに、この報復戦ともいえる「姉川の戦い」では織田・徳川連合軍が勝ちをおさめたが、当時の公卿・山科言継の日記から、信長側もかなりの犠牲者をだしたことが判明している。(本書13ページより引用)
それだけではない。同年には、大坂本願寺、朝倉、浅井、六角といった反対勢力がこぞって蜂起し、絶体絶命の窮地に追い込まれたというのだ。ちなみにこのときは、将軍・足利義昭や関白・二条晴良の調停で朝倉・浅井と和議を結び、一時的に難を脱した。
これらがすべてではないが、いずれにしても信長は決して“無敗の武将”ではなく、多くの負けを経験しているということだ。
新たに明らかになった事実を知ることは、歴史を理解する上で有意義なことではあるだろう。また、これまでとは異なる信長像は、彼に対する親しみにつながっていくかもしれない。著者もまた、同じような思いを抱いているようだ。
むしろ私は、信長がたびかさなる苦杯をなめながらもその都度しのぎ、勢力を伸ばしていったことのほうに驚嘆の思いをいだく。一見、天才性とは無縁と思える忍耐力や粘り強さを、彼は合わせ持っていたのではないか。ひらめきと狂気だけで生き残っていけるような、たやすい時代ではなかった。(本書14ページより引用)
この文章を目にしたとき、戦国時代に対する自分の視野がぱっと広がったように感じた。過去のイメージを覆す新たな知見に、それだけの説得力が備わっているからなのだろう。
そしてその結果、私を悩ませていた“戦国時代に関する知識のなさ”も、多少は解消できたような気がしている。
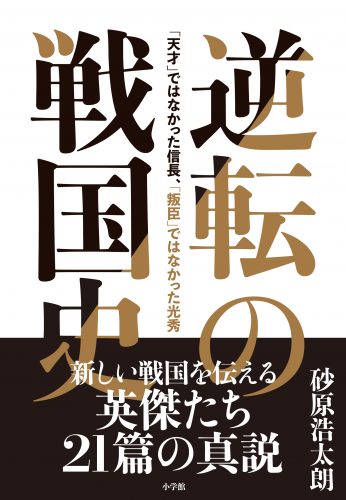
砂原浩太朗 著
小学館
文/印南敦史 作家、書評家、編集者。株式会社アンビエンス代表取締役。1962年東京生まれ。音楽雑誌の編集長を経て独立。複数のウェブ媒体で書評欄を担当。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)、『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)、『人と会っても疲れない コミュ障のための聴き方・話し方』『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)などがある。新刊は『書評の仕事』 (ワニブックスPLUS新書)。2020年6月、「日本一ネット」から「書籍執筆数日本一」と認定される。