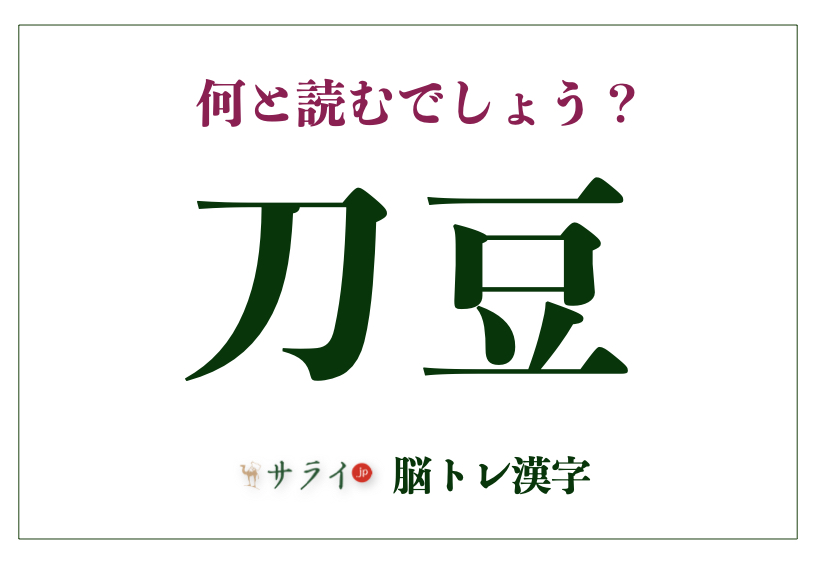日本人の約8割が「疲れている」と回答するなど、疲労は現代的な“国民病”と言われます。仕事や人間関係のストレス、運動や睡眠の不足、スマートフォンへの依存など、様々な原因が指摘されますが、医学的に間違った「食事のあり方」を問題視するのが牧田善二医師です。新著『疲れない体をつくるための最高の食事術』が話題の牧田医師が解説します。
解説 牧田善二(まきたぜんじ)さん(糖尿病・アンチエイジング専門医)

現代人の大半は糖質の過剰摂取である
脳内麻薬ドーパミンという褒美
血糖値を乱高下させ慢性疲労を引き起こすのは、もっぱら糖質であり、肉や魚などのタンパク質や脂質はなんら影響しません。
ですから、疲れたときに肉を食べるのはいいけれど、甘い物や米飯、ラーメンなどを食べると逆効果です。
それなのに多くの人が、疲れたときには甘い物や、ガッツリとした丼飯、大盛りラーメンなどを食べたがります。
なぜ、逆効果であるにもかかわらず、疲れると糖質を摂ってしまうのでしょうか。それは、現代人の多くが“糖質中毒”だからです。
ご自身は糖質をたくさん摂っているつもりなどなくても過剰摂取しており、その結果、自覚なく中毒に陥っています。現代人は、そういう環境に置かれているのです。
どういうことか説明しましょう。
私たち人類の祖先が誕生したのは、約700万年前とされています。その祖先の時代から、私たちのDNAはほとんど変化していません。
大変に長い年月をかけて世代を繫いできた間、祖先たちは狩猟や採集で食べ物を得ていました。おそらく、たまに捕まえた動物の肉や魚、木の実や野草類が主だったはずです。私たちは本来、そういうものを食べるようにできているのです。
農耕技術が生まれて米や小麦を栽培できるようになったのは、ほんの1万年前のこと。ましてや、白い砂糖が広く出回ったのは産業革命以降です。
「日本人はもともと米を食べてきた」というのは間違いで、私たちの体は、糖質をあまり摂らないことを前提に設計されています。
一方で、糖質は最も重要なエネルギー源となる栄養素です。私たちは、糖質を摂ることで得たブドウ糖と、呼吸で取り込んだ酸素を反応させてATP(アデノシン三リン酸)というエネルギー源をつくりだしています。
この作用は、タンパク質や脂質にはできないもので、生きるために糖質は不可欠です。
そのため、人類の体の設計には、「糖質を摂れる機会を見逃さないように」という要素も組み込まれています。
脳はチャンスさえあれば、「もっと糖質を摂りなさい」「ほら、そこに糖質があるじゃないか」と私たちに囁きかけます。
そして、命令通りに糖質を摂ったら、「脳内麻薬とも言われるドーパミンが出て幸せな気分になる」というご褒美をくれます。
でも、この機能が理想的に働いていたのは、なかなか糖質が摂れない遠い祖先の時代まで。身の回りに糖質が溢れている現代社会では、大半の人は過剰摂取し、その結果、疲れを溜め込んでしまうのも当然と言えるのです。
***
世界最新の医学的データと20年の臨床経験から考案『疲れない体をつくる最高の食事術』
現代人の疲れは過労やストレスではなく、「食」にこそ大きな原因がある。誤った知識に基づく食事は慢性疲労ばかりか、肥満や老化、病気をも呼び込む。健康長寿にも繋がる「ミラクルフード」の数々を、最新医学データや臨床経験を交えながら、具体的かつ平易に解説している。
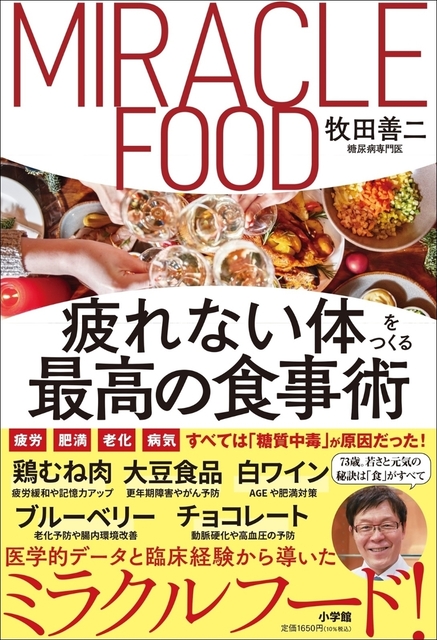
牧田善二/著 四六判208ページ 小学館刊 1650円(税込)