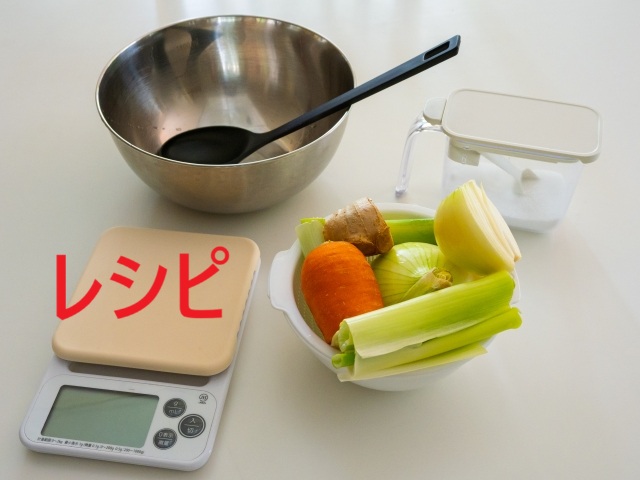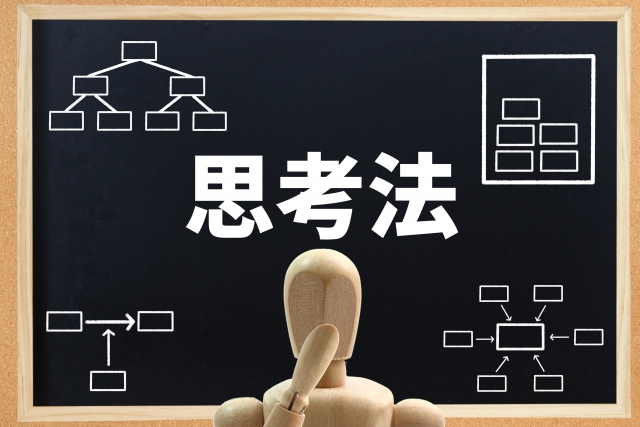マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)」が、ビジネスの最前線の用語や問題を解説するシリーズ。今回は、部下の人材育成について識学視点から考察します。
はじめに
個人の成長がそのまま組織の成長に繋がる時代、私たちはどのような優先順位で人材育成に取り組むべきなのでしょうか。「部下の長所を伸ばすべきか、それとも短所を克服すべきか」――多くのマネージャーや経営者が直面するこの問いに対し、識学は明確な視点を示しています。
この記事では、「長所強化」か「短所克服」かという二者択一に対し、識学の観点から具体的な答えを探っていきます。
識学が示す人材育成の原則
識学では、人材育成の出発点として「組織と個人の関係性」を明確に定義することを重視します。組織とは、特定の目標を達成するために集まった機能的な集団であり、その中で個人は与えられた役割を果たす存在です。
この考え方に立つと、人材育成の目的は単なるスキル向上ではありません。重要なのは、「個人の能力を組織目標の達成にどう活かすか」という点です。つまり、育成のゴールは「能力の最大化」ではなく、「成果への貢献の最大化」なのです。
そのためには、まず各メンバーが組織の一員として最低限の役割を遂行できる状態に達する必要があります。この基本が揃ってこそ、組織は初めて目標達成へと動き出せるのです。
短所克服を優先すべき理由
組織機能を守るための前提
識学では、「短所克服」を「長所強化」よりも優先すべきだと考えます。理由の一つは、組織の機能を維持するためです。組織は、各メンバーがそれぞれの役割をしっかり果たすことで成り立っています。どれだけ他の能力に長けていても、致命的な短所があることで与えられた役割を遂行できなければ、組織全体に穴が生まれてしまいます。
例えば、ラグビーチームにおいて、いくら足が速くても「タックルができない」選手がいれば、チームのディフェンスは崩れてしまいます。このように、短所は放置すれば、チーム全体の土台を揺るがすリスクになるのです。
長所は自然と伸びる
識学では、長所とは「本人が好きで得意なこと」だと定義されます。ゆえに、特別な支援や介入をしなくても、本人の意欲と行動によって自律的に伸びていく傾向にあります。
組織が限られたリソース(時間・予算・指導工数)を使ってまで長所を伸ばすよりも、まずは組織の成果を妨げる短所を取り除くほうが、コストパフォーマンスの高い投資だといえるでしょう。
長所を活かすには土台が必要
長所を十分に活かすためには、一定の前提条件が整っていることが欠かせません。それが、「組織の一員として最低限の役割を果たせる状態」であることです。
短所が残ったままでは、長所が発揮される以前にトラブルやミスの発生原因となり、チームや上司の対応コストを生むことになります。結果的に、長所を活かすチャンスすら与えられない状況が続いてしまうのです。
つまり、短所を克服することで初めて、長所が活かされるステージに立つ準備が整うというわけです。
短所克服から長所活用へ
識学における人材育成のステップは、以下のように段階的に進んでいきます。
ステップ1:短所を特定し、克服する
まず、メンバーの役割遂行を妨げている短所を明確に洗い出します。そして、具体的な行動計画を立て、継続的な改善を支援します。ここで重要なのは、感情的な指導ではなく論理的・実行可能な施策を行うことです。
ステップ2:役割を全うし、信頼を得る
短所を克服したメンバーは、組織内での信頼を得やすくなります。信頼とは、任せられること、役割を果たすことによって築かれるものであり、それが長所を活かすための扉を開くカギとなります。
ステップ3:長所を活かせる環境を提供する
最後に、本人の得意分野で貢献できる環境や役割を与えることで、モチベーションの向上とさらなる成長を促します。これは、短所克服という「土台」ができているからこそ、組織が安心して機会を提供できる段階です。
まとめ:人材育成の順序を正しく理解する
識学の立場では、人材育成における最初のステップは「短所の克服」であり、それがなければ組織全体の機能が不安定になると考えます。短所を克服し、個人が組織の一員としてしっかりと役割を果たせるようになることで、ようやく長所を活かすためのステージが開かれるのです。
この記事を読んだ皆様は、ぜひ自組織のメンバーに目を向けてみてください。長所を伸ばすことばかりに注力し、短所が放置されていないでしょうか。もし思い当たることがあれば、まずは短所の明確化と克服支援から始めてみてください。
人材育成は「順番」がすべてです。正しい順序でアプローチすることで、個人の成長と組織の成果を両立することが可能になります。
識学総研:https://souken.shikigaku.jp
株式会社識学:https://corp.shikigaku.jp/