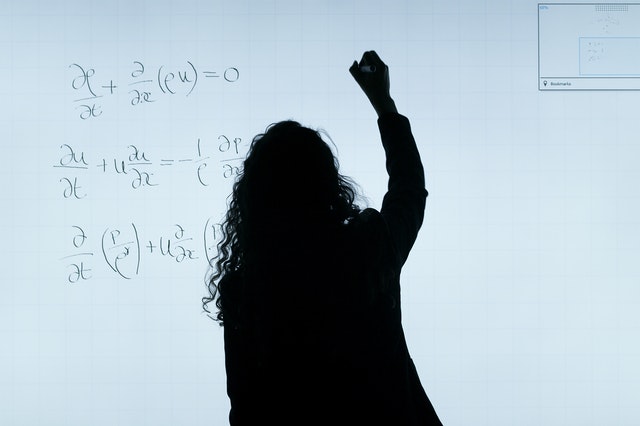2024年から発行される新1万円札の肖像画に選ばれた渋沢栄一。マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研」では、その選定には理由があると説く。2021年大河ドラマ「青天を衝け」の主人公でもある、渋沢栄一について知見を得よう。
* * *
新一万円札の顔に選ばれた渋沢栄一 なぜ岩崎弥太郎ではなく彼が選ばれたのか
2024年から発行される新1万円札で、日本の顔になることが決まっている渋沢栄一。
1万円札の肖像画として3人目になるが、先代の福沢諭吉、初代の聖徳太子に比べると「よく知らない」という印象を持つ人が多いのではないだろうか。
渋沢は、産業らしい産業が皆無であった明治期の日本で、実に500を超える企業の設立に携わり「日本資本主義の父」とまで呼ばれているほどの財界人だ。
そして同時代に活躍した財界人に、三菱財閥の創業者である岩崎弥太郎がいる。
三菱財閥の初代総帥として国の発展を支えたが、その後の三菱グループの発展に多くの言葉は要らないだろう。
日本勃興の近くには、いつも岩崎と三菱の影があった。
そんな明治を代表する二大巨頭だが、渋沢は38歳のある日、44歳であった岩崎から料亭に呼び出されてこう持ちかけられる。
「2人が組めば、日本の実業界を思うままにできる。一緒にやって大金持ちになろうじゃないか」
これに対し渋沢は激怒し席を蹴り、以降二人は長年に渡り反目し続けることになった。[1]
何ら悪い話ではない魅力的なオファーにも思えるが、なぜ渋沢は、岩崎の誘いを断ったのだろうか。
そして、三菱グループの創業者として多大な功績を残した岩崎ではなく、なぜ渋沢が1万円札の顔に選ばれることになったのだろうか。
経営のステージがエスカレーターのように上がっていった
ITバブルと呼ばれていた2000年代の前半、筆者がIT系のベンチャー企業で役員をしていた時のことだ。
当時はまだガラケーが、ビジネスツールとしてやっと行き渡った時代。
インターネット回線はビジネスユースでもISDNが一般的で、家庭ではアナログ回線のダイヤルアップでメールやWebサイトを閲覧していた。
23時から翌朝8時まで定額でアナログ回線を使える「テレホーダイ」といえば、40代以上の世代には懐かしい思い出だろう。
そんな時代に同社では、インターネット回線を経由して動画や音楽を楽しめる野心的なサービスを仕掛けようとしていた。
ハッキリ言って無茶にもほどがある。
当時のインターネット回線で動画を流すというのは、言ってみれば風呂いっぱいの水を細い一本のストローで吸い上げるようなものだ。
仮にやろうと思っても何時間かかるか想像もつかない上に、そもそも回線容量やインフラだけの問題ではない。
再生側のPCの性能、著作権の問題、コンテンツホルダーをその気にさせるインセンティブやコンテンツ業界特有の利権構造など、到底解決できると思えない難題が多すぎる。
アーリーステージにあるベンチャーが取り組めるような仕事ではなかった。
しかし若さ特有の怖いもの知らずも手伝って、全役職員ができると信じていた。
そして同社では、
・大容量コンテンツを環境に縛られずに安定して配信する技術
・不正コピーを防止するコンテンツ保護技術
の2つに絞り、この領域で世界を取るという経営方針を最終的に定めた。
インターネットの将来性を考えると、やがて音楽や動画を配信サービスで楽しむ時代は必ず来るはずだ。
そして時代が変わっても、間違いなく必要とされ続ける技術はこの2つだろう。
だからその領域で、世界的なパイオニアになることを決めた。
しかし、やろうと思えば成功できるほど、世の中は甘くない。
事業化に見通しを立てることもできず、マネタイズの時期や方法の考え方もわからない。
複雑な業界構造をどうやって変えるのか、見当もつかない
日銭を生まない事業に人員を割き続けるようなキャッシュの余裕もない。
しかし、尖った技術には自信がある。
考えあぐね頼ったのが、筆者の古巣である証券会社であり、そしてVC(ベンチャーキャピタル)だった。
自社のもつ事業構想や考え方、技術は、世の中を変えるほど価値があり必要とされるものなのか。
それをテストして欲しいといくつかのVCに投資を求め、結果として2億円を超える初めての投資を受けることに成功した。
資金調達に成功した夜、役員・幹部で居酒屋に繰り出し、祝杯を上げた時のことは20年以上経っても忘れようがない思い出になっている。
しかし、想像を超える事業の成長はここからだった。
都銀系のVCを通じ系列大手商社の紹介を受けると、インフラ系、コンテンツホルダー系のあらゆる方面に次々に商談が広がる。
そして、インフラ大手N社と同社を中心に、ついにネット配信の試験サービス事業が立ち上がった。
おそらくこのコンテンツ配信ビジネスは日本で指折りの早期、もしかしたら日本初ではないだろうか。
当然プレスリリースもされ、同社以外の会社は全て、誰もが知る名だたる会社ばかりだった。
確かに、VCなどから投資を受けていたので、株主にとって企業価値の向上は共通の利益だ。
ある意味で、取引先の紹介は当然の支援と言えるかも知れない。
しかし、一社あたりの持ち株比率はせいぜい数%に過ぎない。
外部株主比率を合計しても、僅か10%である。
51%を超える支配的な持株比率どころか、1/3にも遠く及ぼない外部の持ち株比率で発揮できるオーナーシップは、ほとんど無い。
しかし株主は皆、世間知らず、身の程知らずの経営陣を信じ、全力で応援し、ビジネスの可能性を本気で追求してくれた。
そして、桁外れの現金だけでなく、物心両面で文字通りスケールの違うマネジメントの世界に、同社を押し上げてくれた。
世の中にはこんな世界があるのかと、先人が後進を導き、支援し、時に叱咤激励してくれる価値観があることに感謝した。
そして思い残すことなく、誠実に、全力で、株主と顧客の期待に応えるべくビジスを前に進めることができた。
会社は誰のために存在するのか
話は戻るが、渋沢が岩崎に激怒した理由だ。
渋沢は会社の存在意義を、
「国と国民を富ますことが経営の目的」
であるとし、
「得られた富は広く分配するもので個人が独占すべきでない」
と考えて、財閥の形成を真っ向から否定していた。
そしてそのために必要な組織は株式組織であり、衆知を広く集め優れた経営者を募り、また株主の意見に耳を傾けることこそ、国益に叶うと確信していた。
それに対し岩崎は、
「だめだ,君のいう合本法(株式組織)は,船頭多くして船山に登るの類だ」
と反論する。
すると渋沢は、
「いや,独占事業は欲に目のくらんだ利己主義だ」
と応じて、二人は物別れした。[1]
現在の価値観で言うと、この話は渋沢がカッコよくて岩崎が引き立て役のようにも思えるが、決してそういうことではないだろう。
時代はまだ明治維新から間もない時期で、庶民にまともな教育が行き渡り始めたばかりの頃合いだ。
当然、できる経営者から見れば自分が全てを決定し、全て指図をしたほうが遥かに効率が良いに決まっている。
当然、リスクとリターンは表裏なので、多くのリスクを負った経営者とその一族が多くのリターンを享受する。
何も間違っていない。
しかし渋沢は、そんな時代にあってもこの国の将来を思い描いていた。
庶民の能力はまだまだヒヨコでも、一部の知識層が庶民を支配的に指導し、その体制を固定させることを良しとしなかった。
わかりやすく言うと、
「リスクは俺が取るから、お前がやってみろ」
という、“頼れる上司”のポジションだ。
事業や社会を育てる王道かもしれないが、しかしそれが短期的に見るとどれだけ非効率なことかは、多くのビジネスパーソンが知っているだろう。
できない部下やできそうもない部下に仕事を任せるよりも、自分でやったほうが遥かに早く仕事が終る。
クオリティも高い。
しかし、いつまで経っても事業は、足し算ですら広がっていかない。
言ってみれば、自分の能力を頼りに目先の正面突破を図ろうとしたのが岩崎。
意欲ある後進に知見と資本を提供し、長い目で見て世の中を変えようとしたのが渋沢。
二人の経営スタイルの違いは、そのようなものだったのではないだろうか。
【渋沢がいなければ日本はどうなっていたか? 次ページに続きます】