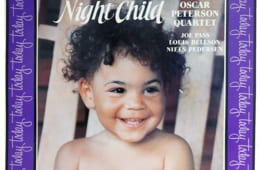文/池上信次
「演奏したそのまま」のイメージが強い「ジャズのライヴ盤」であっても、カットはもちろん、拍手の追加など加工は珍しくないという話題を続けてきていますが、これが面白いと思うのは「ジャズはリアルの記録」という認識を無意識にもっているからですね。しかし、1960年代半ばから、レコードの録音にマルチトラック・レコーダーが広く使われるようになってからは、どんな状況の演奏でも「差し替え」が可能になり、レコードにおいて「ジャズはリアル」は常識ではなくなっているのです。
(1)シンガーズ・アンリミテッド『イン・チューン』(MPS)
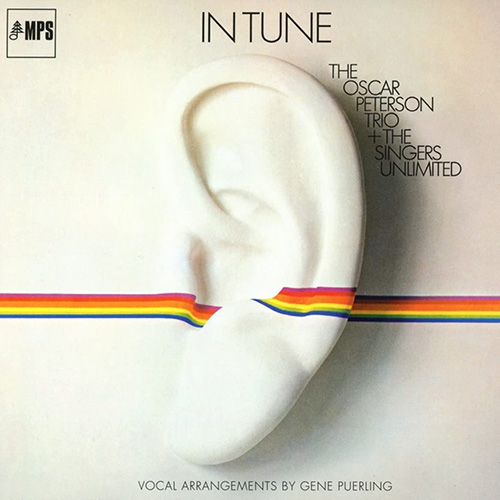
演奏:シンガーズ・アンリミテッド[ボニー・ハーマン、レン・ドレスラー、ドン・シェルトン、ジーン・ピュアリング(ヴォーカル)]、オスカー・ピーターソン(ピアノ)、ジョージ・ムラーツ(ベース)、ルイス・ヘイズ(ドラムス)
録音:1971年7月
シンガーズ・アンリミテッドは女声1、男声3の4人編成ですが、アルバムでは4声を超えるハーモニーが聴かれます。リーダーのジーン・ピュアリングは1950年代に、男性四声グループのハイ・ローズ(The Hi-Lo’s)のリーダーでした。「リアル」を熟知しているからこそ、「非リアル」もより面白いものにできるのでしょう。
1970年代初頭にデビューしたジャズ・コーラスのシンガーズ・アンリミテッドは、マルチトラック・レコーダーを積極的に作品作りに生かしました。彼らはひとりずつパートを順次重ねて録音し、完璧なハーモニーを作ったのです。しかもひとりが複数パートを歌ったりもする、「リアルでは再現できない」コーラスなのです。そもそもこのグループはライヴ活動は前提になく、録音技術の進歩が生んだ「レコードでしか聴けない」グループだったのです。これは「記録」としての録音より、完成度の高い「作品」としてのレコード作りを重視していたということですね。
その一方、ジャズには「リアルな記録」として聴くからこそ面白い演奏ももちろんあるわけです。たとえばすごいアンサンブルが「その場でそれが演奏されている」ことが評価の対象になるわけですね。マルチトラックが普及すると、当然多くのレコードはそれを使って作られるようになりました。よりよいバランス(ミックス)のためというのが、「差し換える」「重ねる」ことよりも大きな理由ですが、すごい演奏になればなるほど「リアルな演奏なのか?」という疑問がついて回ることにもなります。
1970年代半ば、ジャズ界に「フュージョン(当初の呼称はクロスオーヴァー)」のムーヴメントが起こります。「複雑な楽曲構成」とそれを演奏する「高度なテクニック」が魅力のひとつで、たくさんの「名手」たちが、シーンを賑わせました。レコードはマルチトラックで録音すれば、一糸乱れぬキメキメのバンド・アンサンブルは多重録音で、アドリブ・ソロは何度もやっていいテイクを選んで繫げて……といった「作品」作りが可能です。「作品」としてはそれでいいのですが、それを「ジャズとして聴いている」リスナーとしては、それが「リアル」なのかどうかはたいへんに気になるところではあります。演奏している側も「ジャズ」と考えているなら、(リアルであれば)「リアル」を全面的にアピールしたいはずですよね。ジャズにとって「リアル」であることは、大きな魅力のひとつなのですから。いや、考えようによっては「ジャズ」と「非ジャズ」を分ける重要な要素といえるかも。しかしそのためには「修正なし」を証明しなくてはなりません。でも、どうやって?
ちょうどその頃はアナログ・レコードの成熟期で、高音質録音・再生のために、スタジオの作りからレコードの材質にいたるまでさまざまな技術が開発されていたのですが、「究極のレコード録音法」として「ダイレクト・カッティング」が登場しました。これは「演奏しながら直接、音を盤に刻む(カッティング)」というもの。通常は演奏とカッティングの間に存在するテープレコーダーを排したことにより、音質は飛躍的に向上するのですが、オーヴァー・ダビング、ミックスダウンなどは当然できない「2チャンネル一発録音」となります。つまり修正されていない「リアル」が記録されるのです。レコードの歴史の中で「修正不能」の録音方法は、テープレコーダー出現前のディスク録音と、この(原理としては同じ)ダイレクト・カッティングだけです。さらに、これは「LP片面分を、曲間も含めて連続演奏」しなければならず、片面各曲で見せ場を作り、なおかつ最後までミスなし(最後の1音でもミスすれば片面分全部パー)という苛酷な条件も課されるのです。
この高いハードルにもかかわらず、これに飛びついたのがリー・リトナー。フュージョンを代表するギタリストですが、自身のグループ「ジェントル・ソウツ」でのアルバム『ジェントル・ソウツ』(1977年5月録音)をこのダイレクト・カッティングで作ったのです。全編にわたって「複雑」で「高度」な曲が連続するにもかかわらず、グループはアンサンブルにアドリブに素晴らしい演奏を披露しました。このレコードは高音質が第一の目的でしたが、リトナーは「リアル」の証明としてもこれを利用し、それが大きな反響を呼んだのです。これによってリトナーとグループの「リアルな実力」は高く評価されることになりました。これに味をしめた(?)リトナーは、それから1年の間にさらに2枚のダイレクト・カッティング・アルバムを制作し(ダメ押し?)、その評価を不動のものにしました。
(2)リー・リトナー&ジェントル・ソウツ『ジェントル・ソウツ』(JVC)
演奏:リー・リトナー(ギター)、アーニー・ワッツ(サックス)、デイヴ・グルーシン(ピアノ、キーボード)、パトリース・ラッシェン(ピアノ、キーボード)、アンソニー・ジャクソン(ベース)、ハーヴェイ・メイソン(ドラムス)、スティーヴ・フォアマン(パーカッション)
録音:1977年5月28、29日
複雑で長いユニゾン・フレーズと「キメ」が連続する難曲「キャプテン・フィンガーズ」に、当時のリスナーは皆のけぞったことでしょう。腕利きスタジオ・ミュージシャンの集合体が、バンドとしてデビューするに当たっての売りのひとつが、この「リアルなバカテク」だったのです。
しかしながら、「LP片面連続(2〜3曲)ミスなし演奏かつ満足のゆくテイク」を作るのは、さすがに容易ではなかったようで、2枚目のリー・リトナー&ジェントル・ソウツ『シュガー・ローフ・エキスプレス』(JVC)の楽曲解説には、「この曲の収録テイクは全6テイクのうちのテイク3」という記述があります。つまり少なくともLP片面分を6回も(両面で何回?)演奏していたわけです。「作品」を作るならマルチトラックの方がよほど容易だったに違いありませんが、「ジャズマン」リトナーは「リアル」を聴かせることにこだわったのですね。ちなみにリトナーは、全部で5枚のダイレクト・カッティング・アルバムを発表しました。
その後、アナログ・レコードはCDに取って代わられ、ほんとうの「リアル」なメディアはなくなってしまいました。現在のレコーディングにはコンピュータが使用され、いわゆるモダン・ジャズであっても1音単位での差し換えはもちろん、ヴォーカルのピッチ修正さえ普通に行なわれています。そして編集された部分は絶対に耳ではわかりません。レコード/CDでの「ジャズ=リアル」は、いまや昔の話なのです。
文/池上信次
フリーランス編集者・ライター。専門はジャズ。先般、電子書籍『プレイリスト・ウィズ・ライナーノーツ001/マイルス・デイヴィス絶対名曲20 』(小学館スクウェア/https://shogakukan-square.jp/studio/jazz/)を上梓した。編集者としては、『後藤雅洋著/一生モノのジャズ・ヴォーカル名盤500』(小学館新書)、『小川隆夫著/伝説のライヴ・イン・ジャパン』、『村井康司著/あなたの聴き方を変えるジャズ史』(ともにシンコーミュージックエンタテイメント)などを手がける。