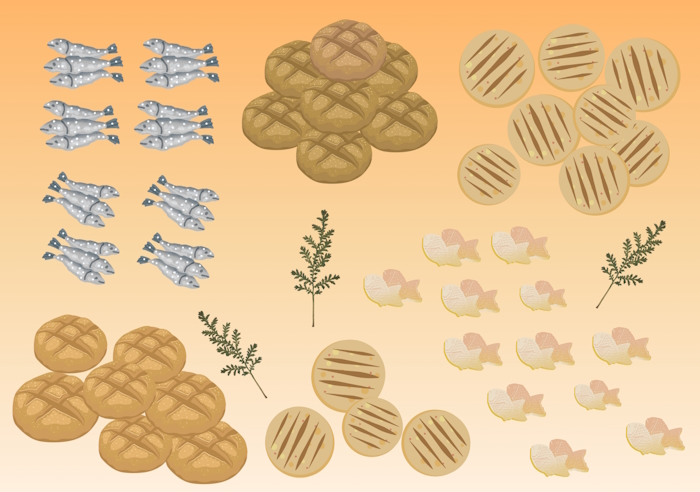今年2017年は明治の文豪・夏目漱石の生誕150 年。漱石やその周辺、近代日本の出発点となる明治という時代を呼吸した人びとのことばを、一日一語、紹介していきます。
【今日のことば】
「やっぱり河豚(ふぐ)は中(あ)たる」
--吉川英治
吉川英治が印章店の小僧を振り出しに、さまざまな職業遍歴を経て人気作家となったことは、割合とよく知られているかもしれない。一方で、文子夫人と仲睦まじい家庭を築く以前、苦い失敗をしていることは、余り知られていないのではないだろうか。
吉川英治が最初の結婚をしたのは大正12年(1923)、31歳の頃だった。妻やすは、関東大震災を経て、英治が文学に専心する決意を固めていく時期に傍らにいたわけで、そうした意味では「糟糠の妻」であった。だが、どこからか、ふたりの間に不和が生じていく。向上心に富む夫と、花街の自堕落さを清算しきれずにいる妻との間の、生活の意識の食い違いのようなものが、次第に拡大していった恰好だった。と同時に、周囲からは「恐妻家」と言われたりもして、英治の心は塞いでいくばかりであった。
昭和5年(1933)のある日、英治はとうとう万年筆1本を懐に、女中の下駄をはいたままふらふらと家を出奔した。そのまま帰宅せず、地方の温泉地を転々とする。
ちょうどこの頃、菊池寛が『オール讀物』のルーツである『文藝春秋臨時増刊オール讀物号』の編集を進めていた。英治はこの雑誌のために、旅先から原稿を書き送った。
英治のいる温泉宿には、東京からひとりの妓が追いかけてきて、ずるずると居続けていた。当然というべきか、不審な男女だと噂が立つ。しまいには、刑事がやってきて事情聴取を受けたりもした。
そもそもこの妓とは、英治が河豚のヒレ酒を飲んだ夜に、過ちを犯した。直木三十五や大佛次郎らと集ったその夜、英治はさして飲めもしないのに、薦められるままに盃を重ねた。知らぬ間に、家庭生活でたまった鬱憤を吐き出そうとしていたのか。英治にとっては、ヒレ酒はもちろん、河豚を口にするのも、この夜が初めてのことだった。
そんなことからはまり込んだ、妓との温泉地放浪は、1年に及んだ。ようやく妓との関係が切れたときには、最初の結婚生活も完全に破綻していた。
後年、再婚して安定した家庭生活を送れるようになった英治は、その夜のヒレ酒を振り返ると、つい掲出のようなことばを呟くのである。「やっぱり河豚は中たる」と--。
文/矢島裕紀彦
1957年東京生まれ。ノンフィクション作家。文学、スポーツなど様々のジャンルで人間の足跡を追う。著書に『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫)『漱石「こころ」の言葉』(文春新書)『文士の逸品』(文藝春秋)『ウイスキー粋人列伝』(文春新書)『夏目漱石 100の言葉』(監修/宝島社)などがある。2016年には、『サライ.jp』で夏目漱石の日々の事跡を描く「日めくり漱石」を年間連載した。