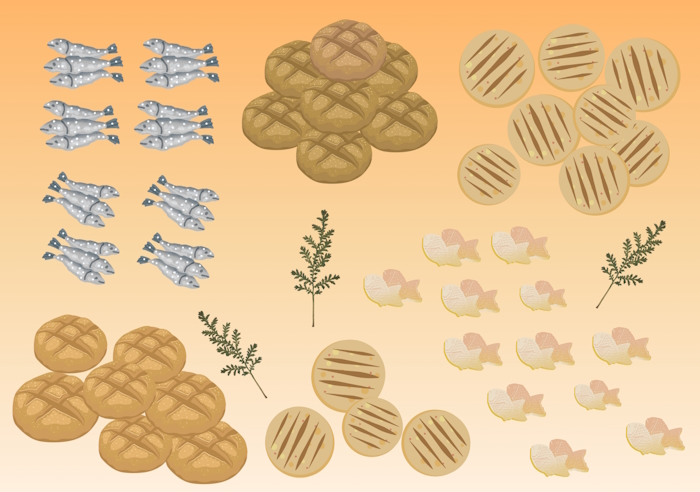今年2017年は明治の文豪・夏目漱石の生誕150 年。漱石やその周辺、近代日本の出発点となる明治という時代を呼吸した人びとのことばを、一日一語、紹介していきます。
【今日のことば】
「パリにいたころ、フランス人は私を牡丹と呼びましたのよ」
--岡本かの子
岡本かの子は、天真爛漫なナルシストだった。己の美貌を確信し、掲出のような台詞をさらりと口にした。『母子叙情』『老妓抄』『家霊』といった豊満で妖しい唯美的小説作品を紡ぐにも、このナルシシズムが一役買っていたに違いない。
生まれは明治22年(1889)。与謝野晶子に師事して、歌人として出発した。処女歌集『かろきねたみ』の上梓は、大正元年(1912)12月のこと。全編肉筆木版刷りのこの歌集は、先輩歌人・斎藤茂吉の目にもとまり、雑誌『アララギ』に賞賛の辞が掲載された。
そんな嬉しい出来事の裏で、その頃、かの子の心は激しく揺れていた。
漫画家である夫の岡本一平が、家庭を顧みず放蕩三昧に明け暮れていた。そのため、行き場を失ったかの子の豊かな恋情は、わが子・太郎を慈しむだけでは燃焼しきれず、いつしか若き文学青年に向かっていた。かの子の女心は、ふたつに引き裂かれていく。
時を重ねるように、かの子は敬慕する兄と最愛の母を亡くす。ふたりとも、「偏愛」と言っていいほど、かの子を可愛がってくれた肉親だった。ひび割れたかの子の胸に、激しい悲嘆の波が押し寄せる。心の堰は切れて錯乱状態に陥り、ついに、かの子は入院を余儀なくされた。
かの子の退院後、夫婦と子供に妻の愛人を加えた4人の奇妙な同居生活がはじまった。それを後押ししたのは、他ならぬ夫の一平だった。妻の精神に破綻をもたらしたそもそもの原因は、自分の放蕩にある。妻の恋する情人をそばに置くことでその心が安定するなら、それでいい。一平は、自分にそう言い聞かせていた。
かの子は、三度の食事より恋愛を生きる糧とし、夫公認の美青年との愛欲に溺れていく。
この奇異な同居生活は、青年に新たな恋が生まれたことで破綻。だが、何年かの時を経て、かの子には再び若い外科医の愛人ができた。その後、画家志望の太郎を連れての夫婦の洋行にも、外科医は当たり前のように付き添った。そんな摩訶不思議な私生活の充実を基底に、かの子は創作に励んだ。
昭和14年(1939)2月18日、かの子は夫と愛人に看取られながら黄泉路へ旅立つ。死に至る病床についてのち、かの子は一度も鏡を見ることがなかったという。自らが確信的に愛した「美貌」の中に、些かたりとも、やつれや醜さを見いだすのを拒絶し、ナルシストであることを貫いたのだ。
柩の中には、夫の一平によって、あふれんばかりの薔薇の花が敷きつめられた。パリで訃報に接した息子の岡本太郎は、父宛ての手紙にこう綴った。
「お母さんのそばに近づくものは、お母さんの情熱に焼きつくされずにはいなかった。お母さんは本当にただ事ではない美しい人生を生きおおせました」
文/矢島裕紀彦
1957年東京生まれ。ノンフィクション作家。文学、スポーツなど様々のジャンルで人間の足跡を追う。著書に『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫)『漱石「こころ」の言葉』(文春新書)『文士の逸品』(文藝春秋)『ウイスキー粋人列伝』(文春新書)『夏目漱石 100の言葉』(監修/宝島社)などがある。2016年には、『サライ.jp』で夏目漱石の日々の事跡を描く「日めくり漱石」を年間連載した。