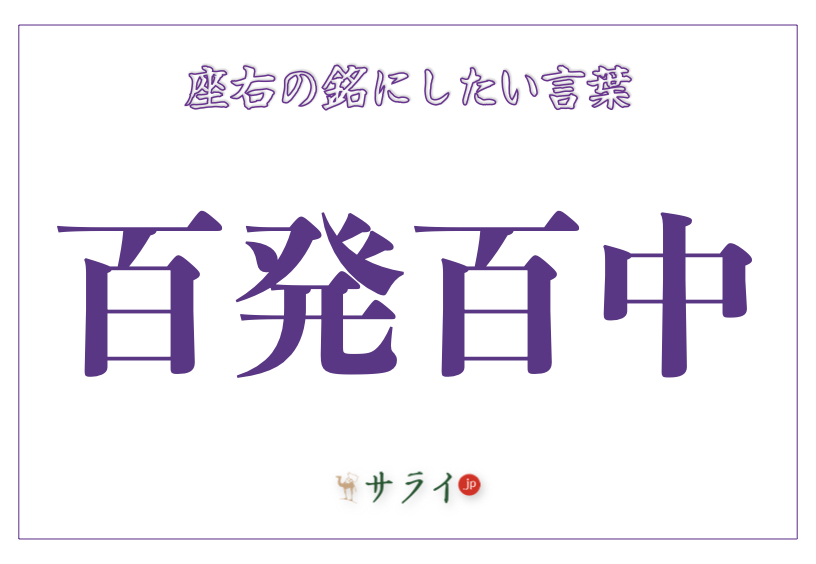日本酒の産地として名高い兵庫県。とりわけ「灘」は、日本酒の最高峰の産地として知られています。なぜ兵庫の日本酒がこれほど評価されているのか。その歴史的背景から現代の名酒蔵まで、兵庫の日本酒の魅力を探ってみましょう。
文/山内祐治
目次
兵庫県の日本酒、知られざる「灘五郷」の歴史と伝統
なぜ兵庫県が日本酒の一大産地になったのか
兵庫県が誇る個性豊かな酒蔵たち
兵庫県が誇る高級日本酒の世界
兵庫県のおすすめ日本酒。初心者からマニアまで楽しめる一杯
まとめ
兵庫県の日本酒、知られざる「灘五郷」の歴史と伝統
兵庫県といえば、日本酒を語る上で絶対に外せない土地です。県の清酒製造量は年間約9万400kL(2023年度)で全国の約3割。県内に66蔵が立地し、日本有数の“量と多様性”を併せ持つ酒どころです。 なかでも「灘」は日本酒の聖地と称されるほど。歴史をたどると、かつて奈良や京都で栄えた酒造りは、やがて西へと広がり、大阪の池田や兵庫の伊丹へと移りました。その後、さらに西へと発展する中で花開いたのが兵庫県西宮市を中心とする「灘」と呼ばれる地域です。
灘が日本酒造りに適していた理由はいくつもありますが、宮水(低鉄・高ミネラル)、冬季の六甲おろしによる低温発酵、江戸へ大量輸送した樽廻船という“水・気候・物流”の三点が歴史的に噛み合った点にあります。宮水は日本酒造りに悪影響を及ぼす鉄分が少なく、かつミネラルが豊富に含まれています。江戸時代、このような水質は大変重宝されました。
現在、灘は「灘五郷」として地理的表示(GI)にも認定されており、西郷、御影郷、魚崎郷、西宮郷、今津郷の5つの里に分かれています。公式に保護されており(製造・貯蔵工程を郷内で行う等の基準)。地域名と一体の品質を示す制度で、産地名表示の信頼性を高めています。ここには「沢の鶴」「菊正宗」「白鶴」といった誰もが知るナショナルブランドから、知る人ぞ知る銘酒まで、様々な酒蔵が軒を連ねています。
なぜ兵庫県が日本酒の一大産地になったのか
兵庫、特に灘地方が日本酒の一大産地となった背景には、いくつかの恵まれた条件がありました。
まず第一に“水”です。前述の「宮水」という良質な湧き水が、日本酒造りに最適でした。
次に“米”です。兵庫県北部には良質な米の産地が広がっており、特に現在では酒米の王様とも呼ばれる「山田錦」の最高峰を産出する“特A地区”と呼ばれるエリア、東条や三木といった地域があります。さらに播磨一帯では“GIはりま”も運用され、“兵庫県産山田錦100%”という厳格な要件で“兵庫=山田錦”の個性を前面に出しています。
そして“物流”の面でも優位性がありました。灘には港があり、江戸時代には大消費地である江戸へと船で日本酒を大量に運ぶことができました。
加えて“人的資源”も豊富でした。丹波などの米作り地域では、冬場になると農閑期となり、その時期に酒造りに携わる“蔵人”を多く輩出しました。これが、丹波杜氏につながっていきます。
このように、米作り、醸造技術、物流、そして人材まで、すべての条件が揃っていたことが、兵庫、特に灘が日本酒の一大産地として発展した理由なのです。なお、“伊丹諸白”と“灘の生一本”は日本遺産に認定されており、近世からの清酒文化を、街並み・技術・物流の物語として今に伝えています。
兵庫県が誇る個性豊かな酒蔵たち
兵庫県には多種多様な酒蔵があります。まずは灘の大手酒蔵として、白鶴酒造、菊正宗酒造、沢の鶴、白鷹、大関などが挙げられます。これらの酒蔵では資料館や酒蔵見学ツアーも開催されており、日本酒の歴史や製造工程を学ぶことができます。
一方、モダンな酒質設計で注目を集める酒蔵もあります。山陽盃酒造の「播州一献」は、丁寧な製法で柔らかい甘さとキリッとした締まりを併せ持つ、モダンなタイプの日本酒を生み出しています。どの特定名称酒も高いクオリティを保ち、幅広く楽しめる銘柄です。
また「龍力」を醸す本田商店は、特に酒米・山田錦の特性を追求する酒造りに定評があります。集落ごとの山田錦の違いを研究し、テロワール(土地の特性)を表現する取り組みは非常にユニークなもの。また同蔵ではクラフトジン「Terroir A」も製造しており、山田錦の特徴を映し込んだ、余韻の長さと膨らみを感じさせます。
山廃や熟成酒への取り組みに定評がある下村酒造店の「奥播磨」も、ファンの間で人気の銘柄です。時間をかけて熟成させることで、広がりのある奥深い味わいを実現しています。
このように兵庫県は、伝統的な大手酒蔵から革新的な小規模酒蔵まで、幅広い選択肢があります。どの酒蔵にも、意外な掘り出し物が見つかる可能性があり、その楽しみは尽きません。
兵庫県が誇る高級日本酒の世界
兵庫における高級日本酒として思い浮かぶのは、山田錦、生酛、そして熟成酒といったキーワードです。兵庫県には大手酒蔵が多く、ある程度まとまった量で品質の高い熟成酒を製造できることが強みです。単に時間をかけるだけでなく、様々な工夫を凝らした熟成酒も多く見られます。
例えば、菊正宗酒造では本来吉野杉の樽酒が有名ですが、ミズナラ樽で熟成させるために、酒精強化し、糖分を残した造りと樽熟成の風味の掛け合わせを行っています。またSAKE HUNDREDの「現外」は、1995年に発生した阪神淡路大震災の際に被害を受けた沢の鶴のタンクに残っていた酒母を熟成させたもので、ストーリー性と味わいの両方で非常に評価が高い製品です。もう二度と意図的に同じ製品を造ることはできないため、熟成の年を重ねるごとに、その価値にふさわしい価格改定がなされています。
熟成酒以外にも、米の表皮をより多く削った山田錦を原料とする純米大吟醸など、様々なタイプの高級酒が揃っており、酒質設計で大きくその表情を変えます。兵庫の高級日本酒は、日本酒をはじめて楽しむ方からベテランまで、様々な好みに応える多様性があります。

https://jp.sake100.com/products/gengai
兵庫県のおすすめ日本酒。はじめてからマニアまで楽しめる一杯
兵庫県のおすすめ日本酒としては、まず生酛造りのお酒は外せません。大阪の池田から、伊丹、灘とつながるエリアにおいて生酛造りが丹波杜氏の手によって高度化、発展します。その伝統を受け継ぐものは特に日本酒らしい風味を楽しめます。
また、日本の歴史における有名な日本酒の一つとして「剣菱」が挙げられます。伝承ですが、忠臣蔵の赤穂浪士が飲んだとされるのが、この「剣菱」。白樫蔵元もそうおっしゃっています。江戸時代の草双紙の黄表紙などにも登場し、幕末や明治時代の偉人たちも愛飲したという歴史あるこのお酒は、元々、伊丹で醸造されていましたが、現在は灘に蔵を移しています。そのため剣菱酒造のラベルには今でも「丹醸」(伊丹の「丹」と醸造の「醸」)という言葉が残されているのです。
剣菱酒造では、複数のお酒をブレンド(アッサンブラージュ)することで、酒質の均一化・安定化を図っています。グレードが上がるほど熟成酒の比率が高くなり、深みのある味わいを楽しめるでしょう。和食全般との相性も抜群で、日本酒の奥深さを実感できます。
まとめ
兵庫の日本酒の最大の魅力は、その幅広さにあります。日本酒造りの総量でナンバーワン。山田錦に代表される酒造好適米生産量でもナンバーワン。こうした日本酒造りにその名を残す県だけあって、どの酒蔵も興味深い歴史や特徴を持っています。
ぜひ実際に現地を訪れ、酒蔵見学や試飲を通じて、兵庫の日本酒文化を体験してみてください。日本酒をテーマにした旅行先として、兵庫はまさに理想的な目的地なのです。

山内祐治(やまうち・ゆうじ)/「湯島天神下 すし初」四代目。講師、テイスター。第1回 日本ソムリエ協会SAKE DIPLOMAコンクール優勝。同協会機関誌『Sommelier』にて日本酒記事を執筆。ソムリエ、チーズの資格も持ち、大手ワインスクールにて、日本酒の授業を行なっている。また、新潟大学大学院にて日本酒学の修士論文を執筆。研究対象は日本酒ペアリング。一貫ごとに解説が入る講義のような店舗での体験が好評を博しており、味わいの背景から蔵元のストーリーまでを交えた丁寧なペアリングを継続している。多岐にわたる食材に対して重なりあう日本酒を提案し、「寿司店というより日本酒ペアリングの店」と評されることも。
構成/土田貴史