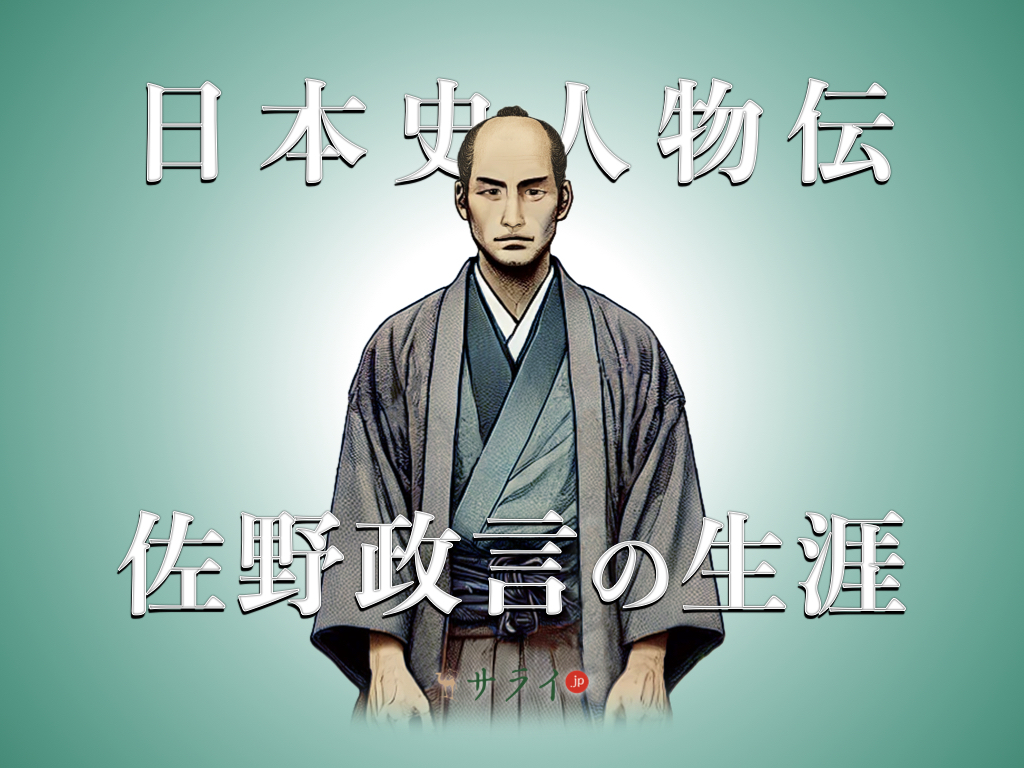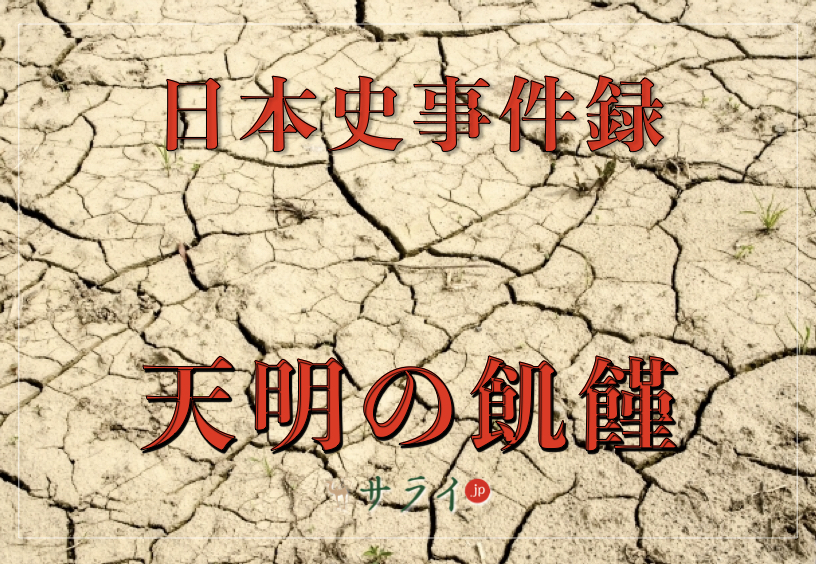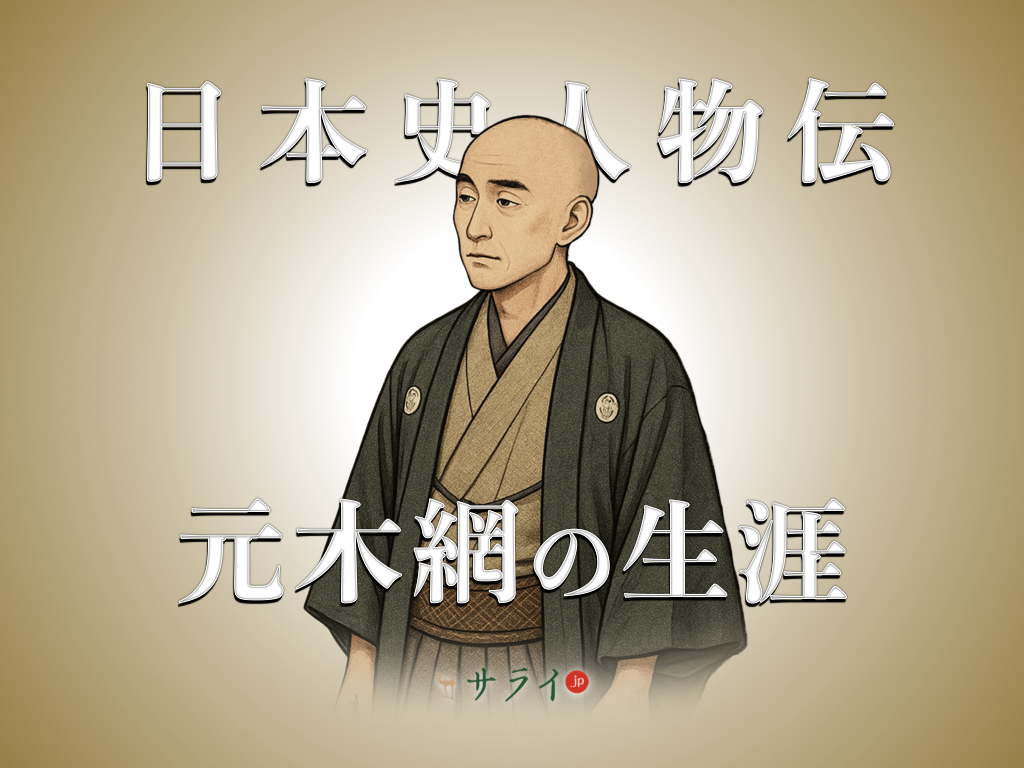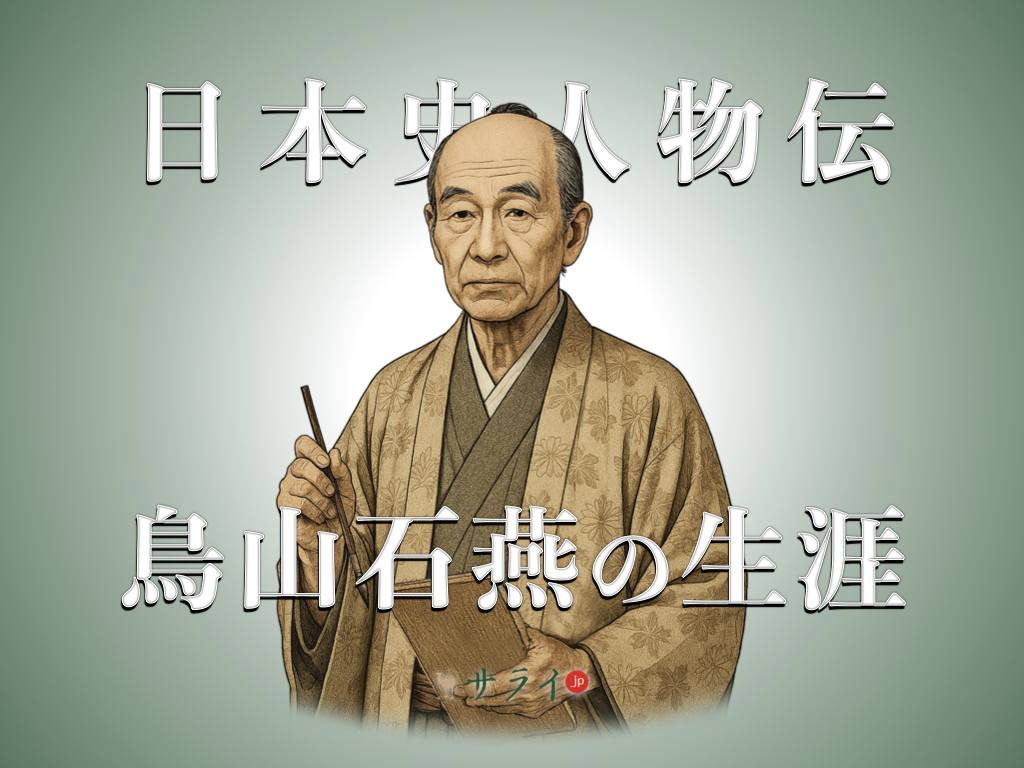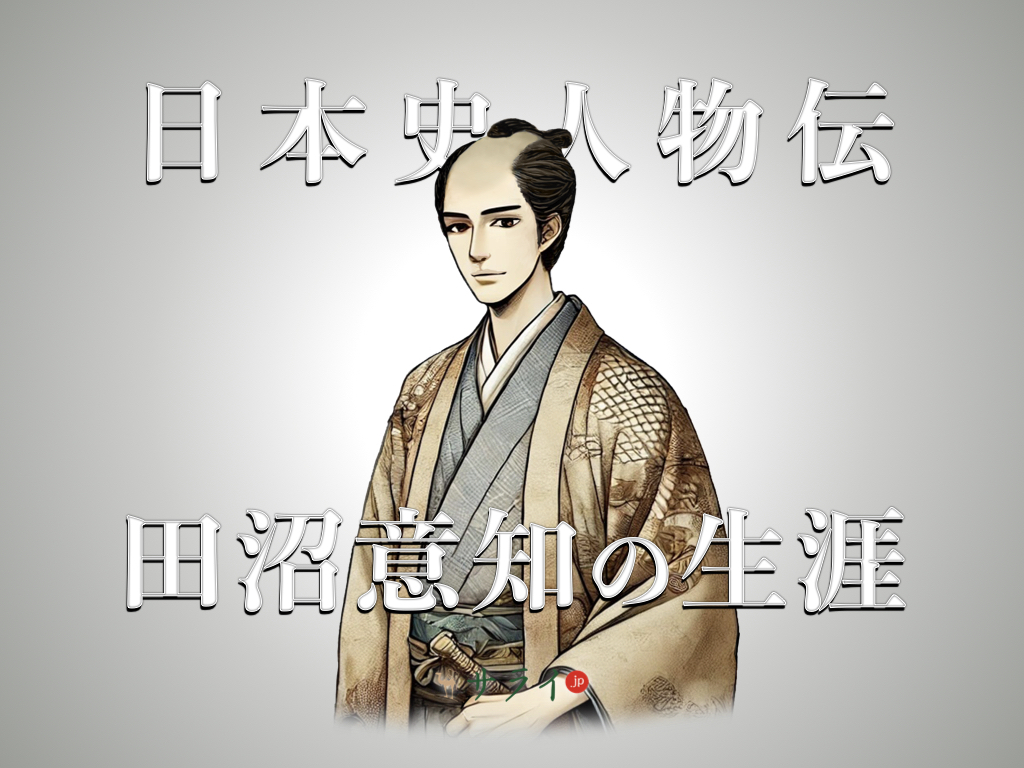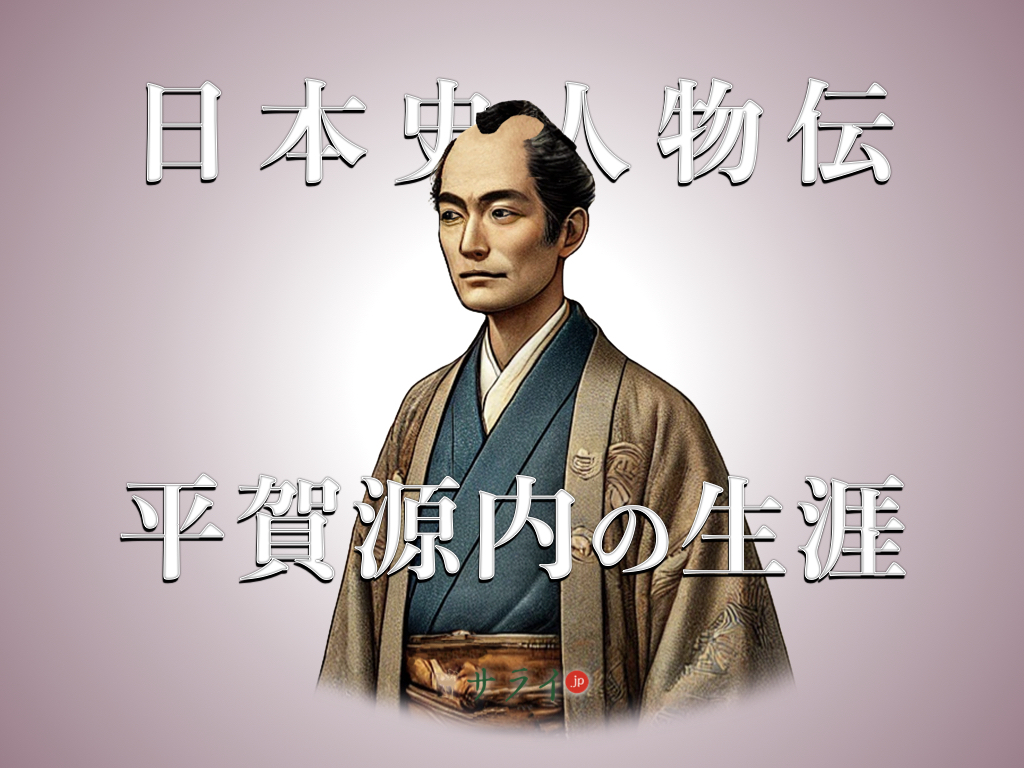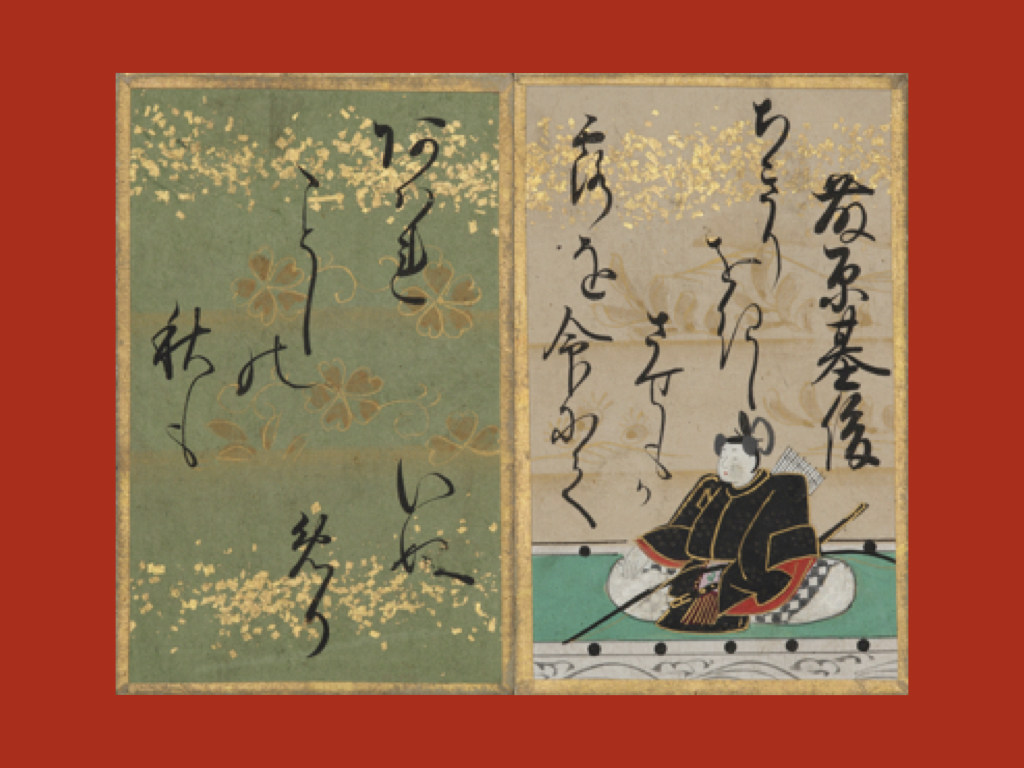はじめに-佐野政言とはどのような人物だったのか
「佐野政言(さの・まさこと)」の名前を、どこかで耳にしたことがあるでしょうか? 江戸時代後期、若年寄・田沼意知(たぬま・おきとも)に刃傷沙汰を起こしたことで知られる中級幕臣です。意知の死によって、政言は「世直し大明神」と称えられ、庶民から熱烈な支持を受ける存在となりました。
彼はなぜ刃傷に及び、どのような最期を迎えたのでしょうか? 史実をもとに辿っていきます。
2025年NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、反田沼の世直し大明神(演:矢本悠馬)として描かれます。

目次
はじめに-佐野政言とはどのような人物だったのか
佐野政言が生きた時代
佐野政言の生涯と主な出来事
まとめ
佐野政言が生きた時代
佐野政言が生きた18世紀後半の江戸は、田沼意次による改革政治のさなかにありました。
商業を奨励し、経済活性化を目指した田沼政治は、成果を上げる一方で、賄賂や縁故による昇進が横行。庶民や下級武士たちの間には不満も渦巻いていました。
そんななか、天明4年(1784)に起こった佐野政言による刃傷事件は、田沼政権への反発感情と結びつき、社会に大きな衝撃を与えることになります。
佐野政言の生涯と主な出来事
佐野政言は宝暦7年(1757)に生まれ、天明4年(1784)に没しました。その生涯を、出来事とともに紐解いていきましょう。
家柄と立身を目指して
佐野政言は宝暦7年(1757)、上野国甘楽郡に400石を領する佐野家に生まれました。佐野家は鎌倉時代から続く名門で、政言は源左衛門常世の末裔にあたります。父・政豊の跡を継ぎ、大番士から新番士へと転じました。
しかし、家禄は中程度で、さらなる出世を望んだ政言は、家系の上で佐野家の家来筋にあたる田沼意次・意知父子に賄賂を贈り、後ろ盾を求めます。

積もった私憤
ところが、意知は賄賂を受け取ったにもかかわらず政言の願いを聞き入れず、逆に佐野家に伝わる七曜旗や系図まで奪い取ったとされます。さらに、将軍・家治の鷹狩に従った際には、雁を射落とした功績を認められず、他の者だけが褒美を受けるという屈辱も味わいました。
こうした数々の私憤が、政言の心に重く積み重なっていったのです。

【江戸城中での刃傷事件。次ページに続きます】