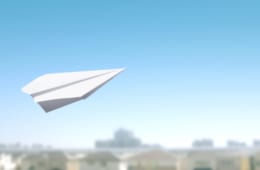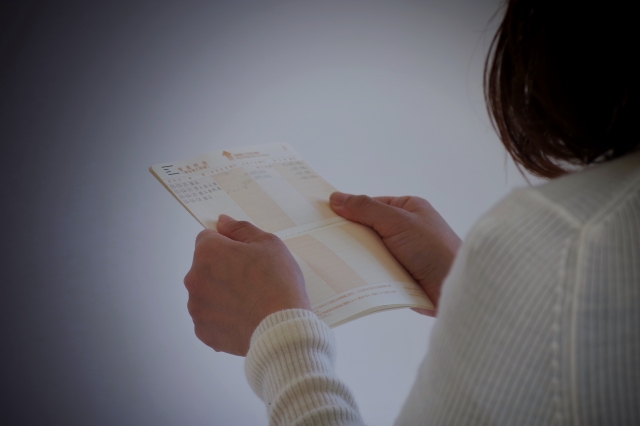文/印南敦史

『老後ひとり暮らしの壁』(山村秀炯 著、アスコム)には、「身近に頼る人がいない人のための解決策」というサブタイトルがついている。つまりはそれだけ、老後にひとり残される人が多いということなのかもしれない。
そして重要なポイントは、“誰も頼る人がいない老後ひとり暮らし”は誰にでも起こりうるということである。いま、無理なく日常を送れているなら、気にする機会もあまりないだろう。とはいえ、決して人ごとではないのだ。
ちなみに著者は、愛知県を中心に遺品整理、生前整理などの事業を行っている人物。さまざまな問題に直面してきたからこそ、老後のひとり暮らしには、若いころや家族と暮らしていたときとは違った「壁」があるものだと実感するのだという。
多くのおひとりさまとお会いする中で感じるのは、「壁」を上手に越える人と、「壁」を見て見ぬ振りをする人がいること。そして、うまく「壁」を越えられる人ほど、自分の生き方に納得していて、幸せに暮らしているように思えます。(本書「はじめに」より)
もちろん、幸せかどうかは本人の感じ方にもよる。だが、実際に暮らしぶりや部屋の様子などを見る限り、“なんの不安も後悔もなくスッキリしている人”には(1)「自分でできないことが増えても、自分で決める」、(2)「孤独は適度に楽しみながらも、孤立はしない」という共通点があったようだ。
たしかにこれは、見逃してはならないことである。軸としての“自分”を維持することができれば、壁を越えて生きられる――納得して“いま”を生きることができる――はずなのだから。
まず(1)「自分でできないことが増えても、自分で決める」に関しては、「コレクション」を例に挙げて考えてみればわかりやすいかもしれない。
模型であれレコードであれ、なにかを集めていた人にも、どこかのタイミングでそれらを「捨てようかな」「処分しようかな」と考えたりすることはあるものだ。
そんなとき、自分の意思で捨てるのだとしたら納得もできるだろう。しかし、家族や他人に捨てられるとしたら腹が立つものでもある。家族や他人は「どうせ捨てるのだから同じだろう」と考えるかもしれないが、当人にとっては自分の意思が非常に重要だからだ。
たとえ同じ結果になろうとも、自由意志で決めたという体験があるかどうかで本人の満足度は大きく変わります。(本書55ページより)
もちろん老後のひとり暮らしでは、なんでも自分でやりたいと思っていたとしても、できることは徐々に減っていくに違いない。だからこそ変化を受け入れて、早めに自分でどんどん決めていくことが大切なのだ。
それができる人は、スムーズにひとり暮らしの壁を越えられていると著者もいう。
また、人間関係は大きなストレスの原因になるものでもあるので、(2)「孤独は適度に楽しみながらも、孤立はしない」も重要な価値観ではあるだろう。ただし、「孤独と孤立は違う」ということを忘れるべきではない。孤独は“感覚”であり、孤立は他者と切り離された“状態”だからである。
このことに関連し、著者は『ムーミン』シリーズに登場するスナフキンを引き合いに出している。
彼は孤独を愛しています。他人に干渉されることなく、自分の思うままに生きる。おひとりさまの達人です。(本書57ページより)
とはいえスナフキンと、友人であるムーミン一家との関わりも『ムーミン』には描かれている。つまりスナフキンは、ひとりの時間を大切にしながらも、決して孤立はしていないのだ。
これは、老後ひとり暮らしの壁を越えるためにも大切なポイントになるそうだ。
歳をとれば、話し相手や相談相手、身元を保証してくれる人、日常生活の世話や介護を頼める人、死後の手続きを頼める人など、セーフティネットとして必要な人間関係というのが出てきます。(本書60ページより)
たしかに、おひとりさまには「人に頼りたくない」「迷惑をかけたくない」という人が少なくない。もちろん、それも個人の選択肢ではあるだろう。しかしそれでも、できないことは人にやってもらってもいいのだ。
ただし、自分ができることは積極的に人に提供するべきでもある。それが共同体を支える相互扶助なのだから。自分や相手になにかあったとき、助け合える誰かがいることはとても大切なのである。
自立することは孤立することではありません。壁をうまく越える人は、ストレスにならない適度な人間関係を上手に築いています。(本書61ページより)
いつか訪れるかもしれない老後ひとり暮らしを成功させるために、この文章は頭にとどめておいたほうがよさそうだ。
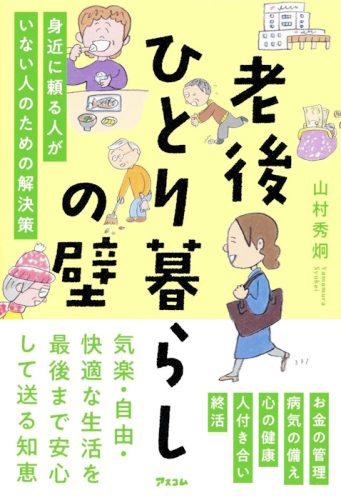
山村秀炯 著
1540円
アスコム
文/印南敦史 作家、書評家、編集者。株式会社アンビエンス代表取締役。1962年東京生まれ。音楽雑誌の編集長を経て独立。複数のウェブ媒体で書評欄を担当。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)、『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)、『人と会っても疲れない コミュ障のための聴き方・話し方』『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)、『書評の仕事』(ワニブックスPLUS新書)などがある。新刊は『「書くのが苦手」な人のための文章術』(PHP研究所)。2020年6月、「日本一ネット」から「書評執筆数日本一」と認定される。