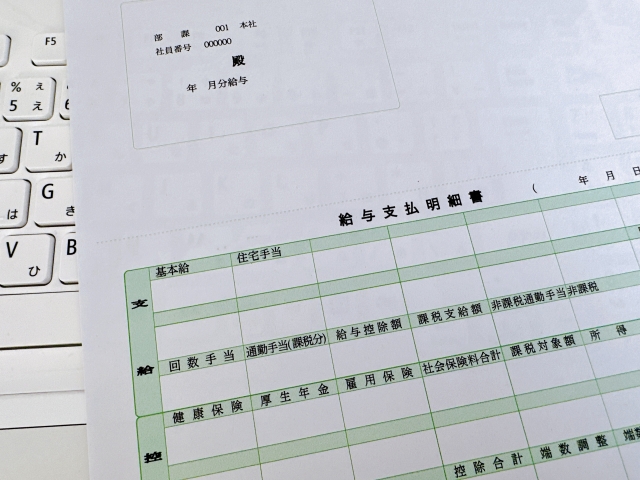マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)」が、ビジネスの最前線の用語や問題を解説するシリーズ。
はじめに
野球・サッカー・バレーボールなどの集団スポーツで、常に強いチームを維持し続けるためにはどのようなマネジメントが必要でしょうか? 何度も県大会を勝ち進み毎年のように全国大会に出場しているチームにはどんな特徴があるのでしょうか? さまざまな手法はありますが、今回は識学の理論を軸に、スポーツに学ぶ組織マネジメントについてお伝え致します。
監督は必要か?
監督不在のチームを時折みかけますが、常に大会上位にいるようなチームでずっと監督が不在な状態は見たことがありません。そもそも、なぜ監督は必要なのでしょうか?
監督が不在であれば、情報収集、戦略立案、フォーメーションの確立、各ポジションの役割設定、全体で守るルールの決定、練習方法の考案、メンバーの選定、試合中の選手の交代、試合中の戦略変更、各選手の管理・評価など、多岐にわたる役割を選手がしなければいけません。選手は自らを成長させるために工夫し練習をこなすためのリソースがなくなり、チームを勝利に導くための責任を持つ意思決定者が不在であればチームは迷走していきます。
毎年選手の能力差は違っても勝ち続けるには監督という役割が必要です。監督が監督の役割を果たし、選手が選手の役割を果たしてこそチームの力は最大化します。そして、本来監督とは1つの大会の一時的な勝利だけでなく、長期的に勝ち続けるチームにすることが求められるのです。そのために必要なマネジメントについて、今回はルールと役割、選手の管理の重要性に絞って、3つの視点から解説していきます。
1.全体で守るルールの決定
常に大会上位にいるようなチームには規律があります。規律とは決定したルールを守っている状態を維持できているということです。グラウンドに入るときは一礼する、道具を投げないなどルールの種類は様々です。上手い下手関係なく誰でも守れるレベルのルールを設定してそれが守れる状態を維持できるかが強いチームの第一歩です。それはなぜでしょうか? その本質を理解しないとこれぐらいいか……と緩くなりいつしかチームは弱くなっていきます。
ルールは守れるように習慣化するまでは、守る方も守らせる方もストレスがかかります。ルールを守らせることに背を向けるということは、いい戦略を決めても、いい練習方法を決めても実行する人、しない人にバラツキがでます。選手が戦略を実行し、決めた練習方法に全力で取り組んだ結果負けたのであれば、戦略や練習方法を見直して改善を続けていけばチームは強くなります。勝つためのノウハウも積み重なっていきます。
しかし、ルールも守れない集団は決めた練習方法にも全力で取り組まないし、戦略も実行できないため、戦略が悪かったのか、実行しない人がいるから勝てないかもわからずに迷走します。そして、ルールを守る人、守らない人で不和が生まれ衝突することもあります。最初は嫌々だったとしても、同じルールを守り続けることは仲間意識も醸成するのです。
誰でも守れるレベルのルールを守れない選手は必ず指摘をすること、そして、指摘をしても守れない選手はどれだけ能力があってもスタメンから外す決断をするべきです。
これは、我々が会社組織をコンサルティングする時も同様のことを伝えます。いくら会社の商品や戦略が良くても、ルールを守り戦略に沿って改善できる組織になっていなければ、他社に追いつかれてしまうのです。
2.フォーメーションの確立と各ポジションの役割設定
スポーツでいうフォーメーションとは、会社での組織図です。そして、各ポジションにどんな役割を設定するかでチームの勝利の確率が変わります。
私たちは組織づくりの基本として適材適所ではなく、「適所適材」をするように推奨しています。対戦相手を研究し、勝つためのフォーメーションを決めて役割を設定し、それから適した人を選んでいくことが重要です。人の特性に合わせたフォーメーションだと、勝つための合理性とズレが生じたとき、チームは勝てなくなります。
前述したように各ポジションの役割を決めても、誰でも守れるルールを守れないようなチームの選手は試合中も自分の役割を無視して好きに動きますので注意しましょう。
また、役割が曖昧であれば選手が良かれと思った動きが、監督の意図した行動とズレることもあります。サッカーであれば、どのエリアをカバーするのか、この場面は攻める、この場面は守るというのはもちろん、1対1の成功率、フリーの場面でのシュート得点率など、必要な役割を数値化することも重要です。
勝つために一人一人がどんな役割を果たすのかを明確化すれば、自分が役割を果たす為にどんな練習をすればいいか見えてきます。全体練習を決めて実行させることも大事ですが、選手の役割を明確化して自主練習で何をするべきかを選手自ら考えさせ実行できる環境を作りましょう。
3.選手の管理・評価
役割に対して目標を設定し、目標が達成したのか未達だったのかを評価し、未達だったのであれば分析と次の行動変化(改善策)を選手に考えさせる。そして、最後に次の目標を再設定して約束する。これがあるべき管理の姿です。
出来ないことをただ叱責して精神的に追い詰めてしまうことは正しい管理ではありません。選手を委縮させ思考停止になり、上手くいかないのは自分のせいではないと他責の思考になって成長も出来ません。選手に考えさせ、自ら意思決定させて行動する環境を作れるかが重要です。
毎日ノートを書かせる監督もいますが、選手が書いてくる内容がただの感想になっては成長できません。成長とは「出来なかったことが出来るようになること」です。選手の不足を明確にして、不足を埋めるための行動変化(改善策)は選手に考えさせる。そして、フィードバックを行い、次の目標を明確にして約束しましょう。
まとめ
スポーツも会社組織もチームで目標を達成するためには、決められたルールを守る環境を作り、同じ方向を向かせる。そして、勝つために必要なフォーメーションを考え、個々がチームに必要な役割を正しく認識できる状態にする。最後に、成長するために自ら考え実行できるような環境を作り評価する。この原則を押さえるべきです。
監督にカリスマ性があり監督が言ったことを忠実に実行できるチームは勝てるようになりますが、チームが勝つだけでなく、選手の先の未来を見据えた育成も考えるのであれば、選手に自ら考えさせるような環境作りが必要です。
今回、考察した強いスポーツチームの勝ち続ける原則が、会社組織を運営するためのヒントになったようであれば幸いです。
識学総研:https://souken.shikigaku.jp
株式会社識学:https://corp.shikigaku.jp/