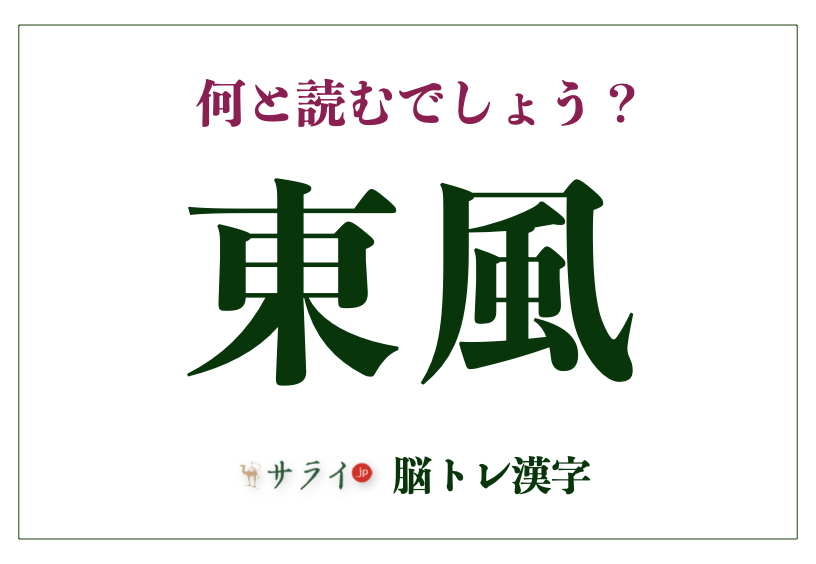救荒食の“お助けイモ”から“嗜好品”へ。食の高みを究める日本の焼き芋文化とは

サツマイモが日本へ入ったのは江戸時代の初期。中国から沖縄を経て鹿児島や長崎で栽培され、江戸後期には東北地方へも達した。
「中南米原産の作物なので寒さに弱く、種芋の管理技術が未熟だった時代は栽培が西日本の一部にとどまっていました。関東まで広がったきっかけは享保の飢饉です」
こう語るのは、埼玉県川越市にあるサツマイモまんが資料館館長の山田英次さんだ。飢饉は享保17年(1732)に発生。1万人前後もの死者が出たというが、サツマイモを植えていた瀬戸内海の島や薩摩藩領では餓死者が出なかった。これに注目したのが儒学者の青木昆陽だ。栽培を奨励する提案書『蕃薯考(ばんしょこう)』を幕府に提出して採用される。
「干ばつや台風に強く、やせ地でも作れる安定性に期待が高まったのです」(山田さん、以下同)
“お助けイモ”と呼ばれる所以だが、さらに広がりを見せる。
「米を補う経済的な食べ物として庶民たちに受け入れられていきます。下級武士の日記にも米に混ぜて炊いたという記述があります。間食としても食べられました」
持ち味の甘さが認知されるなかで誕生したのが、焼き芋という食べ方だ。蒸かし芋より水分が少ないため、より甘みを感じる。
「1800年頃の江戸では焼き芋が大人気で、商品になっていました。木戸番屋(町の詰め所番)の副業として広がるほどでした」
当時の焼き芋は、蓋つきの平釜に並べ蒸し焼きにしたもの。明治になって都市人口が急増すると、安くて腹が膨れる焼き芋は江戸時代以上に喜ばれる。大量生産をこなす専門店も続々と登場した。
石焼き芋の登場は昭和26年

状況が変わるのは関東大震災後だ。パンや洋菓子が増え、甘味の代表格だった焼き芋の影は急激に薄れる。救世主が中国から入ったつぼ焼きの技術だった。叉焼(チャーシュー)を焼く方法で作るつぼ焼き芋は場所を取らず、雑貨や駄菓子を売りながら扱える。目新しさもあり、新たな街の風物詩となっていく。
「さらに昭和26年、鉄板製の箱に小石を入れて焼く石焼き芋が登場します。この道具をリヤカーに載せて街を引き売りする姿は、戦後の都会を象徴する冬の風景です」



焼き芋市場はその後も拡大を続ける。画期的なのは電熱式焼き芋機の普及だ。管理が簡単なため、スーパーやコンビニ、ドラッグストアでも買えるようになった。
味の進化も見逃せない。品種や貯蔵・焼き方などの技術革新により、救荒食だったサツマイモは焼き芋という“嗜好品”になった。
写真協力/共同通信
解説 山田英次さん(サツマイモまんが資料館館長)

※この記事は『サライ』本誌2025年1月号より転載しました。