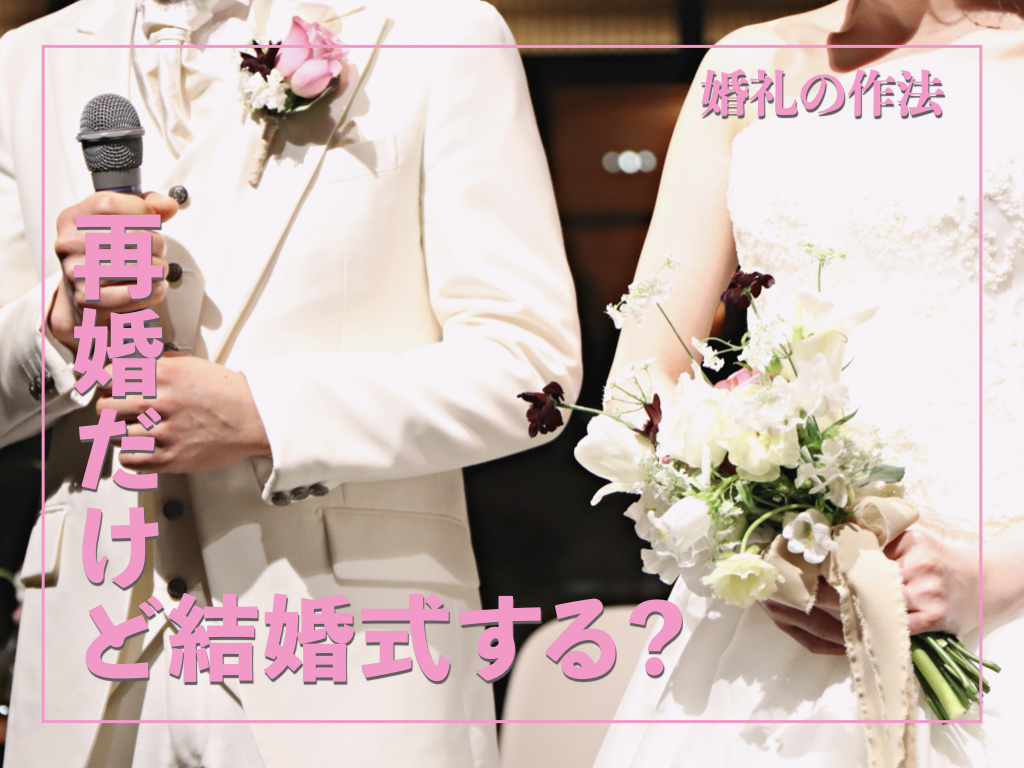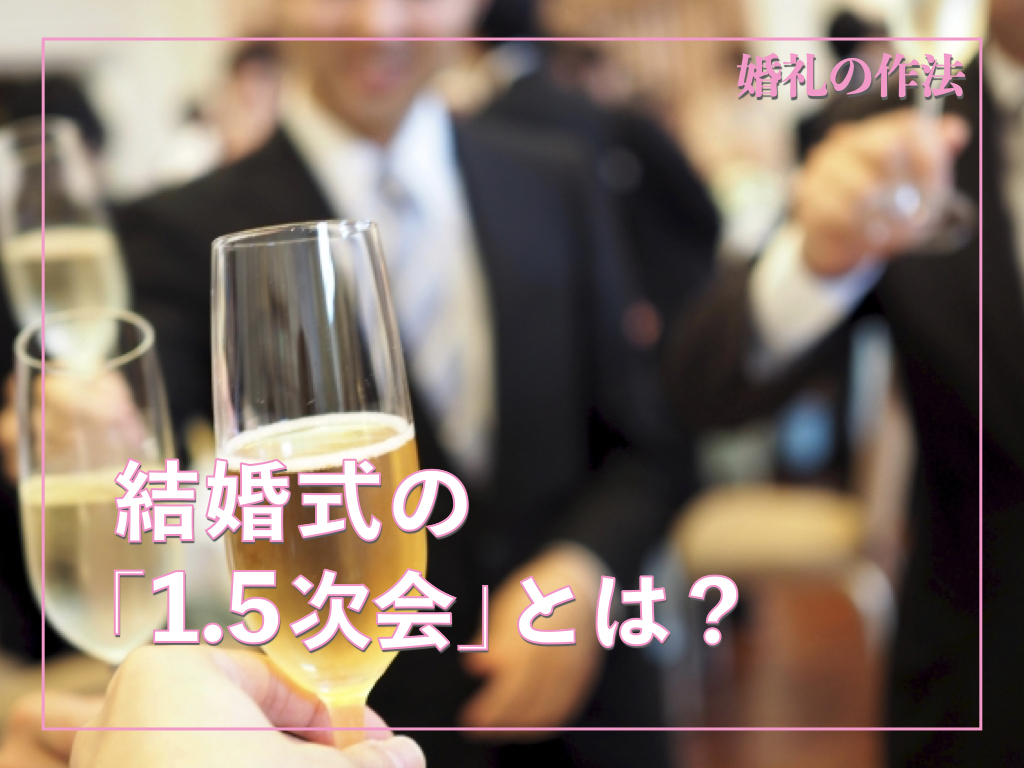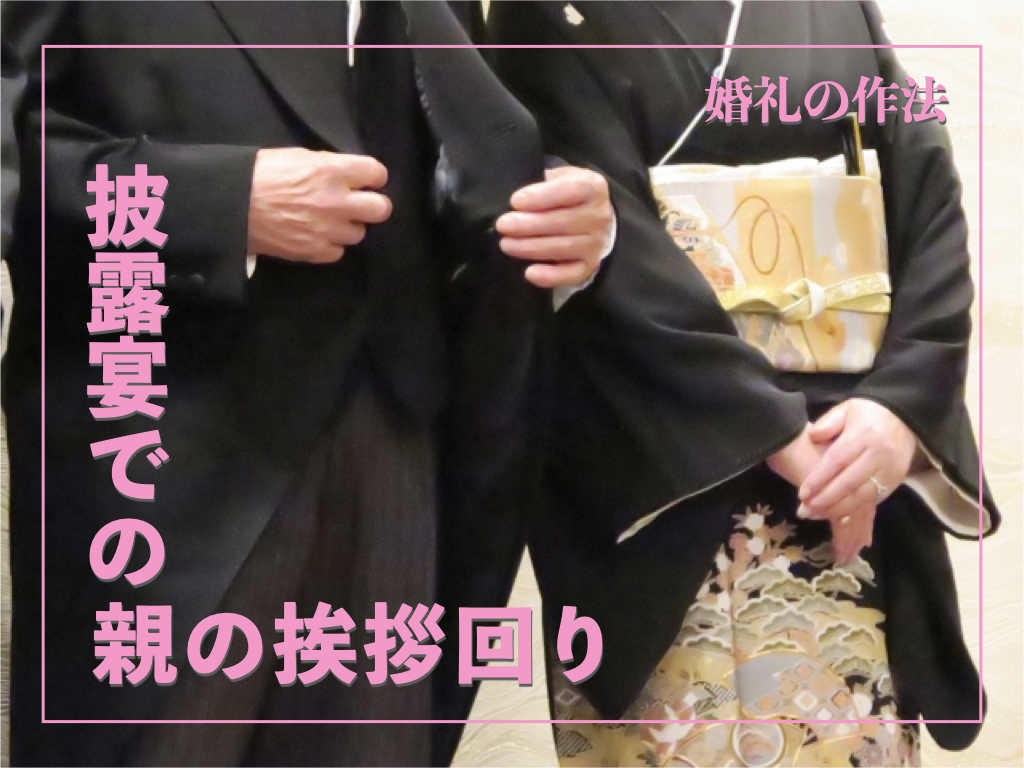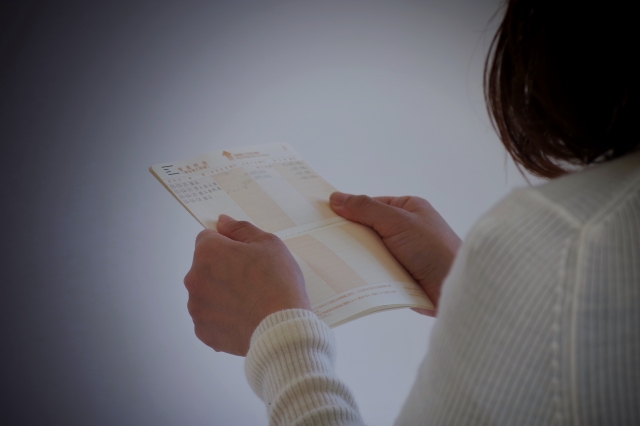近年、結婚式を挙げない「ナシ婚」を選ぶカップルが増えています。親としては戸惑いや不安を感じることもあるでしょう。本記事では、結婚式をしない理由や代替案、親としての関わり方について解説します。子どもの選択を尊重しつつ、家族や親戚との関係を円滑に保つためのヒントをお届けします。
目次
結婚式を挙げないカップルが増えている
結婚式の代替案と親の関わり方
結婚式をしない場合のご祝儀とマナー
最後に
結婚式を挙げないカップルが増えている
形式にとらわれず、自分たちらしい方法で人生の節目を迎えたい。そうした思いから、結婚式を行なわないという選択をするカップルも見受けられます。親としては少し戸惑いを感じることもあるかもしれませんが、背景や考え方を理解することは、円満な親子関係を送るうえで大切な第一歩になります。
結婚式を挙げない理由
結婚式を省略する理由は一つではありません。たとえば、準備にかかる時間や費用を抑えたいという実利的な理由のほか、職場や生活環境の変化で忙しく、落ち着いた時間を確保しにくいという事情があるのかもしれません。
また、本人たちの間で「人前に出ることに抵抗がある」「少人数で静かに過ごしたい」といった気持ちが共有されていることもあります。こうした判断は、軽視や放棄ではなく、むしろ二人がこれからの暮らしを大切に見据えている表れといえるでしょう。
「ナシ婚」「フォト婚」という選択肢
結婚式は挙げず、婚姻届の提出や写真撮影だけを行なう「ナシ婚」「フォト婚」も選ばれています。これらは儀式としての結婚式を重視するよりも、記念を形に残したいという意向が背景にあります。
こうしたスタイルに対して、親世代の中には「それで大丈夫なのか」と不安になる方もいるかもしれません。ただ、大切なのは当人たちが納得し合い、将来への区切りとして前向きにとらえているかどうか。形式より気持ちのあり方を大切にする姿勢も、現代らしい在り方のひとつといえるでしょう。

家族への配慮を忘れないカップルも
結婚式を挙げなくとも、親や祖父母への感謝の気持ちを持ち続けているカップルは多いものです。会食を設けたり、記念品を贈ったり、家族写真を残したりと、別の方法で感謝を伝える工夫をしている例もあります。
そうした小さな行動からも、子どもたちが家族との絆を大切にしている気持ちは伝わるものです。親としては、かたちにとらわれすぎず、その思いを温かく受け止める姿勢が求められます。
結婚式の代替案と親の関わり方
結婚式を挙げないカップルにとっても、人生の節目を大切にする気持ちは変わりません。その思いに寄り添いながら、親としてできる関わり方を模索することが、心の通う家族関係につながります。
ここでは、形式にとらわれず、感謝や祝福の気持ちを表現する具体的な方法と、親としての自然な関わり方を整理してご紹介します。
家族で集まる「節目の席」を提案する
披露宴の代わりに、料亭やレストランでの会食を節目として設ける方もいます。両家の顔合わせや感謝の場にもなります。
子どもたちが何も計画していなさそうであれば、親から「お祝いの記念に、両家で食事でもどう?」と声かけするのもいいでしょう。和やかな雰囲気をつくるために、形式張らず、家庭的な配慮を重ねることが肝要です。
写真撮影への同行や衣装選びでのサポート
フォト婚を選んだカップルの中には、衣装やスタジオ選びに親の意見を求める人もいます。とくに和装を希望する場合、親の経験や知識が頼りにされることも多いものです。子どもたちからの希望があれば、試着や撮影へ同行し、準備までの時間を親子で楽しむこともできます。
子どもから誘いを受けていない場合は、必要以上のサポートをするのは避けましょう。
「記念の贈り物」や「手紙」に気持ちを託す
言葉ではうまく伝えられない気持ちを形に残す手段として、親から記念品や手紙を贈るのも一つの方法です。たとえば、子ども時代の写真をまとめたアルバムや、家族の思い出を語る手紙は、結婚式以上に深い意味を持つでしょう。
贈る側も受け取る側も、自分のペースで気持ちを受け取れるので、感情を共有する場としても穏やかなものになります。形式よりも中身を重んじる現代の傾向に、静かに調和する手段です。
結婚式をしない場合のご祝儀とマナー
結婚式を行なわないスタイルが選ばれる中で、ご祝儀や贈り物、親族間のやり取りについて迷う場面も増えています。形式がないからこそ、礼節の示し方が難しく感じられることもあるかもしれません。
ここでは、ご祝儀やマナーに対する考え方と、親として心がけたい柔らかな対応の工夫について整理します。

ご祝儀の有無は相手との関係性を見ながら判断
結婚式を行なわない場合、必ずしもご祝儀を用意しなければならないという決まりはありません。ただ、親族や親しい知人の間柄では、お祝いの気持ちを形にして届けることが喜ばれる場合もあります。
ご祝儀という形にこだわらず、お祝い金や記念品として贈ることも一案です。大切なのは、贈る側の気持ちが相手にとって負担とならず、自然な形で伝わるように意識することです。
お祝いの品選びは「控えめで実用的」が喜ばれる傾向
記念の贈り物を考えている場合は、控えめで実用的なものが選ばれる傾向にあります。タオルセットやカタログギフトのような、日常に取り入れやすい品が喜ばれます。
あくまで気負わず、「ほんの気持ちです」と一言添えることで、相手にも過度な気遣いを与えることなく、礼儀を保つことができます。形式的な贈答ではなく、心の通うやりとりを大切にしましょう。
受け取る側の対応にも配慮を忘れずに
ご祝儀や贈り物を受け取る側にも、丁寧な対応が求められます。結婚式をしないと伝えていた場合でも、贈り物が届いた際にはお礼の連絡を入れることが望ましいでしょう。できれば、手紙やメッセージカードなどのかたちで感謝を伝えると、丁寧です。
親としては、そうした対応を子どもと一緒に確認したり、必要があれば補足してあげることで、親族間の円滑な関係を支える一助になります。
親族間でのマナーのすり合わせを早めに行う
親戚間で祝儀や贈り物の考え方に差があると、誤解が生じることもあります。「〇〇家は何も贈らなかった」「形式に欠ける」といった印象を防ぐためにも、親として早めに親族同士の意向を共有しておくと安心です。
ご祝儀を辞退する場合でも、簡単な文書や手紙などで伝えると、相手にとっても思いが伝わりやすいでしょう。
最後に
結婚式を挙げない選択は、現代では珍しいことではありません。親としては、子どもの意向を尊重し、柔軟に対応することが大切です。代替案やマナーを理解し、家族や親戚との良好な関係を築くためのサポートを心がけましょう。
監修/トップウエディング https://top-wedding.jp/
構成・執筆/吉川沙織(京都メディアライン)
https://kyotomedialine.com FB