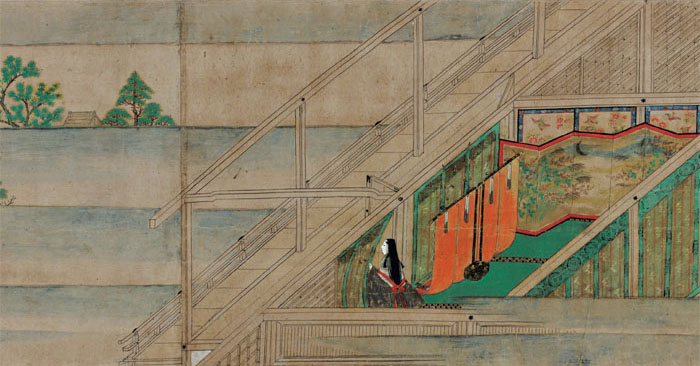人と有用微生物の出会いは太古に遡る。熟れ鮨、醬油、そして酒。複数の発酵を自在に操り、保存のみならず嗜好品にまで味を高める。先人の叡智の結晶である。

今なお人々を魅了する魚と米が醸し出す酸味
すしの原型は、塩に漬けた魚を飯とともに発酵させた『なれずし』 とされる。日本に現存する最も有名ななれずしといえば、琵琶湖沿岸で食べ継がれている鮒ずしだ。
「すしの語源は酸(す)しという説が有力です。調味料の酢が普及すると、酢で酸味を付けた飯に魚をのせた押しずしが生まれました。江戸時代には、手で握った酢飯に魚をのせた握りずしが登場します。発酵を省略し保存性すら問わなくなったわけですが、面白いのは飯の酸味は忘れられていないこと。魚編に旨いと書いて鮨(すし)。すしの本質は酸が生む旨味だと思います」
こう語るのは、滋賀県高島市にある1784年創業の鮒ずし店『魚治(うおじ) 』の左崎謙祐さん(さざき けんすけ・47歳 ※崎は正しくは山かんむりのさき(以下同))。
鮒ずしに使われるのは琵琶湖固有種のニゴロブナ。ほかの鮒より卵のきめが細かく、からすみのような滑らかさを持つ。骨も軟らかくなりやすく濃い旨味が出る。


ニゴロブナは生きたまま搬入される。鱗や鰓(えら)、卵巣以外の内臓を取ったら、口と鰓ぶたから念入りに塩を詰め梅雨明けまで漬ける。

「塩切りした鮒を飯と合わせる本漬けは暑い時期でないとうまくいきません。じゃあ何度がいいのか。そのあたりは難しいんですよ。どの作業も数字に置き換えられない勘のようなものばかりでして」
左崎さんが27歳のときに父が急逝。7代目を継いだものの、分からないことだらけ。左崎さんは、プラスチックに変わっていた漬け桶を昔の木桶に戻してみることから、鮒ずし作りという歴史ある家業に向き合っていった。
木桶に戻して学んだこと

夏に本漬けを行なうのは、高温を好む乳酸菌で一気呵成に発酵を進めるためだ。代々、蔵に入れるのは当主だけ。漂うにおいや肌に感じる湿気、桶に張った水の色から、窓の開閉や水替えの頃合いをつかむ。ふた夏越して納得の熟成を迎えた冬に、桶の蓋を開ける。
「温度がゆるやかに動くほうが味にまるみが出ますね。木桶は理にかなっていると思いました」

左崎さんは、本漬けの米も見直した。それまで使っていたコシヒカリに、木桶全盛時代の大粒で粘りの少ない品種も加えてみた。
「飯の旨さがより実感できました。なれずしの源流を求めてラオスへ行ったことがありますが、飯の量は少なかったです。私たちが受け継いだ鮒ずしでは米をぜいたくに使います。魚の保存から、発酵した飯の味を楽しむほうにいつしか目的が変わったのだと思います」
よい鮒ずしは飯が旨いというのは、鮒ずしにうるさい人たちが口を揃えていう言葉だ。鮒ずしは琵琶湖周辺では年取り魚で、今もおせちより格上の食べ物である。


魚治(滋賀県高島市)

滋賀県高島市マキノ町海津2304
電話:0740・28・1011
営業時間:9時~20時(電話受付時間)
定休日:火曜、第1・第3水曜
※この記事は『サライ』本誌2024年2月号より転載しました。(取材・文/鹿熊 勤 撮影/大橋 弘(橋は正しくは木へんにはしごだかにノ))