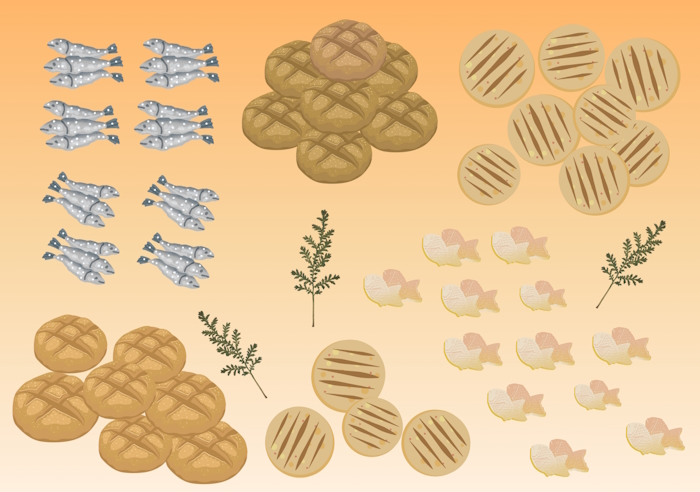取材・文/沢木文

結婚25年の銀婚式を迎えるころに、夫にとって妻は“自分の分身”になっている。本連載では、『不倫女子のリアル』(小学館新書)などの著書がある沢木文が、妻と突然の別れを経験した男性にインタビューし、彼らの悲しみの本質をひも解いていく。
野球一筋で、気の利いた会話ひとつできない男の恋愛
お話を伺ったのは、一史さん(仮名・65歳・会社経営)。
2歳年上の妻が子宮がんで66歳の生涯を閉じたのは1年前のこと。
「闘病は1年間。妻が亡くなってから1年経ったけれど、これが彼女の寿命だったんだと思えるまではまだ遠いね。ああしておけばよかった、こうしておけばよかったと、思うことだらけだよ」
妻との出会いは、大学の入学式。
「彼女は高校卒業後、海外留学してからウチの大学に入学した女性で、僕より2歳年上だった。中高の6年間、野球一筋だった18歳の男からすると、20歳の女はホントに大人だった。山口小夜子さんに似ていて、チェックのスーツを着ていた。パーラメントを吸っており、独特の雰囲気があった。すぐに友達になり、ブームだった西麻布や渋谷のディスコに連れて行ってくれた。僕があまりにもヤボだからすぐに誘われなくなったけどね。西麻布にはもう一つ思い出がある。昔、外苑西通りを『地中海通り』と言ったんだけれど、僕に初任給が出たときに、彼女がレストランを予約してくれた。そこは、びっくりするくらい高い店でね(笑)。彼女は平然と食事をし、全額オゴらされたんだ。1か月間、小遣いがなくて、タバコも吸えず、昼は毎日かけそばだったことを覚えている」
一史さんは、東京の“勤め人”の家庭に生まれた。当時にしては珍しく、両親は共働きだった。板橋区内の団地で育ち、私立中高一貫男子校に進学。それと同時に、両親は近郊に一戸建てを買い、犬を飼った。
一史さんは、背が高くスリムで、どこか英国紳士を思わせる。穏やかで知的で、人に対してフェアであろうとするところがにじみ出ている。日本企業から、外資系のソフトウエア会社に転職し、40歳で起業。物販・Web制作とコンサルティングを手掛けており、社員6人と共に、堅実に仕事を続けている。
【「友達以上、恋人未満」が長く続いた。次ページに続きます】