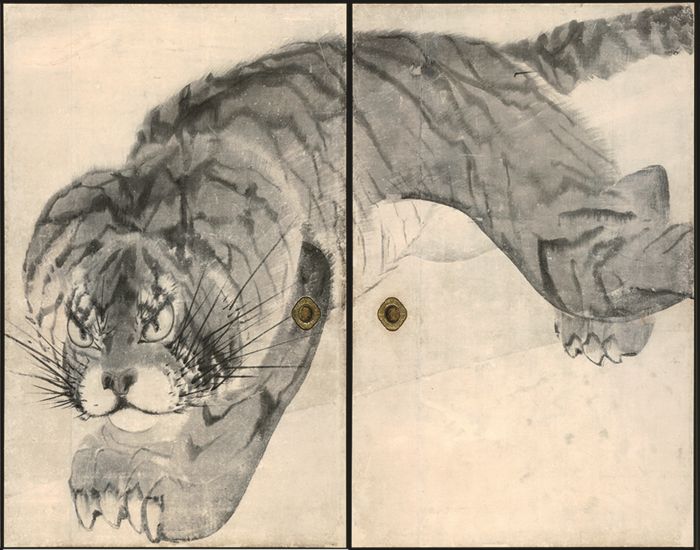取材・文/沢木文

結婚25年の銀婚式を迎えるころに、夫にとって妻は“自分の分身”になっている。本連載では、『不倫女子のリアル』(小学館新書)などの著書がある沢木文が、妻の秘密を知り、“それまでの”妻との別れを経験した男性にインタビューし、彼らの悲しみの本質をひも解いていく。
* * *
三男なのに家を相続できた理由
お話を伺ったのは、義雄さん(仮名・60歳・会社員)。義雄さんの妻は、結婚32年目、コロナ禍の中、離婚をして、家を出て行った。
「ずいぶん勝手なことをするな……と思ったけれど、妻の意志は固かった。もうどうしょうもなかった」
義雄さんは今、親から譲られた都心の広大な家にたった一人で住んでいるという。
「この前、相続の対策をしようと、専門家に聞いたら、不動産価格を出す必要があると言われ、調べて見たらこの家の価値は5億円だって。相続税がとんでもないことになっていて、このままでは息子と娘に迷惑をかけてしまうと戦慄したよ。築30年、雨漏りもしてボロボロなのにね」
都内の名門大学卒業後、東証二部上場の会社に勤務して、定年まで勤めあげた。
「僕は三男で、両親からは何も目をかけられていなかった。興味すら持たれていなかったんじゃないかな。それなのに、なぜ家を相続させられたかというと、長男である兄は婿養子に行ってしまい音信不通に。そして2番目の兄貴は、30年前に34歳の若さで事故で死んでしまったから。バイクでツーリング中に野生動物を避けようとしたらしい。母親が最も愛していたからね。もう大変だったよ。後を追うんじゃないかって、父親と私と妻で必死で面倒を見た。そのときに、子育てが重なったこともあり、彼女には会社をやめてもらった」
2人の子供を育てながら、我が子を失い失意に暮れる姑の世話をする。「嫁ならそれをして当然」という時代の空気が流れていたとはいえ、酷な選択ではなかったのだろうか。
「そうなのかな? 妻は地方の出身で、大学時代に僕と出会って結婚した。彼女は服飾専門学校を出ていた。洋裁ができて、パタンナーとして“服屋”に勤務していたから、それなりに優秀だったんじゃないかな」
義雄さんは“服屋”と言うが、聞けば有名なブランドだった。
「母親の世話をしたこともあり、長男は実家から勘当されて音信不通だし、僕の下の妹はドイツ人と結婚してヨーロッパに住んでいる。とはいえ、親から頭数に入れてもらっていなかった僕が家をもらえたのは妻の功績かな。でも今となってはどうでもいいのだけれど」
【妻の願いで犬を飼った…。次ページに続きます】