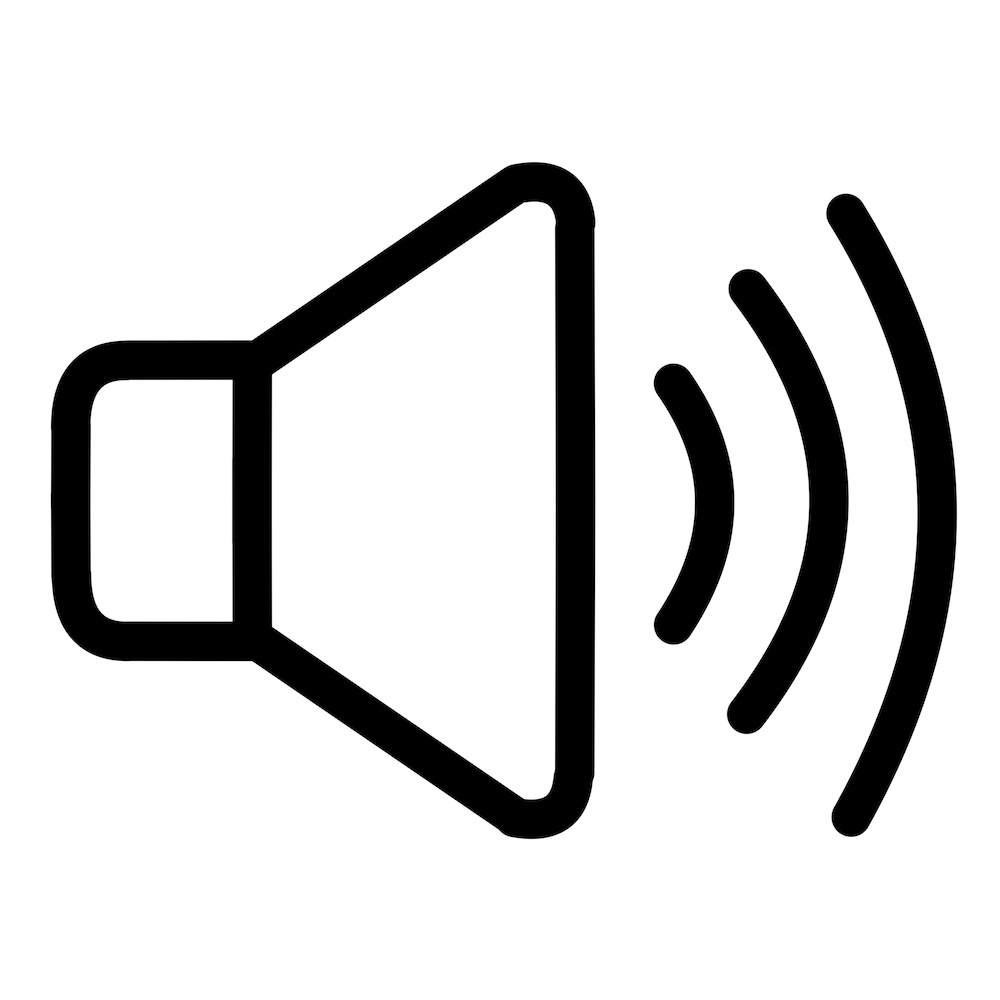取材・文/長嶺超輝
あまり知られていないが、裁判官には、契約や相続などのトラブルを裁く「民事裁判官」と、犯罪を専門に裁く「刑事裁判官」で分かれている。片方がもう片方へ転身することはほとんど起きず、刑事裁判官は弁護士に転身するか65歳の定年を迎えるまで、ひたすら世の中の犯罪を裁き続ける。
では、刑事裁判官は、何の専門家なのだろうか。日本の裁判所は「できるだけ裁判を滞らせず、効率よく判決を出せる」人材を出世ルートに乗せる。判決を片付けた数は評価されるが、判決を出したその相手が、再び犯罪に手を染めないよう働きかけたかどうかは、人事評価で一切考慮されない。
その一方、「人を裁く人」としての重責を胸に秘め、目の前の被告人にとって大切なことを改めて気づかせ、科された刑罰を納得させ、再犯を防ぐためのきっかけを作ることで、法廷から世の中の平和を守ろうとしている裁判官がいる。
刑事訴訟規則221条は「裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる」と定める。この訓戒こそが、新聞やテレビなどでしばしば報じられている、いわゆる「説諭」である。

【前編はこちら】
女手ひとつで育てられてきた、中学2年生の息子は、放課後も教室や図書館に居残って、独学で受験勉強を続け、わからないことは教師に質問するなど、早くから進学を意識して努力を重ねていた。
物静かな性格で目立たなかったが、彼はクラスメイトから厚い信頼を集めていたのである。
そんな息子の成長を生き甲斐として、母はパート勤務に明け暮れ、生活費を稼いだ。職場でどんなに辛いことがあっても、弱音を吐くことはなかった。
ふたりは、週に1度、学校と仕事の終わりに銭湯で待ち合わせて、リラックスした時間を設けるのが習慣になっていた。
不幸な事故は、その帰りがけに突然起きた。
慌ただしい事故直後
夜のとばりが下り始めた街角に、母の絶叫がこだました。
まもなく、けたたましいサイレンを鳴らして、救急車とパトカーが立て続けにやってきた。
息子を乗せたストレッチャーとともに、救急車の後部に同乗した母は、ただただ息子の名前を呼び続けることしかできない。
中学生男子を横断歩道上でひいたとして、業務上過失致死傷罪(当時)で逮捕されたのは、20代の建設作業員の男性だった。
のちに、このドライバーは事故当時、酒に酔っていて、しかも信号無視をして、横断歩道に進入していたことが判明した。
その日は休日で、昼間から自宅でビールや焼酎などを飲み、自家用車に乗って友人らが集まる居酒屋に出かける途中だった。
ただ、交差点の赤信号が連続して引っかかっていたために、いらだち、アルコールの影響で気が大きくなって、青信号の横断歩道に進入したのである。
まもなく、中学生の死亡が確認された。
悲しみに打ちひしがれる間もないまま、母親は警察署への同行を指示され、事情聴取を受けた。
「お母さん、お辛いとは思いますが、ご協力をお願いいたします」
警官からの質問を受けながら、まさか、息子と過ごす最期の日になるとは思わなかった、その日の出来事を思い出す。
銭湯に行くのは、明日でも昨日でもよかったのに、どうして今日にしてしまったのか。
どうして、コンビニに行こうとする息子を止められなかったのだろう。
母はやり場のない自責の念に駆られ、ますます涙が止まらなくなっていた。
14年前、はじめての念願の妊娠が発覚して、みずみずしい喜びと不安が入り交じった感情になったことまで、自然と記憶が遡っていく。その一方で、たった数時間前、コンビニの前で起きた出来事は、ほとんど思い出せなくなっていた。
事情聴取が終わり、警官からひとつの茶封筒が手渡された。
「これは何ですか」
「ご愁傷様です。お棺に入れてあげてください」
封筒の中には、白い塊が入っていた。コンビニ前の路上で発見された、息子の足の骨の一部だと聞かされた母はまた、声を上げて泣き叫んだ。
【次ページに続きます】