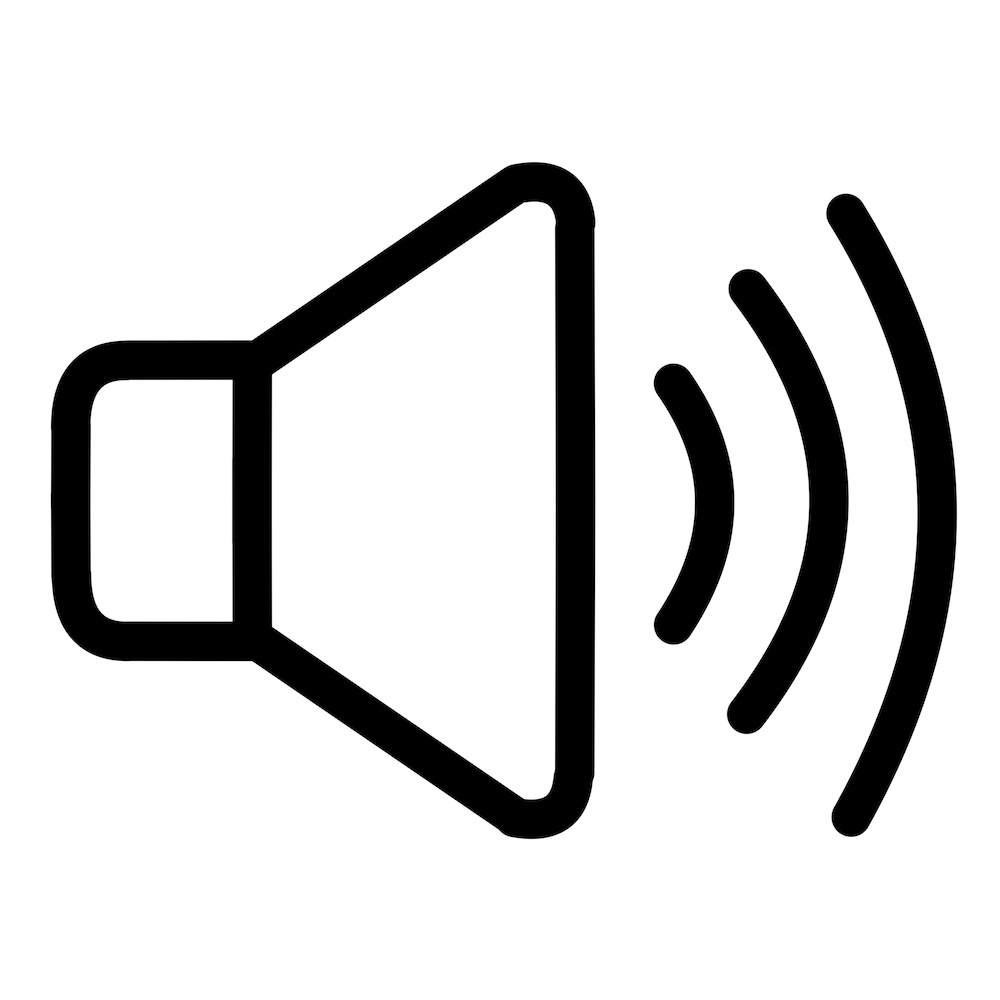処罰感情から程遠かった、当時の刑罰法規
業務上過失致死被告事件の初公判。法廷の検察官は、これから証拠によって証明しようとする事柄、つまり冒頭陳述を声高らかに読み上げていく。
事故当時、被害者である中学生は、衝突位置から20メートル以上も跳ね飛ばされたという現場検証結果が明らかとされた。
傍聴席最前列に座る母は、動揺を隠せない。
被告人は前かがみの姿勢で、微動だにしていない。
中学生が跳ね飛ばされた距離や、自転車の破損具合、さらには現場に急ブレーキ痕が残されていないなどの状況から、被告人の運転した乗用車は、推定時速約50キロで青信号の横断歩道に進入してきたとされた。
被告人は、酒気帯び状態で運転していただけでなく、赤信号無視をしていた。現代日本の刑罰法規であれば「危険運転」に該当する可能性があり、法定刑の最高は懲役30年である。だが、当時は懲役5年が上限だった。
一方で、被害者は青信号の横断歩道上を自転車に乗って渡っていた。過失割合が「10:0」であり、被告人に事故の全責任があることは明らかだった。
弁護人すらも「本件事故の責任については弁解の余地がありません」と、最終陳述で告白してしまうほど、弁護のしようがないケースだったが、その最後には「執行猶予の付いた寛大な判決を求める次第です」と述べ、締めくくった。
犯罪を裁く刑事裁判には、いわゆる「量刑相場」という言葉がある。同じ種類の事件であれば、どんな裁判官が裁いても、ほぼ同じ判決が出されるという「処罰の公平性」がある。
そこから、裁判官同士でお互いに空気を読み合い、無言の忖度をし合う、繰り返しの蓄積によって、「こうした交通事故では、執行猶予が付くだろう」という目星がついてしまうことが、「相場」と表現されるようになったのである。
しかし、本件を担当していた裁判官には、「それではいけない。量刑相場と国民感情が、あまりにも懸け離れている」という思いも去来していた。
取材記者たちが騒いだ判決文
判決当日、裁判官は、同業の法律家たちから批判されるのを覚悟で、大胆な主文を示した。
検察官が求刑していた懲役2年6か月を上回る、「懲役3年」の実刑を言い渡したのである。傍聴席の記者たちがどよめきの声を上げた。
「年間一万人もの命が交通事故で奪われながら、その被害者の命の重みは、法によって十分に保護されていない。まるで、駅頭で配られるポケットティッシュのごとく軽い」
「被害者の無念、命の尊さに比して、加害者は過保護ともいえる現状にあるといわなければならない」
「もはや、立法府による法改正を待っていられない状況にある」
判決文の読み上げは、約20分にも及んだ。被告人だけでなく、まるで社会全体に対する提言を発するかのような内容だった。
また、交通事故被害者の法的な扱いの軽さを「ポケットティッシュ」にたとえる独特の表現も、人々の印象に強く残るものとなった。
裁判官は後に、被害者の母から手紙を受け取った。
そこには「先生の判決で、生きる力をいただきました」と書き記されていたという。
* * *
今年、煽り運転について厳罰化されるなど、交通事故・事件をめぐっての処罰は年々強化されている。
しかし、その厳罰化傾向と、死亡事故の減少という現代社会の成果は、おびただしい数にのぼる交通事故犠牲者の失われた命の上で成り立っているという事実を、決して忘れてはならない。
車やバイクのハンドルを握る方は、今日もまた、どうか安全運転でお願いいたします。
※本記事の裁判の情報は、著者自身の裁判傍聴記録のほか、新聞などによる取材記事を参照させて頂いております。また事件の事実関係において、裁判の証拠などで断片的にしか判明していない部分につき、説明を円滑に進める便宜上、その間隙の一部を脚色によって埋めて均している箇所もあります。ご了承ください。
取材・文/長嶺超輝(ながみね・まさき)
フリーランスライター、出版コンサルタント。1975年、長崎生まれ。九州大学法学部卒。大学時代の恩師に勧められて弁護士を目指すも、司法試験に7年連続で不合格を喫し、断念して上京。30万部超のベストセラーとなった『裁判官の爆笑お言葉集』(幻冬舎新書)の刊行をきっかけに、記事連載や原稿の法律監修など、ライターとしての活動を本格的に行うようになる。裁判の傍聴取材は過去に3000件以上。一方で、全国で本を出したいと望む方々を、出版社の編集者と繋げる出版支援活動を精力的に続けている。