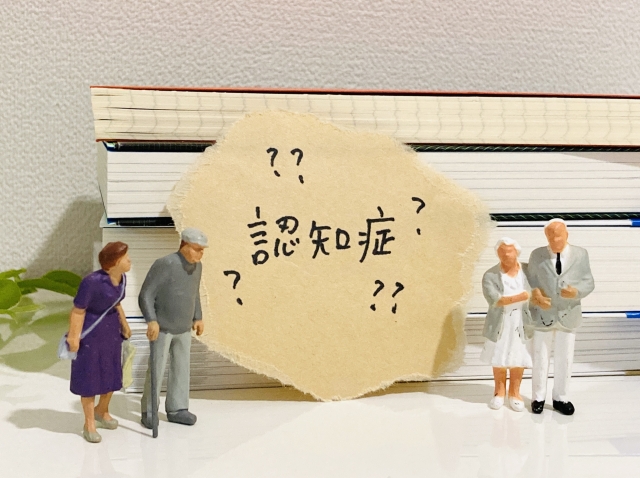取材・文/坂口鈴香

「もしかしたら、うちの親、認知症かも?」と不安を抱き、きょうだいに相談してみても「そんなはずはない」と否定されたという人は少なくない。前編は、否定するきょうだいが障壁になって医療機関を受診できなかったり、きょうだいの関係が悪くなったりした人の話を紹介した。
【前編はこちら】
医師に「認知症ではありません」と断言されて
家族間の意見の相違については、専門家ではないし、親に対する感情の温度差もあるのである程度は仕方ない部分はある。しかし、松坂さんのように医療機関を受診して認知症と診断されたあとでも、親を長く診ていた別のかかりつけ医が、その診断に疑問を呈することもある。家族は混乱するし、かかりつけ医との今後の関係を考えて困惑してしまうことにもなる。
前編で紹介した松坂さんの場合、母親が長く受診していた内科医が「お母さんは認知症ではない」と断言した。少し状況は違うが、「40代で認知症になった夫」(https://serai.jp/living/1229168)で紹介した中道美佳子さん(仮名・52)の場合もそうだ。中道さんの夫には、病識がない。というのも、夫は自分が「おかしい」と訴えていたのに、医師から「回復している」と言われて、「病気は治った」と思い込んでしまった。ところが、会社からも検査を再度受けてほしいと言われて別の病院で再検査したところ、医師から「会社に行けているのが奇跡」と驚かれるほど脳の萎縮が進んでいたという。それでも夫はかたくなに「自分は治っている」と信じて、会社にも行き続けていた。道がわからなくなっても迷っているとは認めない。本人にとっては、「回復している」という医師の言葉が希望になったのかもしれないが、家族はそのせいで振り回され、より追い込まれることになってしまった。
身近でみているから認知症に気づかない専門職も
あるケアマネジャーは、「かかりつけ医が認知症を否定することは少なくありません。身近で見ているだけに、かかりつけ医だけでなくケアマネジャーが認知症に気づかないこともあります」と言う。自身、何度も似たようなことを経験していると証言する。
「医師の前ではしっかりした返答ができるし、過去の話も整合性が取れているので、長年診てきた医師が認知症に気がつかないというのはよくあることです」
こんなこともあったと言う。
「ある認知症の男性の担当になったときのことです。その男性にずっとかかわっている訪問看護師から認知症だと聞いて、その方の生活保護の担当ケースワーカーに連絡を取ったのですが、そのケースワーカーから、『あなたは〇さんを認知症だと思うんですか!』と怒られました。お金の話もできるし、好きな相撲や野球チームの話もできる。新しい力士や野球選手の名前も間違えずに言えるので、ケースワーカーが認知症だと思わないのは無理もないのかな、とは思うのですが……」
そんなときに、このケアマネジャーが頼りにするのが看護師だ。担当する利用者に医療ケアが必要なら訪問看護を導入し、医師との間に入ってもらっている。
「なかでも、精神科勤務歴のある看護師は信頼できて、さまざまな場面で助けられてます。看護師の経験や人柄によるところは大きいですが、認知症の方本人だけでなく、家族にも寄り添ってくれるので、家族の精神的安定もはかれる。いいことずくめです」
ケアの仕方によっては、この好きなスポーツに詳しい認知症の男性のように、軽度認知症の状態を長く維持することもできると胸を張る。これは朗報だろう。
「長くかかわっているから、気づけない」こともよくある認知症。「そんなはずはない」と頭から否定する前に、一度周囲の声に耳を傾けてみてほしい。早期発見につながると、その後の介護者の心身への負担も軽減されるはずだ。
取材・文/坂口鈴香
終の棲家や高齢の親と家族の関係などに関する記事を中心に執筆する“終活ライター”。訪問した施設は100か所以上。20年ほど前に親を呼び寄せ、母を見送った経験から、人生の終末期や家族の思いなどについて探求している。