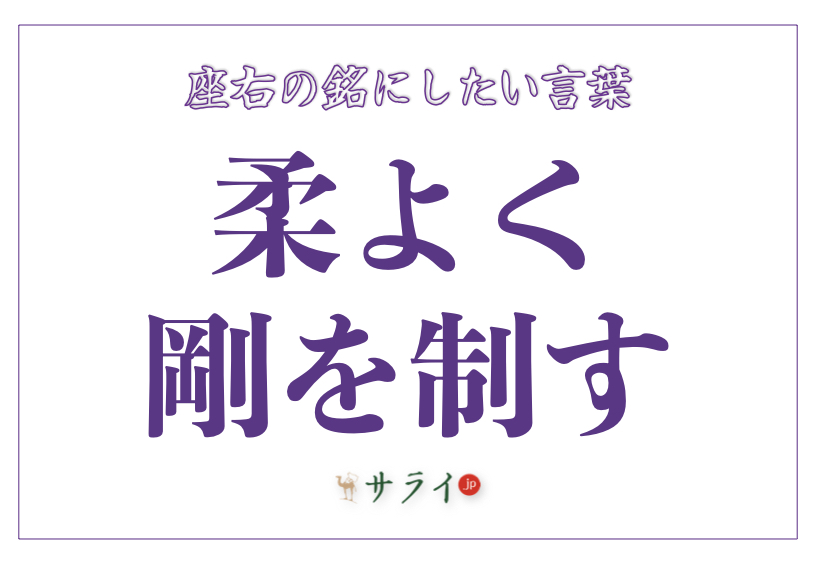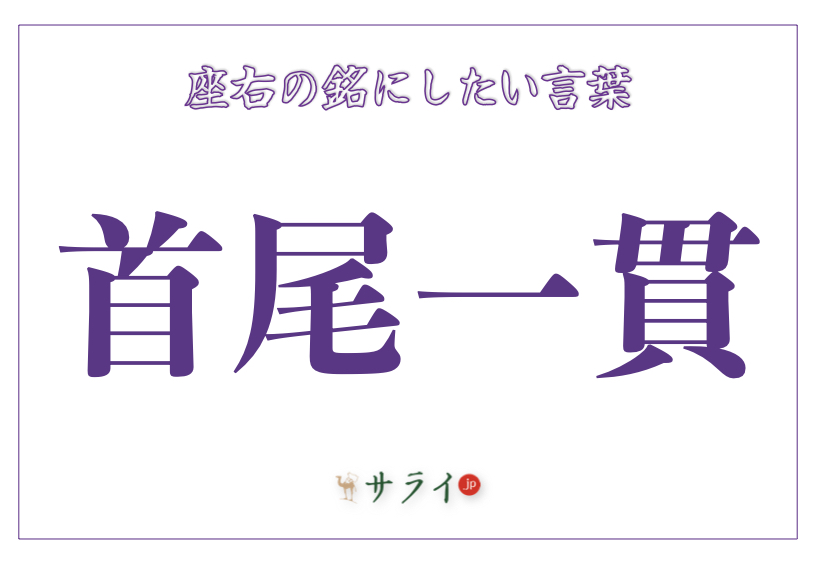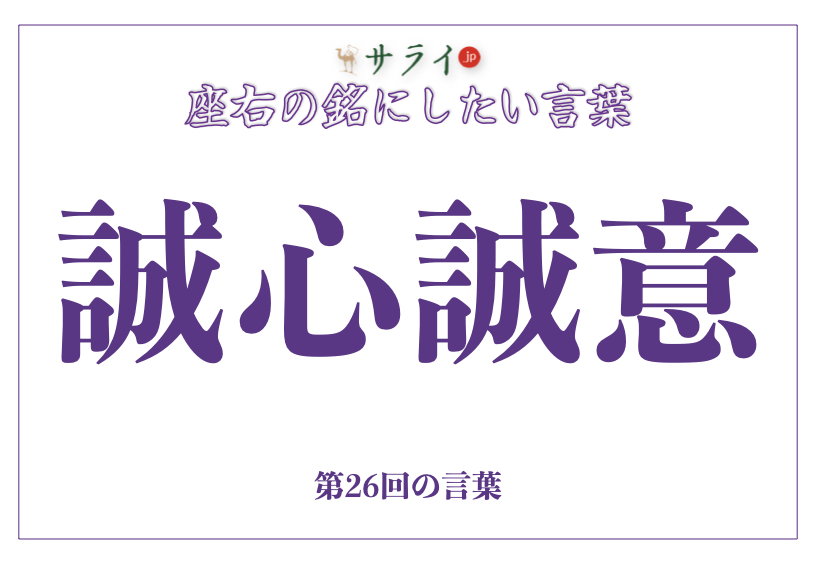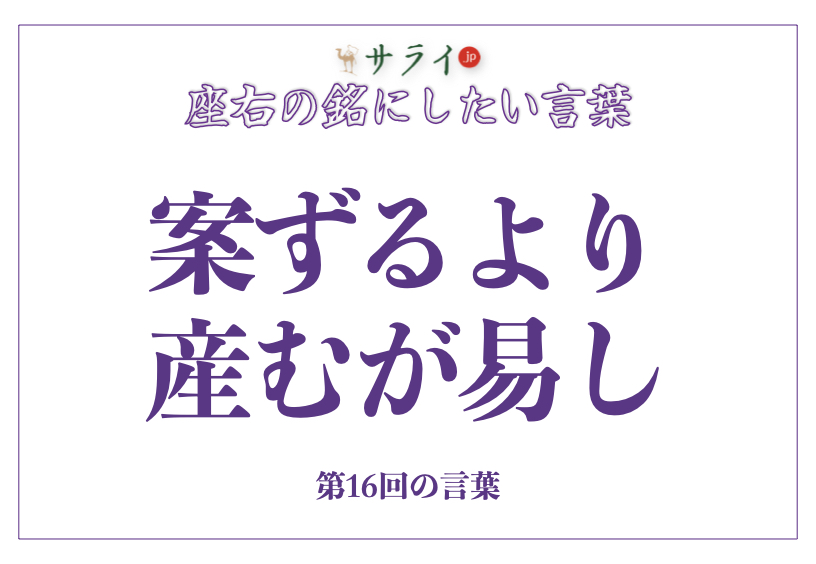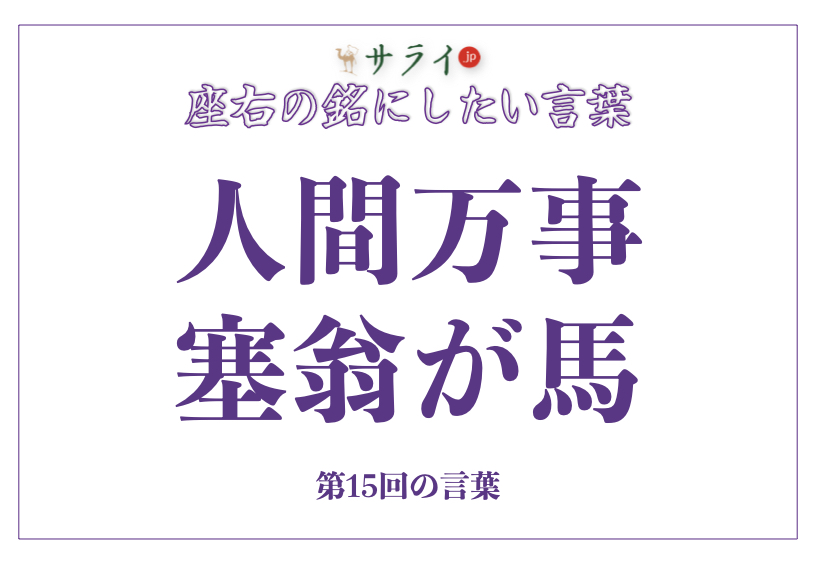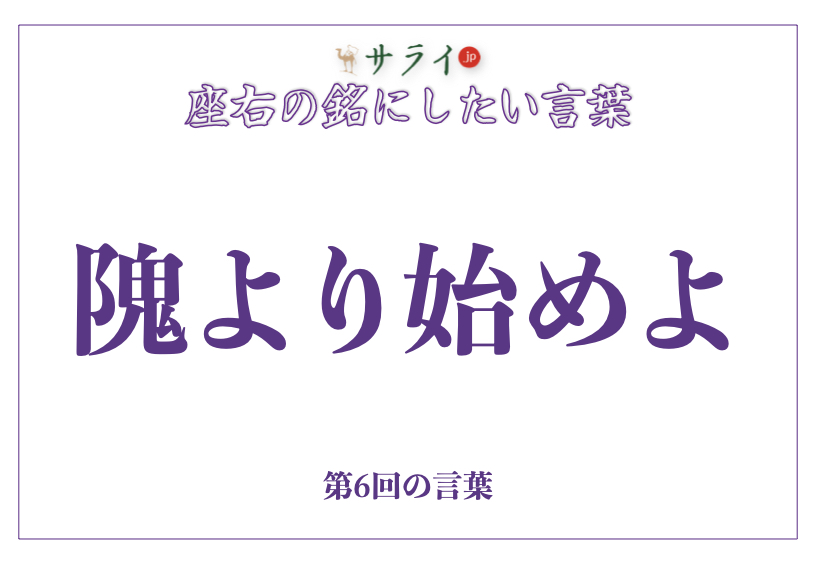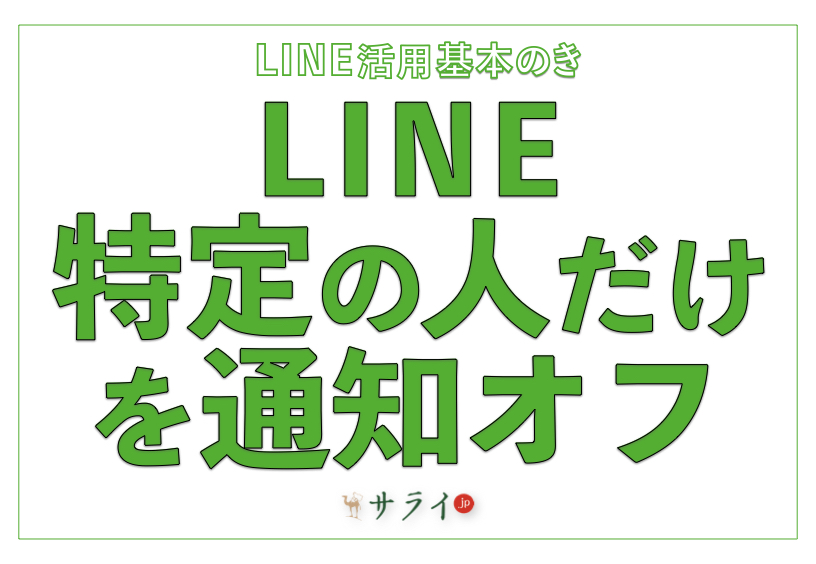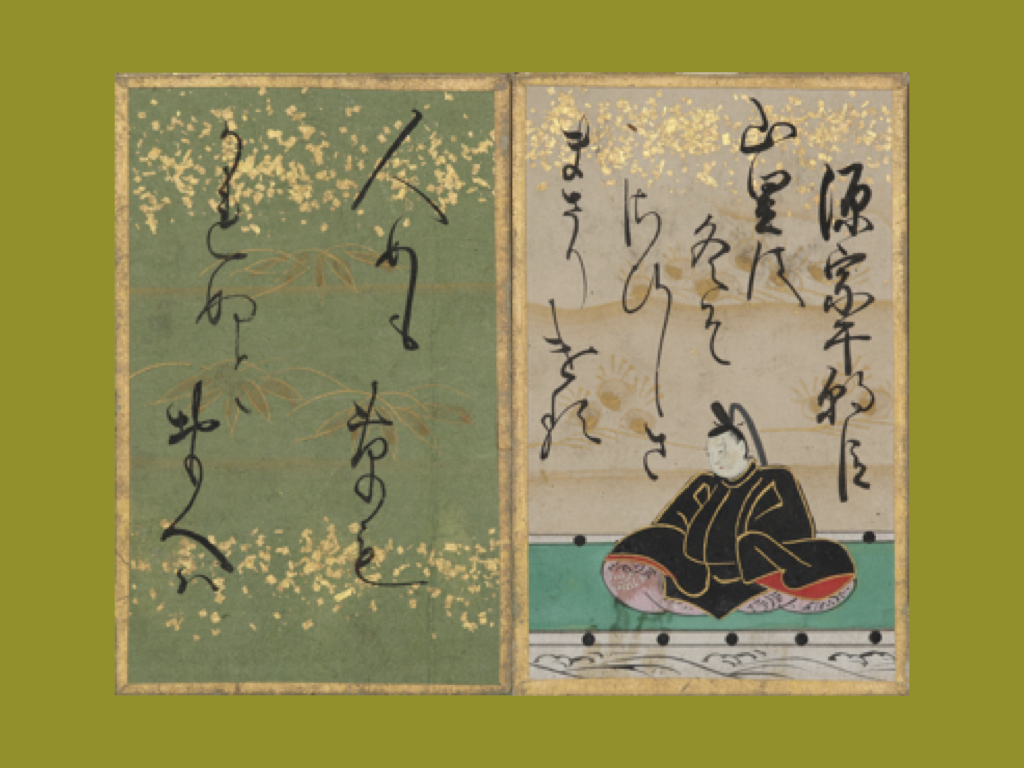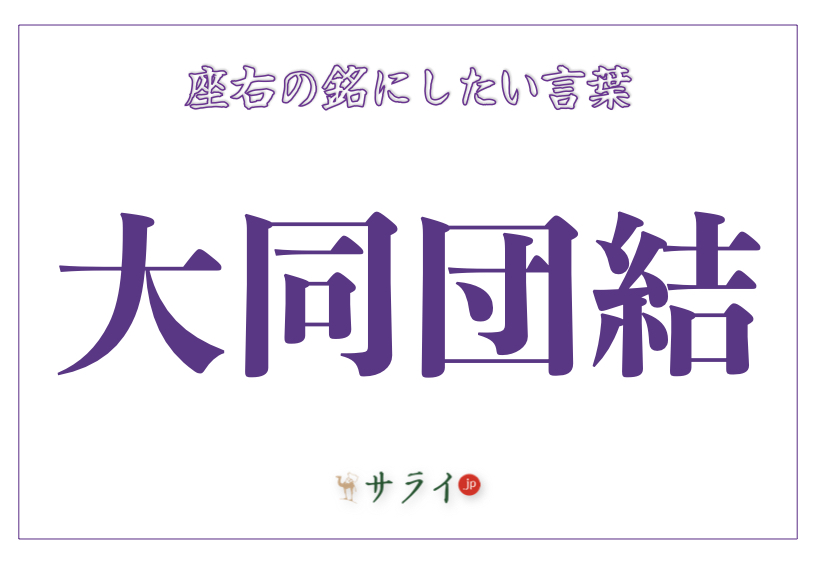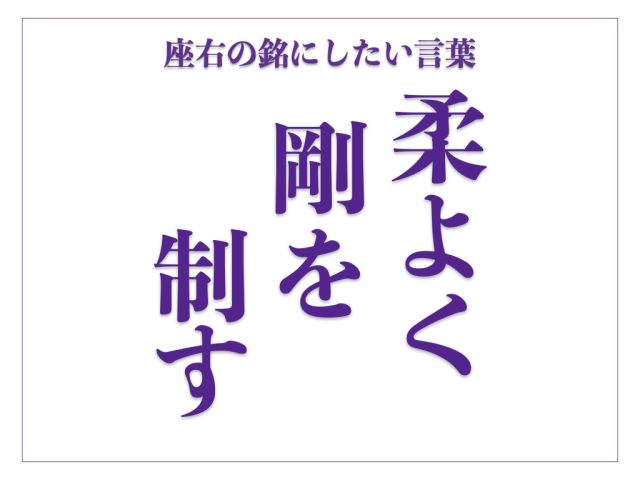
サライ世代にもなると、血気盛んであった頃からすれば、角も取れて随分と丸くなったように思います。また、人生長く生きていれば、それなりに多くのことを学び、悟ることができたようにも感じます。
しかし、その一方で未だ多くを悟りきれていないことも自覚するものです。若い頃「もっと、勉強すればよかった」と後悔するのは、まだまだ、頭が柔軟な証拠。先人が残してくれた名言や諺から、若かりし頃とは一味も二味も違った学びや悟りが得られるのではないでしょうか?
今回の座右の銘にしたい言葉は「柔よく剛を制す(じゅうよくごうをせいす)」 です。
目次
「柔よく剛を制す(じゅうよくごうをせいす)」の意味
「柔よく剛を制す」の由来
「柔よく剛を制す」を座右の銘としてスピーチするなら
最後に
「柔よく剛を制す」の意味
「柔よく剛を制す」について、『⼩学館デジタル⼤辞泉』では、「しなやかなものは、かたくて強いものの鋭い矛先を巧みにそらして、結局は勝利を得る。転じて、柔弱なものが、かえって剛強なものに勝つ」とあります。
例えば、風に吹かれる柳の枝を想像してみてください。硬い木は強風で折れてしまうことがありますが、柳の枝はしなやかにたわむことで風の力を受け流し、決して折れることはありません。このように、相手の力を利用したり、柔軟に対応したりすることで、よりよい結果を得る。それが「柔よく剛を制す」の本質です。
これは単に物理的な強さの話だけではありません。人間関係や仕事においても、頑なに自分の主張を通そうとするよりも、相手の意見に耳を傾け、柔軟に対応する方が、結果的に物事がスムーズに進み、よりよい関係性を築けることが多いのではないでしょうか。
「柔よく剛を制す」の由来
この言葉の由来には諸説ありますが、一般的には古代中国の思想家、老子の『道徳経(老子)』や、兵法書『三略(さんりゃく)』にその由来があるとされています。
『道徳経(老子)』には次のようにあります。
天下莫柔弱於水。而攻堅強者莫之能勝。
【書き下し文】
天下に水より柔弱なるは莫し。而も堅強を攻むる者、これに能く勝る莫し。
【現代語訳】
天下に水より柔らかく弱いものはないが、堅く強いものを攻めるには、これに勝るものはない。
水は形がないようでいて、岩を削り、山をも動かす力を持っています。直接ぶつかるのではなく、流れるように障害物を迂回し、あるいは長い時間をかけて侵食していく水の性質は、まさに「柔よく剛を制す」を体現しています。
また、『三略』には、「柔能く剛を制し、弱能く強を制す」と記されています。こちらは兵法の書であり、弱い立場であっても、柔軟な戦略や知恵を用いることで、強大な敵に打ち勝つことができる、という意味合いで使われています。

「柔よく剛を制す」を座右の銘としてスピーチするなら
この言葉を座右の銘としてスピーチするときには、新しい情報や考え方を柔軟に受け入れ、状況に合わせてしなやかに対応する「柔」の姿勢こそが、大切であるというエピソードを交えて話すと聴衆を惹きつけるでしょう。以下に「柔よく剛を制す」を取り入れたスピーチの例を挙げます。
変化への対応についてのスピーチ例
私の座右の銘は「柔よく剛を制す」です。若い頃は力で物事を解決しようとしがちでしたが、人生経験を重ねる中で、本当に強いのは、しなやかさや柔軟さではないかと感じるようになりました。相手の意見に耳を傾け、状況に合わせて柔軟に対応すること。
例えば、新しいスマートフォンの使い方、キャッシュレス決済、オンラインでの手続きなど、戸惑うこともあるかもしれません。「もう年だからできない」と頑なに拒否するのではなく、「ちょっと試してみようか」と、好奇心を持って新しいことに触れてみる。
完璧にできなくても構いません。少しずつでも新しいことを学び続ける柔軟な姿勢が、脳の活性化にもつながり、時代の変化に取り残されることなく、自信を持って生活していく力になります。
水が岩を穿つように、穏やかさの中にこそ、物事を動かす真の力がある。そう信じて、これからの人生も、しなやかに歩んでいきたいと思っています。
最後に
「柔よく剛を制す」は、ただの格言ではなく、人生哲学とも言えるものです。私たちサライ世代が持つ豊かな経験と知恵は、まさにこの「柔」の力を発揮するための土台となります。頑固さではなく円熟味を、対立ではなく調和を。そんな「柔よく剛を制す」の精神を胸に、これからの人生を、より一層豊かで、穏やかなものにしていきませんか。
●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com