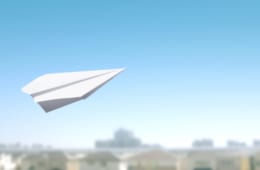文/印南敦史

どこを人生のゴールとするかという判断は人それぞれだし、もちろんそこに正解はないだろう。だが多くの場合、50歳あたりを境に“限界のようなもの”が見えてくるので、以後は年齢を重ねていくごとに“まとめ”を意識するようになるのではないだろうか? だから、「終活」などということばが生まれ、一般化したりもするのだ。
だが当然ながら例外もあり、50歳以降の人生をアグレッシヴに駆け抜ける人もいる。たとえばそのいい例が、『悩んでも迷っても道はひとつ ~マリ共和国の女性たちと共に生きた自立活動三〇年の軌跡~』(村上一枝 著、小学館)の著者だ。
なにしろ小児歯科の開業医を49歳だった1989年に辞し、単身ボランティアとして西アフリカのマリ共和国に渡ったというのだから。
いつかは開業医を辞めてアフリカへ行き、人々を助けることを私の人生における最終的な仕事としよう。家族のいない私には人生に残すものはない。必要とされるところに必要なことを残そう。そう思うようになった。人生には学び、修業をし、生活を築く時代があり、人生の後半にはこれまで得たことをフィードバックしていく時期があるのだと思っていた。私にとって、まさにその時がきたのではないかと考えていた。(本書16ページより)
そのため、マリでのボランティア活動が決まるまでの準備に費やした数年で考えはより確固たるものとなり、単身でマリへ渡ることになんの躊躇もなかったという。
かくして現地に入ってからは、農村地域の村民と力を合わせながら自立活動を続け、1993年にはNGO「カラ=西アフリカ農村自立協力会」を設立。その5年後には代表に就任した。
井戸掘りによる水の確保、識字教育と学校建設、助産師の育成と産院開設、病気予防と衛生知識の普及、女性の収入獲得のための適性技術(裁縫や野菜園の設置など)の指導といった日常生活に必須なことを中心に、活動は多岐にわたる。
その活動の重要なポイントは、単に現地の人々を「支援する」のではなく、「自立」を促し続けてきたということだ。ボランティア活動初期の時点で、「支援」とは支援側が『してあげるものなのか?』という疑問を強く感じていたというのである。
もちろん「してあげる支援」もときには必要なのかもしれないが、少なくとも著者のスタンスはそうではなかったということだ。
私が考える支援事業は、緊急時に支援するような一時的なものではなく、活動の対象となっている人たちが健康で幸せな生活を自立して構築するように促すことだ。できるだけ外部からの支援に頼らずに、自ら努力することが最重要前提だと思っている。(本書25ページより)
これは理にかなった考え方ではないだろうか? ボランティアの目的は「困っている人を助けること」であるだけに、しばしば「助ける側」と「助けられる側」という関係性ができてしまいがちだ。しかし、それでは根本的な解決にはならない。なぜなら著者やその仲間たちの支援は永久に続くものではなく、終わりがあるからだ。
この先さらに温暖化が進み、自然環境が悪化して、農作物の収穫量が減少するような状況でも、現地の人々は生きていかなければならない。それだけではなく、農村地域は医師や病院が極端に少なく、衛生面や病気についてのリスクも非常に大きい。したがって、さまざまな問題をクリアしていける生活能力を身につけてもらう必要があるわけだ。
常に主体は地域の住民であり、支援する側はその補助的な存在でいい。物を与え、お金を与える団体であってはいけない。自らが考え作り出すように仕向けることが重要である。そうでなければ、われわれがいなくなったら何も残らないではないか。(本書44ページより)
そこで、マリでの支援事業を始めるにあたっては、マリ人の技術者に指導的な立場になって働いてもらうことを意識したという。日本人である著者の役割は、あくまで事業の統括とコーディネート。アフリカ人の心はアフリカ人のほうがよく理解できて当然であり、指導者を育てることこそが大切だと考えたのだ。
もちろん長い時間はかかったわけだが、結果的に現地の人たちには自立心が芽生え、それは収入を高めることになった。衛生面も向上し、安心して生活ができるようになったという。
「成果が見えると人は動く」という著者のことばには大きな説得力がある。
支援を続けていると当然良いことばかりではない。私は途上国における支援とは何かを学ばぬままこの仕事に飛び込み、経験をもとに現場を見ながら考えて活動を続けてきた。そのために、事業の立案には、それが的確であるかどうかが常に不安であった。事業の結果を見て、その都度功罪を判断していた。
事業の結果が功罪の「罪」とならないように考え、見極めることは大変であった。(本書111ページより)
つまり「やりすぎ」ではいけないし、「やり足りない」のも問題だということだ。もちろん、支援の加減も重要なポイントとなるだろうし、村の人の要請をうのみにするだけでは、自立心を妨げてしまう。人種や環境は違えど「人」が相手であることは変わらないのだから、日常的に細心の注意が要求されたわけである。
ちなみに著者の現地での活動は、2017年ごろから変化していく。マリ北部の内戦や多発するイスラム過激派組織の襲撃によって、滞在が危うくなったため、現地からの撤退を余儀なくされたのだ。だが83歳(2023年時点)になられた現在もなお、日本から支援を続けている。2020年にはノーベル平和賞にノミネートされたそうだが、それも長年にわたるマリ農村地域88か村の生活向上と人材育成という取り組みが評価されたからにほかならない。
そうした30年以上に及ぶ活動のプロセスを細かく綴った本書は、なにかに取り組もうとするとき、なにを意識するべきなのか、なにをしてはいけないのかなどを改めて実感させてくれる。そして、そこから得たものは、なにかをしようとしているすべての人にとっての糧となるだろう。

村上一枝 著
小学館
1650円
文/印南敦史 作家、書評家、編集者。株式会社アンビエンス代表取締役。1962年東京生まれ。音楽雑誌の編集長を経て独立。複数のウェブ媒体で書評欄を担当。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)、『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)、『人と会っても疲れない コミュ障のための聴き方・話し方』『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)、『書評の仕事』(ワニブックスPLUS新書)などがある。新刊は『「書くのが苦手」な人のための文章術』(PHP研究所)。2020年6月、「日本一ネット」から「書評執筆数日本一」と認定される。