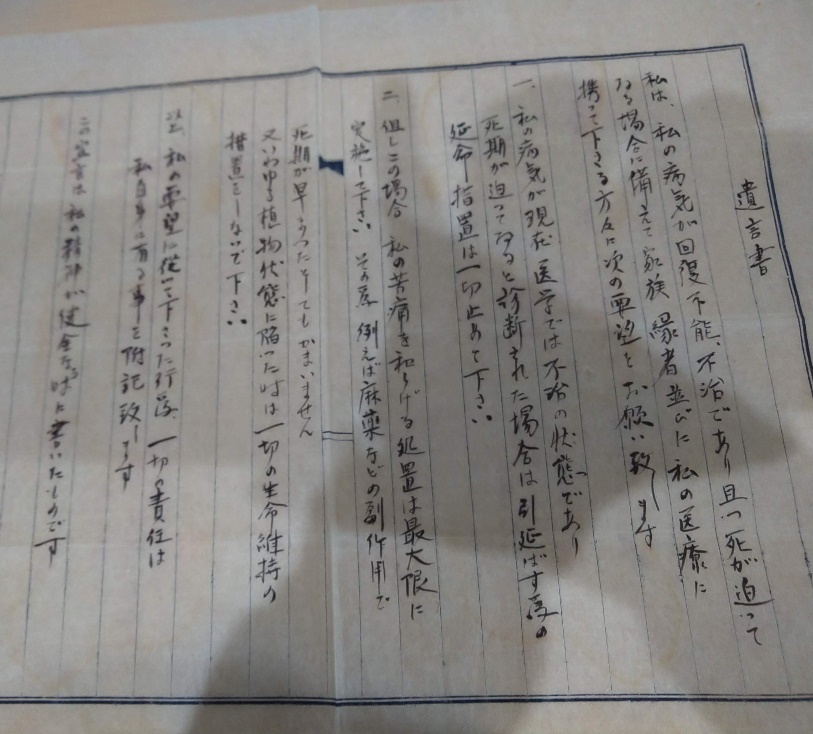母と一緒に暮らしたかった
そんな父の様子を見るにつけ、再び母への悔いが襲ってくる。
「母をサ高住に置きざりにした自分を責めてしまいます。母ともっと一緒に暮らしたかった。母もきっとそう思っていたはずです。文句ひとつ言わず、一人サ高住に残った母の気持ちを思うと、いたたまれなくなるんです。この罪悪感は一生ついて回るでしょう」
妻に対する気持ちを聞くと、「もう終わってますから」と、それ以上の言葉はなかった。親のことで言い争いをしていたころは、まだ相手に変わってほしい、変わってくれるかもしれないという期待があったのだろう。今はもう感情的なやり取りはない。交わすのは事務連絡ばかりだ。
不思議なのは妻だ。あんなに自分の親を優先していたのに、今はあまり付き合っていないようだという。
「何があったのかはわかりませんし、私から聞く気もありません。ただ、せっかく親が生きているんだったら、生きているうちにもっと付き合えばいいと思う。私のように、後悔することになるぞと」
それは、沢登さん夫婦だって同じなのではないか、という言葉は飲み込んだ。妻には妻の言い分があるだろう。他人はジャッジできない。
そして今回の教訓。「将来介護をしてもらうんだから同居費用は親が持つ」なんて、不用意に言ってはいけない。もっとも、先立つものがあればの話だが。
取材・文/坂口鈴香
終の棲家や高齢の親と家族の関係などに関する記事を中心に執筆する“終活ライター”。訪問した施設は100か所以上。20年ほど前に親を呼び寄せ、母を見送った経験から、人生の終末期や家族の思いなどについて探求している。