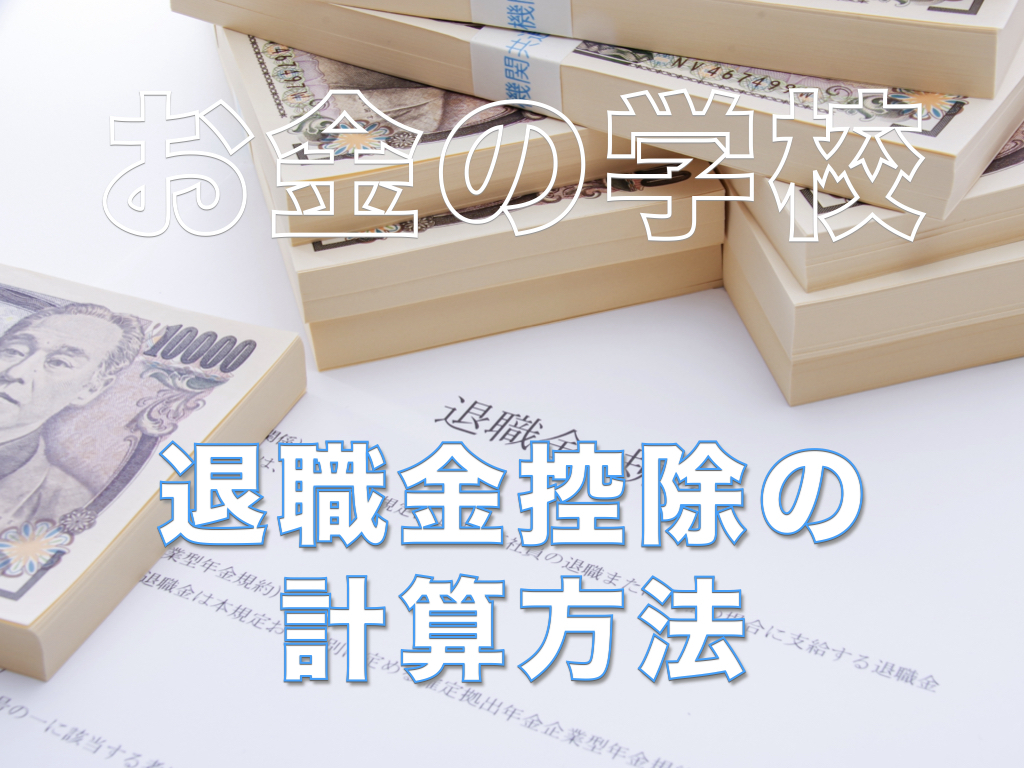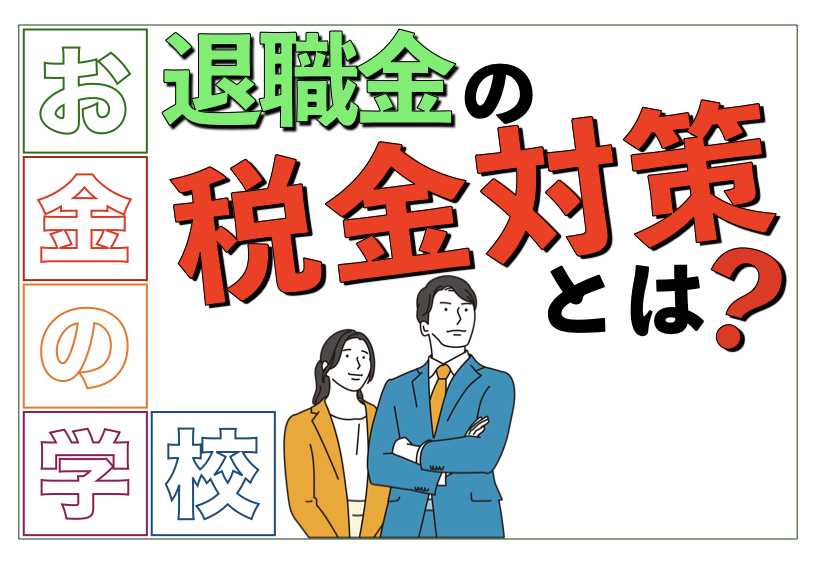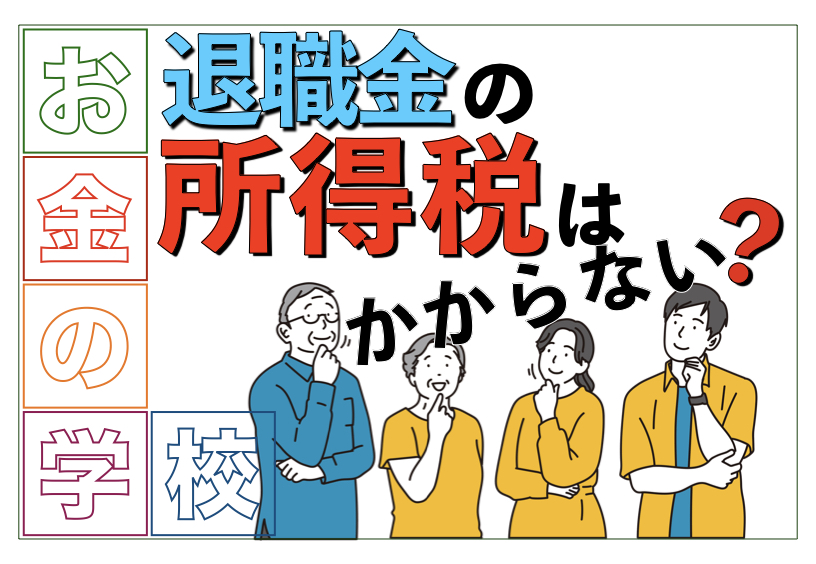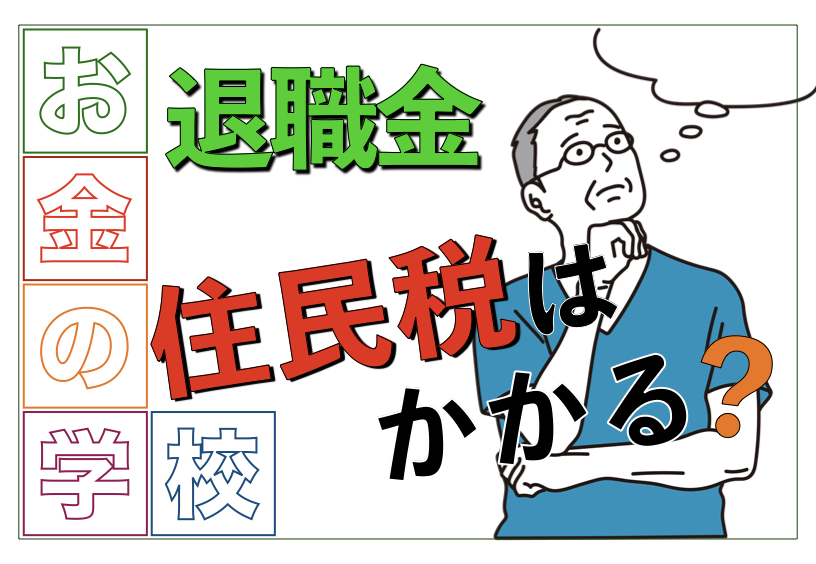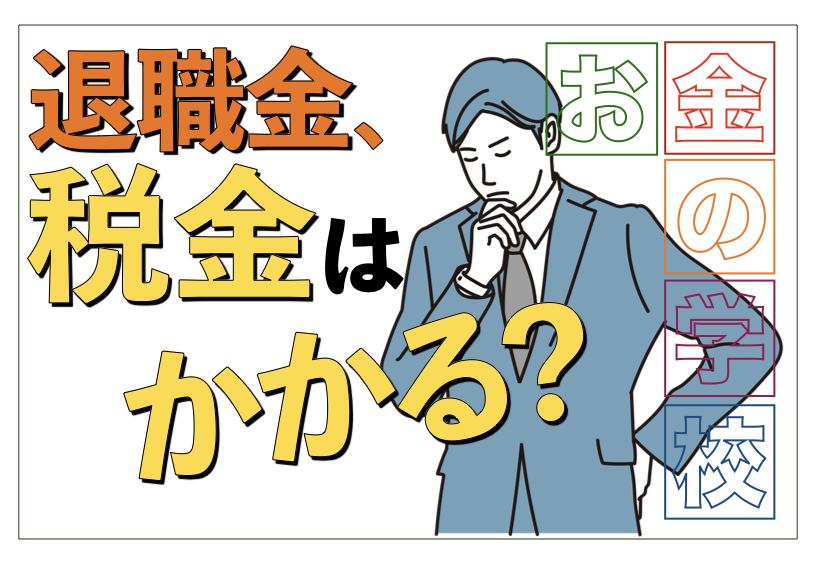退職金は老後を豊かに楽しく過ごすための大事な資金になります。会社から退職金を受け取る時にかかる税金はおよそいくらぐらいになるのか? 退職金控除はどのくらいか? 気になる計算方法について学んでおきましょう。
100歳社会を笑顔で過ごすためのライフプラン、ライフブック(R)を提唱する、ファイナンシャルプランナー・藤原未来が解説します。

目次
退職金控除の計算方法
退職所得控除は2回目も使える? 転職・再雇用時の適用ルールとは
退職所得控除はなくなる? 最新の税制改正と今後の見通し
退職所得控除の賢い活用法|節税メリットを最大化する方法
退職金控除の確定申告
まとめ
退職金控除の計算方法
退職金の所得税は「退職所得金額」に所定の税率を掛けて計算しますが、「退職所得金額」は、原則として次のように計算します。
退職所得金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
「退職所得控除額」は、退職金の税金計算のために特別に用意されたもので、「収入金額」から差し引くことができます。
退職所得控除額の基本ルール
退職所得控除額は勤続年数によって計算方法が以下のように異なります。
ア)勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には、80万円)
イ)勤続年数が20年超の場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
収入金額=受け取った退職一時金が「退職所得控除額」と同額もしくは小さい場合には「退職所得金額」がゼロまたはマイナスになります。
具体的な計算方法と計算例
例えば、次の参考ケースのような場合には退職所得金額はゼロになり、退職金には所得税も住民税もかかりません。
【参考ケース1】勤続年数が10年4か月の人の場合
勤続年数は11年になります(端数の4か月は1年に切上げ)。
「退職所得控除額」=40万円×(勤続年数)=40万円×11年=440万円
となりますので、退職金が440万円以下であれば所得税、住民税ともにかかりません。
【参考ケース2】勤続年数が24年7か月の人の場合
勤続年数は25年になります(端数の7か月は1年に切上げ)。
「退職所得控除額」=800万円+70万円×(勤続年数-20年)=800万円+350万円=1,150万円
となりますので、退職金が1,150万円以下であれば所得税、住民税ともにかかりません。
iDeCoと退職金控除の関係|控除額の計算にどう影響する?
iDeCoは個人で準備する退職金の制度の一つですので、iDeCoを一時金で受け取る場合も、退職金控除の適用の対象となります。退職金とiDeCoを同じ年に一時金で受け取ると、合計額が大きくなり、控除額を超えた分に税金がかかる可能性があります。例えば、会社の退職金だけで退職所得控除を使い切る場合、iDeCoの一時金部分に課税されることがあるのです。

退職所得控除は2回目も使える? 転職・再雇用時の適用ルールとは
退職金を2回以上受け取る人も少なくありません。会社の企業型確定拠出年金(DC)やiDeCoも一時金で受け取ると退職所得控除が適用される対象の退職金として扱われるのです。2回以上受け取る場合、退職所得控除は適用されるのでしょうか?
転職・退職2回目の場合、控除はどうなる?
転職などで退職金を2回以上受け取る場合でもケースによっては、退職所得控除の適用を受けることができます。現在のルールでは、5年以内に2回目の退職金を受け取る場合、控除額が調整されるため、1回目の退職所得控除をフルで使ってしまうと、2回目の控除額が減ります。
このように5年以内に2回目の退職金を受け取ると控除が制限されるルールを「5年ルール」などと呼ぶことがあります。裏を返せば、受取のタイミングが5年以上空いていれば、通常の計算が適用されるということです。
退職所得控除はなくなる? 最新の税制改正と今後の見通し
退職所得控除は退職金が老後の生活資金の支えとして重要な役割を担うことから優遇制度として充実したものでしたが、近年の退職時期の高齢化など働き方の変化によって、過剰な控除となるケースが増えてきたとされ、制度の見直しが議論されています。
退職金控除の改正ポイントと今後の影響
2026年1月1日以降、複数回退職金を受け取る場合は控除の調整期間が5年から10年に延長されるという改定が決定しています。この改定による影響は以下の2つのケースとなります。
ケース1:2回の退職金受け取りの間隔が10年以上
1回目と2回目の退職金受け取りの間隔が10年以上空いていれば、それぞれの退職金に通常の退職所得控除が適用されます。
ケース2:2回の退職金受け取りの間隔が10年以内
2026年以降、1回目の退職金受取日から10年以内に2回目の退職金を受け取ると、勤続年数の重複分が調整され、控除額が減額されます。具体的な例は以下の通りです。
【具体例】
1回目:2027年に退職し、退職金を受け取る
2回目:2034年(7年後)にiDeCoを一時金として受け取る
→この場合、退職金受け取りの間隔が10年以内のため、1回目の勤続年数と2回目の勤続年数(iDeCoの場合、掛け金の拠出期間)の重複分が調整され、控除額が減額されます。

退職所得控除がなくなる可能性はあるのか?
退職所得控除が将来的になくなる可能性については、現時点ではありませんが、控除の縮小や計算方法の見直しが進む可能性は高いと考えられます。
「長期勤続優遇の見直し」が議論されている
現在の退職所得控除は「勤続年数が長いほど有利(20年超の部分は1年70万円控除)」な仕組みとなっていますが、短期間の転職者が不利になるため、改正の議論が続いています。退職所得控除の「20年超の部分の優遇措置(70万円ルール)」を一律40万円に引き下げる案が一時検討されたこともあります。
退職所得控除の賢い活用法|節税メリットを最大化する方法
退職金にかかる税金を最小限に抑えるために、退職所得控除の賢い活用法について見ておきましょう。
1.退職所得控除を2回使えるようにする
例えば、会社の退職金とiDeCoを「10年以上の間隔を空けて」一時金で受け取れば、それぞれに退職所得控除が適用されます。これにより、2回分の控除を使えるため、税負担が大きく軽減されることとなります。
2.一時金と年金を組み合わせることで税負担を分散できる
退職金は「一時金」「年金」「一時金+年金の併用」の3種類の受け取り方があるのが一般的です(企業によっては一時金のみなどの規定がある場合もあります)。例えば、退職金を一時金で受け取り、iDeCoは年金で受け取ると、退職所得控除と公的年金等控除の両方が適用されるため、税負担が軽減されるケースもあるので、シミュレーションしてみるといいでしょう。
退職金控除の確定申告
退職金の所得税は自分で確定申告をする必要があるのでしょうか? 答えは、あらかじめ「退職所得の受給に関する申告」をしていれば「不要」です。
退職金を受給する際に、勤務先(iDeCoの場合は金融機関)に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、勤務先(金融機関)が所得税額及び復興特別所得税額を計算し、退職金から源泉徴収されることになります。したがって、原則として確定申告は必要ありません。
まとめ
退職金は出来るだけ税金がかからないように受け取りたいものです。「一時金」または「年金」による受取り方法で、それぞれの税金の計算方法は違いますので、自分自身の退職金の予定額を把握したうえで、「一時金」で受け取るか「年金」で受け取るか、どちらを選択すると有利なのか検討してみましょう。
資産運用や投資のアドバイスは、今や銀行などの金融機関の窓口でもさかんに行なわれています。同時に、インターネット上でもYouTubeやSNSを通じて色々な人がそれぞれの立場から投資術などを発信しています。しかし、それらのアドバイスは本当にあなた自身に適したものなのでしょうか?
さまざまな金融商品が出回っている世の中だけに、あなたの味方になって守ってくれる相談相手を持つことが必要な時代になっています。
●取材協力/藤原未来(ふじわらみき)

株式会社SMILELIFE project 代表取締役、1級ファイナンシャルプランニング技能士。2017年9月株式会社SMILELIFE projectを設立。100歳社会の到来を前提とした個人向けトータルライフプランニングサービス「LIFEBOOK®サービス」をスタート。米国モデルをベースとした最先端のFPノウハウとアドバイザートレーニングプログラムを用い、金融・保険商品を販売しないコンサルティングフィーに特化した独立フランチャイズアドバイザー制度を確立することにより、「日本人の新しい働き方、新しい生き方」をプロデュースすることを事業の目的とする。
問い合わせ先:03-6403-5390(株式会社SMILELIFE project)
株式会社SMILELIFE project(https://www.smilelife-project.com)
●編集/京都メディアライン(HP:https://kyotomedialine.com FB)