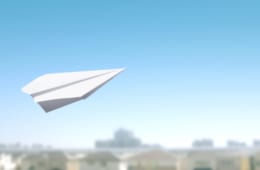文/印南敦史

まず明らかにしておく必要があるが、少なくとも私個人は、『あの世の歩き方: この世じまいの“地図”を手にすればもう迷わない!』(江原啓之 著、小学館)に書かれていることを“全面的に”支持できるわけではない。
受け止め方、感じ方、考え方は人それぞれだから、もちろん自分の見解を押しつける気は毛頭ない。が、「私はこれまでにも時々あの世を旅しています」というような記述を目にすると、やはり素直にそれを受け止めることができないのである(性格が屈折しているのかもしれない)。
同じような思いを抱く方は多少なりともいらっしゃるだろうし、そういった方にとって、本書の前半はいささか許容しづらいはずだ。なぜならその内容は、著者のことばを借りるなら“死んだあとに必ず行くあの世について、とことん紹介するあの世のツアーガイド”なのだから。
そんなわけで最初は、少なくとも前半について多少の抵抗感を覚えたことは否定できないのだ。だが読み進めていくうちに、別の思いが生まれてきたこともまた事実。
もしスピリチュアルな価値観を受け入れることができなかったとしても、ファンタジー作品を読んでいるような気持ちになれれば、相応の楽しみ方ができるのだ。するとやがて、「基本的には信じられないけど、でも、たしかにあの世ってこういうものなのかもしれないな」と、心のどこかに許容できる部分が生まれてくるのである。
そうした余裕、いいかえれば精神的な幅の広さを持つことは大切だと思うし、そこまでたどり着ければ、必然的に相応の価値が生じるのではないだろうか? そう、著者のガイドを参考にしながら“あの世をツアーする”ような気分になり、それを楽しめばいいのだ。
だが、仮に「どうしても受け入れられず、楽しめなかった」としても問題はない。なぜなら本書の本質は、むしろ第4章「『この世じまい』という旅支度を」から始まる後半にこそあるからだ。
これからの人生を、いかに心地よく生きるか。それが本書後半のテーマです。「『この世じまい』って、終活のことじゃないの?」と、思った方、当たらずとも遠からず。
死を見つめることは重要。どのように死にたいかを考えることは、どのように生きていきたいのか、自分の人生を見つめることにつながります。(中略)
今を充実させながら、精一杯生き抜かなければ、あの世の旅はいい旅にならないのです。(本書88ページより)
たしかに死と向き合う以上、その過程のどこかで“終活”と向き合う必要があるだろう。けれども現実問題として、「終活をしなければいけない」と思いながらも、なかなか動けないものだったりもする。しかし、だったら「終活せねば」と身構えるのではなく、まずは心地よく生きる方法を探ってみるべきだと著者は主張するのである。
目指すのは、心地よさを追求していったら、いつのまにかこの世じまいできちゃった。そして、充実した気持ちであの世に旅立つという最期の景色が見えた。結果、まわりに迷惑をかけず、「いい死に方だったね」とみんなにうらやましながれて大団円……という人生。
(本書89〜90ページより)
そんなことができるのかと思えなくもないが、難しく考えなくてもいいのだと著者は主張する。いま、自分が心地よくないなと思っていること、気になることをひとつずつ整理し、クリアにしていけばいいというのである。つまり本書は、そのための指南書でもあるのだ。
そういう意味において、「この世じまいのポイントは、心地よさの追求」であるという部分はとても重要な意味を持つことになる。
自分の心地いい人生はどういうものか。
自分の心地いいフィールドはどうしたら作れるか。
自分が心地よく生き、死んでいくには、何が必要か。
(本書93ページより)
ただし、それは“わがまま”なものであってはならない。この世じまいにつきものの、お墓や仏壇、お葬式、身のまわりの品の処分について考えるときも、「誰かに迷惑をかけないかな」だけでなく、「環境にやさしい方法かな」という視点も忘れるべきではないというのだ。
そこまで考えて実践できてこそ、本当の意味での心地よさの追求が実現できるというわけだ。
こうした考え方を軸として、以後の章では「お墓、仏壇」に関する迷信や因習、この世の未練の立ち切り方、お金の問題、そして死に方についての考えなども解説されていく。そういう意味では、本書は実用的でもある。
ただ、実用面がどうであれ、最終的にどうしても気になってしまうのは死の怖さではないだろうか? だからこそ、以下の文章を意識しておくべきだ。
死の恐怖や不安を抱えているよりも辛いのは、やはり執着があることだと、私は思います。
私は死んだあとに悔やみたくない。いかに充実した今日を生きるかを考えたい。(中略)
今日を一番楽しくしたい! あるのは、今日と明日だけ。昨日すらない。
(本書221ページより)
惜しむ気持ちはあるけれど、なにかを失ってしまったとしても、仕方がないとあきらめる。したがって、執着が残らない最期のあり方だって選ばなくてはならない。執着をひとつでも減らしておくべきだということで、たしかにそれこそが本質であるに違いない。

江原啓之 著 小学館
文/印南敦史 作家、書評家、編集者。株式会社アンビエンス代表取締役。1962年東京生まれ。音楽雑誌の編集長を経て独立。複数のウェブ媒体で書評欄を担当。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)、『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)、『人と会っても疲れない コミュ障のための聴き方・話し方』『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)、『書評の仕事』(ワニブックスPLUS新書)などがある。新刊は『「書くのが苦手」な人のための文章術』(PHP研究所)。2020年6月、「日本一ネット」から「書評執筆数日本一」と認定される。