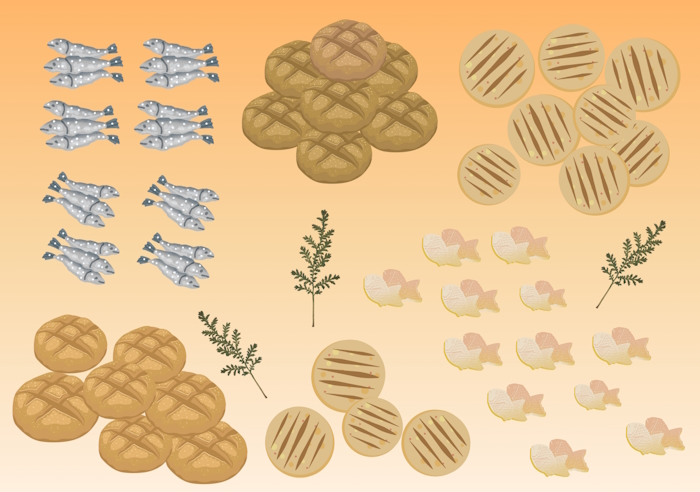取材・文/坂口鈴香

上岡晋さん(仮名・62)はレビー小体型認知症の義母、喜佐子さん(仮名・88)と同居し、介護している。夫を早く亡くした後も自由奔放に生きてきた喜佐子さんだったが、喜佐子さんに反発しウツを患い、ついに自死した次女の幻覚を見て、毎日名前を呼んでいる。
【3】はこちら
東京本社高知営業所
幻覚が見えるというのは、レビー小体型認知症の特徴だ。本人にはつらい症状なのはもちろんだが、夜中など叫び出したりして介護者が疲弊することも多い。でも上岡さんは「もう慣れました」という。
「義母の寝室の真下の部屋で寝ているんですが、上で義母が歩き回っていたり、物を投げたりしているのはよくわかります。廊下で水音がすると、おもらししているなというのもわかる。生存確認できていると思って、あとは放っといています」
「義母の介護をしていなければ、東京で仕事をしていただろうし、東京の街を闊歩して議論していただろう」とは思うが、「何でオレが」とか「自分の人生は介護で犠牲になった」という気持ちになることはないという。一方で、喜佐子さんと生活する中でのストレスがあるのもまた事実だ。
「義母に何か言われても話を逸らすことができるんですが、こっちもストレスが溜まっていると口げんかをすることもあります。10秒くらいワーっと言って、それ以上続けても不毛なので、私が外に出ていくようにしています」
「お金がなくなった」「あなたが盗ったんじゃないの」などという言葉は、認知症によるものとわかっていてもストレスになるし、夜中に喜佐子さんがおもらしをして床を拭いていると「オレ、何してんのかな」とも思う。
「それでも週6回デイサービスに行くと、あとは自分の時間。誰にも文句を言われることもない。これは何ものにも代えがたいですね」
高知にも根付いてきたのを感じる。誘われてはじめたバドミントンクラブは新たに別サークルを立ち上げて、会員は100人にまで増えた。ストレス解消に、夜飲みに行く友達も増えた。昼間から格安でゴルフできるのも高知だからだ。清流があって自然にも恵まれている。
「高知は良いところだけど、ひとつだけ不満があって、私と話が合う“おもしろい男”がいないこと。働いていて、がんばっている女性は多いですが。だから東京や大阪から転勤で来ている人と話すとおもしろい。それにここにずっといると決めているわけではありません。義母が施設に入ったりすると、東京に戻るかもしれません。東京も10年見ないとガラッと変わっているから、楽しみにしています。だから今の意識は“東京本社高知営業所”みたいなものですね」
壊れたおもちゃを見るような感覚
実の親ではないから、良いこともある。上岡さんには、実父を介護した経験があった。
「7年ほど前、認知症で寝たきりになった父を1年半くらい、毎週末東京から高知に帰って介護しました。多い月には飛行機代が40万円くらいになりました。それでもお金にかえられない経験でした。父とはそれまで一緒に酒を飲んで語り合ったこともなく、心残りがありました。父は私のこともわからなくなりましたが、父を介護して見送ることができて、後悔はなくなりました」
そう言い切る上岡さんだが、実親の介護にはやりきれない感情がともなうことも多々あったという。
「父は便や尿を漏らすと泣いていたんです。あの厳格だった父が……と悲しかった。これは実の親だから持つ感情でしょう。だから今義母がおもらしをしても、実親ではないのでそれほど感情的にならず、客観的にとらえることができる。これは良いことだと思います。言い方は悪いですが、“壊れたおもちゃ”を見るような感覚でしょうか」
次回に続きます。
取材・文/坂口鈴香
終の棲家や高齢の親と家族の関係などに関する記事を中心に執筆する“終活ライター”。訪問した施設は100か所以上。20年ほど前に親を呼び寄せ、母を見送った経験から、人生の終末期や家族の思いなどについて探求している。