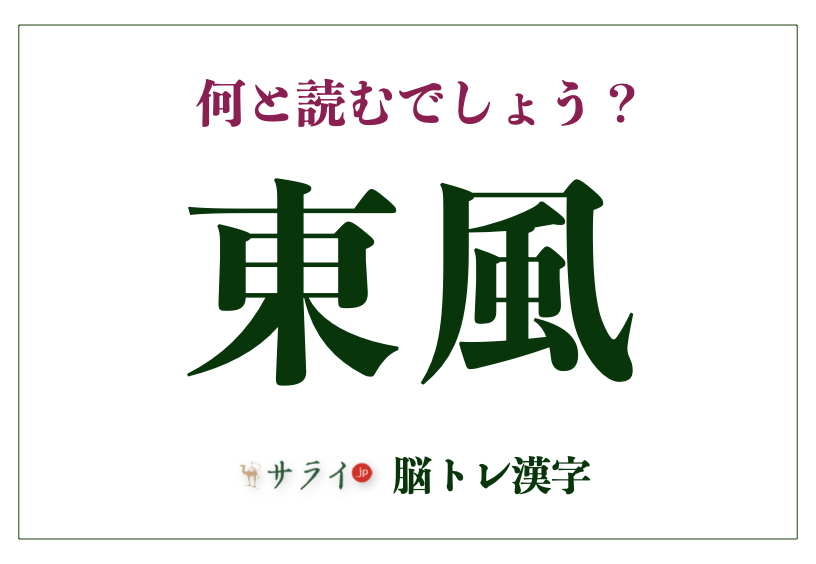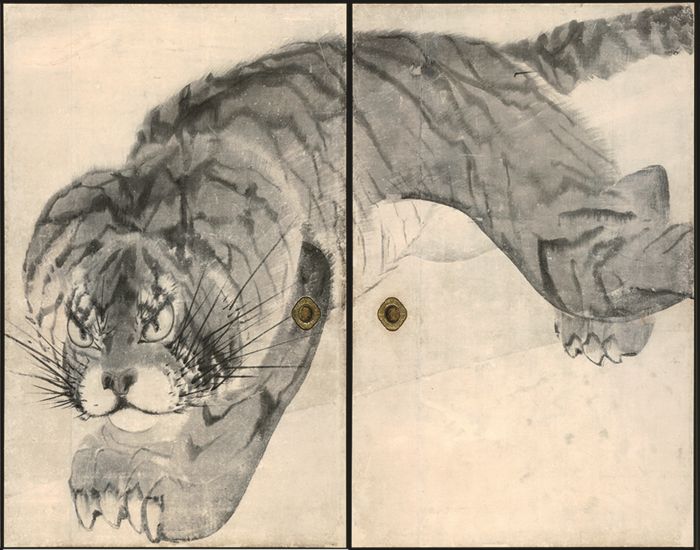取材・文/坂口鈴香

レビー小体型認知症と診断された妻の母親・喜佐子さん(仮名・88)を、東京と高知を行き来しながら介護していた上岡晋さん(仮名・62)はその後高知に生活の本拠を移し、喜佐子さんと完全同居して介護することにした。喜佐子さんが困ったことだけ手を差し伸べるという“上岡さん流介護”で、上岡さんと喜佐子さんは自然と家族になっていた。
【2】はこちら
もう遅いので、帰ります
“家族”ではあるが、1年半ほど前から喜佐子さんは上岡さんのことがわからなくなった。それまでは時々わからなくなることはあっても、再び思い出していた。
「昨年妻が高知に帰ってきたときのことです。妻と一緒の布団で寝ていたんですが、そこに義母が入ってきて『あなたたち、何やってるの?』と大騒ぎになったんです。これで義母は私のことをわかっていないなと確信しました。それ以来、完全に忘れられています」
今、喜佐子さんにとって上岡さんは「親戚の大切な人」という存在だ。
ドキっとするようなエピソードもある。上岡さんと会話していると、突然「あなた、いい男よね」と言ったかと思うと、「けど、あなたとは寝ないわよ」ときっぱり言い放った。
「イヤ、こちらにもそのつもりはないので、『もう夜遅いので、帰ります』と言って、実家に帰りました」
数か月前には、こんなこともあった。
「夜『寒い』と言うので様子を見に行ったら、毛布だけ掛けていて、部屋の暖房も切れていたんです。それで体をさすって、カイロを入れ布団をかけてあげたら、義母が『ここに入って』と言って、ニコっと笑って『久しぶりね』と……」
喜佐子さん、なかなかやるではないか。
亡くなった次女の幻覚が見える
そもそも喜佐子さんはどんな人だったのだろうか。俄然興味が湧いて聞いてみると、昔からかなり型破りな女性だったことがわかった。
「お嬢さん育ちでかわいがられ、嫁ぎ先では夫を30代で亡くしたものの、残った資産でアパートや駐車場を経営。妻と妹を人に預けて世界中を旅したり、宝塚や松竹を見に行く。妻や妹の幼いころの写真はほとんどないくらい自由奔放で、世間からどう見られようと気にしない性格でしたね」
上岡さんが妻との結婚の許しをもらいに行ったときのセリフがまた豪快だ。
「エマニエル夫人のような籐椅子に座って、『あなた、きれいな足の女性がお好みと聞いたけど、どうなの? 私の足』と、足を見せるんです。『きれいですね』と答えると、『娘は私ほどじゃないけど、まあまあよ。それでいいの?』と。これが結婚を許すということでした」
だから、現在の喜佐子さんの言動も、あながち認知症のせいとばかりは言えないのかもしれない。
上岡さんの妻は、そんな奔放な母親を反面教師として育った。その対極にあって苦しんだのが妻の妹だった。喜佐子さんに反発し、若いころからウツに苦しみ、躁状態になると喜佐子さんの目の届かないところで働いて生活しようと家を出て、調子が悪くなると喜佐子さんの助けを求めて戻ってきた。
そして8年前、自ら死を選んだ。発見したのは喜佐子さんだったという。
「妹は仕事したこともない。友達も少ない。恋人もいない。義母は自分とはまったく違う次女のことを今も背負っているようで、毎日名前を呼ぶんです。『さっきまでいたのに、どこに行ったの?』と、幻覚も見えている」
自由奔放に生きてきた喜佐子さん。その母の存在に苦しんで、ついに自死した次女。今喜佐子さんは毎日次女の幻覚を見ては、名前を呼ぶ。
いっそ完全に忘れてしまえば、幸せなのか。それとも娘の死を忘れていることは幸せと言えるのか――。
次回に続きます。
取材・文/坂口鈴香
終の棲家や高齢の親と家族の関係などに関する記事を中心に執筆する“終活ライター”。訪問した施設は100か所以上。20年ほど前に親を呼び寄せ、母を見送った経験から、人生の終末期や家族の思いなどについて探求している。