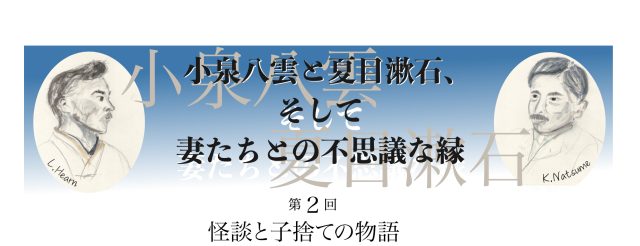
小泉セツ&小泉八雲の夫婦がモデルとなった朝の連続テレビ小説『ばけばけ』が注目されています。実はその小泉夫妻と、明治の文豪・夏目漱石と妻・鏡子は、不思議と重なり合う縁で結ばれていた、というのをご存じでしょうか。
夏目漱石の研究家として知られ、『心を癒す漱石の手紙』などの著書を持つ、作家で雑誌編集記者の矢島裕紀彦さんによると、二人の文豪とその妻たちには奇縁と呼ぶしかないような不思議なつながりがあると言います。
多数の文献や手記を紐解きながら、二組の夫婦の知られざる素顔を全26回の連載にて紹介します。
第2回では夏目漱石の怪談から見えてくる、小泉八雲が与えた影響を考察します。
文・矢島裕紀彦
夏目漱石が描いた怪談『夢十夜』
小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)というと、多くの人が『耳なし芳一』『雪女』『青柳物語』『むじな』などの怪談を思い浮かべるだろう。一般にはあまり知られていないことかもしれないが、夏目漱石にも八雲作品とみまごうような怪談めいた小説がある。
その代表的なものが『夢十夜』。《こんな夢を見た》の書き出しではじまる夢の物語の連作である。中で、とくに注目すべきは、その「第三夜」だ。
父親が6歳になる自分の子をおぶって、田圃道を歩いている。背中の子は盲目のはずなのに、辺りの景色がはっきり見えている。
対話しながら歩いているうちに何だかとてつもなく気味が悪くなって、背中の子をどこかへ捨ててしまおうと思い、父親は闇の向こうに見える森へ向かって進んでいく。
「御父(おとっ)さん、重いかい」
「重かあない」
「今に重くなるよ」
会話をしながら、父親は、石塔の案内する「日が窪」のほうへと歩いていく。いつのまにやら雨が降っている。
「此処だ、此処だ。ちょうどその杉の根の処だ。御父さん、その杉の根の処だったね」
背中の子に言われ、父親はつい答えてしまう。
「うん、そうだ」
「文化五年辰年だろう」
言われると、父にもそれらしく思える。
「お前がおれを殺したのは今から丁度百年前だね」
背中の子にズバリとそう切り込まれ、父は100年前のこんな闇の晩に、この杉の根でひとりの盲人を殺したという自覚が忽然と起こる。ああ、自分は人殺しだったんだなと気がついた途端に、背中の子どもが石地蔵のように、ずしりと重くなった――。
なんとも空恐ろしい心地のする物語である。人間が生まれながらに背負っている“罪”のようなものまで感じさせる。さらに言えば、物語の奥底に、漱石が若い頃に鎌倉の禅寺で与えられ、通過できずに終わったという公案(禅師から坐禅者に授けられた課題)「父母未生以前本来の面目」(自分の父も母も生まれぬ前の自己の真の姿)につながるものを読み取ることもできるだろう。
この『夢十夜』の「第三夜」は、小泉八雲が出雲の国の伝承譚として伴侶のセツから聞き取って、来日後最初の著作である『日本瞥見記』(書名は『知られぬ日本の面影』『日本の面影』など複数の訳がある)の第21章「日本海に沿うて」の中に記した挿話からインスピレーションを受けた部分もあったのではないかと推測されている。八雲の録した伝承とは、出雲の国の持田浦という村に伝えられるという、次のような子捨ての話である。
ある百姓の男は、貧しさから子どもを持つことを諦め、女房に赤ん坊が生まれるとその度ごとに川に流し、周囲には死産だったと誤魔化していた。
その後、ようやく少し蓄えができて、今度は生まれた赤ん坊を育てはじめ、父親はある月夜の晩に生後五か月の赤ん坊を抱いて庭に出る。そこで父親が、
「アア! コンヤハ メズラシイ エエ ヨダ!」
と声を上げると、まだ乳離れのしていない赤ん坊がいきなりこう言い放つ。
「オトッツァン! ワシ ヲ シマイ ニ ステサシタトキモ チョウド コンヤ ノ ヨーナ ツキヨ ダッタネ!」
生後五か月のこの赤ん坊の台詞が、『夢十夜』(第三夜)の背中の子どもの台詞と共鳴するというのである。この伝承譚を、八雲は、《その百姓は坊主になった》という一文で結んでいる。
実際のところ、漱石は米国ニューヨークの出版社ホートン・ミフリン社から1894年(明治27年)に刊行された『日本瞥見記』(『知られぬ日本の面影』)の原書を読んでいるはずだ。
それは、漱石が東京帝国大学(現・東京大学)における『十八世紀英文学』の講義(明治38年9月~40年3月)において、当時のロンドンで男子が鬘(かつら)を常用していたことに言及し、次のように語っていることからも明らかである。
何しろ日本の女の髷(まげ)の様に色々の種類の発達した所を以て見ると、一時の流行は凄まじいものであつたに違いない。(略)鬘の種類を挙げて見ると story wigs, bob wigs, riding wigs,(略)いくら書いても書き切れない程ある。閑があれば十八世紀の鬘と云ふ論文を書いたら可(よ)からうと思ふ位出て来る。小泉先生の髷の研究以上の仕事である。
ここでいう「小泉先生の髷の研究」とは、八雲が『日本瞥見記』の中で日本女性の髪や結い方などについて記した「女の髪」と題する文章(第18章)を指している。もう少しページを繰って読み進めていけば、21章の持田浦の伝承譚が登場してくる。
顧みれば、漱石も八雲も、親の身勝手から、幼くして両親と離れるという切ない過去を背負っていた。ふたりが著した「子捨ての物語」には、そんな来歴が投影されていたのかもしれない。
なお、漱石は八雲の『怪談』も、早い時期に原書で読んでいる。
小泉八雲の生前最後の著書であり、代表作でもある『KWAIDAN』

『怪談』は、明治37年(1904)4月、LAFCADIO HEARN著『KWAIDAN』としてアメリカのホートン・ミフリン社から刊行された。『耳なし芳一』『雪女』『ろくろ首』などの17の怪奇譚と、虫に関する3篇の随筆が収められた一冊である。怪奇譚には、古くから日本に伝わる『諸国奇談』『臥遊奇談』『怪物與論』『古今著聞集』などの原典があり、そこに小泉家出入りの農夫らから聞きとった民間伝承も加わる。『KWAIDAN』は、こうした半ば埋もれかけていた説話をもとに、セツ夫人の献身的な協力を得て、八雲が創造的に再構成して“命”を吹き込み英語で綴り直した「再話文学」の集成なのである。
語り継がれてきた小さな物語や迷信にこそ、民衆の喜怒哀楽や目に見えぬ世界への想念が込められていると、八雲は考えていた。八雲はこうも語っている。
たとえわれわれが、幽霊をめぐる古風な物語やその理屈づけを信じないとしても、なお今日、われわれ自身が一個の幽霊にほかならず、およそ不可思議な存在であることを認めないわけにはいかない。(『文学における超自然的なものの価値』)
『KWAIDAN』刊行から半年後の9月26日、八雲は狭心症のため東京・西大久保の自宅で急逝した。八雲は日本在住14年の間に11冊の著作を世に出しているが、『KWAIDAN』は生前に刊行され手にしていた最後の著書であり、渾身の代表作であった。
漱石は同年12月、まだ日本国内では余り出回っていないこの一書を、偶然に手にとった。門弟の皆川正禧が、門弟仲間の野間真綱に渡してほしいと、漱石のもとに2冊の洋書を置いていった。その1冊が『KWAIDAN』だったのである。漱石は野間宛ての手紙に《皆川は(略)洋書を二冊僕に托して君にやつてくれろといひ置いて行つた 一冊はハーンの怪談で御蔭で之を通読した》と綴り、その僥倖を喜んだのだった。
漱石が翌明治38年(1905)1月に発表した『倫敦塔』も、怪談めいた恐くて切ない作品と言っていい。日本に暮らした八雲が日本の伝承をもとに再話文学を紡いだのと対照的に、ロンドンに留学した漱石はロンドン塔にまつわる歴史や伝説を一篇の物語に仕立て上げた。続いて書かれた『琴のそら音』『趣味の遺伝』も、評論家の江藤淳をして「怪談もの」と言わしめた作品。八雲の『KWAIDAN』を読んだことで、知らぬ間に刺激された面もあったかもしれないが、いずれ、漱石もなかなかの怪談好きなのである。

なお、『怪談』をはじめとする八雲の著作を日本語で身近に読めるようになったのは、昭和初年の全集刊行以降という。昨今では、英語、日本語以外にもさまざまな言語に翻訳されて世界に発信され、親しく読み継がれている。
* * *

矢島裕紀彦(やじま・ゆきひこ)
1957年、東京都生まれ。早稲田大学政経学部卒。作家・雑誌編集記者。文学、スポーツ、歴史など幅広いジャンルをフィールドに“人間”を描く。著書に『心を癒す漱石の手紙』『文士の逸品』『文士が愛した町を歩く』『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』『ウイスキー粋人列伝』『著名人名づけ事典』『こぼれ落ちた一球』『石橋を叩いて豹変せよ』『あの人はどこで死んだか』など多数。グランドセイコー広告の掌編小説シリーズ『時のモノ語り』で2018年度朝日広告賞朝日新聞特別賞受賞。https://atelier1328.com
(この連載を通しての主な参考文献)
『漱石全集』全28巻、別巻1(岩波書店、1993~1999年)/夏目鏡子述・松岡譲筆録『漱石の思い出』(文春文庫、1994年)/夏目伸六『父・夏目漱石』(文春文庫、1991年)/夏目伸六『父・漱石とその周辺』(芳賀書店、1967年)/高浜虚子『回想子規・漱石』(岩波文庫、2002年)/松岡陽子マックレイン『漱石夫妻 愛のかたち』(朝日新書、2007年)/荒正人『増補改訂漱石研究年表』(集英社、1984年)/江藤淳『漱石とその時代』第1部~5部(新潮新書、1970~1999年)/『新潮日本文学アルバム夏目漱石』(新潮社、1983年)/『別冊國文学 夏目漱石事典』(学燈社、1990年)/『夏目漱石の美術世界』(東京新聞、NHKプロモーション、2013年)/出久根達郎『漱石先生とスポーツ』(朝日新聞社、2000年)/江戸東京博物館・東北大学編『文豪・夏目漱石』(朝日新聞社、2007年)/平岡敏夫『「坊つちやん」の世界』(塙新書、1992年)/恒松郁生『漱石 個人主義へ』(雄山閣、2015年)/小泉節子、小泉一雄『小泉八雲 思い出の記 父「八雲」を憶う』(恒文社、1976年)/小泉八雲、平井呈一訳『日本瞥見記』上・下(恒文社、1975年)/小泉八雲、平井呈一訳『東の国から・心』(恒文社、1975年)/小泉八雲、平川祐弘編『怪談・奇談』(講談社学術文庫、1990年)/小泉八雲、池田雅之編訳『虫の音楽家』(ちくま文庫、2005年)/『明治文学全集48 小泉八雲集』(筑摩書房、1970年)/小泉時共編『文学アルバム小泉八雲』(恒文社、2000年)/小泉凡監修『小泉八雲、開かれた精神の航跡。』(小泉八雲記念館、2016年)/池田雅之監修『別冊太陽 小泉八雲』(平凡社、2022年)/池田雅之『小泉八雲』(角川ソフィア文庫、2021年)/田部隆次『小泉八雲』(北星社、1980年)/長谷川洋二『八雲の妻』(今井書店、2014年)/関田かをる『小泉八雲と早稲田大学』(恒文社、1999年)/梶谷泰之『へるん先生生活記』(恒文社、1998年)/池野誠『松江の小泉八雲』(山陰中央新報社、1980年)/工藤美代子『神々の国』(集英社、2003年)/工藤美代子『夢の途上』(集英社、1997年)/工藤美代子『聖霊の島』(集英社、1999年)/平川祐弘編『小泉八雲回想と研究』(講談社、1992年)/平川祐弘『世界の中のラフカディオ・ハーン』(河出書房新社、1994年)/熊本大学小泉八雲研究会『ラフカディオ・ハーン再考』(恒文社、1993年)/西川盛雄『ラフカディオ・ハーン』(九州大学出版会、2005年)/西成彦『ラフカディオ・ハーンの耳、語る女たち』(洛北出版、2024年)/池田雅之『日本の面影』(NHK出版、2016年)/ラフカディオ・ハーン『小泉八雲東大講義録』(KADOKAWA、2019年)/芦原伸『へるん先生の汽車旅行』(集英社インターナショナル、2014年)/嵐山光三郎『文人暴食』(新潮文庫、2006年)/河東碧梧桐『子規を語る』(岩波文庫、2002年)/『正岡子規の世界』(松山市立子規記念博物館、1994年)/『子規全集』18巻、19巻(講談社、1979年)/『志賀直哉全集』第8巻(岩波書店、1999年)/『芥川龍之介全集』第4巻(岩波書店、1996年)/瀬沼茂樹『評伝島崎藤村』(筑摩書房、1981年)/矢島裕紀彦『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫、2009年)/矢島裕紀彦『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』(NHK生活人新書、2003年)/矢島裕紀彦『文士が愛した町を歩く』(NHK生活人新書、2005年)/矢島裕紀彦『文士の逸品』(文春ネスコ、2001年)






























