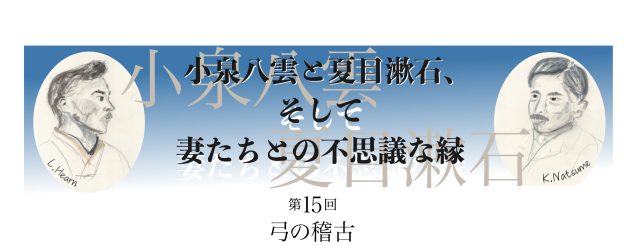
小泉セツ&小泉八雲の夫婦がモデルとなった朝の連続テレビ小説『ばけばけ』が注目されています。実はその小泉夫妻と、明治の文豪・夏目漱石と妻・鏡子は、不思議と重なり合う縁で結ばれていた、というのをご存じでしょうか。
夏目漱石の研究家として知られ、『心を癒す漱石の手紙』などの著書を持つ、作家で雑誌編集記者の矢島裕紀彦さんによると、二人の文豪とその妻たちには奇縁と呼ぶしかないような不思議なつながりがあると言います。
多数の文献や手記を紐解きながら、二組の夫婦の知られざる素顔を全26回の連載にて紹介します。
第15回では、八雲と漱石が共にのめりこんだ、弓道のエピソードをご紹介。独特なフォームで技を極めた八雲、一日に200本も弓を引いたという漱石。二人の弓道への情熱ぶりがうかがえます。
文・矢島裕紀彦
ほぼ時を同じくして弓道を習い始めた八雲と漱石

明治は、江戸と地続きの時代である。侍や武芸は現代よりずっと身近な存在であった。
たとえば、セツの養父の稲垣金十郎にしてからが、幕末、松江藩士として京の警護に当たり、鳥羽・伏見の戦いにも参加しているのだ。
ただ、金十郎が八雲の長男・一雄に語り聞かせる京都勤番中の話は妙に面白おかしく、当時の会計日記に「烏丸通りに良き店見付け早速家来を遣す、あん三文、かりん糖二文」の記述を残すような甘党ぶりを見せていたという。どこかトボけた味わいのある人物であったのだろう。
明治24年(1891)11月、八雲は松江中学から熊本五高へと転任する。このとき、教え子たちから八雲に感謝の印の記念品として贈られたのは日本刀(短刀)であった。ここにも武士の時代の残照がある。
中学の生徒を代表して大谷正信が送別の言葉を送り、八雲は答辞を述べた。
親愛なる生徒諸君。――
わたくしはみなさんから贈られた、あの銀の唐獅子が鞘の上に躍り、下げ緒を通したみごとな柄(つか)に眠っている、あの美しい刀を頂戴したときに、自分がどんな思いをしたか、とてもここでは申し上げることができません。すくなくとも、思いのたけをここで申し上げることは不可能です。ただ、あの贈り物を拝見したときに、わたくしは昔からみなさんがよくいう諺をおもいだしました。「刀はサムライの魂なり」という諺です。そこで、なるほど、みなさんがこのすばらしいお土産の品を選んだのは、つまり、みなさんがたの魂を形にあらわしてくれたのだなと、わたくしはそういう心持がいたしました。
熊本転任に当たり、八雲はセツ夫人とともにセツの養父母や養祖父らを、家族として連れていった。学校側が紹介した洋式の外国人官舎は断り、最初、手取本町の旧士族の持ち家だった屋敷に住み、翌年、広い庭と離れのある坪井西堀端の家に転居した。
その自宅の150坪もある広い庭で、八雲は義父の稲垣金十郎から弓の指南を受けた。まさしく武士からの直伝。八雲も手にすり傷をつくるほど稽古に打ち込んだ。熊本五高の同僚の教師たちも弓道を嗜んだらしいから、その影響もあったのだろうか。自宅での弓の稽古のため、金十郎は普段から隠居部屋で、矢羽根や弓絃の修理、的の制作に熱心に取り組んでいたという。
八雲は左目が不自由というハンデがありながら、首尾はまずまずで、気をよくしていたようだ。その個性的なフォームについては、あとでふれる。
八雲が熊本五高在任中の明治27年(1894)春、夏目漱石も弓道をはじめている。
きっかけは、同年2月頃、血痰があって医師の診察を受け、肺結核の疑いを告げられたことだった。漱石は数年前に実兄ふたりを結核で亡くしており、しかも側近くで看護に当たっていた。医師が疑いを持つのも無理からぬことだった。検痰の結果、結核菌は検出されなかった。だが、医師からは、念のため服薬を続ける一方で、滋養物をとり、適度な運動を取り入れながら摂生するよう勧められた。
漱石はこの頃、帝国大学の寄宿舎から大学院に通っていた。ちょうど周囲で弓道をやりはじめた者たちがいて、漱石もこれに加わり、次第にのめりこんだのである。
弓をはじめた漱石は、早速、すでに大学を中退し新聞社勤めをはじめている友人の正岡子規に宛てて、こんな手紙を書いている。
其後(そのご)病勢次第に軽快に相成(あいなり)目下は平生に異なるところなく至て健全に感じ居(おり)候(そうら)へども 服薬は矢張以前の通(とおり)致し 滋養物も可成(なるべく)食ひ居候(略)当時は弓の稽古に朝夕余念なく候
弦音にほたりと落る椿かな
弦音になれて来て鳴く小鳥かな
弦音の只聞ゆなり梅の中
(明治27年3月12日付)
末尾に書き添えられた3句から、春のひと日、漱石と仲間たちが溌剌と弓を引く姿が、はじける青春の弦音とともに眼前に立ちのぼってくる。
さらに、ふた月半後の5月31日付、大学の同級生で山口高等学校教師の菊池謙二郎に宛てた書簡では、漱石は具体的な数字を上げて自身の稽古ぶりを伝えている。
小生は其後毎日弓術を強勉致居候(略)朝夕両度に百本位は毎日稽古致居候
この「朝夕両度に百本位」の弓の稽古とは、どれほどの強度であったのか。試みに、渋沢栄一編纂『徳川慶喜公伝』を繙いてみたい。
徳川幕府最後の将軍・徳川慶喜は、大政奉還、江戸城無血開城を経て、その後の長い隠遁生活(大正2年76歳で没するまで)を、持ち前の凝り性からさまざまな趣味に没頭して過ごしたことで知られるが、弓道に関して次のような逸話が伝えられている。
大弓は初は毎回百五十本と定め、家臣は三人づつ日毎に当番を定めて御相手仕(つかまつ)りしに、御相手の人々却って疲労を覚ゆるさまなりき。老後には医師より運動の過激なるを言上し、百本に減じ給ひしも、是れにても尚三時間は費されき。斯くて薨去の年の春までは、必ず日課のやうになされたり。
武門の頂点にあった慶喜にして、日に100~150本の稽古。それで、付き添う者が疲れてしまうほどだったというのだから、漱石の「朝夕両度に百本」の弓道熱は並外れたものであったと言わなければならない。
個性的ながらも弓道を極めた八雲

八雲は明治29年(1896)9月、東京へ移り住んだ。このとき、セツの養父の稲垣金十郎も家族として当たり前に同行した。転居先の市谷富久町の家でも、金十郎は裏手の寺院(瘤寺)の林との間にある草地に出て、家族一同の見守る中、見事な弓の腕前を見せていたという。当時まだ5歳かそこらだった八雲の長男・一雄が、弓を引く祖父と父の姿をよく記憶し、後世に伝えている(文中、「雲峰院様」は金十郎のこと)。
瘤寺の山の斜面へ的を懸けて、相当の距離から片肌脱いだ雲峰院様がよっ引(ぴい)てひょうと放つ矢は、真直に飛んで行って惜気もなくカーンと朗かな音を立てて的へ命中する率が多かったのです。(略)父はいつも大概傍で見物していましたが、でも、一、二度は、足の開きや肘の張具合を雲峰院様から教えられて射ったことがありました。懸眼鏡をいっさい用いぬ、否、持ち合せぬ父は、まず最初に懐から小さな持手のついた独眼鏡を取り出して、じいっと的を見定めた後、眼鏡をしまって、それから一気に引いたと思うと、もうひょうと放つのです。父の矢は的へ当らぬまでもその近くへ一直線に少しも震うことなく飛んで行くのを、雲峰院様初め一同は奇異なことに思っていました。(『父「八雲」を憶う』)
小泉家に同居していた書生やお抱え車夫が弓を借りて試みても、放たれた矢の軌道は、大きな山形を描いたり、ひょろひょろとよろけたり、途中から地面をかすったりして、まっすぐに飛ばなかったというから、八雲は極めて個性的なやり方ながら、ひとつの技芸を身につけつつあったことが窺える。
皆が射ち終わると、一目散に走って矢を拾いにいくのが、幼い一雄の楽しみだった。あるとき、金十郎が弓をひきしぼって最後の一矢を放とうとしているとき、それを待ちきれず、一雄が的の方へ向かって駆け出してしまったことがあった。
次の瞬間、その一雄の頭をかすめるようにして、金十郎の放った矢が飛んだ。大人たちは叫び声を上げ、顔面蒼白となった。この時以来、金十郎や八雲は二度と弓を手にすることはなかったという。
弓を手離した金十郎は、その後、折にふれ一雄に、「坊がもうつうと大(で)ッけになったら我(わす)が起倒流の柔術(やわら)を教えちゃる」と口にしていたが、その思いを果たさぬまま、一雄が7歳となる明治33年(1900)11月、59歳で鬼籍に入った。
* * *

矢島裕紀彦(やじま・ゆきひこ)
1957年、東京都生まれ。早稲田大学政経学部卒。著書に『心を癒す漱石の手紙』『打つ 掛布雅之の野球花伝書』(以上、小学館文庫)『漱石「こころ」の言葉』『ウイスキー粋人列伝』(以上、文春新書)『夏目漱石 100の言葉』(宝島社)『文士の逸品』(文藝春秋)『文士が愛した町を歩く』『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』(以上、NHK生活人新書)『石橋を叩いて豹変せよ 川上哲治V9巨人軍は生きている』(NHK出版)『こぼれ落ちた一球 桑田真澄、明日へのダイビング』(日本テレビ出版部)『あの人はどこで死んだか』(主婦の友社)ほか多数。漱石没後百年の2016年、サライ.jp で『日めくり漱石』を1年間連載。グランドセイコー広告の掌編小説シリーズ『時のモノ語り』で2018年度朝日広告賞朝日新聞特別賞受賞。https://atelier1328.com
(この連載を通しての主な参考文献)
『漱石全集』全28巻、別巻1(岩波書店、1993~1999年)/夏目鏡子述・松岡譲筆録『漱石の思い出』(文春文庫、1994年)/夏目伸六『父・夏目漱石』(文春文庫、1991年)/夏目伸六『父・漱石とその周辺』(芳賀書店、1967年)/高浜虚子『回想子規・漱石』(岩波文庫、2002年)/松岡陽子マックレイン『漱石夫妻 愛のかたち』(朝日新書、2007年)/荒正人『増補改訂漱石研究年表』(集英社、1984年)/江藤淳『漱石とその時代』第1部~5部(新潮新書、1970~1999年)/『新潮日本文学アルバム夏目漱石』(新潮社、1983年)/『別冊國文学 夏目漱石事典』(学燈社、1990年)/『夏目漱石の美術世界』(東京新聞、NHKプロモーション、2013年)/出久根達郎『漱石先生とスポーツ』(朝日新聞社、2000年)/江戸東京博物館・東北大学編『文豪・夏目漱石』(朝日新聞社、2007年)/平岡敏夫『「坊つちやん」の世界』(塙新書、1992年)/恒松郁生『漱石 個人主義へ』(雄山閣、2015年)/小泉節子、小泉一雄『小泉八雲 思い出の記 父「八雲」を憶う』(恒文社、1976年)/小泉八雲、平井呈一訳『日本瞥見記』上・下(恒文社、1975年)/小泉八雲、平井呈一訳『東の国から・心』(恒文社、1975年)/小泉八雲、平川祐弘編『怪談・奇談』(講談社学術文庫、1990年)/小泉八雲、池田雅之編訳『虫の音楽家』(ちくま文庫、2005年)/『明治文学全集48 小泉八雲集』(筑摩書房、1970年)/小泉時共編『文学アルバム小泉八雲』(恒文社、2000年)/小泉凡監修『小泉八雲、開かれた精神の航跡。』(小泉八雲記念館、2016年)/池田雅之監修『別冊太陽 小泉八雲』(平凡社、2022年)/池田雅之『小泉八雲』(角川ソフィア文庫、2021年)/田部隆次『小泉八雲』(北星社、1980年)/長谷川洋二『八雲の妻』(今井書店、2014年)/関田かをる『小泉八雲と早稲田大学』(恒文社、1999年)/梶谷泰之『へるん先生生活記』(恒文社、1998年)/池野誠『松江の小泉八雲』(山陰中央新報社、1980年)/工藤美代子『神々の国』(集英社、2003年)/工藤美代子『夢の途上』(集英社、1997年)/工藤美代子『聖霊の島』(集英社、1999年)/平川祐弘編『小泉八雲回想と研究』(講談社、1992年)/平川祐弘『世界の中のラフカディオ・ハーン』(河出書房新社、1994年)/熊本大学小泉八雲研究会『ラフカディオ・ハーン再考』(恒文社、1993年)/西川盛雄『ラフカディオ・ハーン』(九州大学出版会、2005年)/西成彦『ラフカディオ・ハーンの耳、語る女たち』(洛北出版、2024年)/池田雅之『日本の面影』(NHK出版、2016年)/ラフカディオ・ハーン『小泉八雲東大講義録』(KADOKAWA、2019年)/芦原伸『へるん先生の汽車旅行』(集英社インターナショナル、2014年)/嵐山光三郎『文人暴食』(新潮文庫、2006年)/河東碧梧桐『子規を語る』(岩波文庫、2002年)/『正岡子規の世界』(松山市立子規記念博物館、1994年)/『子規全集』18巻、19巻(講談社、1979年)/『志賀直哉全集』第8巻(岩波書店、1999年)/『芥川龍之介全集』第4巻(岩波書店、1996年)/瀬沼茂樹『評伝島崎藤村』(筑摩書房、1981年)/矢島裕紀彦『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫、2009年)/矢島裕紀彦『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』(NHK生活人新書、2003年)/矢島裕紀彦『文士が愛した町を歩く』(NHK生活人新書、2005年)/矢島裕紀彦『文士の逸品』(文春ネスコ、2001年)





























