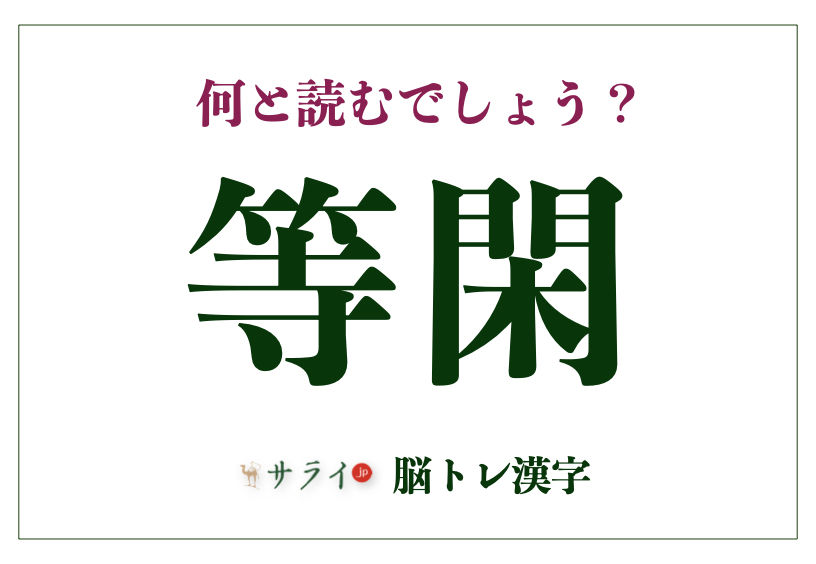言葉遊びがおもしろい
I:さて、第5回で印象に残ったのは、「平賀源内がきた。ってなもんで親父様たちゃはしゃいじまって、鯛の味噌ずに四方(よも)の赤、のめやうたえやチンチンドン」という蔦重の台詞でした。
A:『べらぼう』には「ありがた山の寒がらず」「もうこれしか中橋」とか「かたじけ茄子」「そこだけは言うてもおくれな小夜嵐」などの言葉遊びのたぐいの台詞が頻出しています。
I:『初めての大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」歴史おもしろBOOK』でも紹介されていますが、こうした言葉遊びの流れが、昭和にもつながっていて「あたり前田のクラッカー」なんていうのがそうらしいんですよね。『歴史おもしろBOOK』の取材で、国文学研究資料館の松原哲子特任准教授に聞いたのですが、人気漫画『名探偵コナン』第93巻でも「ありがた山のホトトギス」という登場人物の台詞があるのですよ。
A:最近、50年ほど前の人気ドラマ『ありがとう』が東京МXテレビやBS12などで再放送されていますが、「その手は桑名の焼き蛤」という台詞が出てきたりしていました。ですから、こうした言葉遊びも息が長い。
I:「恐れ入り谷の鬼子母神」とか私もついいってしまったりします。そして、すごいなと思ったのが、前出の松原哲子准教授が学生時代に江戸時代の草双紙を読み込んで、言葉遊びの語句を抜き出す作業をしていたということです。今週蔦重が発した「鯛の味噌ずに四方の赤」というのも、松原准教授によると、弘前藩邸にいた通称「津軽のおぢい」なる人物が考案したのだといいます。
A:ここまで広がっていた江戸の言葉遊びがなぜ衰退したのか、いずれ稿を改めて紹介したいと思います。
●編集者A:書籍編集者。『べらぼう』をより楽しく視聴するためにドラマの内容から時代背景などまで網羅した『初めての大河ドラマ べらぼう 蔦重栄華乃夢噺 歴史おもしろBOOK』などを編集。
●ライターI:文科系ライター。月刊『サライ』等で執筆。猫が好きで、猫の浮世絵や猫神様のお札などを集めている。江戸時代創業の老舗和菓子屋などを巡り歩く。
構成/『サライ』歴史班 一乗谷かおり