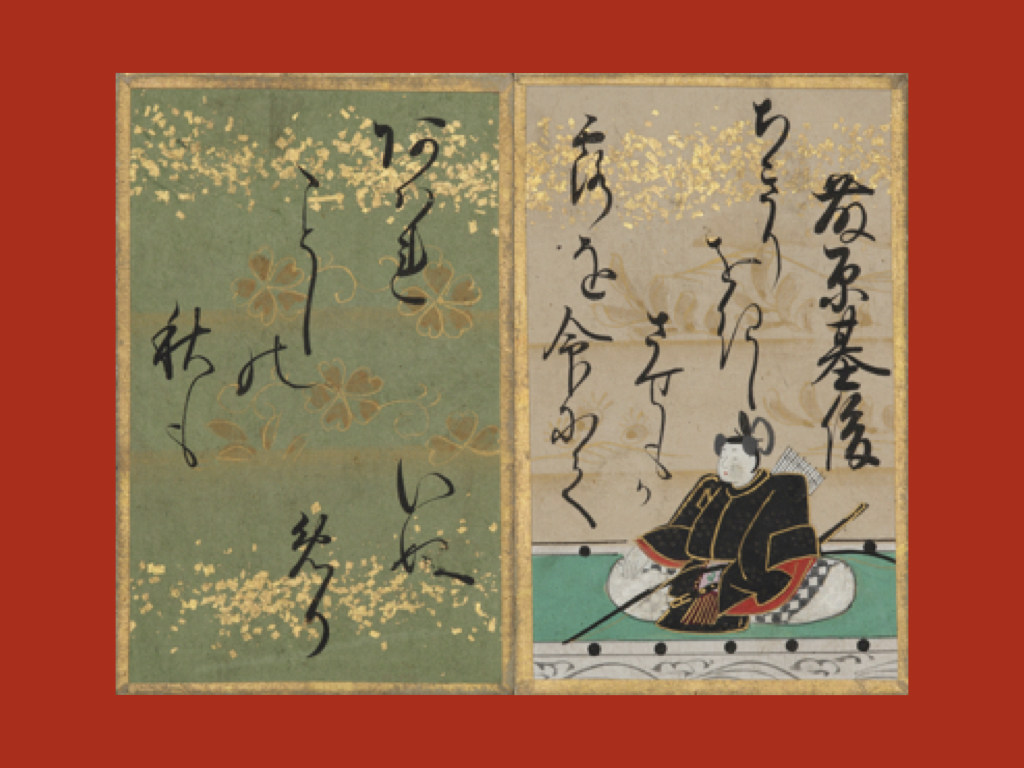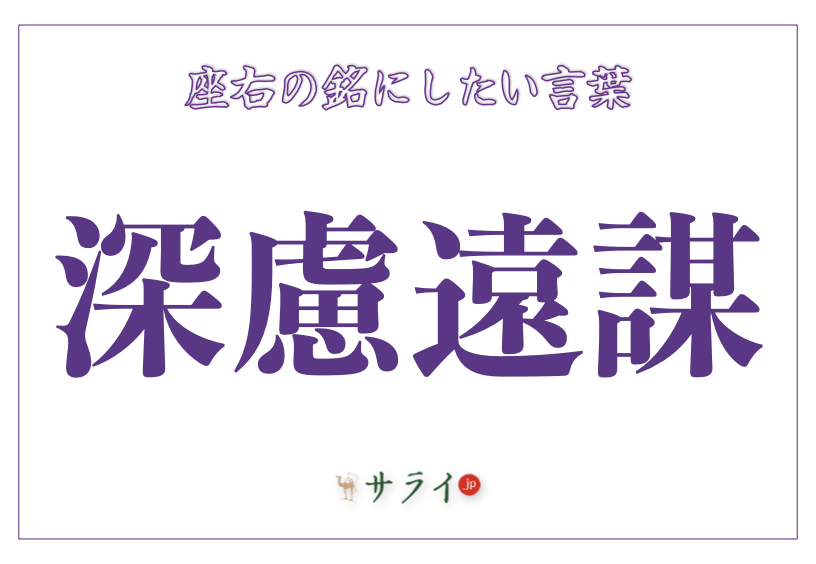ドラッグストアで陳列されていて、よく目にする漢方薬。
「苦いけど体によさそう」「葛根湯は知っているけど……」など、「そもそも漢方ってどんなもの?」と思っている方も多いのではないでしょうか。
そんな基本的な漢方に関する疑問や基礎知識を、漢方の専門家にわかりやすく解説してもらいます。
今回のテーマは、「潤腸湯(じゅんちょうとう)」です。
ヨガインストラクター・ライターの高橋かなこさんと、あんしん漢方(オンラインAI漢方)の薬剤師、碇 純子さんに教えてもらいました。
潤腸湯はどんな方におすすめ?

漢方薬が目指すのは苦痛を和らげるための対症療法ではなく、根本的な解決です。
体質の改善に働きかけることのできる漢方薬は、「同じ症状を繰り返したくない」という思いに応えてくれます。
潤腸湯は胃腸を潤す働きがあるといわれていますが、具体的にどんな不調に効果が期待できるのでしょうか?
便秘にお悩みの方
潤腸湯は常習性便秘解消に効果が期待できる大黄甘草湯(だいおうかんぞうとう)が含まれているため、腸を潤して便通をよくする働きがあるといわれています。
高齢者や虚弱者の便秘症によく使われ、「何日も便が出ない」「便が出ても全部出切った感じがしない」といった方におすすめです。
コロコロとした便が出る方
便が出ていても、腸が乾燥しているとうさぎやシカのような、コロコロとした便が出る場合があります。
潤腸湯は、この症状に有効な麻子仁丸(ましにんがん)と同様に、腸内の水分量を増やして乾燥して硬くなった便をスッキリ気持ちよく体外に排出しやすくします。
便秘による肌トラブルにお悩みの方
腸内環境が悪くなると、腸の動きが鈍くなって老廃物が体外に十分排出されなくなるといわれています。
その老廃物が血流に乗って全身にめぐることで、肌にも影響があらわれ、ニキビなどの不調が生じてしまうのです。
そのため、潤腸湯で腸内環境を整えることで、間接的に肌トラブルの解消に貢献できる可能性があります。
潤腸湯と併せて行いたいストレッチ

便秘の改善にはストレッチが効果的です。
その理由は、ストレッチによって腸の動きを活性化させ、排便を促す効果が期待できるからです。
とくに、腹部や腰回りを伸ばすストレッチは、腸のぜんどう運動を促し、便の移動をスムーズにすると考えられます。
呼吸と連動させて体をほぐしてあげましょう。
腸を刺激するストレッチ
(1)うつ伏せになり、両腕は体の横に置く。
おでこは床につけて、両足は腰幅程度に開く。
(2)息を吸いながら脚、胸、腕を持ち上げる。
脚は片方ずつ持ち上げて、指先とつま先を後ろにしっかり伸ばす。
(3)目線は正面に向けて、3〜5呼吸ほどキープする。
勢いで腰を反らすと腰痛の原因になります。
お尻、内ももに力を入れて無理のない範囲で行いましょう。
体をうまく持ち上げられない場合は、上半身と両腕は床につけたまま、下半身のみを持ち上げてみてください。
両手でしっかり床を押すと、実践しやすいですよ。
仙骨(おしりのすぐ上)を刺激するストレッチ
仙骨は骨盤の後ろにある三角形の骨で、骨盤の神経が集中しています。
この部分を刺激したり温めたりすることで、便秘の改善につながるといわれています。
(1)仰向けでひざを立てる。
(2)両手は体の横に置き、息を吸いながらお尻を持ち上げる。
肩からひざまで一直線をキープする。
(3)息を吐きながらお尻をストンと床におろす。
10回ほどくり返しましょう。
ベッドや布団の上は柔らかすぎて効果が薄れる可能性があるので、床にヨガマットなどを敷いて行うのがおすすめです。
潤腸湯に副作用はある? 安心して服用するには

漢方薬は自然由来の生薬からできているので、一般的には西洋薬より副作用が少ないといわれています。
しかし、場合によっては下記のような副作用があらわれる可能性があります。
・発熱、から咳、息切れ、呼吸困難
・尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる
・体がだるくて手足に力が入らない、手足がひきつる、手足がしびれる
・皮膚や白目が黄色くなる
上記のような症状がみられる場合は、すみやかに服用を中断して医療機関を受診してください。
このような副作用が生じないようにするためにも、ご自身の体に合った漢方薬を選ぶことが重要です。
しかし、初めて漢方薬を購入する場合は、何を選べばいいのか悩みますよね。
そんなときは、スマホで気軽に専門家に相談できる「あんしん漢方」のようなオンラインサービスを利用してみるのもおすすめです。
漢方のプロが体質に合った漢方薬を見極めて、お手頃価格で自宅に郵送してくれますよ。
便秘解消で健康的な体に

水分を摂ったり運動をしたりしていても、便秘になることはあるでしょう。
そんなときは、漢方薬の力に頼るのもひとつの手段です。
漢方薬は医療機関でも処方されることがあり、薬の観点から効果も認められています。
なお、初めて服用する場合は、専門の医師や薬剤師に相談してくださいね。
ご自身の体に合った漢方薬を知って、無理のない範囲でストレッチなどと組み合わせながら普段頑張ってくれている体をケアしていきましょう。
<この記事の監修者>

高橋かなこ
2021年よりRYT200(全米ヨガアライアンス認定)修了インストラクターとしてオンラインを中心に幅広い年齢層へのヨガレッスンを担当。企業での事務経験から、デスクワークで疲れた部位や崩れた姿勢のためのレッスン組み立てを得意とする。
自身のダイエット成功経験から、美しい体を作るためには食の大切さや思考も大切だと痛感。同じように悩む人に向けて精力的にメディアでの情報発信を行う。
症状・体質に合ったパーソナルな漢方をスマホひとつで相談、症状緩和と根本改善を目指すオンラインAI漢方「あんしん漢方」でもサポートを行っている。

碇 純子(いかり すみこ)
薬剤師・元漢方薬生薬認定薬剤師 / 修士(薬学) / 博士(理学)
神戸薬科大学大学院薬学研究科、大阪大学大学院生命機能研究科を修了し、漢方薬の作用機序を科学的に解明するため、大阪大学で博士研究員として従事。現在は細胞生物学と漢方薬の知識と経験を活かして、漢方薬製剤の研究開発を行う。
世界中の人々に漢方薬で健康になってもらいたいという想いからオンラインAI漢方「あんしん漢方」で情報発信を行っている。
●あんしん漢方(オンラインAI漢方):https://www.kamposupport.com/anshin1.0/lp/?tag=221432a9sera0246&utm_source=sarai&utm_medium=referral&utm_campaign=250315
イラスト:にゃたり