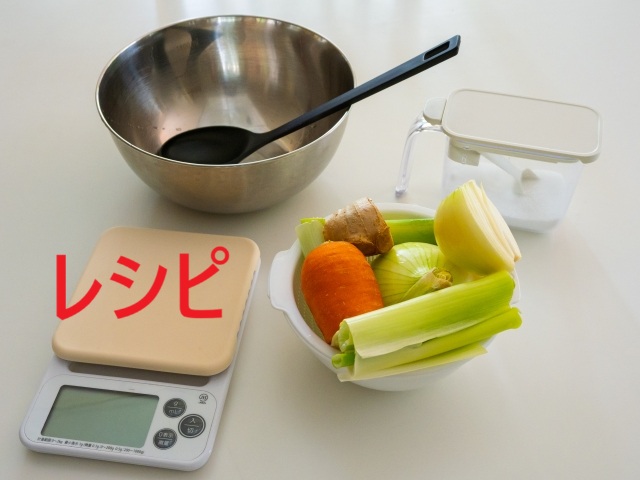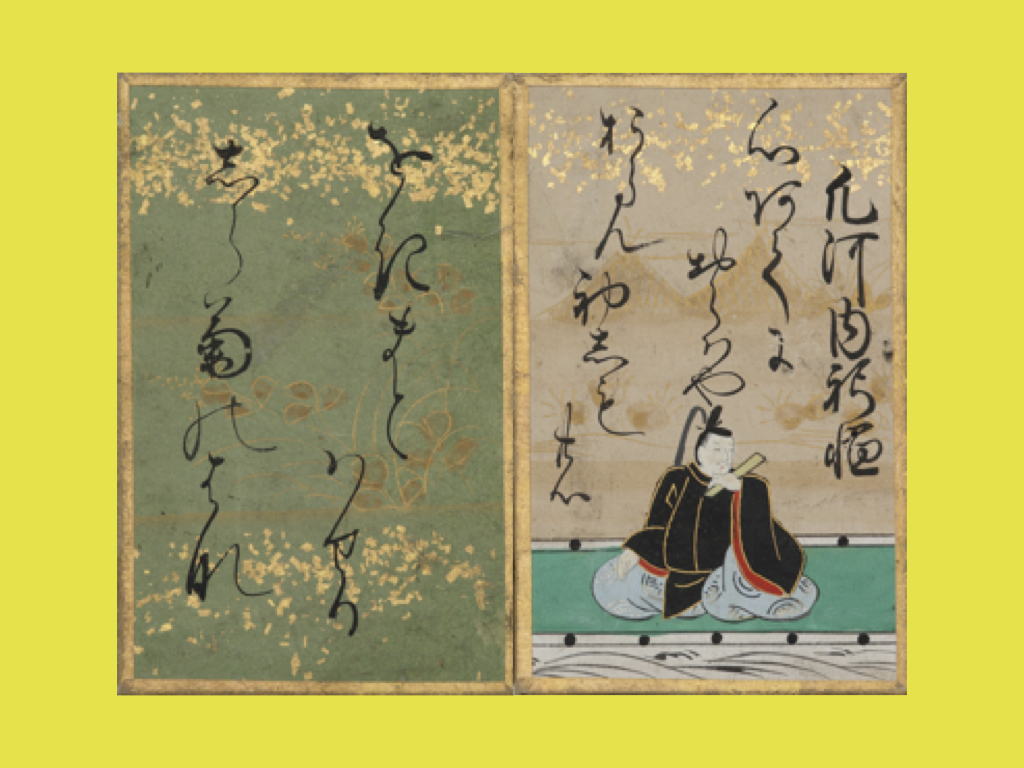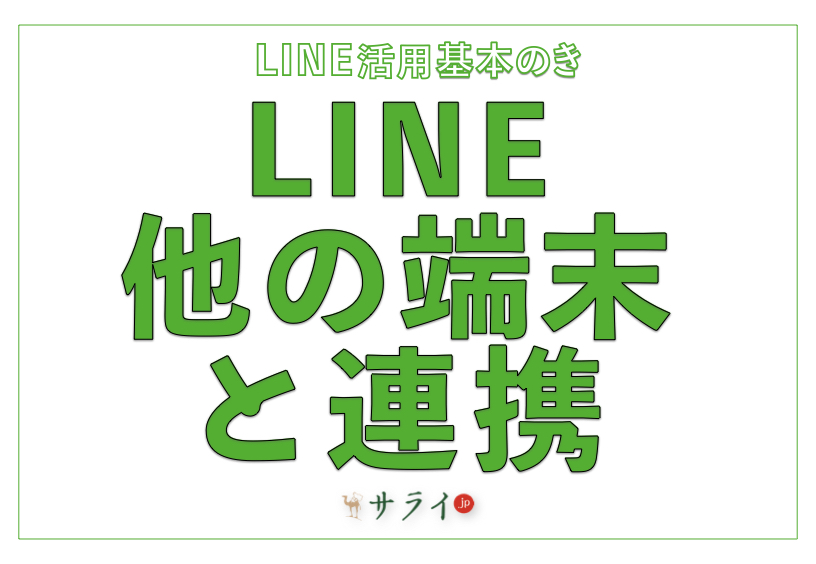マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)」が、ビジネスの最前線の用語や問題を解説するシリーズ。今回は、会社というコミュニティの価値と個人が仕事を頑張る意味について、識学的視点で考察します。
同郷の人に出会ったときの特別感
日常の中で、初対面の人と「えっ、同じ故郷なんですか?」と分かった瞬間、急に距離が縮まる経験をした方は少なくないでしょう。それまで他人だった相手が、同じ土地で育ったという共通点を知っただけで、親近感が湧き、安心感さえ覚える。この心理は不思議ですが、多くの人間が持つ普遍的な感覚です。
なぜそう感じるのか。それは「自分と同じコミュニティに属している人」と無意識に判断するからです。人は個人そのものよりも、その人が「どのコミュニティに属しているか」で価値を推し量る傾向があります。
同郷という事実は、その人の能力や性格に直結しているわけではありません。それでも「同じ場所で育った仲間」という意識が、好意的な評価につながります。これと同じ構造が、学校や部活動、会社といった他のコミュニティでも成立しているのです。
コミュニティが与える「先入観的評価」
例えば、相手が「甲子園常連校の野球部出身」と聞けば、「きっと野球が上手い」「努力してきた人だ」と想像してしまうでしょう。逆に無名のチームにいたと聞けば、実際には能力があっても同じ印象は持たれにくいはずです。
つまり、人は「その人個人」を見る前に、「どの集団に属していたか」で評価を下すのです。これは社会生活のあらゆる場面に存在しています。少なからず、下記のように判断をすることがあるのではないでしょうか。
・有名大学出身 →「頭がいいに違いない」
・大手企業勤務 →「能力が高いのだろう」
・老舗企業の社員 →「信頼できそうだ」
このように、所属する組織やコミュニティの評価が、個人の評価を大きく左右します。
会社という「コミュニティブランド」
識学の観点から見ると、この「所属による評価」は極めて重要です。なぜなら、個人の評価を高める最短ルートは、自分が属するコミュニティ、つまり会社の価値を高めることだからです。
どんなに優秀な個人であっても、組織そのものの評価が低ければ、その人が外部から受ける印象も限定的になります。逆に、会社が高いブランド価値を持っていれば、その組織に属しているだけで社員個人も高く評価されやすくなります。
識学では「人は所属する組織を通じて評価される」ことを前提に、会社の成果や結果を最優先に考えます。なぜなら、組織全体の成果こそが、最終的に社員一人ひとりの価値につながるからです。
組織の価値を高める責任
ここで多くの人が勘違いしがちなのは、「会社が社員のために価値を高めてくれる」という発想です。しかし、識学では、組織の価値を高めるのは経営者だけでなく、社員一人ひとりの行動の積み重ねだと考えます。
会社というコミュニティのブランドは、そこで働く個人の成果の総和によってしか築かれません。つまり、あなたが日々の業務を中途半端に行えば、その分だけ会社の評価を下げ、結果的に自分自身の評価も下がる。逆に、自分の責任を果たし、結果にこだわる働きを続ければ、会社全体のブランドが高まり、その恩恵を最も受けるのは他でもない自分なのです。
この「組織の評価は巡り巡って自分に返ってくる」という因果関係を理解すれば、仕事を頑張る理由は極めて明確になります。
識学的に見た「仕事を頑張る意味」
識学では、組織運営において感情よりも「ルール」と「結果」を重視します。その理由は、組織の価値を高めるためには、個々の感情に左右されることなく、全員が結果にコミットする仕組みが不可欠だからです。
この観点から整理すると、仕事を頑張る理由は以下のように言い換えることができます。
1.組織の成果が自分の評価を規定する
所属コミュニティのブランドが高いほど、自分の市場価値は自動的に上がる。
2.成果を出す仕組みに従うことで組織の価値は高まる
組織内のルールを守り、自分の役割を果たすことが会社の成長に直結する。
3.会社の価値が高まれば、最終的に自分のキャリアも豊かになる
転職・独立・対外的評価、すべてにおいて「どの会社にいたか」が効いてくる。
つまり、仕事を頑張ることは「会社に貢献する」だけでなく、「自分自身をより価値ある人間にする」ための合理的行動なのです。
「同郷の喜び」を仕事に置き換える
ここで冒頭に戻りましょう。たまたま同郷の人に出会うと、理由もなく好意的に感じてしまう心理。これを会社に置き換えれば「同じ会社にいた」というだけで、人は評価を受けやすくなる、ということです。
たとえば、ある人が誰もが知る有名企業に所属すると聞けば、その人をよく知らなくても「優秀そうだ」と思ってしまう。この効果はまさに、同郷で話が弾む現象と同じ構造です。
では、あなたが今所属する会社が、外部から「優秀な人材を輩出している」「成果を出している」と評価される組織であればどうでしょうか。その時点で、あなた自身の社会的価値は大きく高まります。 逆に、会社の評判が低ければ、「あの会社にいた人」というだけでネガティブな先入観を持たれる可能性もある。つまり、自分の努力が自分自身のためになるだけでなく、会社の評価を通じて何倍にも跳ね返ってくるのです。
自覚すべきは「所属の責任」
識学が強調するのは、組織に所属する以上、その組織の評価に自分も直結しているという自覚です。個人が「会社は会社、自分は自分」と切り離して考える限り、成果に対して主体性を持てません。
しかし、現実には、外部の人からは「○○社の社員」という肩書きで見られるわけです。だからこそ、所属している会社を軽んじることは、自分自身の評価を軽んじることに等しいのです。
「仕事を頑張るべき理由」を感情論や自己成長論で語るのではなく、所属と評価の因果関係で説明できるのが識学的なアプローチです。
まとめ
人は他人を「どのコミュニティに属しているか」で判断します。これは同郷で意気投合する心理や、有名校・有名企業出身者を優秀であるに違いないと抱く心理と同じです。
だからこそ、今あなたが所属する会社というコミュニティの価値を高めることが、最終的にあなた自身の価値を高める最短ルートとなります。識学が説くように、ルールに基づいて結果を出し続けることが組織のブランドを高め、それが「社員一人ひとりの市場価値」を押し上げていくのです。言い換えれば、「仕事を頑張る理由」は自己犠牲の精神論ではなく、きわめて合理的な自己防衛であり、自己成長戦略でもあります。
同郷の人に出会ったときの喜びが、あなたに教えてくれること。それは「人はコミュニティで人を判断する」という現実です。そして、その現実を踏まえれば、今いる会社を強くすることが、自分自身を強くすることにつながるとご理解いただけるでしょう。
識学総研:https://souken.shikigaku.jp
株式会社識学:https://corp.shikigaku.jp/