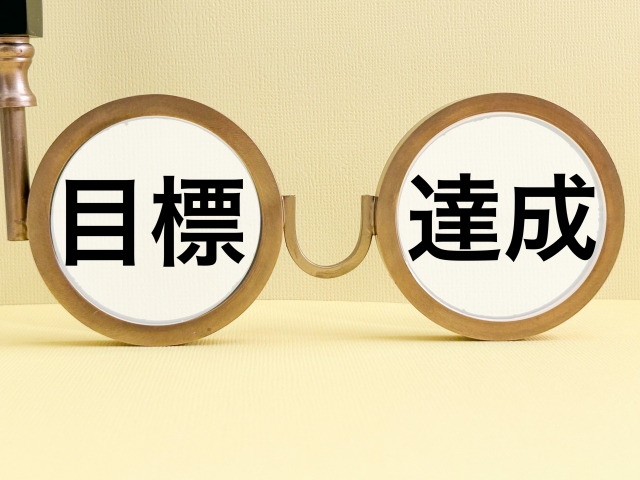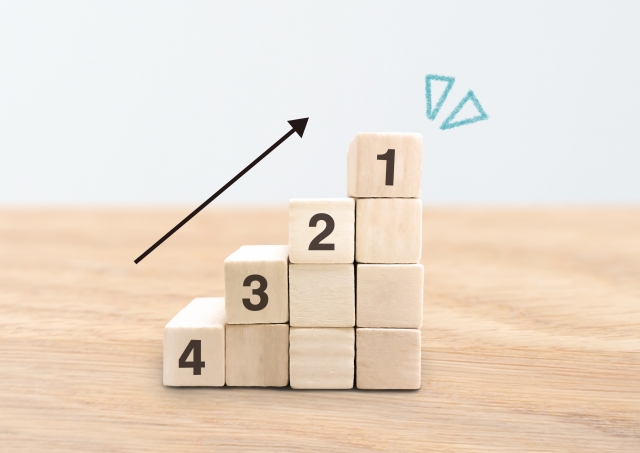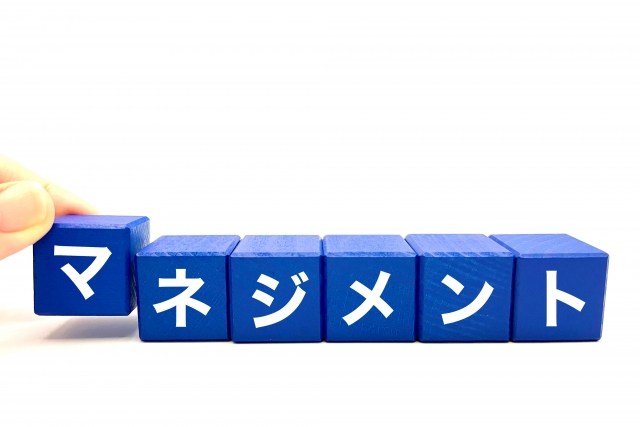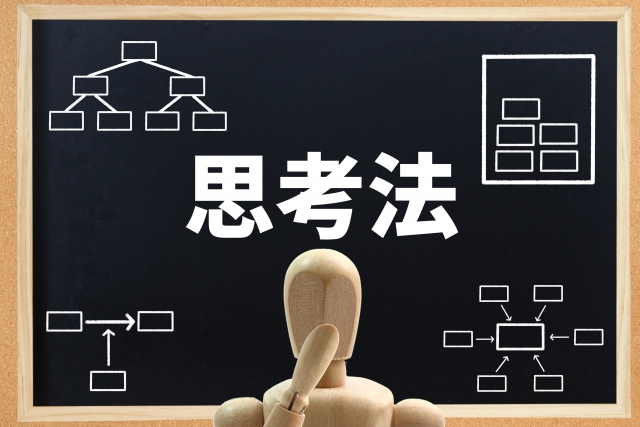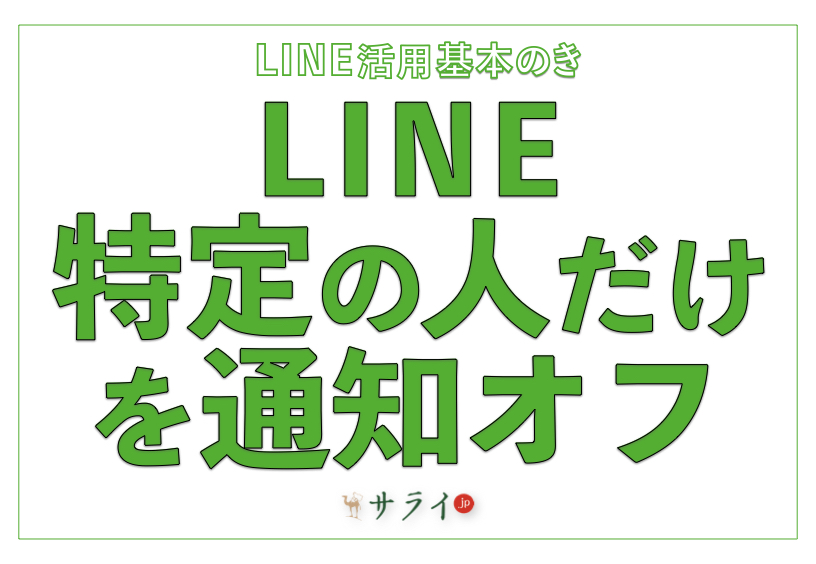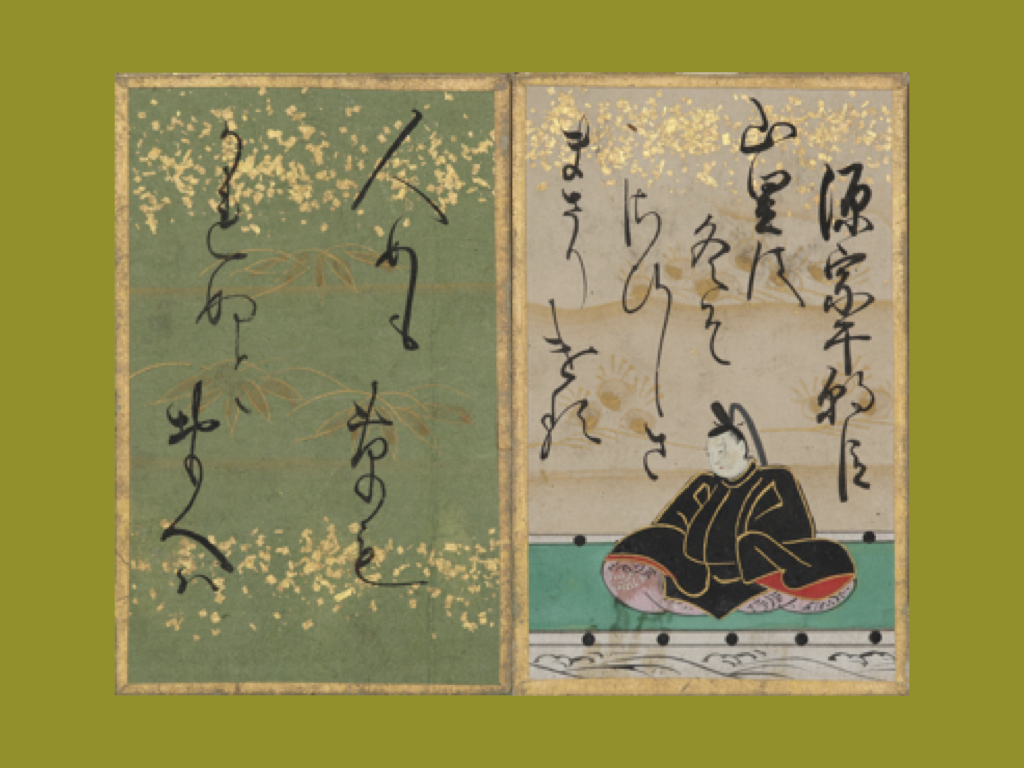マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)」が、ビジネスの最前線の用語や問題を解説するシリーズ。
はじめに
優れたプレーヤーとして成果を出してきたあなたが、管理職になり部下指導でつまずいていませんか?
「名選手、名監督にあらず」という格言が示すように、原因はプレーヤー時代の「成功体験」と「思考の癖」が管理職の役割と根本的に異なる点にあります。
この記事では、識学の観点から、そのつまずきの理由を明確にし、チームを勝たせる管理職になるために必要な「マインドセット」と「マネジメント手法」を具体的に解説します。
プレーヤーの「個人最適」と管理職の「組織最適」
優れたプレーヤーが管理職になってつまずく最初の根本原因は、役割の定義をアップデートできないことにあります。
プレーヤーの役割は、「個人のパフォーマンスを最大化し、成果を上げること」です。自分のやり方、自分の感覚、自分のモチベーションを最大限に活用し、目の前の目標を達成することがミッションです。これは、組織内での「個人最適」を追求する行動と言えます。
一方で、管理職の役割は「部下や組織全体の成果を最大化すること」です。管理職自身がどれだけ優秀でも、部下が結果を出せなければ、その管理職の評価は低くなります。管理職は、仕組みやルールを通じて組織全体を動かし、結果を出すことに責任を負います。
この役割の違いを認識できない管理職は、無意識のうちにプレーヤー時代の思考に引きずられます。例えば、部下の成果が上がらないとき、「自分がやった方が早い」と自らプレーヤーとして介入してしまう、あるいは、部下を指導するよりも自分の個人目標達成を優先してしまうといった行動です。
識学では、管理職は「マネジメントを最優先にする」ことが原則です。仮にプレイングマネージャーとして個人目標を持っていたとしても、最優先すべきは「チームのマネジメント」です。個人の成績が部下より悪くても、マネジメント職としての権威や指導する姿勢は崩してはいけません。
この「位置の概念」を明確にし、自らの役割が「組織最適」に変わったことを頭と心で理解することが、優れた管理職への第一歩となります。
「感覚論」から脱却できない優秀さの罠
管理職の仕事は「感情」ではなく「理論」でマネジメントすることが不可欠ですが、優れたプレーヤーほど、この「理論」の導入に苦労します。なぜなら、彼らがプレイヤー時代に成果を出してきた方法は、往々にして属人的な「感覚論」や「才能」に基づいているからです。
例えば、「ここぞというときの嗅覚」「自然に体が動く感覚」「顧客のニーズを感じ取る直感」など、言語化が難しく、再現性の低い能力で成功を収めてきました。そのため、部下が同じようにできないのを見ると、「なぜできないんだ」「気合が足りない」といった抽象的で感情的な指導になりがちです。
部下の立場からすれば、感覚的な指導は「何をすべきか」が明確にならず、成長につながりません。管理職の仕事は、誰がやっても同じ結果が出せる「再現性」を組織に持ち込むことです。
マネジメントとは「理論的に数字や数値を追求する」行為です。
・具体的な行動量(例:アポイント件数、架電数)の目標設定
・ルールに基づいた具体的な行動の指示
・目標と結果の差分に対するフィードバック
このように、「感情」を排し、「理論」に基づいて部下に接することで、部下は「何を、どれくらい、どうすれば良いか」を理解できます。優れたプレーヤーの「自分ができたからお前もやれ」という主観的な発想から、「この仕組みと理論に従えば成果が出る」という客観的な仕組みへ、思考を切り替える必要があるのです。
モチベーション管理は不要! 成長機会の提供こそが本質
多くの優れたプレーヤー出身の管理職は、部下の「モチベーション管理」に熱心になりがちです。自分が高いモチベーションで成果を出してきたため、部下のやる気を引き出すことが管理職の仕事だと誤解してしまうのです。
しかし、識学では、部下のモチベーションを管理することはマネジメントの失敗につながると考えます。モチベーションは部下自身の感情であり、管理職がコントロールできるものではありません。飲み会で一時的に雰囲気が良くなったり、優しく声をかけて部下がやる気を出したように見えても、それは長続きしません。それどころか、管理職が感情に介入すればするほど、部下は「上司に気に入られる行動」を選ぶようになり、本質的な成果追求から遠ざかる危険性があります。
管理職が本当にすべきことは、部下のやる気を「与える」ことではなく、「成長させる」ことです。人は、「明確な目標」に向かって「公正な評価」を受けながら「成長」していると感じるときに、自発的な高いモチベーションを発揮するものです。
優れた管理職は、以下の環境を整備します。
1.明確なルールの提示:評価基準や行動規範を明確にし、部下に迷いなく取り組ませる。
2.平等性の徹底:部下の個人的な事情をマネジメントに持ち込まず、全員に平等に、緊張感のある関係性で接する。
3.長期的な視点での指導:部下が結果を出せないときも焦って手伝わず、部下自身が学び、壁を乗り越える機会を奪わない。
つまり、管理職は、部下が仕事を通して成長し、成果を出せる「仕組み」を構築することに注力すべきであり、感情論であるモチベーション管理は部下自身に任せるべきなのです。
部下を「平等に扱う」ためのプロフェッショナルな距離感
優秀なプレーヤーは、チームに貢献するために、同僚や部下と密な「仲間」のような関係性を築こうとしがちです。しかし、これが管理職の立場になると、「不公平感」を生む原因となり、組織の機能を低下させます。
部下と個人的な関係が深まると、以下のような問題が発生します。
・特定の部下の個人的な事情(体調、家庭の事情など)を考慮し、他の部下よりも業務負担を軽くする。
・自分の気に入った部下を贔屓し、客観的な基準ではない評価や昇進を行ってしまう。
・部下のネガティブな感情に引きずられ、マネジメントの判断が感情的になる。
管理職には「部下と一定の距離をおく」ことが求められます。これは冷たい関係を作るということではなく、「部下を平等に扱う」ためのプロフェッショナルな姿勢です。
部下のマネジメントは、個人的な心情や感情を介入させず、会社が定めたルールと評価基準に基づいて淡々と行うべきです。管理職が「位置」を明確にし、部下全員と常に緊張感のある平等な関係性を保つことで、組織には健全な緊張感が生まれ、部下は「自分は公正に評価されている」と感じることができます。
部下から情報を受け取る際も、「自分の頃はこうだった」と決めつけたり、対話を楽しんだりするのではなく、意思決定に必要な「事実情報のみ」を吸い上げ、客観的な判断を下すことを徹底すべきです。
まとめ
優れたプレーヤーが管理職でつまずく根本原因は、プレーヤー時代の「個人最適」な思考と「感覚的な成功体験」を、管理職の「組織最適」な役割に切り替えられないことにあります。チームを勝たせる優れた管理職になるためには、マインドセットを強制的にアップデートする必要があります。
・役割の明確化:個人の成果ではなくマネジメントを最優先にする。
・理論的指導:感情や感覚論を排し、数字やルールに基づいた再現性のある指導に徹する。
・モチベーションからの脱却:モチベーション管理ではなく、部下の成長機会と公正な評価の仕組みを提供することに注力する。
・平等性の徹底:部下と一定の距離を置き、個人的な事情に左右されず、全員をプロフェッショナルとして平等に扱う。
もし、あなたが今、優秀なプレーヤーであったがゆえにマネジメントで悩んでいるならば、それは「才能」や「人間力」の不足ではありません。必要なのは、「管理職としてのマインドセット」と「理論的なマネジメントの知識」です。
明日からあなたがやるべき行動は、「今日から自分はプレーヤーではない。組織を勝たせる仕組みを作る管理者だ」と心に刻み、部下との関わりにおいて「感情」ではなく「ルールと理論」で判断することです。それが、チームを勝利に導く第一歩となるでしょう。
識学総研:https://souken.shikigaku.jp
株式会社識学:https://corp.shikigaku.jp/